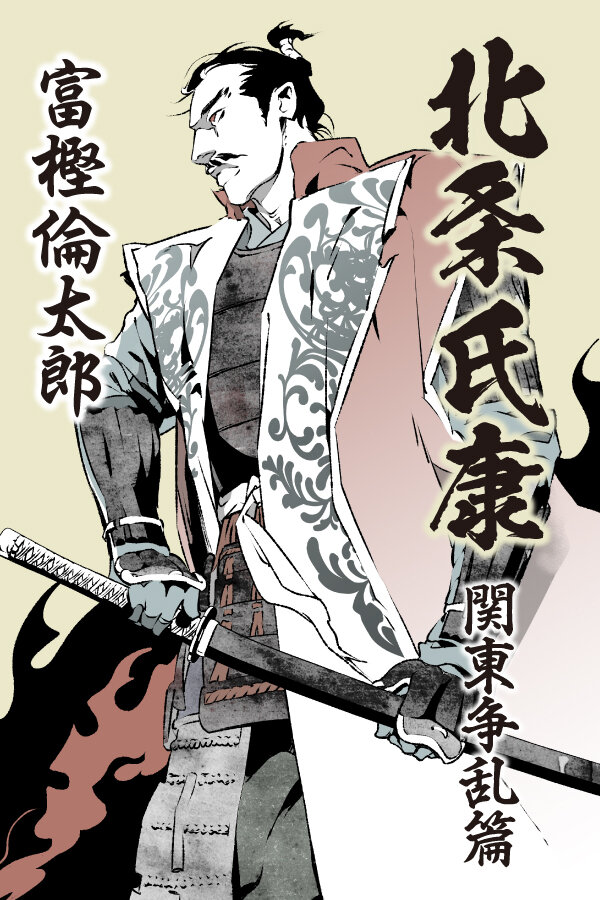北条氏康 関東争乱篇第四十九回
十一
二月四日、この日、上杉憲勝は氏康の降伏勧告を受け入れ、開城した。断続的に一年半の長きにわたって続けられた松山城攻防戦は、ここに終止符が打たれた。
憲勝は氏康と信玄の前に引き出され、助命されて小田原に送られた。これ以降、憲勝の名前は歴史から消える。
二月四日に開城したという事実は重要である。
なぜなら、景虎の率いる二万の軍勢が松山城に迫っていたのだ。開城の翌日、すなわち、二月五日に景虎は松山城開城の事実を知った。松山城への急行軍の道々、松山城から落ちのびてきた敗残兵たちに出会ったからである。
「嘘だろう......」
景虎は天を仰いだ。
(なぜだ? なぜ、もう一日凌ぐことができなかったのだ。あと一日、たった一日ではないか......)
間に合いようもなかったのであれば、景虎もそれほど悔しがらなかったかもしれない。
しかし、明日には松山城に到着するというところまで来ていた。太田資正も景虎を追って進軍しているし、いずれ里見軍もやって来るであろう。
あと一日か二日、上杉憲勝が持ちこたえていれば、松山城郊外で、景虎と信玄・氏康による一大決戦が行われていたはずなのだ。
「おのれ、おのれ!」
景虎は地団駄踏んで悔しがり、怒りで顔が真っ赤になり、腰抜けめが、と憲勝を罵った。
開城を知っても景虎は行軍をやめず、六日には松山城が見えるところに着いた。
松山城には武田軍と北条軍が入っており、武田と北条の旗がこれ見よがしに翻っている。
それを見て、景虎は逆上し、
「出てこい、わしと戦え。尋常に勝負しろ」
馬に乗って城のそばを走り回った。
景虎の格好は独特だから城方も、すぐにそれが景虎だとわかり、信玄と氏康に知らせた。
「ほう、長尾が来ましたか」
「見物に行きましょうか?」
「そうしましょう」
信玄と氏康が物見台に上ると、なるほど、頭を白の五條袈裟(ごじょうけさ)で包んだ裹頭(かとう)姿の景虎が漆黒の駿馬に跨(また)がり、何やら叫びながら走り回っている。
「確かに、あれは長尾殿ですな」
「総大将が城の近くまで寄せてきて、馬で駆け回るとは......」
呆れた男だ、と信玄が溜息をつく。
「いったい、何を叫んでいるのでしょう」
氏康は、景虎が何を言っているのか聞き取ってくるように小姓に命ずる。
しばらくすると小姓が戻って来て、景虎の言葉を伝える。
「ほう、勝負しろ、と。まるで一騎駆けの武者ですな」
「どうしますか?」
氏康が信玄を見る。
「放っておきましょう。そのうち疲れて帰るでしょう。馬鹿を相手にする必要はない」
「長尾殿は馬鹿でしょうか?」
「ええ、大馬鹿です。越後に引っ込んでおとなしく国を治めていればいいのに、何の得にもならぬことばかりしている。家臣や領民が哀れですな」
そう言いながら、依然として馬を走らせつつ叫んでいる景虎に信玄は冷たい目を向ける。
十二
いくら挑発しても、信玄と氏康が松山城から出てこないので、景虎も諦めて岩付城まで兵を退いた。
景虎の怒りの矛先は資正に向けられる。
おまえが万全の備えをしなかったから、松山城は敵の手に渡ってしまったのだ、おまえを信頼していたからこそ、岩付城も松山城も任せたのではないか、わしの期待を裏切りおって......と景虎は資正を責め立てた。
「ご覧下さいませ」
資正は冷静に目録を差し出した。
それは松山城に武器弾薬、食糧がどれほど備えられていたかを忠実に書き記したものだった。
資正自身、憲勝の器量を危ぶみ、いつか憲勝がしくじったとき、その責めを自分が負わされるかもしれないと警戒して、自分はできる限りのことをしたのだという証拠を残したのである。
「ふうむ......」
景虎は目録を目にして唸る。
なるほど、この目録を見れば、いかに資正が松山城のために尽力したかがよくわかる。備えは万全だったのだ。
最終的に致命傷になったのは水の手を切られたことだが、そもそも、竹束の楯で敵軍が鉄砲を防ぐことに成功した時点で、気の利いた者であれば、城内に水を蓄えていたはずである。それを怠ったために、水の手を切られるや、たちまち城兵は渇きに苦しむことになった。
「つまり、松山城が落ちたのは七沢七郎のせいだということだな?」
「いや、それは......」
資正が慌てる。松山城を失った責任を憲勝に転嫁するつもりはない。五万という途方もない大軍に包囲された松山城が、わずか三千の兵で三ヶ月以上も持ちこたえたことを認めてほしいという気持ちなのだ。憲勝を責めるために景虎に目録を見せたわけではない。
あと一日か二日持ちこたえていれば、と景虎は繰り返すが、景虎が越山して関東に入ったのは二ヶ月も前なのだから、もっと早く進軍していれば、こうはならなかったはずなのだ。
もちろん、資正も景虎の抱えている事情は承知している。敵に決戦を挑むだけの兵力がなかったのだ。同じように松山城にも開城せざるを得ない事情があった。それを理解してほしい、と資正は願う。
「せめて七沢七郎が腹を切っていれば、わしも、これほど怒りはしないであろう。ところがどうだ、腹を切るどころか、北条に膝を屈して小田原に向かったという。それほど己の命が大事か? 城と引き換えに命乞いをするとは、信じられぬ腰抜けよ。違うか?」
「......」
資正が言葉を失う。
景虎の言うことは正しい。何も間違っていない。
資正自身、なぜ、憲勝は死んでくれなかったか、という思いなのだ。勝負は時の運である。それ故、落城は恥ではない。武士の意地を見せて死ねば、それなりに賞賛される。
しかし、命乞いして城を明け渡したと見做されれば、
「何という腰抜けか」
「武士の風上にもおけぬ」
と罵倒されるのである。
「人質がいたな。連れてこい」
景虎が言う。
「お待ち下さいませ」
資正が跳び上がる。
憲勝を松山城の守将に任じるに当たって、資正は二人の息子を預かった。人質という名目だが、実際には、松山城が戦火にまみれたとき、扇谷(おうぎがやつ)上杉氏の血筋が絶えるのを怖れ、岩付城で預かることにした。万が一、憲勝が死んでも、その息子たちが生きていれば扇谷上杉氏再興の礎(いしずえ)にできるからだ。
憲勝は戦死しなかったものの、北条氏に捕らえられて小田原に送られてしまった。政治的生命は絶たれたと言っていい。
そうなれば、扇谷上杉氏の血統を未来に繋ぐことができるのは、憲勝の二人の息子たちということになる。扇谷上杉氏の再興を悲願とする資正にとっては何よりも大切にしなければならない貴重な駒なのである。
「まだ、ほんの子供でございますれば、父親の責めを負わせるのは酷でございます。どうか、ご容赦下さいませ」
「......」
景虎は返事をしない。
やがて、二人の子供たちが引き立てられてきた。
まだ元服もしていない少年たちである。二人とも十歳前後であろう。すっかり怯えてしまい、泣きじゃくって震えている。
「斬ってしまえ」
冷酷な顔で景虎が命ずる。
「御屋形さま、どうか、どうか、ご容赦を」
資正が叫ぶ。
「ならば、おまえの首を代わりに差し出すか?」
「......」
資正が息を呑む。
「斬れ」
景虎の小姓たちが二人の少年たちを斬る。
「その首を小田原に送るのだ」
そう言うと、景虎が席を立つ。
「......」
後には資正が残る。がっくりと膝をつき、地面に転がるふたつの首を見て、
(扇谷上杉氏は、この世から消えた......)
と深い溜息をつく。
松山城を失ったことには、ひとつの城が敵の手に渡ったというだけではなく、景虎が支配している上野まで失いかねないという重大な意味がある。
松山城のおかげで、一年半もの長きにわたって、氏康は上野に手を出すことができなかった。
逆に考えれば、今後は松山城を足場にして、易々と上野に兵を入れることができるということだ。
景虎にとっては大打撃である。
しかし、松山城と引き換えに得たものもある。
景虎は、今や山内上杉氏の当主である。
上杉氏には四家あり、そのうち、山内と扇谷が有力だ。昔から、この両家がしのぎを削ってきたが、両家が争っているうちに北条氏が着々と力をつけ、河越の戦いで扇谷上杉氏を滅ぼし、その後、山内上杉氏を圧迫し、ついに当主の憲政は越後に亡命せざるを得なくなった。このとき、山内上杉氏も滅亡したようなものであった。
その山内上杉氏が息を吹き返したのは、憲政が家督を景虎に譲ったからである。
景虎は上杉氏全体の当主のつもりでいる。
だからこそ、歴史上、長尾景虎は上杉謙信と呼ばれるのだ。山内謙信ではない。
上杉氏は景虎のもとに結集すればいいのであって、今更、山内とか扇谷とか区別する必要はない、というのが景虎の考えなのである。
その景虎にとって、資正の望む扇谷上杉氏の再興は嬉しいことではない。迷惑なのである。扇谷上杉氏など消えたままでいい。それが景虎の本心なのだ。
しかし、表立って口にできることではない。
由緒ある扇谷上杉氏を再興したいと、扇谷上杉氏の忠臣だった資正が願うのは当然で、それを天晴れよ、見事な心意気よ、と景虎は賞賛すべきであって、それを邪魔したり、叱責すべきではない。
特に体面や世間体を人並み以上に気にする景虎ならば尚更だが、本心は愉快ではない。
憲勝が北条氏に降(くだ)ったことは、扇谷上杉氏の血を引く者たちを粛清する絶好の口実になった。
憲勝の代わりに処罰するという名目で、二人の息子たちを処刑することができた。それによって、今度こそ扇谷上杉氏は完全に滅び去った。資正の野望は潰(つい)え去ったのである。
松山城を失った代わりに、景虎はより大きなものを手に入れたと言っていい。
信玄と氏康が景虎との決戦を避けたため、景虎はひどく不機嫌な様子で岩付城にやって来て資正を責め、その日のうちに憲勝の息子たちを処刑した。
翌日、岩付城を後にすると、それから二ヶ月にわたって武蔵と下野にある北条方の城を攻めた。それほど大きな戦果を得ることはできず、松山城を失った鬱憤晴らしのような感じだった。
四月七日に厩橋城を出て、帰国の途に就いたが、景虎は機嫌がよかった。この数ヶ月で多くの城や広い領地を失ったにもかかわらず、付き従う小姓たちと笑い合いながら、馬上で酒を飲んだ。
名実共に上杉氏全体の主となったという満足感のせいであったろう。
(関東争乱篇 了)
Synopsisあらすじ
一代にして伊豆・相模を領した偉大なる祖父・北条早雲、その志を継いだ父・氏綱。一族の悲願・関東制覇を期する氏康の傍らには、祖父が育てた軍配者・小太郎がいた! 河越夜襲で劇的勝利を収めた氏康を待つものは……北条三代目の生涯を描く人気シリーズ第四弾。
〈北条サーガTHE WEB〉http://www.chuko.co.jp/special/hojosaga/
Profile著者紹介
1961年、北海道生まれ。98年に第4回歴史群像大賞を受賞した『修羅の跫』でデビュー。「SRO 警視庁広域捜査専任特別調査室」「生活安全課0係」シリーズを始めとする警察小説から、『早雲の軍配者』『信玄の軍配者』『謙信の軍配者』の「軍配者」シリーズや『北条早雲』全5巻などの時代・歴史小説まで、幅広いジャンルで活躍している。
Newest issue最新話
- 第四十九回2024.05.27
Backnumberバックナンバー
- 第四十八回2024.05.20
- 第四十七回2024.05.13
- 第四十六回2024.05.07
- 第四十五回2024.04.26
- 第四十四回2024.04.22
- 第四十三回2024.04.15
- 第四十二回2024.04.08
- 第四十一回2024.04.01
- 第四十回2024.03.25
- 第三十九回2024.03.18
- 第三十八回2024.03.11
- 第三十七回2024.02.26
- 第三十六回2024.02.19
- 第三十五回2024.02.13
- 第三十四回2024.02.05
- 第三十三回2024.01.29
- 第三十二回2024.01.22
- 第三十一回2024.01.15
- 第三十回2023.12.25
- 第二十九回2023.12.18
- 第二十八回2023.12.11
- 第二十七回2023.12.04
- 第二十六回2023.11.27
- 第二十五回2023.11.20
- 第二十四回2023.11.13
- 第二十三回2023.11.06
- 第二十二回2023.10.30
- 第二十一回2023.10.23
- 第二十回2023.10.16
- 第十九回2023.10.10
- 第十八回2023.10.02
- 第十七回2023.09.25
- 第十六回2023.09.19
- 第十五回2023.09.11
- 第十四回2023.09.04
- 第十三回2023.08.28
- 第十二回2023.08.21
- 第十一回2023.08.14
- 第十回2023.08.07
- 第九回2023.07.31
- 第八回2023.07.24
- 第七回2023.07.18
- 第六回2023.07.10
- 第五回2023.07.03
- 第四回2023.06.26
- 第三回2023.06.19
- 第二回2023.06.12
- 第一回2023.06.07