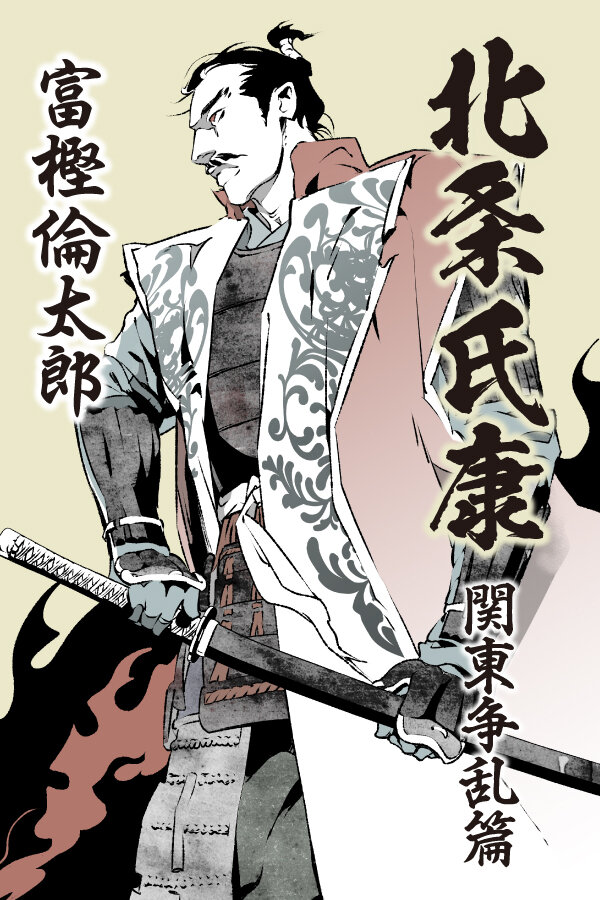北条氏康 関東争乱篇第四回
八
河越城から松山城に向かっているとき、氏康は景虎が越後に去ったことを知った。
せっかく景虎と決戦するつもりで大軍を率いて来たのに、肩透かしを食った格好である。
だが、氏康は怒りもせず、落胆もしなかった。
すぐ次のことを考え始める。
「このまま真っ直ぐ小田原に帰るのも芸がない。せっかくだから、公方さまにご挨拶して帰ることにしよう。そろそろ、公方さまにもはっきりしてもらわなければならぬしのう」
武蔵と東相模で募った兵を領地に戻し、小田原から率いて来た五千の兵を率いて、氏康は古河に向かった。
(なるほど......)
氏康の政治家としての才能に、小太郎は感心した。
公方さまに挨拶して帰る、と言われて、ようやく小太郎にも氏康の狙いがわかった。
このあたり、軍事を専門とする小太郎と、軍事だけでなく、政治や外交においても優れた才能を持つ氏康との差というものであろう。
(長尾と戦をするというのは本気ではなく、むしろ、こっちが主眼だったのかもしれぬな)
と想像すると、小太郎は氏康の凄みを思い知らされる気がする。
言うまでもなく、古河公方(こがくぼう)・足利晴氏(はるうじ)に挨拶するために、わざわざ兵を率いて古河に出向くというのんきな話ではない。
氏康の妹が晴氏に嫁いでおり、すでに梅千代王丸という子を産んでいる。十二歳である。
氏康は、晴氏に対して梅千代王丸を古河公方家の跡取りにすることを執拗に晴氏に要求しているが、晴氏はのらりくらりとかわし続けている。
晴氏には藤氏(ふじうじ)という後継ぎがいて、もう子供もいる。つまり、晴氏から藤氏へ、藤氏からその子へと古河公方を継承する流れは決まっているのだ。
そこに氏康が横槍を入れてきたわけである。
氏康の要求が無理筋だが、正論が通る時代ではない。力のある者の言うことが正論になるのだ。
六年前、晴氏は河越の戦いで氏康に敗れ、それ以来、氏康には頭が上がらない状況が続いているが、藤氏から梅千代王丸に後継ぎを変えることだけは頑として承知せず、四年前には、藤氏こそが古河公方家の嫡男であり、次の古河公方になる者だと宣言し、その披露まで行った。
これに激怒した氏康は、梅千代王丸を、その母と共に北条氏の城である葛西城に移し、古河から葛西に公方府を移すことを強引に晴氏に認めさせた。
だが、晴氏が古河公方であり、その後継ぎは藤氏、そして、二人が古河に留まっているという状況には何の変化もない。
晴氏とすれば、氏康に実権を奪われて、どうせ自分は何もできないのだから、公方府がどこであろうと関係ないと開き直っているのである。
その後、天文の大地震が起こったり、山内憲政との間で上野を巡る攻防戦が展開されたりして氏康は忙殺されたので、古河公方の一件は棚上げ状態になっていた。
(いつまでも曖昧なままにしておくことはできぬ)
今度こそ、ケリを付けよう、と氏康は覚悟を決めたのであろう。
氏康は、晴氏がどういう人間かよく知っている。
民のことなど何も考えず、政治も軍事も取り巻きに丸投げして、日がな一日、遊興に耽(ふけ)っている腑抜けなのである。強い信念など何も持っていないが、気位だけは高い。そういう人間の扱いを、氏康は、よく心得ている。今までは古河公方という権威に遠慮していただけである。
古河に着いた氏康は、五千の軍勢で城を囲んだ。これから城攻めを始めると言わんばかりの物々しさである。
晴氏は氏康に使者を送り、なぜ、すぐに城に入らず、武装したままでいるのか、と詰問した。
「公方さまがここに来られよ。来ないのなら、城を焼き払う」
と、氏康は使者に伝えた。
晴氏は仰天し、また使者を送り、無茶なことを言うな、何か誤解があるようだから、城で話し合いたい、といくらか下手に出てきた。
「明日、夜が明けたら、城を焼き払う。誰一人、城から出ることは許さぬ」
と、氏康は使者を追い返した。
「薬が効きすぎるのではないでしょうか?」
小太郎は心配したが、
「あれくらいで、ちょうどいいのだ」
「公方さまが来なかったら、どうなさるのですか?」
「城を焼くさ。半分くらい焼けば、慌ててやって来るだろう」
氏康は平気な顔をしている。
「それでも来なければ......?」
「そう案ずるな。大丈夫だ。公方さまは来る。自分の命より大切なものはないと思っているのだからな」
あの手合いを動かすには、頭を下げても駄目なのだ、刃物を突きつけて脅かすのが手っ取り早い、と氏康は笑う。
実際、その通りであった。
その夜、晴氏は城を出て、氏康のもとにやって来た。その場で、氏康は梅千代王丸を公方家の嫡男に据えることを強く要求した。
「しかしのう......」
この期に及んでも、晴氏は渋った。
「ならば、城にお戻りなさいませ。明日、城は丸焼けになる。中にいる者たちは、皆、焼け死ぬ。そうなれば、公方家を継ぐ者は梅千代王丸しかいなくなるでしょう」
「本気でそのようなことを申しておるのか?」
「多くの者たちを巻き添えにするのが嫌だとおっしゃるのであれば、この場で公方さまの首を刎ねてもよいのですぞ」
氏康が睨む。
「まさか、本気ではあるまい」
「河越でわたしを裏切ったときに、そうしてもよかったのです」
「......」
晴氏の顔色が変わり、ぶるぶる震え出す。
ついに、
「わかった。その方に従おう」
がっくりと肩を落とす。
十二月十二日、晴氏は藤氏を廃嫡し、葛西城にいる梅千代王丸に古河公方家の家督を譲った。まだ元服もしていない、わずか十二歳の古河公方の誕生である。氏康にとって、大きな外交的な成果であった。
九
この時期、氏康は、もうひとつ大きな外交に取り組んでいた。
今川、武田との三国同盟の締結である。
主導したのは今川の軍配者・太原雪斎(たいげんせっさい)である。
すでに七年前、武田と今川は同盟を結んでいる。
今川は駿東地方を取り戻すために北条との国境付近に兵を出し、同盟に従って、武田晴信(はるのぶ)も出陣した。
太原雪斎の立案した壮大な計画が進み、扇谷上杉氏・山内上杉氏・古河公方家が河越城を包囲し、北条家は絶体絶命の危機に陥った。
東西に敵を抱えていたのでは身動きが取れないので、氏康は、まず武田と、次いで今川と和睦した。両家の要求する領地を割譲しなければならなかったが、和睦が成立したおかげで、東の敵に全力を傾けることができるようになり、ついには河越の合戦で大勝利を得た。
その大勝利をきっかけに、北条家は大きく躍進し、今では武蔵から上野へと支配地が広がっている。
氏康の前途は順風満帆と言っていい。
そんなときに、なぜ、武田や今川と手を結ぼうとするのか?
きっかけは、二年前の六月、今川義元の正妻が亡くなったことである。武田晴信の姉だ。
両家の緊密な関係を維持するために、新たな婚姻が議されたが、そのとき、雪斎が、
「いっそ北条家も巻き込んでしまいましょう」
と言い出したのである。
雪斎は大きな絵を描くのが好きな男だ。
今川・武田・北条という三つの巨大な大名家を婚姻によって結びつけるという思いつきに夢中になった。駿府、小田原、甲府を使者が盛んに行き来するようになった。
夢のような話だが、それが実現すれば、三家にとって、大きな旨味がある。
今川の目は西に向いている。
遠江(とおとうみ)・三河を征するだけではなく、尾張や美濃にも進出し、いずれは京に上りたいというのが今川義元の野望である。全力を西に向けるためには、東で国境を接する北条家とは事を構えたくないのが本音だ。
武田は南信濃を制圧し、今は北信濃に侵攻している。北信濃の豪族たちの抵抗はしぶといものの、彼らを攻め滅ぼすのは時間の問題と思われていた。
そこに長尾景虎が現れた。
先代の晴景は、武田による信濃侵略に無関心だったが、景虎は、そうではない。まだ景虎自身は信濃に出てきていないが、北信濃の豪族たちへの手厚い後援を始めているから、景虎の出兵は時間の問題であろう、と晴信は覚悟している。
氏康の仇敵である山内憲政が越後に亡命し、上野奪回を景虎に要請したことも晴信も知っているから、北条と同盟すれば、共同で景虎に対処できると考えた。
北条家の方針は今川とは真逆で、その目は東に向いており、西に関心はない。関東八ヵ国を支配下に置くことが悲願なのである。上野を奪った今、氏康は房総半島全域の支配を目論んでおり、そのためには安房(あわ)の里見氏を打倒する必要がある。武田や今川と争うのは無駄なのだ。
三家が手を結べば、それぞれの目標に向かって全力で邁進することができる。
雪斎の骨折りで、三家の婚姻話が着々と進んだ。
氏康の嫡男・新九郎氏親と晴信の娘の結婚、氏康の娘と義元の嫡男・氏真(うじざね)の結婚、晴信の嫡男・義信(よしのぶ)と義元の娘の結婚、この三つである。
まず、この年十一月二十七日、武田家に義元の娘が輿入れした。これで武田と今川は新たな絆を得た。
あとのふたつは、そう簡単にいかなかった。
同じ時期に、晴信の娘が氏康の嫡男・氏親に輿入れする予定だったが、氏親は、三月に亡くなってしまった。
新たに嫡男となった松千代丸が晴信の娘を娶ることになったが、松千代丸は元服していないので、とりあえず、婚約だけすることにして、正式な結婚は元服後ということになった。
義元の嫡男・氏真と氏康の娘の結婚は更に難航した。娘が六歳の幼女で、すぐに駿府に送って結婚させることができなかったのだ。そのため結婚は二年先ということになったが、それでは同盟が成立しないので、代わりに、氏康の四男・助五郎(すけごろう)が駿府に赴くことになった。後の氏規(うじのり)で、このとき八歳である。
助五郎は、義元の妹を母として生まれたから、義元の甥である。義元の母・寿桂尼(じゅけいに)は祖母である。
そういう濃い血縁関係があるので、実質的には人質だったが、体裁としては、義元や寿桂尼の家族として扱われることになった。
ちなみに助五郎が駿府で暮らしているとき、隣の屋敷には松平竹千代、後の徳川家康がいた。年齢の近い二人は、この時期に友情を育み、その縁は、後々、北条氏が滅亡するときまで続くことになる。
Synopsisあらすじ
一代にして伊豆・相模を領した偉大なる祖父・北条早雲、その志を継いだ父・氏綱。一族の悲願・関東制覇を期する氏康の傍らには、祖父が育てた軍配者・小太郎がいた! 河越夜襲で劇的勝利を収めた氏康を待つものは……北条三代目の生涯を描く人気シリーズ第四弾。
〈北条サーガTHE WEB〉http://www.chuko.co.jp/special/hojosaga/
Profile著者紹介
1961年、北海道生まれ。98年に第4回歴史群像大賞を受賞した『修羅の跫』でデビュー。「SRO 警視庁広域捜査専任特別調査室」「生活安全課0係」シリーズを始めとする警察小説から、『早雲の軍配者』『信玄の軍配者』『謙信の軍配者』の「軍配者」シリーズや『北条早雲』全5巻などの時代・歴史小説まで、幅広いジャンルで活躍している。
Newest issue最新話
- 第四十九回2024.05.27
Backnumberバックナンバー
- 第四十八回2024.05.20
- 第四十七回2024.05.13
- 第四十六回2024.05.07
- 第四十五回2024.04.26
- 第四十四回2024.04.22
- 第四十三回2024.04.15
- 第四十二回2024.04.08
- 第四十一回2024.04.01
- 第四十回2024.03.25
- 第三十九回2024.03.18
- 第三十八回2024.03.11
- 第三十七回2024.02.26
- 第三十六回2024.02.19
- 第三十五回2024.02.13
- 第三十四回2024.02.05
- 第三十三回2024.01.29
- 第三十二回2024.01.22
- 第三十一回2024.01.15
- 第三十回2023.12.25
- 第二十九回2023.12.18
- 第二十八回2023.12.11
- 第二十七回2023.12.04
- 第二十六回2023.11.27
- 第二十五回2023.11.20
- 第二十四回2023.11.13
- 第二十三回2023.11.06
- 第二十二回2023.10.30
- 第二十一回2023.10.23
- 第二十回2023.10.16
- 第十九回2023.10.10
- 第十八回2023.10.02
- 第十七回2023.09.25
- 第十六回2023.09.19
- 第十五回2023.09.11
- 第十四回2023.09.04
- 第十三回2023.08.28
- 第十二回2023.08.21
- 第十一回2023.08.14
- 第十回2023.08.07
- 第九回2023.07.31
- 第八回2023.07.24
- 第七回2023.07.18
- 第六回2023.07.10
- 第五回2023.07.03
- 第四回2023.06.26
- 第三回2023.06.19
- 第二回2023.06.12
- 第一回2023.06.07