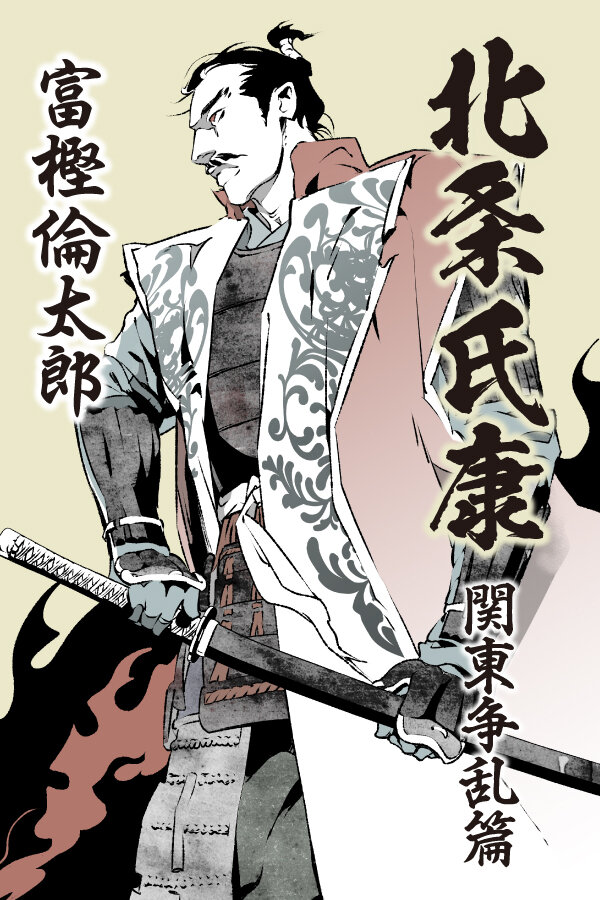北条氏康 関東争乱篇第四十四回
三
松山城の守将は上杉憲勝である。
前名を七沢七郎という。
出自が定かではなく、扇谷朝良(ともよし)の子であるとも、朝興(ともおき)の子であるとも言われる。
扇谷上杉氏の最後の当主は朝定(ともさだ)だが、朝定の養祖父が朝良で父が朝興だから、憲勝は朝定の大叔父か兄ということになる。兄だとすれば庶出なのであろう。年齢もはっきりしないが、子供たちの年齢から推測すると四十代半ばから五十代半ばくらいの男盛りだったであろう。
いずれにしても、家臣として朝定に従っていたことは間違いなく、河越の合戦の際には朝定のそばにいたはずである。北条軍に大敗を喫して扇谷上杉氏が滅亡すると、憲勝は奥州に逃れた。
扇谷上杉氏の再興を目指す太田資正が、長尾景虎の関東進出を再興の好機と判断し、憲勝を呼び戻した。憲勝に松山城を預けたのは、朝定が松山城を本拠としていたからである。
憲勝には政治や軍事の才能はない。
河越の合戦では、どの場面にも名前が出てこないから、そもそも戦場に姿を見せたかどうかも怪しいし、敗北を喫した後、北条氏の追及を怖れて逃げ回るだけで、例えば、資正のように扇谷上杉氏の遺臣を結集して北条氏に対抗しようとしたり、扇谷上杉氏を再興しようと努力したり、何かしら政治的な動きを見せた痕跡もない。
要は何もしなかったわけで、資正に呼び戻されなければ、歴史に名前が現れることもなく、奥州の僻地でひっそりと死んだに違いない。
資正は憲勝に三千の兵を預けて松山城を守らせた。
堅固な松山城に三千の兵を入れれば、守将が無能だとしても、半年くらいは籠城に耐えられるはずであった。それだけの時間があれば、岩付から資正も駆けつけられるし、越後の長尾景虎に越山を要請することもできる。
三田氏を滅ぼし、藤田氏を屈服させた氏康は、兵を休めることなく、直ちに北上して松山城を囲んだ。
電光石火の動きである。
これが三度にわたる松山城攻防戦の最初である。
いずれ北条軍が現れることを予想していたから、憲勝も籠城準備は進めていたものの、氏康の進軍が速すぎて、十分に準備できないまま籠城せざるを得なくなった。
「困ったのう。どうしたものか......」
憲勝は、おろおろした。物見櫓に上ると、見渡す限り、野原にも谷にも山の斜面にも北条の旗が翻り、所狭しと北条兵が埋め尽くしている。まさに蟻の這い出る隙間もない。
「そうご心配なさいますな」
資正から憲勝の補佐役に任じられている三田五郎左衛門や広沢兵庫介信秀らが宥めるが、憲勝の心配は増すばかりである。
戦慣れしている補佐役たちとすれば、
(この城は、そう簡単には落ちぬ)
と自信を持っている。
天然の要害にあって、守りやすく攻めにくいというのもそうだし、何より大きいのは水が豊富だということであった。人間は食糧がなくても何とか耐えられるが、水がなければ耐えられない。水があるかどうかは、その城の耐久性に直結する重大な要素なのだ。
しかし、いくら言葉を尽くして説明しても憲勝は納得せず、
「岩付に使者を送れ。美濃に来てもらわねば、どうにもならぬ」
資正に援軍要請せよ、と執拗に命ずる。
使者を送るといっても、松山城は完全に包囲されている。北条軍の目をかいくぐって使者が岩付に向かうのは至難の業であろう。
ここで軍事史に残る画期的な作戦が演じられる。
軍用犬の活用である。伝令犬とか間諜犬とも言われる。
この逸話は『関八州古戦録』や『甲陽軍鑑』に記載されている。『関八州古戦録』は歴史書ではなく、歴史読物の類だから、時代考証も不正確だし、かなりいい加減なことも書いてあるので信用できないものの、『甲陽軍艦』は甲州流軍学の教科書で、ある程度は信用できる。
それによると、太田資正は子供の頃から犬が好きで、常に何頭もの犬を飼って訓練していたという。
資正はいずれ北条軍が反撃してくるだろうと警戒し、松山城が十重二十重に包囲されることまで予期していたというから、よほど軍事的な嗅覚に優れていたのであろう。
その際、松山城と岩付城の連絡が途絶えることを心配し、犬の活用を思いついた。岩付で訓練した犬たちを松山城に連れて行き、犬の訓練係が岩付に帰ってから犬たちを松山城から出した。犬には帰巣本能があるから、訓練係や飼い主を慕って、岩付に戻って来た。中には戻らない犬もいたらしいが、かなりの犬たちが戻った。松山城から岩付まで直線距離で四十キロくらいあり、最初は戻るのに数日かかったが、慣れてくると一日で戻る犬も現れた。
憲勝は援軍要請の手紙を書くと、それを小さな竹筒に入れて犬の首にくくりつけ、犬を松山城から放った。犬は無事に岩付に着いたという。
憲勝の手紙を読み、資正は松山城が包囲されたことを知ったが、すぐには動きようがない。
北条軍が多すぎるのである。
資正が率いていくことができるのは二千くらいのもので、それでは、とても歯が立たない。
結局、長尾景虎に越山してもらわないことには、どうにもならないのである。
資正は直ちに景虎宛てに書状を認(したた)め、越山を要請した。
資正の賢いところは、
(わしが頼むだけでは、どうにもならぬ)
と考えたところである。
すでにこの頃には、川中島における長尾と武田の激戦について広く知れ渡っており、双方に多数の死傷者が出たことを資正は知っている。
景虎とすれば、今は兵を休めたいのが本音に違いない。
北条軍に包囲されたとはいえ、凡将が守っても半年くらいの籠城に耐えられるほど松山城は堅固な城である。なぜ、わしが慌てて越山しなければならぬのか、と景虎が腹を立てても不思議はない。
(関白さまの頼みであれば断ることはできまい)
この時期、近衛前嗣(このえさきつぐ)は古河城にいる。
前嗣だけでなく、上杉憲政もいるし、足利義氏に対抗して景虎が擁立した足利藤氏もいる。
彼らは、まさかこれほど迅速に氏康が反転攻勢を仕掛けてくるとは予想していなかった。あっという間に武蔵を取り返し、今は松山城に押し寄せている。多少でも軍事のわかる者であれば、氏康が岩付城を放置して松山城に押し寄せたのは、上野に攻め込むためだと容易に想像できるはずである。
しかし、近衛前嗣も足利藤氏も軍事に関しては素人だし、憲政も似たようなものだ。
松山城を落としたら、氏康は返す刀で岩付城を攻めるであろうし、岩付城が落ちれば、次は古河城が危ない......そんな内容の伝言を資正の使者が伝えると、
「えらいことやで。北条が攻めてくるがな」
まるで明日にでも氏康が古河城に攻めかかってくるかのように近衛前嗣は慌てふためき、
「長尾に来てもらわな、どないもならんで」
すぐさま景虎に書状を送り、越山を要請した。
資正の狙い通りである。
景虎の最大の弱点は権威に弱いことである。
春日山城にいるときは朝夕の勤行を欠かさないほど毘沙門天を敬っているが、人間世界では天皇や将軍を至高の存在として最大限の敬意を払っている。これまで天皇や将軍の言葉に一度として異を唱えたことがなく、どんな無理難題を押しつけられても、ふたつ返事で承知してきた。
関白は将軍に次ぐ存在である。
景虎が逆らうことなどあり得ない。
直ちに越山を了承し、出陣の準備を始めた。
景虎ほどの軍事的な天才は日本の歴史においても稀であり、恐らく、源義経がかろうじて肩を並べるくらいであろう。相手と互角の兵力で野戦をすれば、景虎に勝利できる武将は、少なくとも戦国時代には存在しない。
氏康はそれを承知しているから、徹底して野戦を避け、ひたすら籠城した。
武田信玄ほどの天才でも景虎には歯が立たず、やむなく景虎と戦うときは、必ず越後勢を上回る兵力を動員した。
それほどの軍事的な天才が、戦のことなど何も知らない素人に踊らされてあたふたと出陣の支度をする姿は滑稽であり、もはや喜劇と言うしかない。
もっとも、氏康にとっては喜劇どころではない。
半年前、小田原に攻め込まれた悪夢が甦ったに違いない。その恐るべき越後の虎は、前嗣に約束した通り、十一月に関東に出てきた。
四
「長尾は、どう出てくるでしょうか?」
板敷きに広げた絵図面に視線を落としながら、氏政が訊く。
「うむ......」
氏康は腕組みして、睨むように絵図面を見つめながら小首を傾げる。
その絵図面には武蔵と上野の主要な城が書き込まれている。
氏政と氏康の二人の視線は、自分たちが包囲している松山城と、越山してきた長尾景虎がいる厩橋(まやばし)城に交互に向けられている。
「風間党からの知らせはないか?」
氏政が新之助康光に訊く。
「出陣の支度は進められており、近々、軍勢が城を出ると思われます」
康光が答える。
「やはり、出てくるか」
氏政がうなずく。
「わざわざ越後から慌ただしくやって来たのだから、戦をするつもりでいるのは間違いあるまい。だが、肝心なのは、そこではない。長尾は、どうするのか......」
氏康が首を捻る。
景虎が越後から連れて来た兵は五千ほどである。
一年前、越山したときは八千の兵を率いていたから、今回はかなり少ない。
氏康と氏政も、ふた月前の川中島の激戦については熟知している。風間党が探っただけでなく、合戦の当事者である武田信玄からも詳しい知らせが届いたからだ。武田の被害も甚大だが、長尾の被害は、それを上回るという。元々、武田と長尾の動員能力には大きな差があるから、同じだけの兵を失っても、長尾の方が被害はより深刻である。武田以上の損失を被ったとすれば、長尾の動員能力はかなり減殺され、それが五千という数に如実に表れている、と氏康は判断する。
それでも景虎が到着すると、上野の豪族たちが兵を率いて駆けつけたから、今では八千を超える兵力を景虎は握っている。
景虎が八千の兵を率いて南下してきたらどうするか、その対応を話し合っているわけである。
松山城を包囲する北条軍は、一万を超えている。数だけ見れば長尾軍を上回っているが、戦上手の景虎を相手にするとなれば、この程度の兵力差には何の意味もない。むしろ、劣勢と考えるべきであった。
これまで氏康は景虎との直接対決を徹底的に避けてきた。そのやり方を踏襲するのであれば、松山城の囲みを解いて、さっさと河越城に引き揚げるべきであろう。
だが、それは、あくまでも長尾景虎と単独で対峙する場合である。
どういうことかといえば......。
松山城の包囲を決めたとき、氏康は、いずれ景虎が越山してくるに違いないと考え、景虎を迎え撃つにあたって、ひとつの味付けをした。
武田信玄に共同作戦を呼びかけたのである。長尾景虎という共通の敵を叩くために手を組もうというのだ。
この呼びかけを信玄は快諾し、十一月初め、西上野に侵攻した。早速、長尾方の城を攻め、高田城や国峰城を落とした。
川中島の合戦によって長尾軍が今までになく弱体化していることを、信玄は知っている。景虎を叩く絶好機である。時間を与えて、長尾軍の回復を許せば、また北信濃に出てくるに決まっている。景虎を相手に戦うことの無意味さを強く感じているから、何とかケリを付けたいと信玄は思案している。
とは言え、長尾軍だけでなく、武田軍も甚大な損害を被ったから、自分の方から積極的に動こうという考えはなかった。
そこに氏康からの申し出である。
氏康と手を組めば、川中島の合戦で失った兵力を氏康が補ってくれる。氏康が一万を超える兵力で松山城を囲んでいることを信玄は知っている。自分が同じくらいの兵を率いて西上野に侵攻すれば、両軍の兵力は二万を超える。
景虎がどれほどがんばったところで、掻き集められるのは、せいぜい一万くらいの兵力に過ぎないと信玄は見切っているから、景虎が越山すれば、二倍の兵力で景虎との決戦に臨むことができる。
信玄も氏康も、単独で景虎と対峙するのは分が悪いと承知しているが、二人が協力して景虎と立ち向かえば、そう簡単には負けないだろうという自信がある。しかも、兵力は二倍なのだ。
景虎が厩橋城から出てくるかどうかを氏康が注視しているのは、そうなれば、信玄と連絡を取り合って、景虎を挟み撃ちにできるからであった。
しかし、景虎は鼻の利く男である。
氏康と信玄の思惑を見抜くであろう。
それでも敢えて出陣するのか、あるいは自重するのか、それによって氏康と信玄の対応も変わる。
十一月二十六日、長尾軍が動いた。
五千の長尾軍が厩橋城を出て、南下を始めた。松山城を救援するのが目的だ。
氏康のもとには、忍びからの報告が続々ともたらされる。
「長尾は五千で出てきましたか」
「うむ、厩橋城に三千の兵を残したようだな」
氏政の言葉に氏康がうなずく。
「それでなくても少ない兵をふたつに分けるとは、弾正少弼殿らしくないやり方に思われます」
康光が言う。
「てっきりすべての兵を率いて出陣すると思っていたがのう」
氏政がうなずく。
「五千の兵を率いているのは柿崎景家のようだ」
「え、弾正少弼殿ではないのですか?」
氏政が驚く。
「厩橋城に残っているらしい。武田の動きを警戒しているのであろうよ」
ふふふっ、と氏康が笑う。
狙い通りの展開になってきたので嬉しいのだ。
「しかし、どれほど戦上手だとしても、わずか三千で武田と戦うのは無理だと思いますが」
康光が首を捻る。
「われらと武田を合わせれば二万を超える。そもそも八千では、どうにもならぬのだ。普通ならば、厩橋城に籠もっておとなしくしているのだろうが、松山城を見捨てることができぬのであろう。だから、最も愚かな策を採った」
氏康が言う。
「こちらにとっては、ありがたいことですな。どうしますか?」
「柿崎如きが相手なのであれば、あれこれ考えることもあるまい。八千ほど率いて、わしが迎え撃つ。その方は松山城に目を光らせておれ」
「は」
氏政が頭を下げる。
「まさかと思いますが、実は柿崎ではなく、弾正少弼殿が五千を率いているということはないでしょうか?」
康光が懸念を口にする。
「それはないだろう。城を出た長尾軍の中に『毘』の旗はないそうだ。たかが旗ひとつと思うかもしれぬが、わしもあの男のことがわかってきた。出陣するのであれば、必ずや『毘』の旗を携えているはず。他の者にとってはどうでもいいようなことに妙に律儀な男なのだ」
「なるほど」
「万が一、五千を率いているのがあの男なのであれば、武田が厩橋城を攻め落とす。退路を断たれ、わずか五千で北条と武田と戦う羽目になる。どっちに転んでも、わしらに悪いことではない」
「おっしゃる通りです」
康光がうなずく。
「腕が鳴りますなあ、父上。ついに長尾と戦うことができる。北条の領国で好き勝手なことばかりしおって、目にもの見せてやりましょうぞ」
ああ、できれば、わしも戦いたい、と氏政が溜息をつく。
「そう気負うな。長尾との戦いは、これからも続くのだ」
氏康がたしなめる。
その翌日、十一月二十七日早朝、松山城の北、生野山(なまのやま)で北条軍八千と長尾軍五千が激突した。これを生野山の戦いと呼ぶ。
氏康が見抜いたように、長尾軍の中に景虎はいなかった。厩橋城に残ったのである。
柿崎景家も猛将だが、一軍を率いる大将の器ではない。大将の下知に従って勇猛果敢に戦うのが似合っている。戦上手の氏康と渡り合うほどの器量はない。しかも、兵力において大きく劣っているのだから、まともに戦えというのが無理というものだ。
一丸となって突進してくる長尾軍を、氏康は見せかけの退却で自陣の奥深くに引き寄せ、いつの間にか長尾軍を緩やかに包囲する。
北条軍が反転し、長尾軍を迎え撃つ体勢を取る。
四半刻(三十分)ほど一進一退の攻防が続いたものの、長尾軍の左右から北条軍の伏兵が攻撃を始めると、これに手を焼いた長尾軍がじりじり後退する。
しかし、そこにも北条軍が待ち伏せしていた。
退路を断たれ、四方から波状攻撃を仕掛けられて、柿崎景家は敗北を悟った。
「御屋形さまに顔向けできぬ。ここで腹を切る」
責任を取って自害しようとしたが、周囲の者たちに止められ、這々の体で厩橋城に逃げ帰った。
戦いは昼前には決着した。
北条軍の圧勝である。
景虎が指揮を執っていなかったとはいえ、長尾軍がこれほどの敗北を喫するのは、何年もなかった。長尾に与する上野の豪族たちに動揺が広がったのは当然であろう。
Synopsisあらすじ
一代にして伊豆・相模を領した偉大なる祖父・北条早雲、その志を継いだ父・氏綱。一族の悲願・関東制覇を期する氏康の傍らには、祖父が育てた軍配者・小太郎がいた! 河越夜襲で劇的勝利を収めた氏康を待つものは……北条三代目の生涯を描く人気シリーズ第四弾。
〈北条サーガTHE WEB〉http://www.chuko.co.jp/special/hojosaga/
Profile著者紹介
1961年、北海道生まれ。98年に第4回歴史群像大賞を受賞した『修羅の跫』でデビュー。「SRO 警視庁広域捜査専任特別調査室」「生活安全課0係」シリーズを始めとする警察小説から、『早雲の軍配者』『信玄の軍配者』『謙信の軍配者』の「軍配者」シリーズや『北条早雲』全5巻などの時代・歴史小説まで、幅広いジャンルで活躍している。
Newest issue最新話
- 第四十九回2024.05.27
Backnumberバックナンバー
- 第四十八回2024.05.20
- 第四十七回2024.05.13
- 第四十六回2024.05.07
- 第四十五回2024.04.26
- 第四十四回2024.04.22
- 第四十三回2024.04.15
- 第四十二回2024.04.08
- 第四十一回2024.04.01
- 第四十回2024.03.25
- 第三十九回2024.03.18
- 第三十八回2024.03.11
- 第三十七回2024.02.26
- 第三十六回2024.02.19
- 第三十五回2024.02.13
- 第三十四回2024.02.05
- 第三十三回2024.01.29
- 第三十二回2024.01.22
- 第三十一回2024.01.15
- 第三十回2023.12.25
- 第二十九回2023.12.18
- 第二十八回2023.12.11
- 第二十七回2023.12.04
- 第二十六回2023.11.27
- 第二十五回2023.11.20
- 第二十四回2023.11.13
- 第二十三回2023.11.06
- 第二十二回2023.10.30
- 第二十一回2023.10.23
- 第二十回2023.10.16
- 第十九回2023.10.10
- 第十八回2023.10.02
- 第十七回2023.09.25
- 第十六回2023.09.19
- 第十五回2023.09.11
- 第十四回2023.09.04
- 第十三回2023.08.28
- 第十二回2023.08.21
- 第十一回2023.08.14
- 第十回2023.08.07
- 第九回2023.07.31
- 第八回2023.07.24
- 第七回2023.07.18
- 第六回2023.07.10
- 第五回2023.07.03
- 第四回2023.06.26
- 第三回2023.06.19
- 第二回2023.06.12
- 第一回2023.06.07