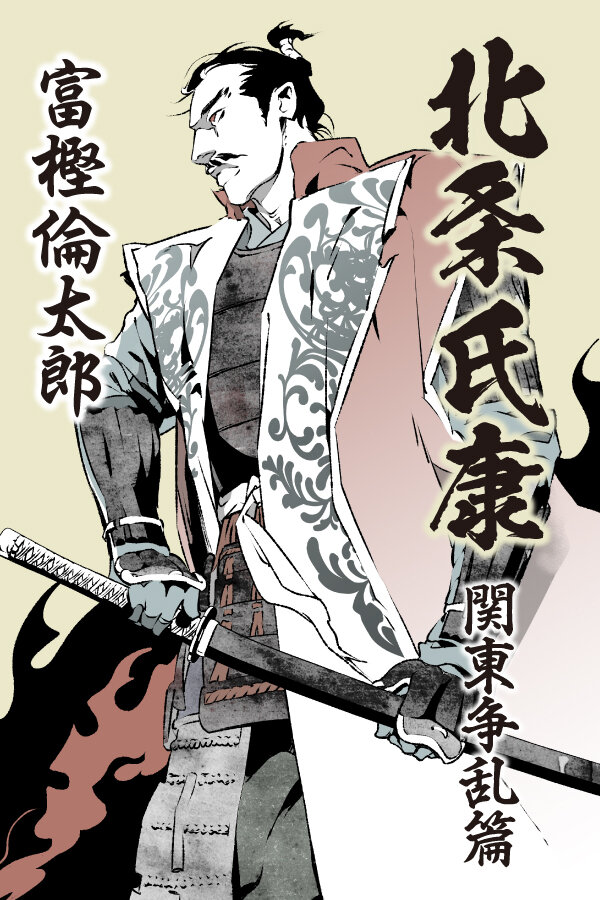北条氏康 関東争乱篇第四十七回
七
古河城を奪った氏政は、葛西城に向かって氏康と合流するのではなく、松山城に向かった。氏康の指示である。
氏康の第一目標は葛西城を落とすことで、松山城を落とすことではない。
にもかかわらず、氏政を松山城に向かわせたのは、古河城が落ちた影響を測ることと松山城の防備の堅さや士気の高さを見極めるためであった。
本格的に松山城を攻めるのは葛西城を落とし、武田信玄と合流してからになるが、まずは地均(じなら)しをしておこうという考えなのである。
氏政の軍勢が松山城に向かえば、岩付城の太田資正の目は葛西城ではなく松山城に向けられるはずであった。葛西城が落ちれば房総半島が、松山城が落ちれば上野が危うくなる。
どちらも重要だが、資正にとって、より重要なのは松山城である。松山城が落ちれば、岩付城は北条氏の勢力圏に浮かぶ孤島になってしまうからだ。松山城と連携する限り、岩付城は孤島ではなく、北条氏に対する防波堤の役目を果たすことができる。
「城をひとつ落としただけなのに、大した変わり様だな」
氏政が言うと、
「古河城は、ただの城ではなかったということです。北条の強さを示すには、長尾を戦で破るより、ずっと効き目があったのかもしれませぬ」
康光がうなずく。
古河から松山城に向かう道々、それまで日和見を決め込んで、どっちつかずの態度を取っていた豪族たちが、続々と、氏政の元に駆けつけ、
「北条家に尽くしたい」
と臣従の申し出をしたのである。
元々は北条家に従っていた者たちである。
去年、長尾景虎が越山し、上野、武蔵、相模を席巻し、ついには小田原城に迫るのを見て、
(北条氏は終わりだ)
と見切りを付けて景虎の元に馳せ参じたのである。
つまり、一度は北条氏を裏切った者たちが、何食わぬ顔で、改めて臣従を申し出てきたわけである。
正義感が強く、一本気な氏政とすれば、
(こんな連中は信じられぬ、また長尾景虎が大軍を率いて現れれば、当家を裏切るに違いない)
という気持ちだったが、そういう事態が生じることを予想していた氏康から、
「笑って受け入れよ」
と事前に釘を刺されている。
力のない豪族どもは、風見鶏のように強い方に靡(なび)くものだ、いちいち腹を立ててはならぬ、北条家が強さを保てば、あの者たちが裏切ることもないのだ......そう諭されていたから、氏政は臣従を願い出る者たちをにこやかに迎え、小言も言わずに受け入れた。氏康の戒めがなければ、氏政は彼らの不忠を罵倒し、追い返してしまったかもしれない。
古河城を落とし、近衛前嗣、山内憲政、足利藤氏を逃走させたことには、たかが城ひとつという話ではなく、大きな政治的な意味があったわけである。
それを氏政は肌身で感じた。
松山城を包囲し、攻撃を仕掛けた。
まずは小手調べである。
その結果、松山城の守りは依然として強固だとわかった。去年の秋に苦しめられた大量の鉄砲は今も松山城にあって、北条軍を城に寄せ付けなかった。
「思った通りだったな」
「まったくです」
氏政の言葉に康光がうなずく。
二人の顔に悲観の色はない。
むしろ、満足げである。
松山城の守りが堅いということは、岩付城が手薄だということなのである。松山城を死守するために、太田資正は自分の兵力を割いて松山城に送ったからだ。
だから古河城の救援に赴くこともできなかったのであろうし、今現在、危機に瀕している葛西城を助けることもできないであろう。
氏政とすれば、それが確かめられれば十分なのである。すぐさま葛西城を攻めている氏康に使者を送り、松山城の現況を伝え、資正が岩付城から動くことはなさそうだという見通しも付け加えた。
それを知った氏康は全力で葛西城を攻撃し、援軍の来る望みのない葛西城に降伏勧告を行った。降伏すれば城兵の命を助けるが、拒否すれば皆殺しにするという二者択一の選択を突きつけたのだ。
四月二十四日、この降伏勧告を受け入れ、葛西城は落ちた。
氏康の思惑通り、武蔵の失地回復は順調に進んだ。
次は、いよいよ松山城攻略である。
武田信玄と共に松山城を攻め落とし、上野を取り戻すのだ。
当然、長尾景虎は黙っていないだろうから、武田と北条の連合軍が長尾軍と決戦することになる。
こうして、日本の戦史において有名な松山城攻防戦の最終章が幕を開ける。
八
葛西城を落とした後、氏康は次の攻略目標を松山城に定め、着々と攻撃準備を進めた。
松山城の包囲を続け、人の出入りを許さないようにした。城の守りは堅固だが、城兵の数はそれほど多くないから、北条軍の包囲網を突破して外部の味方に連絡できないようにし、食糧や武器の補給も許さなかった。
総攻撃を始めるのは武田信玄が合流する秋以降と決めていたから、その時期を目処に松山城周辺に兵が集まるように命令を下している。その命令に従って、各地から続々と兵が集まり、城を包囲する北条軍の数は日毎に増えた。
十月には北条軍は三万を超えるほどの大軍になっている。これを指揮するのは氏政で、それを北条綱成が補佐した。
氏康自身がようやく腰を上げ、小田原を出たのは十一月の初めである。
当然ながら、松山城の上杉憲勝と岩付城の太田資正は強い危機感を抱き、越後の長尾景虎に越山を要請した。
景虎も氏康の動きには注意を払っている。
だが、それ以上に武田信玄の動静を気にしている。
風間党を中心とする北条氏の諜報網の優秀さはよく知られているが、長尾氏も風間党ほど優秀ではないにしろ、数多くの忍びを抱えている。彼らの報告で、間もなく信玄も出陣すると景虎にはわかっている。
景虎がすぐに動こうとしなかったのは、思うように兵が集まらないからである。
長尾軍は、去年の川中島の激戦の痛手から、まだ十分に回復していないのだ。
手をこまねいているわけにもいかず、景虎は安房の里見氏に使者を送った。武蔵に兵を出し、資正と協力して北条軍の背後を脅かしてほしいという依頼である。この種の依頼を一年前にはしていないから、景虎自身、焦りを感じていたのであろう。
実際、氏康が動員した三万という兵力は、この当時の北条氏の限界に近いほどの大軍である。領国から兵を掻き集めたのだ。何が何でも松山城を落としてやるという氏康の意気込みの表れであった。その意気込みが景虎の焦燥を生んだ。
更に景虎を驚かせたのは、氏康と歩調を合わせるように上野に進軍してきた武田軍が二万を超える大軍だったことである。
川中島の痛手から回復していない長尾軍とは対照的に武田軍はすでに完全に立ち直っていたのだ。
十一月中旬、北条軍と武田軍が合流した。両軍合わせて五万五千という途方もない大軍である。これだけの大軍が、氏康の小田原城や景虎の春日山城と比べれば、哀れなほど小さな城に過ぎない松山城を囲んだ。
武田軍が到着すると、早速、氏康は氏政と二人で、信玄と嫡男・義信を案内した。城を包囲する北条軍の陣地を見て回り、武田軍の配置を相談した。
「すでに派手に戦をなさったようですな」
松山城を望見しながら、信玄が言う。
最も外側にある堀は埋められてしまい、その向こうにある柵もなぎ倒されている。柵の内側にあった外曲輪は焼け落ちている。そのあたりの様子から判断すれば、北条軍がかなり押し込んでいるように見える。
「いいえ、そういうわけでは......」
氏康は歯切れが悪い。
氏康が到着する以前、ひと月ほど氏政と綱成が城を囲んでいた。
氏康の指示は城から誰も出してはならぬ、誰も城に入れてはならぬ、というもので、城を攻めろとは命じていない。城攻めは武田軍と合流してから開始するつもりだったからである。
しかし、根っからの猛将である綱成が敵を前にして黙っていられるはずがない。
「攻めろとは命じられておりませぬが、攻めてはならぬとも命じられておりませぬ。つまり、われらに任せるということでしょう」
綱成は氏政の尻を叩いて、すぐさま攻撃を始めた。
その結果、松山城の外曲輪を焼き払い、城兵を追い込むことに成功した。
氏康がやって来たとき、綱成は鼻高々に自慢したが、氏康は苦い顔をしただけで、少しも誉めなかった。
なぜなら、城の姿は見苦しくなったものの、それ以外に大した戦果はなかったからである。見た目が変わっただけで、城の防御力そのものは、まったく落ちていないのだ。
氏康が見栄を張る男であれば、外曲輪を焼き払ったことを得意げに信玄に話しただろうが、生憎、氏康は、そういう男ではない。正直に話した。
「ほう、そうですか。相変わらず、鉄砲に苦しめられていますか」
信玄がうなずく。
城方の防御力の要は大量の鉄砲である。
鉄砲を何とかしない限り、曲輪をひとつやふたつ奪ったくらいでは大勢に変化はない。
「その方は、どう思うぞ?」
信玄が義信に訊く。
義信は、石橋を叩いても簡単に渡らないという信玄に比べると、血の気が多く、猪突猛進型の武将である。父の信玄より、祖父の信虎の血を色濃く受け継いでいるのかもしれない。
「この城を攻めたことがありませぬ故、どれほど手強いかよくわかりませぬ」
と、義信は至極、真っ当な考えを述べる。
「ならば、攻めてみるかのう」
信玄は氏康に顔を向け、
「いかがでありましょう。五千ほどの兵で一度攻めてみたいと思うのですが」
「ふうむ......」
内心、
(まともに攻めかかれば、鉄砲や弓矢の餌食になるだけなのだが......)
と思っているが、せっかく援軍に駆けつけてくれた信玄の顔を潰すわけにはいかないので、
「ならば、そうしましょう」
と、氏康はうなずく。
早速、準備を始め、十一月末、武田・北条の先鋒五千が松山城に攻めかかった。本城の周りにある小さな曲輪は呆気なく奪うことができた。
ここまではよかった。
悲劇は、その後に起こった。
本城は柵ではなく、石垣に囲まれているから、柵のように押し倒すことはできない。よじ登らなければならない。
城方は、石垣を登ってくる武田兵と北条兵を石垣の上から鉄砲で狙い撃ちにした。上から下に向けて、それほど離れていない敵を撃つのだから百発百中である。
この日の戦いについては、いくつかの軍書に書き残されているが、いずれも武田軍と北条軍、両軍合わせて四百人以上が死んだと記されている。五千人で攻めて、四百人が死んだとすれば壊滅的な死亡率であり、にわかには信じがたいが、死者ではなく、死傷者が四百人だとすれば十分にあり得る。それだけの被害を相手に与えうるほど大量の鉄砲が松山城にあったからである。
わずか半日でこれほどの損害を被るとは信玄も予想していなかったらしく、この攻撃を最後に、松山城を正攻法で攻めることはなくなる。
五万五千の兵が、三千の兵が籠城する松山城を攻めあぐねて立ち往生する......氏康の脳裏には十六年前の河越の戦いが甦ったかもしれない。そのとき追い込まれていたのは氏康の方だった。今度は氏康が攻める側である。
凡庸な大将が指揮していれば、十六年前のように大軍を擁する攻め手が自壊することもあり得るかもしれない。
しかし、今度は違う。
攻め手を指揮するのは武田信玄と北条氏康である。
日本史に名を残すほどの名将だ。
名将と凡将の違いは何か?
突き詰めれば、引き出しの多さと思考の柔軟さということになるであろう。
正攻法の城攻めが失敗するや、すぐさま信玄は、
(まともなやり方で落とすことはできぬ)
と考え、まともでないやり方をすることにした。
すでに述べたが、この松山城攻防戦では、それまでになかった特徴的な戦法が現れた。
ひとつには軍用犬の活用であり、ひとつには大量の鉄砲の投入である。
三つ目、ここで信玄が捻り出したのは、土木工事によって城を落とそうという独創的な戦術であった。
Synopsisあらすじ
一代にして伊豆・相模を領した偉大なる祖父・北条早雲、その志を継いだ父・氏綱。一族の悲願・関東制覇を期する氏康の傍らには、祖父が育てた軍配者・小太郎がいた! 河越夜襲で劇的勝利を収めた氏康を待つものは……北条三代目の生涯を描く人気シリーズ第四弾。
〈北条サーガTHE WEB〉http://www.chuko.co.jp/special/hojosaga/
Profile著者紹介
1961年、北海道生まれ。98年に第4回歴史群像大賞を受賞した『修羅の跫』でデビュー。「SRO 警視庁広域捜査専任特別調査室」「生活安全課0係」シリーズを始めとする警察小説から、『早雲の軍配者』『信玄の軍配者』『謙信の軍配者』の「軍配者」シリーズや『北条早雲』全5巻などの時代・歴史小説まで、幅広いジャンルで活躍している。
Newest issue最新話
- 第四十九回2024.05.27
Backnumberバックナンバー
- 第四十八回2024.05.20
- 第四十七回2024.05.13
- 第四十六回2024.05.07
- 第四十五回2024.04.26
- 第四十四回2024.04.22
- 第四十三回2024.04.15
- 第四十二回2024.04.08
- 第四十一回2024.04.01
- 第四十回2024.03.25
- 第三十九回2024.03.18
- 第三十八回2024.03.11
- 第三十七回2024.02.26
- 第三十六回2024.02.19
- 第三十五回2024.02.13
- 第三十四回2024.02.05
- 第三十三回2024.01.29
- 第三十二回2024.01.22
- 第三十一回2024.01.15
- 第三十回2023.12.25
- 第二十九回2023.12.18
- 第二十八回2023.12.11
- 第二十七回2023.12.04
- 第二十六回2023.11.27
- 第二十五回2023.11.20
- 第二十四回2023.11.13
- 第二十三回2023.11.06
- 第二十二回2023.10.30
- 第二十一回2023.10.23
- 第二十回2023.10.16
- 第十九回2023.10.10
- 第十八回2023.10.02
- 第十七回2023.09.25
- 第十六回2023.09.19
- 第十五回2023.09.11
- 第十四回2023.09.04
- 第十三回2023.08.28
- 第十二回2023.08.21
- 第十一回2023.08.14
- 第十回2023.08.07
- 第九回2023.07.31
- 第八回2023.07.24
- 第七回2023.07.18
- 第六回2023.07.10
- 第五回2023.07.03
- 第四回2023.06.26
- 第三回2023.06.19
- 第二回2023.06.12
- 第一回2023.06.07