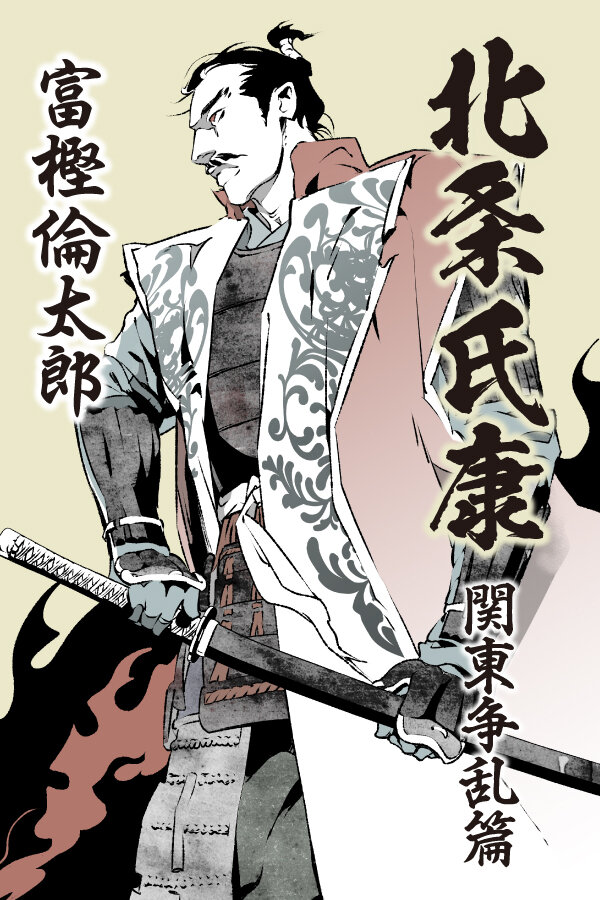北条氏康 関東争乱篇第四十八回
九
防備の固い城を攻め落とすには、基本的にふたつの方法しかない。
ひとつは、城を厳重に包囲し、水と食糧が尽きるのを待ち、城方が渇きと飢えに苦しんで音を上げるのを待つことだ。攻撃するわけではないので、兵の損失を抑えることができるし、時間に余裕があるときは最も有効な方法である。
しかし、今はふさわしいやり方ではない。時間をかけると長尾軍が援軍に駆けつけるからである。
もうひとつは力攻めである。
強大な火力を持つ大砲があれば、大砲で城壁を破壊することができる。
だが、それが可能になるのは、ずっと先の話で、この時代には、そんな威力のある大砲はない。
柵があれば引き倒し、堀があれば渡り、壁があればよじ登らなければならないのである。
信玄と氏康は、最初にこれをやった。
五千の兵で侵入を試みた。
結果は散々であった。
鉄砲に狙い撃ちされ、多くの死傷者を出した。
愚かな者が指揮を執っていれば、何度も同じ攻撃を繰り返し、いたずらに兵を減らして自滅したであろう。他に方法がないから、無謀な突撃をするしかないのだ。
信玄の非凡なところは、どんなやり方であろうと兵が城に侵入すればいいのであって、わざわざ鉄砲の待ち構えている城壁をよじ登る必要はないと考えたことである。これが思考の柔軟さである。
(穴を掘らせよう)
と考えた。
城の外から掘り進め、城内に続く坑道を作ろうとした。
それまでこんなことを考えた武将はいない。
古代中国には実例があるが、日本にはない。万里の長城を造営できるほど優れた土木工事技術のある国だから可能なのだ。
信玄には、その技術がある。
古来、甲斐は貧しい山国である。田畑に適した土地が少なすぎるため、普通に農耕に励んでいるだけでは食っていくことができない。天候不順で凶作になると、たちまち飢饉が発生した。
信玄の父・信虎の時代から武田氏は年中行事のように他国への侵略を繰り返したが、これは信虎が戦争好きだったというわけではなく、他国から奪わなければ甲斐の民が食えないという理由である。信虎の侵略は、食糧調達の手段だったのだ。
北条や今川といった力のある大名が治めている国と戦うのは容易ではないから、信虎と信玄は、さほど力のない豪族たちが乱立してしのぎを削っている信濃に目を付けた。甲斐に比べるとはるかに肥沃な国である。
信濃における征服地が広がるにつれて甲斐は豊かになっていき、川中島の激戦で長尾軍を追い払うことで最終的に信濃の領国化に成功した。
だが、征服地ではなく自国となれば、もはや、収奪ばかりはできない。甲斐の民も信濃の民も同じように慰撫(いぶ)する必要があるからだ。
政治家としての信玄の凄みは、農業だけに頼っているのでは、いずれまた行き詰まると理解していたことで、それ故、征服戦争を続けながら、金山の開発に手をつけた。農業は天候に左右されるし、それは人間の力ではどうにもならないが、地中から金を掘り出すことに天候は関係ない。
運にも恵まれた。豊かな鉱脈を持つ金山が次々に見付かったからである。信玄の時代に掘り出された金は甲州金と呼ばれ、武田氏を支えた。徳川幕府が成立し、幕府の手で貨幣制度が確立された後も甲斐地方では甲州金が流通していたというから、江戸時代になっても、まだ金の産出が続いていたわけである。
金山開発に熱心だったおかげで、武田氏には当時としては最先端の土木技術が蓄積されており、多くの技術者も抱えている。
松山城攻めを遠くから眺め、味方の兵が次々と鉄砲で撃たれるのを見て、
「坑道を掘らせてみましょう」
と傍らの氏康に信玄が言ったのは、ごく当たり前の発想であった。
しかし、氏康と氏政は大いに驚いた。
「そんなことができるのですか」
「できます」
信玄が自信たっぷりにうなずく。
「まずは試してみましょう」
十
結果から言えば、坑道を掘ることで城内に侵入しようという試みは失敗した。
坑道そのものは順調に掘り進むことができた。
このあたり、武田の金掘衆の持つ技術力の凄さであろう。
だが、城方に知られた。
それも当然で、坑道を掘り進めるときには大きな音が周辺に響き渡るし、掘り出した土を外に運び出す必要がある。坑道の周辺では作業に関わる多くの者たちが忙しげに立ち働いている。その様子を見れば、
「地面に穴を掘って城に攻め込む気だぞ」
と誰にでもわかる。
敵が真正面から城に攻めかかってくるのなら鉄砲や弓矢で狙えばいいが、地面からやって来るのでは、そうはいかない。城内に動揺が広がった。
「心配することはない」
と言った者がいる。
籠城しているのは兵だけではない。
僧侶もいる。
戦死した兵を弔うという役割を担っている。
その僧侶の一人が漢籍に詳しく、
「敵が地中に穴を掘って攻めてくるときは、こちらから向かい穴を掘ればいい」
と言ったのである。
中国では、土木工事で城を攻め落とすやり方は、それほど珍しくないらしく、いくつもの事例が兵書に載っているという。
こういうことである。
敵がどのあたりに坑道を掘り進めているかがわかったら、それに向かって城からも坑道を掘っていく。どこかでふたつの坑道がぶつかることになるが、そのとき城方から大量の水を流せば、敵の坑道は水没し、敵兵は溺れ死ぬことになる。
これがうまくいった。
城方には武田の金掘衆のような土木技術はないが、地面に穴を掘るくらいのことはできる。武田方の坑道の在処について、大体の見当を付けて穴を掘っていき、坑道にぶつかれば、そこから大量の水を流し込んだ。
金掘衆にとって不運だったのは、松山城が崖の上にあったことである。平地にあれば、地面と平行に坑道を掘っていくが、自分たちより上にある城だから、坑道を上に向かって掘っていくことになる。上から水を流されれば、奔流となって坑道を流れ下り、金掘衆を押し流した。平地の坑道であれば、そうはならなかったはずである。
「どうにもうまくいきませんな」
氏康には信玄の失敗を責めるつもりはまったくない。坑道を拵えたのも信玄だし、坑道で溺れ死んだのも信玄の金掘衆なのである。北条軍は傍観していたに過ぎない。
「そうですな」
何事か思案しながら、信玄がうなずく。
「まだ続けますか?」
「いいえ、やめましょう」
金掘衆の損失を惜しんだ。兵を補充するのはそう難しくないが、金掘衆はそうはいかない。技術を身につけるのに時間がかかるのだ。
土木工事によって松山城を落とすことに成功していれば、日本の軍事史上における輝かしい事例として記憶されることになったであろうが、結果的に失敗した。
しかし、城を落とすには、力攻め以外の方法もあることを示したという意味で画期的だと言っていい。
実際、後に豊臣秀吉は土木工事の活用で赫々(かっかく)たる戦果を上げることになる。清水宗治の高松城を人工湖で水没させたことが最も有名である。
「もう一度、城を攻めてみましょう」
そう信玄が言ったから氏康は驚いた。
「しかし......」
「もちろん、ただ力攻めしても鉄砲の餌食になるだけでしょう。何らかの工夫が必要です」
政治家としても武将としても、多くの引き出しを持つのが信玄の特徴である。思考が柔軟なので、役に立つと判断すれば、新たなやり方を取り入れることを躊躇わないし、古いやり方も平気で捨てる。
実は金掘衆に坑道を掘らせながら、信玄はある実験をしていた。
最初に五千の兵で松山城を力攻めしたとき、戦況を眺めながら、信玄は一人の兵に注目した。
おかしな格好をしていた。何かを背負っているのである。遠眼鏡で見ると、竹の束であった。
(何をするつもりだ?)
見ていると、その兵は空から矢が降ってくると、パッと地面に伏せる。矢は竹の束に当たり、兵は無傷である。立ち上がると、城壁に取り付いて、よじ登ろうとする。城方は上から鉄砲で狙い撃ちにする。周りの兵がばたばたと城壁から落ちるが、その兵だけは落ちない。玉は当たるのだが、どうやら竹の束が防いでいるらしい。竹が玉を撥ね返し、貫通しないのである。その兵は途中で落下したが、怪我をしたからではなく、足を滑らせたせいである。
戦いの後、信玄はその兵を呼んだ。
話を聞くと、その男の村では、男たちが兵として駆り出されるとき、昔から竹の束を背負っていく風習があるのだという。矢から身を守るためである。
普通は、身を守るために楯を持つが、男の村は貧しいので立派な楯を拵えることも買うこともできず、そのあたりに生えている竹を切ってきて、それを束ねて背負っているだけなのである。
信玄の凄みは、
(竹は鉄砲の玉を撥ね返すらしい)
と見抜いたことだ。慧眼であろう。
早速、竹を使って、兵の身を守る道具を拵えるように命じた。竹の束を背負うだけでなく、そこに様々な工夫をしてみよ、と付け加えた。
できあがったのが竹束の楯である。竹がばらけないように紐でしっかり結びつけただけの、ごく簡単なものだ。これを楯にして城に近付くのである。楯として手に持つだけでなく、背中にも竹束を背負う。空から降ってくる矢を防ぐためだ。
これを大量に拵えて兵たちに持たせ、信玄と氏康は城攻めを始めた。
子供でも思いつくような単純なものだが、驚くほど効果的で、死傷者が大きく減った。皆無とは言えなかったのは、時たま、竹と竹の間を抜ける玉にやられる兵がいたからである。
ちなみにこの竹束の楯は、戦国時代が終熄するまで、鉄砲を防ぐ最も有力な道具として重用されることになる。軍事史上における信玄の功績のひとつと言っていい。
竹束が登場してから、城方は劣勢になった。
最大の打撃は水の手を切られたことである。
それまでは水の手に近付く武田や北条の兵たちを鉄砲で狙い撃ちにしていたが、竹束のせいでそれができなくなった。目の前でみすみす水を止められてしまった。食糧はまだ豊富にあるが、水が乏しくなり、城方の士気が急激に落ちた。
武田と北条の連合軍が松山城を包囲して、すでに三ヶ月が経っている。わずか三千の兵が五万の連合軍と互角に渡り合ってきたのである。
この三ヶ月の持つ意味は大きい。
長尾景虎の要請に応え、安房の里見氏は援軍を送ることを決め、その軍勢が安房から上総、下総へと北上を続けている。
松山城を落とすために氏康が大軍を招集したため、北条氏の領国では、どの地域でも守備兵が不足している。里見軍が快進撃を続けているのは、里見軍が強いからではなく、里見軍を迎え撃つ北条軍がいないせいである。今の勢いを保つことができれば、里見軍は間もなく武蔵に入るであろう。岩付城の太田資正と合流すれば、氏康と信玄にとって大きな脅威になるのは間違いない。
景虎自身、すでに越山して関東に入っている。
上野に入って、そのまま南下して松山城に向かわなかったのは、まだ兵が少なすぎるからである。景虎が率いているのは八千で、これでは、いかに戦上手の景虎でも五万以上の敵に決戦を挑むことはできない。
上野から下野に入って、関東管領として各地の豪族たちに参集を命じた。景虎に怖れをなし、豪族たちは慌てふためいて駆けつけた。すぐに景虎の兵力は一万を超えた。
(二万はほしい)
というのが景虎の本音だ。
二万の兵があれば、たとえ敵が五万であろうと野戦ならば互角に戦う自信がある。
氏康や信玄と互角に渡り合っているところに里見軍と資正が駆けつけて氏康と信玄の背後を衝けば、確実に勝利が手に入るというのが景虎の胸算用である。
決して荒唐無稽な話ではない。
景虎は、北信濃を巡って信玄と勝ったり負けたりを繰り返し、一度は氏康を小田原城に追い詰めている。しかも、関東管領である。その圧倒的な武力と威光、声望は関東全域に鳴り響いている。
松山城に向かって進軍し、関東の武士たちに檄を飛ばせば、動揺する者も多いであろうし、今は氏康に与(くみ)している者たちの中からも寝返る者が出てくるであろう。
つまり、氏康と信玄とすれば、景虎がやって来ないうちに何としても松山城を落とさなければならないわけである。
(長尾景虎との野戦だけは避けたい)
これは信玄と氏康の本音なのだ。
竹束の楯で鉄砲を防ぐという妙案を信玄が思いつかなければ、松山城は難攻不落のままであったろうし、そうなれば、否応なしに景虎との野戦に引きずり込まれてしまったはずである。
歴史に、もしも、というのは禁句だが、敢えて想像をたくましくすれば、もしも松山城近郊で景虎、信玄、氏康の三者による一大決戦が行われていれば、その後の日本の歴史が大きく変わったことは間違いない。現実の歴史においても、この三者は信長の天下統一に大きな影響を与えたのだから、例えば、この決戦で景虎が勝利すれば、信長が太刀打ちできないほどの強大な力を手に入れて景虎が天下人になった可能性は高い。
逆に景虎が敗れれば、信玄の力が増し、天下人になる道を着実に進んだかもしれない。
歴史には、時として、歴史の流れを大きく変えるような一瞬があるものだ。
古くは大化の改新がそうであろうし、近くは桶狭間の奇襲がそれに当たる。後の時代であれば、関ヶ原の戦いや鳥羽伏見の戦いがそうであろう。
この松山城攻防戦の最終局面でも、その歴史を動かす一瞬が現れようとしている。
景虎が現れるまで松山城は持ちこたえることができるのか否か。それによって歴史が変わる。
現実の戦場においては、竹束の楯のせいで水の手を切られた城方が苦しんでいる。水なしで、あとどれくらい持ちこたえることができるか、その一点に松山城を巡る戦いの焦点は絞られた。
籠城戦において城方が追い詰められたとき、どれほどの耐久力を発揮できるかは、突き詰めて言えば、城主の器量にかかっている。
城兵が城主を信頼して一枚岩にまとまっていれば、たとえ泥水を啜ってでも城を守り抜こうとするものだ。
逆に、城主に人望がなければ、積み木細工が崩れるように呆気なく籠城戦は終わることになる。
この松山城攻防戦の勝敗の帰趨は、七沢七郎という、ほんの少し前まで世間にまったく知られていなかった男、今では上杉憲勝というもっともらしく名乗らされている男の器量に委ねられたわけである。
つまり、歴史を変えるかもしれないこの重大局面で、最も重要な役回りを演じるのは景虎でも信玄でも氏康でもなく、上杉憲勝というごく平凡な、軍事的にも政治的にも何の取り柄もない男なのである。
Synopsisあらすじ
一代にして伊豆・相模を領した偉大なる祖父・北条早雲、その志を継いだ父・氏綱。一族の悲願・関東制覇を期する氏康の傍らには、祖父が育てた軍配者・小太郎がいた! 河越夜襲で劇的勝利を収めた氏康を待つものは……北条三代目の生涯を描く人気シリーズ第四弾。
〈北条サーガTHE WEB〉http://www.chuko.co.jp/special/hojosaga/
Profile著者紹介
1961年、北海道生まれ。98年に第4回歴史群像大賞を受賞した『修羅の跫』でデビュー。「SRO 警視庁広域捜査専任特別調査室」「生活安全課0係」シリーズを始めとする警察小説から、『早雲の軍配者』『信玄の軍配者』『謙信の軍配者』の「軍配者」シリーズや『北条早雲』全5巻などの時代・歴史小説まで、幅広いジャンルで活躍している。
Newest issue最新話
- 第四十九回2024.05.27
Backnumberバックナンバー
- 第四十八回2024.05.20
- 第四十七回2024.05.13
- 第四十六回2024.05.07
- 第四十五回2024.04.26
- 第四十四回2024.04.22
- 第四十三回2024.04.15
- 第四十二回2024.04.08
- 第四十一回2024.04.01
- 第四十回2024.03.25
- 第三十九回2024.03.18
- 第三十八回2024.03.11
- 第三十七回2024.02.26
- 第三十六回2024.02.19
- 第三十五回2024.02.13
- 第三十四回2024.02.05
- 第三十三回2024.01.29
- 第三十二回2024.01.22
- 第三十一回2024.01.15
- 第三十回2023.12.25
- 第二十九回2023.12.18
- 第二十八回2023.12.11
- 第二十七回2023.12.04
- 第二十六回2023.11.27
- 第二十五回2023.11.20
- 第二十四回2023.11.13
- 第二十三回2023.11.06
- 第二十二回2023.10.30
- 第二十一回2023.10.23
- 第二十回2023.10.16
- 第十九回2023.10.10
- 第十八回2023.10.02
- 第十七回2023.09.25
- 第十六回2023.09.19
- 第十五回2023.09.11
- 第十四回2023.09.04
- 第十三回2023.08.28
- 第十二回2023.08.21
- 第十一回2023.08.14
- 第十回2023.08.07
- 第九回2023.07.31
- 第八回2023.07.24
- 第七回2023.07.18
- 第六回2023.07.10
- 第五回2023.07.03
- 第四回2023.06.26
- 第三回2023.06.19
- 第二回2023.06.12
- 第一回2023.06.07