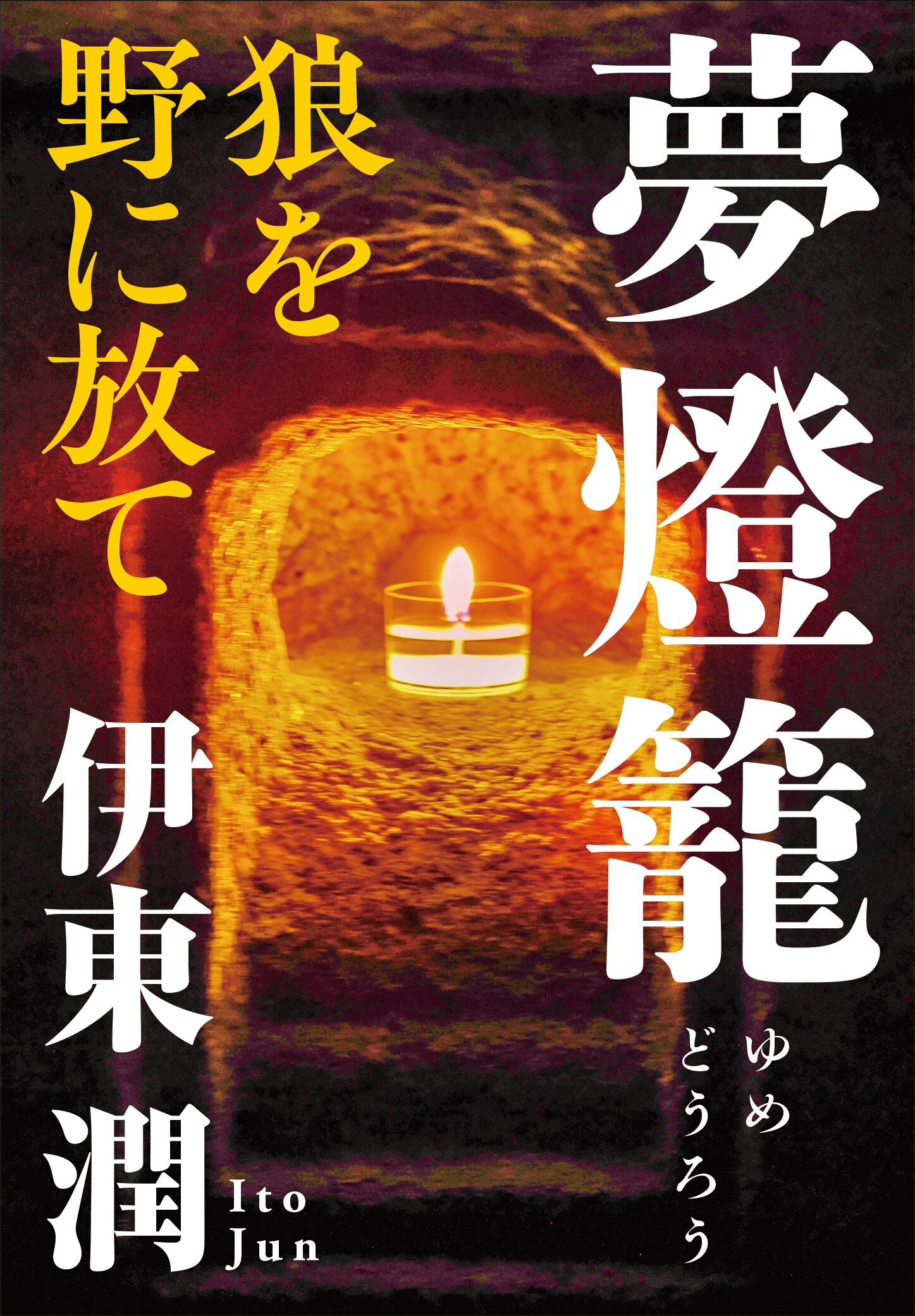夢燈籠 狼を野に放て第15回
二
その後も、株の取得は順調に進んだ。とくに留吉が手腕を発揮したということもないが、面白いように実績が上がるので、横田は上機嫌で、留吉が顔を出す度にキャバレーに誘った。
岩井は横田産業の一室を借り、株の売買に関する事務手続きを行っていた。つまり留吉がまとめた話を実務面で進めていくのが、岩井の仕事になる。
小口株主が大半だったが、次から次へと売買を成立させた留吉は、昭和二十五年も押し迫った頃、ある株主の許を訪れた。
――目黒区緑ヶ丘か。この辺りだな。
尾津のいた新宿とは対照的に、そこは閑静な住宅街だった。近くに教会があるのか、讃美歌が聞こえてくる。それが、この街にやけに似つかわしい。
――平岡家か。ここだな。
表札を確かめ、ようやく探し当てた株主の家の呼び鈴を鳴らすと、お手伝いさんらしき人が出てきた。
用件を述べると、「少しお待ち下さい」と言って中に戻っていった。
しばらく待っていると、突然、若い男が出てきた。
「親父は今、不在にしています。出直して――、あっ」
「あっ」
その顔を見た留吉は驚いた。それは相手も同じらしく、互いに顔を見合わせながら言葉が出なかった。
「ま、まさか、三島さんですか」
「そうです。あなたはもしや――」
留吉が名乗ると、三島の顔に笑みが広がった。
「親父は不在ですが、まあ、お上がり下さい」
三島が居間に通してくれたが、留吉は事情が分からない。三島はお手伝いさんに、コーヒーを出すよう指示している。
「いやー、驚きました。『末げん』でお会いした方ですね」
「その通りです。こちらこそ、突然のことに言葉もありません」
「全くです。御縁というのは不思議ですね。いや、実に不思議だ」
「暗がりだったのに、覚えていていただき恐縮です。あらためまして坂田留吉です」
「三島由紀夫、いや、ここでは平岡公威(きみたけ)です」
二人は改めて挨拶を交わした。
「どうしてこちらにおられるんですか」
「ここが私の家なんですよ。厳密には、父の家に同居させてもらっています」
それを聞いて、ようやく留吉は納得した。
「そうでしたか。それは失礼しました」
「いいんです。それで、今日はどんなご用で」
留吉が事情を説明する。
「なるほど、そういうことですね」
「それにしても、お父上が白木屋の株をお持ちというのも奇遇すぎますね」
「そんなこともありません。父の梓(あずさ)は、かつて農商務省に勤めていましてね。その時に勧められて買ったのでしょう」
「ああ、なるほど。それで納得がいきました」
「株の売買について、僕は門外漢なので何とも言えません。あらためて父に会っていただけますか」
「もちろんです。次回は事前に電話させていただき、約束を取り付けてからまいります」
「それがよろしいでしょう」
用件も済み、辞すのによいタイミングだったが、ちょうどコーヒーが運ばれてきた。
三島が「お急ぎでなければ、コーヒーを飲んでいって下さい」と言うので、その言葉に甘えることにした。
三島が留吉の経歴を聞いてきたので簡単に説明すると、「ほう、満州ですか。僕も行きたかったな」と言って、いかにも悔しそうな顔をした。
「でも、満州では苦労しました」
「今となっては、よい経験だったのではありませんか」
「まあ、そうとも言えますが、その時は辛かったです」
「それは申し訳ない」
留吉は三島と同じ文学畑ということで、中原中也のことを思い出した。
「あっ、そうだ。かつて私は中原中也氏と知り合いだったんです」
「ああ、そうでしたか。僕は会ったことはないんですよ」
「文芸の世界は狭いようで広いんですね」
「というか、戦前、私は学生でしたからね」
三島と中原は十八歳も差がある上、中原が亡くなった時、三島は十二歳だったので、当然と言えば当然だった。
「そうでしたね。これは失礼しました」
その後、留吉は読んだばかりの『仮面の告白』について語ると、三島はうれしそうに裏話などしてくれた。
ちょうどコーヒーも飲み終わったので、執筆の邪魔をしてはならないと思い、留吉は席を立った。
「では、改めまして」
「そうですね。私はここで親と同居しているので、次に来た時にでも、またお話ししましょう」
そう言うと、三島は玄関まで見送ってくれた。
その後、父の梓と何度か会い、株の売買の話がついた。梓は五千株ほどしか持っていなかったので、少し色を付けただけで売却に同意してくれた。
そして訪問の度に、留吉は三島と歓談し、親交を深めていった。
【第15回】
三
横田の計画は順調に進んでいた。昭和二十六年いっぱい地道に株を買い集めたことで、横田の許には公開買い付けをしなくてもよいだけの株が集まっていた。
横田は留吉の仕事ぶりを評価し、経営企画室長の肩書を与えた。しかも歩合は百株あたりいくらと決まっているので、昭和二十六年一年だけで、留吉の年収は普通の勤め人の三倍から四倍になった。
こうしたことにより、業績もさっぱりで不人気株の典型だった白木屋の株価は、徐々に上がり始めた。翌昭和二十七年(一九五二)上半期に百円に乗せた同株は、九月には百六円をつけ、これに気づいた仕手筋の買いが入り始め、それに個人株主が追従することで提灯がつき(追随者が増えること)、年末には百八十円をつけた。
そこからは勢いだった。昭和二十八年(一九五三)初頭に二百円の大台に乗せると、あっという間に三百円まで暴騰した。
だが白木屋の幹部は、まだ買い占めに気づいていなかった。というのもこの頃、株式の大ブームが到来し、多くの企業が暴騰を続けていたからだ。白木屋の経営陣は、まだ業績は上向いてはいないものの、経営努力が認められ、さらに消費ブームの到来を予見しての暴騰だと思い込んでいた。そして十二月二十八日の大納会で、白木屋の株は三百六円をつけた。
これにより、さすがの白木屋経営陣も、買い占めが行われていることに気づいた。だが、白木屋は勘違いをしていた。関西系の大丸百貨店が関東進出を狙い、阪急グループの小林一三(いちぞう)系の買い占めだと思ったのだ。
この時代、買い占めが行われていても、一年に一度の名義の書き換えまで、誰が行っているかは分からない。そのため様々な憶測を生んでいたが、それがいよいよ明らかになる日が来た。
二十九年一月末、株主名簿が締め切られ、名義の書き換えが行われた。
横田名義で二十万二千株、横田産業名義で五十二万六千株、さらに佐藤哲名義で三十万株といった具合で、買い占めの犯人が誰か明らかになった。しかも横田系だけで百万株を超えているのだ。これは、白木屋の発行済み株式数の四分の一を超える。
これに対して白木屋サイドは、鏡山忠男社長が十万四千株、渡辺建常務が六千六百株、その他の取締役を合計しても三万株ほどで、さらに株式持ち合いで、朝日生命が四十万株、東京生命が十二万株持っている程度で、とても太刀打ちできる株数ではなかった。
横田の作戦勝ちだった。
経済・株式系の新聞社を集めた記者会見で、横田は演説をぶった。
「戦後十年近く経ち、日本経済は成長を遂げてきました。しかしまだ序の口です。本物の成長はこれからです。この国は、日本人自身が信じられないほどの経済大国になるでしょう。しかしながら、いまだ戦前の残滓(ざんし)を引きずるようにして生き残っている企業が多数あります。それらの企業は銀行や保険会社に株を持ってもらい、株価がわずかに上昇することでお茶を濁し、一切の経営努力をしません。しかし同じ分野に新興企業が参入しようとすると、彼らは血統や学閥で手を組み、新たな者たちに門を閉ざします。これでは日本経済に成長の余地があっても、成長の限界が見えてきます。そうした企業には、お灸をすえる必要があります」
横田が手振り身振りで熱弁を振るう。
「そうした企業には、戦前戦中と同じ顔ぶれの経営陣が残っています。彼らがいる限り、経営は何も変わりません。それを変えていくには、勢いのある新興企業が大株主となり、経営に加わることしかありません」
トレードマーク蝶ネクタイにタキシード姿の横田は、フラッシュがたかれる中、にこやかに続けた。
「白木屋は、そうした企業の典型です。その仕入れた商品は劣悪で高価。しかも流行からは一歩も二歩も遅れています。陳列の仕方も購買意欲をかき立てるものではなく、ただ漫然と商品を並べているだけです。しかもレストランときたら、単にお客様の腹を満たすためだけに存在し、お客様に『おいしい』と言ってもらえるような代物ではありません。最もひどいのがおもちゃ売り場です。昭和七年の火事は四階のおもちゃ売り場が火元でした。そこにはセルロイド製のおもちゃが大量に売られていたからです。その後、セルロイド製おもちゃの一掃運動が起こり、町中のおもちゃ屋さんでも、できる限りセルロイド製は置かないようになりました。白木屋もその例に漏れず、火事の直後は置きませんでしたが、いつの間にかセルロイド製おもちゃが復活し、火事の前と変わらぬ状態に戻りました。これは火事を全く反省していないことの証左です。しかも防火設備も火事の後に導入した火災報知器があるだけで、三越では設置が終わったスプリンクラーも設置されていません」
スプリンクラーとは天井に設置され、火災発生時に大量に散水できる装置で、この頃は設置費用が高く、まだ普及していなかった。
実は、このスプリンクラーが後に横田の運命を左右することになるが、それはまた別の話になる。
「このように白木屋の経営陣は漫然と経営しているだけで、お客様のことを考えているとは言えません。それゆえ今こそ経営陣を刷新すべきです」
期せずして拍手が起こった。記者たちが拍手するなど、こうした会見では珍しいことだが、横田の説得力ある弁舌に、記者たちも圧倒されたのだろう。
拍手の中、横田は何度も頭を下げながら締めた。
「不肖横田英樹、世のため人のためなら何でもいたします。白木屋の株取得はその序の口にすぎず、これからも産業界に旋風を巻き起こすつもりでおります」
――実に見事だ。
横田マジックとしか表現のしようがない弁舌に、記者たちも打たれたのか、しばし沈黙した後、ようやく席を立ち始めた。
会場で横田の話を聞いていた留吉が控室に行くと、横田は得意満面でオレンジジュースを飲んでいた。
「いやー、疲れた。疲れた」
「見事な記者会見でした」
留吉が空いていた隣に座すと、横田が肩を抱いた。
「これも坂田さんのおかげです」
「いや、私は個人株主から地道に株を集めただけです」
「とんでもない。地道な仕事ができる人ほど貴重です。ただし、これからは大勝負を挑んでいきます」
「大勝負ですか」
「そうです。大株主を味方に付けていくのです」
「そんなことができるんですか」
白木屋の株主は鏡山社長たちの知友たちで、それを切り崩していくのは容易ではない。
「できます。具体的なあてもあります」
「いったい誰ですか」
「日活の堀久作社長です」
留吉は息をのんだ。堀久作といえば立志伝中の人物で、今は日活グループの総帥として映画界の頂点に君臨している。
オレンジジュースを一口飲むと、横田が続けた。
「堀社長も白木屋を買収しようとしています。われわれが手を組めば、白木屋はギヴアップします」
「ということは、堀社長はライバルではないんですか」
「堀さんは物の道理に通じた人です。話せば分かってくれます」
横田は自信満々だった。
「そこでご相談なのですが、坂田さんは、これから私の代わりに横田産業の顔として、様々な財界人と交渉していただきたいんです」
「私が、ですか」
「そうです。これまで見てきたお人柄や実績から、私の代わりができるのは坂田さんしかいません」
「それはありがたいお言葉ですが――」
留吉は京都支店長という肩書から、経営企画室長という肩書に代わっただけだ。その肩書では、財界の有力者たちから見下される恐れがある。
「もちろん、それなりの地位を用意します」
「それなりの地位とは何ですか」
「取締役ではどうですか」
「私が横田産業の取締役ですか」
そうなれば経営責任が発生するので、容易には辞められなくなる。
「次の取締役会で選任します。お引き受けいただけますね」
「いや、待って下さい」
留吉は目の前の仕事に全力投球してきたので、具体的にやりたいことはない。だが、このまま横田の船に乗り込んでしまえば、途中で下りるのは容易ではない気がする。
「実は、岩井さんには社外監査役に就いてもらうことになっています」
監査役会を設置する会社には三名以上の監査役が必要で、そのうち二名は社外監査役で構わない。岩井の場合、金井から引き継いだ顧客があるので、社外という立場を崩せないのだろう。
「岩井は了承したのですか」
「はい。坂田さんは外出が多いので、岩井さんに先に話を持っていったところ、快く了解していただけました」
それでも留吉は、どうかするか考えあぐねていた。
――この話を断ったところで、何かあてがあるわけではない。それなら話に乗ってもよいのではないか。
そう思う反面、横田の考え方についていけない部分もある。
「私の人間性に不信を抱いておいでですね」
「いや、そうではなく――」
「分かっています。私自身、つくづく自分は阿漕(あこぎ)な男だと思っています」
阿漕とは強欲でずうずうしいという意味だが、義理や人情に欠けるという意味もある。
横田がしみじみと続ける。
「だからこそ、正義の人に近くにいてほしいのです。それがお二人なのです」
「どういうことですか」
「私の悪い癖が出てしまいそうになった時、私に諫言(かんげん)していただきたいのです」
「諫言ですか」
「そうです。これから私は、血統や学歴が重視される社会に打って出ます。そうなれば一流の人間にならねばならない。そして横田産業を世界に通用する大企業に育てていきたいのです。そのために、お二人が必要なのです」
――そこまで考えていたのか。
横田の深慮遠謀に、留吉は舌を巻いた。だが、志は高ければ高いほどいい。
――横田を助けるのも運命か。
留吉の決意が凝固し始めていた。
「分かりました。お受けいたします」
「それはよかった。よろしくお願いします」
横田が満面の笑みを浮かべた。
だが留吉は、底知れぬ泥沼に足を踏み入れた気もしていた。
Synopsisあらすじ
戦争が終わり、命からがら大陸からの引揚船に乗船した坂田留吉。しかし、焦土と化した日本に戻ってみると、戦後の混乱で親しい人々の安否もわからない。ひとり途方に暮れる留吉の前に現れたのは、あの男だった――。明治から平成へと駆け抜けた男の一代記「夢燈籠」。戦後復興、そして高度成長の日本を舞台に第2部スタート!
Profile著者紹介
1960年、神奈川県横浜市生まれ。早稲田大学卒業。『黒南風の海――加藤清正「文禄・慶長の役」異聞』で第1回本屋が選ぶ時代小説大賞を、『国を蹴った男』で第34回吉川英治文学新人賞を、『巨鯨の海』で第4回山田風太郎賞と第1回高校生直木賞を、『峠越え』で第20回中山義秀文学賞を、『義烈千秋 天狗党西へ』で第2回歴史時代作家クラブ賞(作品賞)を受賞。
Newest issue最新話
- 第51回2026.02.04
Backnumberバックナンバー
- 第50回2026.02.02
- 第49回2026.01.22
- 第48回2026.01.15
- 第47回2026.01.08
- 第46回2026.01.01
- 第45回2025.12.25
- 第44回2025.12.18
- 第43回2025.12.11
- 第42回2025.12.04
- 第41回2025.11.27
- 第40回2025.11.20
- 第39回2025.11.13
- 第38回2025.11.06
- 第37回2025.10.30
- 第36回2025.10.23
- 第35回2025.10.16
- 第34回2025.10.09
- 第33回2025.10.02
- 第32回2025.09.25
- 第31回2025.09.18
- 第30回2025.09.16
- 第29回2025.09.04
- 第28回2025.08.28
- 第27回2025.08.21
- 第26回2025.08.14
- 第25回2025.08.07
- 第24回2025.07.31
- 第23回2025.07.24
- 第22回2025.07.17
- 第21回2025.07.10
- 第20回2025.07.03
- 第19回2025.06.26
- 第18回2025.06.19
- 第17回2025.06.12
- 第16回2025.06.05
- 第15回2025.05.29
- 第14回2025.05.22
- 第13回2025.05.15
- 第12回2025.05.08
- 第11回2025.05.01
- 第10回2025.04.24
- 第9回2025.04.17
- 第8回2025.04.10
- 第7回2025.04.03
- 第6回2025.03.27
- 第5回2025.03.20
- 第4回2025.03.13
- 第3回2025.03.06
- 第2回2025.02.27
- 第1回2025.02.20