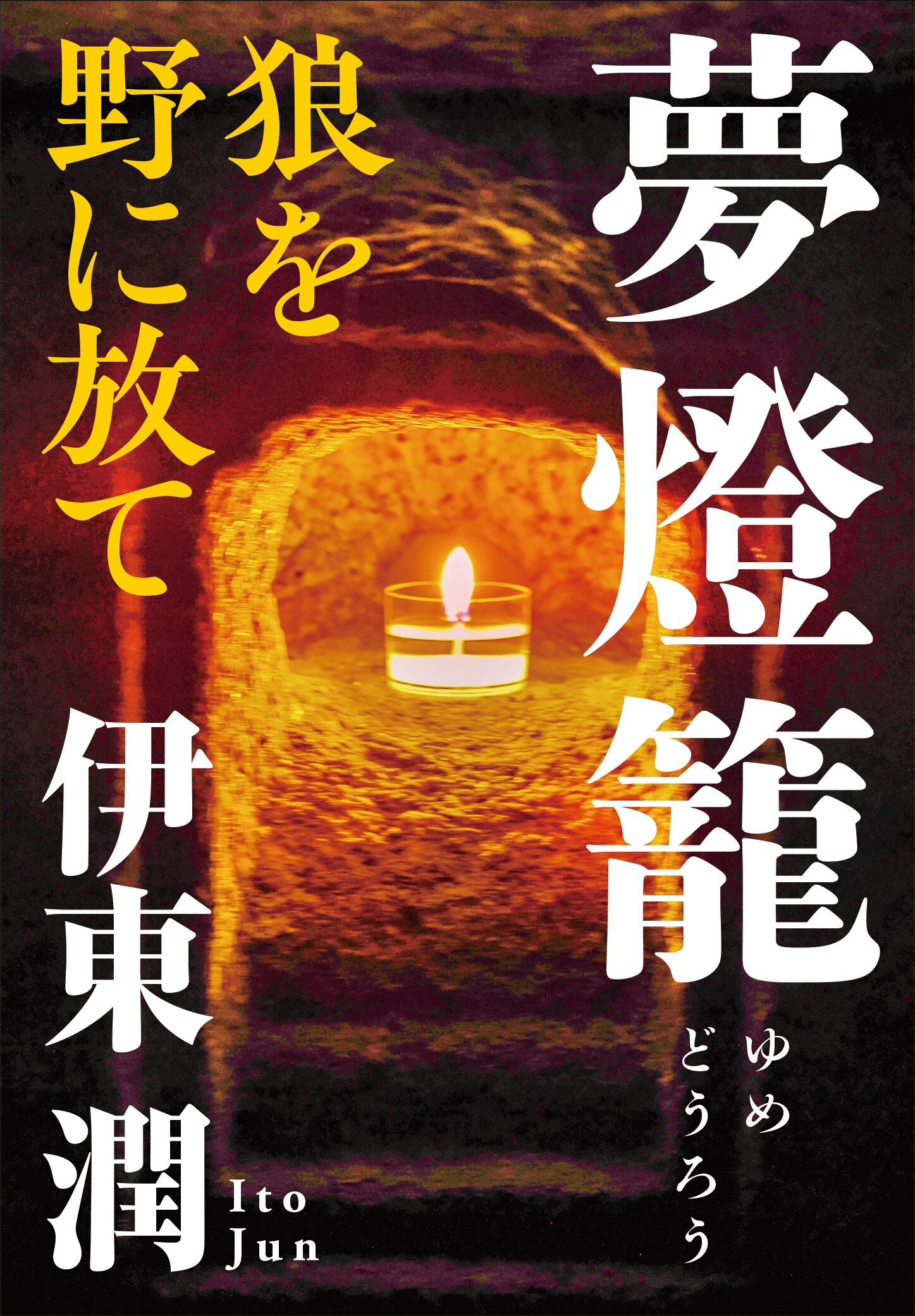夢燈籠 狼を野に放て第7回
七
留吉は福井製糸工業まで行き、平身低頭して謝罪した。友野と額田に悪口雑言を叩かれたが、何とか一カ月待ってもらえることになった。だが年末支払いを厳守しないと、福井製糸工業は不渡りを出してしまうという。そのため留吉は個人保証で支払いを確約する念書を取られた。しかも振り込まれなかった場合、福井製糸工業は高利貸から金を借りることになるので、その金利も含めて支払うことになった。
――致し方ない。
だが唯一の光明として、留吉の誠意を先方に認めてもらえたのは収穫だった。留吉は横田の責任とせず、すべては自分の見通しが甘かったこととして謝罪したので、最後は友野も「分かった。君を信じよう」と言ってくれた。
そうなれば何としても約束を守らせねばならない。留吉は京都に戻るや、東京に向かった。
横田産業に着き、何も言わずに横田の部屋に入ろうとすると、秘書の女性に止められた。この女性は番頭格で、横田の愛人だと言われている。
「社長のご意向を伺ってからです」
「分かった。早くしろ」
しばらくして先客らしき人が出てくると、しきりに横田に頭を下げている。横田は尊大な態度でその客を送り出した。
客が帰り、ようやく留吉は社長室に招き入れられた。
「兄貴、いや、もう坂田支店長と呼びましょう。うちはヤクザじゃないからね」
横田が対面の座を勧めたので、留吉は何も言わずに座った。
「いや、参ったね。今、来ていた客は総会屋です。あいつらはね、世間のダニなんですよ」
「そんなことはいいから、福井製糸への支払いが遅れたのは、どういうわけですか」
留吉は怒りを抑えかねたが、横田は社長なので礼節だけは守ろうとした。
「ああ、その件ですか。あれは説明したではないですか。一ヶ月分の金利が浮くんでね」
「しかしそれでは、契約に反するじゃないですか」
契約書を取り交わした際、十一月末に残金の二万円を払うと明記されていた。
「そうでしたね。でも、それで福井製糸さんが裁判所に訴えたわけではないですよね」
「訴えられなければ、何をやってもよいのですか」
「支店長、世の中は様々です」
「話をそらさないで下さい。まず十二月中に、二万円を振り込んでいただけるんですね」
横田は何も言わない。
「私は個人的に保証もしているんだ。振り込んでもらわなければ困ります」
音を立ててお茶を飲んだ後、横田が言った。
「分かりました。間違いなく振り込みましょう」
「それで安心しました」
「しかし、これからは勝手に個人保証などしないでいただきたい」
確かに企業に所属する者が、個人との境目を曖昧にすることは間違っている。
「その件については、お詫びしましょう」
「分かっていただけたなら、それで結構」
横田の巧妙な話法で、どちらが悪いのか分からなくなってしまったが、ここで、それ以上追及すれば、横田は臍を曲げ、「払わない」と言い出すかもしれない。そのため留吉は怒りを抑えた。
「さあ、では繰り出しますか!」
横田が明るい声で言う。
「繰り出すって、どこに」
「決まっているじゃないですか。銀座ですよ」
留吉は横田のペースに乗せられ、銀座に繰り出すことになった。
八
横田は約束通り、期日までに福井製糸に二万円を振り込んでくれた。そのため留吉の信用は何とか維持できた。それだけでなく別の会社との取引に乗り出した時、逆に福井製糸の口添えで取引が成立したこともあった。そのお礼で福井製糸に出掛けると、社長の友野は、「私は横田産業も横田英樹なる者も信用していない。だがあんたは信用している。信用こそ商売の世界では宝だ。それを大切にしていきなさい」と諭してくれた。
だが、それから半年もしないうちに、福井製糸は不渡りを出して倒産した。その後、友野も総務部長の額田の行方も杳として知れず、二人に会うことは二度となかった。
様々な困難に出遭いながらも、京都支店の売り上げは上々で、留吉は次第にビジネスの面白さの虜になっていった。
昭和二十三年(一九四八)、留吉は京都と福井を往復し、多くの取引を成立させた。横田率いる東京の本社も業績は順調で、昭和二十四年(一九四九)一月、横田産業は株式上場に踏み切り、晴れて横田産業株式会社となった。
同年四月、留吉は東京本社に顔を出し、昨季の業績を報告すると、横田は満面の笑みを浮かべた。
「昨季はお疲れ様でした。京都支店はよくやってくれています」
「ええ、社員も五人を数え、事業は順調に進んでいます」
「そうですね。この数字を見る限り問題はありません。しかし、そろそろ繊維のだぶつきは収まりつつあるのでは」
「そうなんです。もう安い製糸も出尽くしましたし、軍需産業の残滓も絞り尽くされた感があります」
実際にここ一年余、京都と福井を往復し、軍需産業に携わっていた様々な企業とかかわりを持ってきたが、安価に仕入れられる製糸もなくなりつつあり、一つひとつの取引の利益率は下降気味だった。だが、留吉には新たな事業に乗り出す目処が立っていた。
「社長が進駐軍御用工場の認可をもらってくれたおかげで、買収した紡績会社に力を入れていけば、業績は安定するはずです」
すでに横田産業は紡績工場を複数経営していた。これは横田が積極的に買収したというより、軍需がなくなり、経営が苦しくなった紡績会社の方から売却を申し入れてきたからだ。それを聞いた横田は、伝手をたどって進駐軍に入り込み、賄賂をばらまいて進駐軍御用工場の認可を取り付けた。そのため今は、買収した紡績会社が進駐軍向けの衣類を製造している。
「ああ、なるほど。それもそうですね」
だが、横田は別のことを考えているのか、さほど話に乗ってこない。
「進駐軍御用達となれば、利益は保証されたも同じですからね」
「そうですね。ただしいつまでも進駐軍がいるとは限りませんし、先行きは不透明です」
進駐軍は最盛期で七十二万人余もいたが、この頃は四十一万人余に減っていた。このペースで行けば、さらに減少することが見込まれた。
「先行きが不透明なら、徐々に民需に切り替えていけばよいだけです」
「仰せご尤も。ただし作れば売れる時代は、そろそろ終わりますからね」
横田が言うように、戦後の経済成長は、吉田茂を首班とする内閣による経済振興優先策、中東からの安価な原油の輸入、円安、旺盛な消費購買力、安価な労働力といった要素が重なり合って出現した。今後も経済は成長を続けるだろうが、業界や企業ごとの成長格差は生まれてくるはずだ。
「私もそう思います。これまでは戦後復興の掛け声の下、国民が生活の豊かさを求め、次から次へと物を買ってくれました。しかし将来有望な成長産業と、さほどでもない産業の成長格差は生まれてくるでしょう」
留吉はラジオで聞いた評論家の話を受け売りした。
「そうなんです。ですから、うちのような身軽な企業は、最も成長が望める分野に進出すべきなのです」
「ということは、紡績業を続けないのですか」
「私も考えに考えたのですよ。確かに紡績業を続けていれば、安定的な稼ぎは見込めるでしょう。しかし繊維産業にも、陰りが見えてきています」
「ちょっと待って下さい。衣服が国民に行き渡ったとはいえ、衣服は消耗品です。しかも国民、とくに若い女性がおしゃれに関心を持ちつつあります。やり方次第で、紡績産業は将来性があると思います」
「その通りです。しかしもっと莫大な利益を生み出す産業があります」
「それは何ですか。例えば電気通信関係ですか」
「それもありますが、そちらは門外漢なので手を出すのは危険です」
終戦直後の昭和二十年、井深大らが東京通信研究所を立ち上げていた。そして翌年には東京通信工業株式会社として、真空管電圧計の製造販売を開始していた。彼らの事務所は銀座白木屋デパートの三階にあり、横田と一緒に買い物に行った折、横田が井深らに挨拶で顔を出したのに付き合ったことがある。そのためすぐに念頭に浮かんだのだ。
「では、もっと有望な業種があるのですか」
「はい。あります」
「それは何ですか」
横田がもったいを付けるように、音を立てて茶をすすると言った。
「不動産です」
「えっ、不動産とは、土地の売買ですか」
「そうです。私はこれまで、いくつかの不動産を所有してきましたが、どれも高騰しています。これまで稼いだ金のすべてを不動産に注ぎ込んでもよいと思っています」
この頃、横田は田園調布に家を買い、そこで家族六人で暮らしていた。そのほかにも藤沢、鎌倉、熱海、軽井沢、箱根仙石原に邸宅を購入していた。とりわけ熱海の邸宅は元梨本宮邸、軽井沢の邸宅は元伏見宮別邸で、購入して価値が上がるのを待ち、売り払うつもりのようだ。また静岡県下の山林数百万坪をも購入していた。
また横田は、銀座一丁目の小さなビルを買い取り、「メリーカンパニイ」というOSS(進駐軍向けデパート)事業も始めていた。
これらの不動産はすべて五年月賦で購入したが、月賦を払い終わらないうちに、土地の値段が上がっていくので、笑いが止まらない状況だった。遂に横田および横田産業所有の不動産の評価額は二十億円を超え、それを元手にさらに大きな物件を購入しようというのが、横田の目論見なのだろう。
「不動産は、そんなに有望なのですか」
「有望です。たとえ復興の槌音が聞こえなくなっても、日本経済が成長を続ける限り、土地も値上がりを続けます」
「この会社は社長のものです。何をしようが社長の自由ですが、今稼働している紡績工場はどうするのです」
「それを売り払っていただくのが、坂田支店長の仕事です」
「私が売り払うのですか」
「そうです。買ったものは売る。これがビジネスの基本です」
横田の話が横道にそれそうになったので、留吉は話を戻した。
「売り払うと言っても、横田産業の傘下に入ったばかりの工場もあるんですよ」
「いいですか」
横田が留吉を憐れむような顔で言う。
「これからの日本は、生き馬の目を抜くような競争社会になります。それに勝つも負けるも経営手腕次第です」
「しかし横田産業の社員となった紡績工場の従業員たちは、どうするのです」
「彼らは、この横田と命運を共にしようと思って社員となったわけではありません。会社が買収されたから、そのまま働き続けているだけです。経営者が別の者に代わっても、給料が支払われるなら文句はないでしょう」
「待って下さい。昨年の業績は悪くないですし、横田産業が一流会社と財界に認められるには、堅実な事業も必要なのでは」
横田が首を左右に振る。
「いかにも堅実さは大切です。しかし今は激動期です。だからこそ手綱を緩めてはならないのです」
――横田は慧眼だ。言っていることは正しいかもしれない。
横田の話術には独特の説得力がある。その話術に多くの者が乗せられ、振り回されてきた。その一人が留吉なのだ。
「しかし、土地を買い増すにしても、得意の五年月賦なら、紡績業を手放さなくてもよいのでは」
「いや、私には狙っている大きな物件があります。そのためには、資金があればあるほどよいのです」
「それは何ですか」
「今は、某物件としか申し上げられません」
この時は、横田は留吉にも具体的な物件名を告げなかった。
「つまり正当な方法では、手に入れられない物件なんですね」
「いや、商法上は全く問題のない手を使います。つまり法に触れることは何一つしません」
「分かりました。それは置いておいて、問題は紡績工場です。今から買い手を見つけて売買を成立させるには、一年や二年は掛かります」
横田の双眸が鋭く光る。
「私は現金を必要としています。売却は半年以内に済ませていただきたい」
「それは無理というものです。買い手を探すところから始めるんですよ」
「分かっています。しかし無理を承知で言っています。坂田さんならできるはずです」
「買いかぶらないで下さい。私は会社や工場を売却した経験などありません」
「商法や手形法に詳しい法律の専門家を探します」
法律の専門家と聞いてピンと来たのは、親友の岩井壮司のことだ。
「それよりも買い手のあてはあるのですか」
「東レ、帝人、東洋紡、大日本紡績(後のユニチカ)などの大手は、ここが勝負所と見て拡大を図ろうとしています。逆に言えば、今なら最も高く売却できるのです」
横田の調査力と決断力は並大抵のものではなかった。横田が続ける。
「坂田さんが製糸や紡績の世界に身を投じるというなら、そのまま売却した企業に移っていただいても構いません」
――そうか。その手もあったな。
留吉は、自分の専門分野をそろそろ決めねばならないと思っていた。それで縁があって製糸や紡績関連の仕事に就けたので、それを専門としようと思っていた。その矢先に、この話が出てきたのだ。
――ここが人生の岐路か。
製紙や紡績の世界に身を投じれば、確かに安定的な人生が歩めるだろう。しかし、それが自分の求めているものかどうかは分からない。だいいち工場ごと採用されても、経営者は雲の上だ。横田との関係のような密な関係を築くことはできないだろう。となれば一生、人に使われる身となるかもしれない。
かつて母を探して福岡まで行った時、関東から流れてくる女たちのために郷友会をやっていた鯨料理店の主の言葉が、脳裏に浮かんだ。
「いいかい兄ちゃん、この世はな、運命を選択できる者とできない者がいる。例えば、俺は曲がりなりにも店主だ。何を仕入れるかから、どんな料理を『おしながき』に並べるのかを選択できる。だが宮仕えのお役人や会社勤めの月給取りは、偉くならない限り、上の者の選択した仕事をするだけだ。そんな人生、俺は真っ平だね」
――どちらが、より自分で自分の道を選べる仕事なのか。
今の留吉は横田の下にいるので、すべてを自分で決定できるわけではない。だがいつかは、自分が選択して決定できる立場に就きたい。そのためには、どちらの道に行くかを決めねばならない。
――しかも、俺も若くはない。
留吉は今年で四十歳になる。道に迷っている余裕はない年齢だ。
「少し考えさせて下さい」
「もちろんです。この横田と共に道を行くか、袂を分かつかは坂田さん次第です」
「分かりました。熟慮させていただきます」
「できれば――」
横田が真剣な顔で言う。
「これから私は大きな勝負に挑みます。その時に坂田さんが傍らで支えてくれれば、たいへん助かります」
それが横田の殺し文句なのだろう。だが留吉は、横田のような生粋の実業家ではない。ただ事業を通じて、世のため人のために役立ちたいという思いがあるだけだ。
「ありがとうございます。少なくとも、紡績工場の売却まではお付き合いします」
たとえ短期間でも、この業界で生きてきたからには、そこまでの責任が留吉にはある。
「それはありがたい。では、売却に力を注いで下さい」
横田が座ったまま深く頭を下げた。
Synopsisあらすじ
戦争が終わり、命からがら大陸からの引揚船に乗船した坂田留吉。しかし、焦土と化した日本に戻ってみると、戦後の混乱で親しい人々の安否もわからない。ひとり途方に暮れる留吉の前に現れたのは、あの男だった――。明治から平成へと駆け抜けた男の一代記「夢燈籠」。戦後復興、そして高度成長の日本を舞台に第2部スタート!
Profile著者紹介
1960年、神奈川県横浜市生まれ。早稲田大学卒業。『黒南風の海――加藤清正「文禄・慶長の役」異聞』で第1回本屋が選ぶ時代小説大賞を、『国を蹴った男』で第34回吉川英治文学新人賞を、『巨鯨の海』で第4回山田風太郎賞と第1回高校生直木賞を、『峠越え』で第20回中山義秀文学賞を、『義烈千秋 天狗党西へ』で第2回歴史時代作家クラブ賞(作品賞)を受賞。
Newest issue最新話
- 第51回2026.02.04
Backnumberバックナンバー
- 第50回2026.02.02
- 第49回2026.01.22
- 第48回2026.01.15
- 第47回2026.01.08
- 第46回2026.01.01
- 第45回2025.12.25
- 第44回2025.12.18
- 第43回2025.12.11
- 第42回2025.12.04
- 第41回2025.11.27
- 第40回2025.11.20
- 第39回2025.11.13
- 第38回2025.11.06
- 第37回2025.10.30
- 第36回2025.10.23
- 第35回2025.10.16
- 第34回2025.10.09
- 第33回2025.10.02
- 第32回2025.09.25
- 第31回2025.09.18
- 第30回2025.09.16
- 第29回2025.09.04
- 第28回2025.08.28
- 第27回2025.08.21
- 第26回2025.08.14
- 第25回2025.08.07
- 第24回2025.07.31
- 第23回2025.07.24
- 第22回2025.07.17
- 第21回2025.07.10
- 第20回2025.07.03
- 第19回2025.06.26
- 第18回2025.06.19
- 第17回2025.06.12
- 第16回2025.06.05
- 第15回2025.05.29
- 第14回2025.05.22
- 第13回2025.05.15
- 第12回2025.05.08
- 第11回2025.05.01
- 第10回2025.04.24
- 第9回2025.04.17
- 第8回2025.04.10
- 第7回2025.04.03
- 第6回2025.03.27
- 第5回2025.03.20
- 第4回2025.03.13
- 第3回2025.03.06
- 第2回2025.02.27
- 第1回2025.02.20