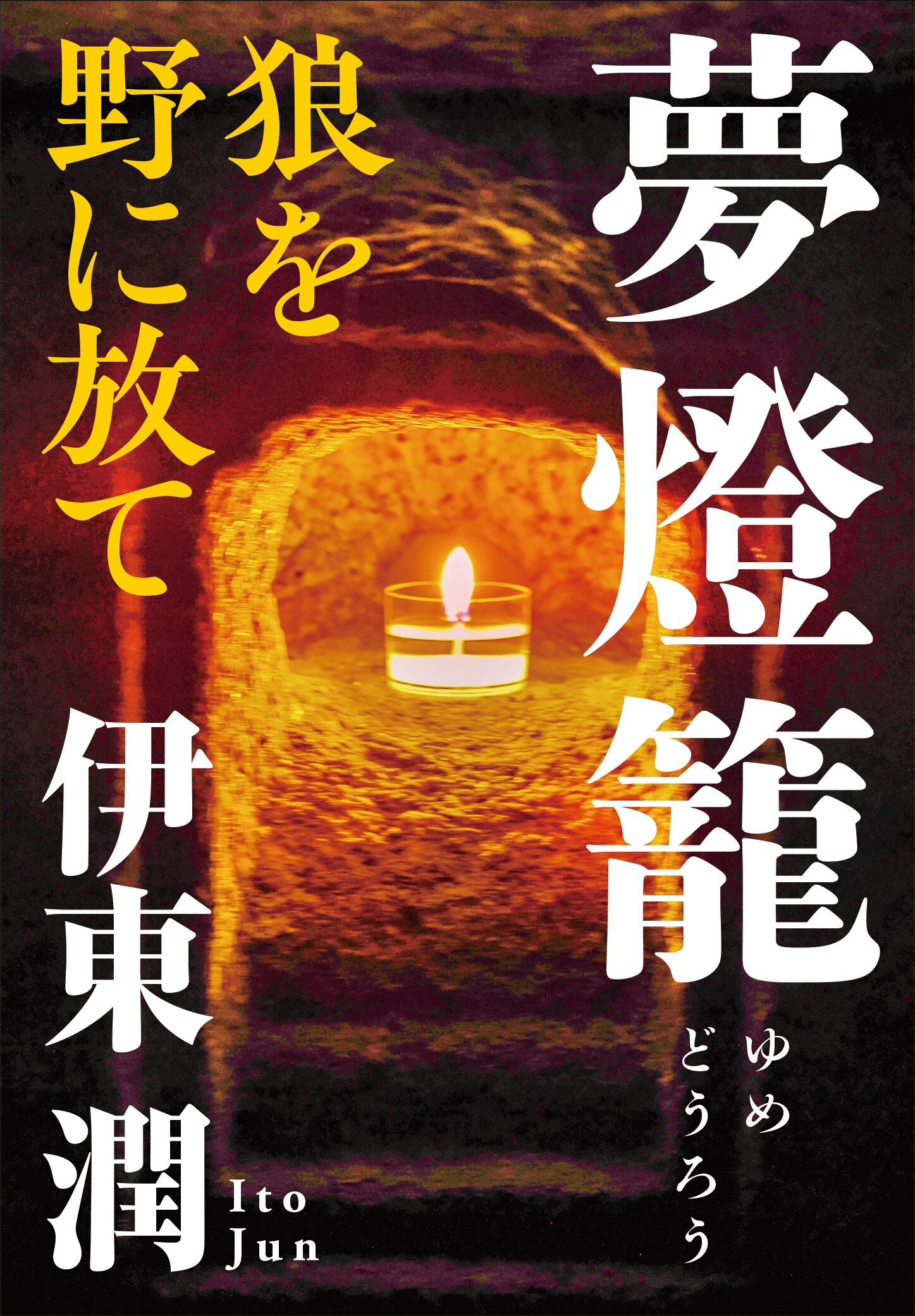夢燈籠 狼を野に放て第11回
十二
昭和二十五年(一九五〇)の松の内が終わった頃、留吉、横田、岩井の三人は、白木屋の前に佇んでいた。
――ここが東洋一の百貨店か。
眼前には、九階建てのモダンな外装のビルディングが屹立していた。
これまで留吉は、二度ほど白木屋を訪れたことがある。岩井も一度は来たと言っていた。だが留吉は買い物に来ただけなので、店内を漫然と歩いただけだ。おそらく岩井も同じだろう。
今回、横田は「売り場の見方を知らないと、私が買収したい理由が分からないでしょう」と言って、二人を連れてきた。
すでに自分のものになったかのように、横田が言う。
「デパートは立地です。白木屋は日本橋の中心にあり、立地は最高です」
白木屋は中央区日本橋一丁目にある。かつては江戸三大呉服店の一つで、初代の大村彦太郎が、寛文二年(一六六二)に間口一間半という小さな小間物屋を開いたのが始まりになる。その後、羽二重地(はぶたえじ)、晒木綿(さらしもめん)、ちりめん、毛氈(もうせん)、紗(しゃ)、綾(あや)なども手掛けていくことで業容を拡大させ、江戸有数の呉服店へと成長する。
明治維新後も積極的に拡大路線を走り、順調に業績を伸ばしていた白木屋だが、昭和七年、八階建ての建物の四階以上を全焼させ、十四人もの死者を出したことで大きな打撃を受けた。
この時は歳末大売出し中で、四階のおもちゃ売り場のクリスマスツリーの豆電球が故障したため、男性社員が修理しようとしたところ、誤って電線がソケットに触れたため火花が飛び散り、それがクリスマスツリーに燃え移り、さらに引火しやすいセルロイド製のおもちゃに飛び火し、大火災になったという。
横田が得意満面に言う。
「これから買い物はレジャーの一種になります。つまり辺鄙(へんぴ)なところにあっても、お客様は行きません。日本橋という東京の中心にあるからこそ、お客様は集まるのです」
横田の言には説得力があった。
――つまり何かが必要だからデパートに行くのではなく、休日のちょっとした気晴らしとしてデパートに行くというのか。
「買い物は思い出作りでもあるのです。『この着物は、いつ誰々と来た時に買ったな』と思い出すことで、よい買い物をしたなとなるのです」
留吉にも未来の買い物のイメージが浮かんできた。
三人は、それぞれ回転扉を押して一階に入った。
「回転扉は空調効果が高く、防塵・防音効果があるとはいえ、入りにくいことこの上ない。気軽に入れるように改装せねばなりません」
横田が独り言のように言う。
一階のエントランスは天井が高く取ってあり、大きなシャンデリアが吊るされている。
「シャンデリアは地震の時、落ちやすい。チェーンで落下防止の補強をせねばなりません」
確かにシャンデリアは、中心部分が金具で止めてあるだけだ。
――あれが外れれば、大事故につながりかねない。
留吉のような素人(しろうと)でも、そのくらいのことは分かる。
一階は吹き抜けになっており、中二階の手すりが四面をめぐっている。そこに摑まり、一階を見下ろす小さな子供の姿が見える。
「中二階の手すりが低い。まあ、お子さんがよじ登ることはないと思いますが、四面に網を張っておく必要がありますね」
岩井が言う。
「今日は随分とすいていますね」
「そうですね。平日の昼でも、これはひどい」
正月セールも終わった後の平日だからか、店内は閑散としており、和服姿の女店員たちが暇を持て余すように立っている。
「あれを見れば、三越との違いは一目瞭然ですね」
その時期や客の混雑具合にもよるが、確かに三越の方が、女店員がてきぱきと働いていた気がする。
「店員の数が多すぎるんです」
横田が顔をしかめて続ける。
「ここは必要以上に店員を雇っています。この光景を見れば、それは歴然です。にもかかわらず店員を減らそうとしない。これこそ経営の怠慢というものです」
横田の声が大きいので、店員たちが何事かとこちらを見ている。
「それに通路が狭い。これでは休日の混雑時に、客が擦れ違うこともできない。しかも通路に商材を積んでいる。これでは客は買い物を楽しめないどころか、緊急時の避難にも差し支える。このデパートは一度火事まで出しているのに、そこから何も学んでいない」
横田が細かい点を指摘する。
「あの紳士コーナーの帽子置き場を見て下さい。ぎりぎりまで詰めて帽子を置いていますね」
岩井が疑問を呈する。
「その何が悪いのですか」
「ああした高級帽は、高級品なりの陳列をしなければなりません。つまりスペースを取って、いかにも高級だという品格を漂わせねばならないのです」
「そういうものですか」
「そういうものです。あっ、あれを見て下さい」
横田が婦人服コーナーの「晴れ着安売り」という横幕を指す。
「あれは、売れ残った晴れ着を安く売ろうとしているんです。でも正月も終わったというのに、誰が買いますか」
横田がしかめ面で続ける。
「仕入れ担当にやる気がないから売れ残るんです。おそらく卸元の呉服問屋が適当に見繕(みつくろ)い、送られてきたものを並べただけでしょう。呉服問屋は仕入れにうるさい担当がいるデパートには人気のあるものを、白木屋のようにやる気のない仕入れ担当のデパートには、売れ残りを押し付けます。それで売れ残れば、安く売らねばならなくなる。それで仕入れ担当が罰せられるわけではない。しかも新春セールが終わったにもかかわらず、一階の目立つ場所で晴れ着を売っている。売りたいのは分かるが、買いたい人はいない。つまり売り場が無駄になっているんです」
横田が熱弁を振るう。おそらく何人かの店員には聞こえているだろう。
「経営は、こうした細部から腐っていくのです」
一階を見ただけで、横田は白木屋のすべてを見通していた。
その後、各階を見回りながら、横田はさんざん小言を言った末、最上階のレストランに入った。
「好きなものを頼んで下さい。勘定は私が持ちます」
ケチな横田が珍しく気前がいいので、留吉はステーキを、岩井はハンバーグ定食を、 横田はサンドイッチを頼んだ。
それらが運ばれてくると、一口かじっただけで、またぞろ横田の講釈が始まった。
「このサンドイッチを見て下さい。パンは乾燥しているし、中の具は少ない。これで三百円もします。町中の喫茶店なら、もっとよいものを二百円ほどで食べられます。こんなサンドイッチを町の喫茶店が出したら、客は来なくなります」
横田はサンドイッチのかじった部分を指し示しながら言う。
その時、留吉のステーキと岩井のハンバーグが運ばれてきた。
「ああ、そのステーキは焼き過ぎですね。ステーキはレア、ミディアム、ウェルダンの三種の焼き方から、お客にどれがよいかを選ばせねばなりません。しかしここは、お客から生焼けというクレームがつくのを嫌がり、すべてウェルダンにしているのでしょう。ほら、そんなに焦げている部分があったら食欲も失せます」
確かに黒ずんだ部分が多いので、留吉の食欲も失せてきた。
「ハンバーグは裏を返して見せて下さい」
岩井がハンバーグの裏を見せる。
「それは手ごねではなく冷凍食品ですね」
「どうして分かるんですか」
岩井が首をひねる。
「手ごねの場合、練ったばかりなので、面がもっとごつごつしています。ここのハンバーグは、表も裏もきれいに水平になっている」
「どうして水平になるんですか」
「冷凍食品は箱に詰められ、送られてきます。つまりいくつもを重ねてくるので、自然に押しつぶされて水平になるのです」
言われてみればその通りだ。
「会社というのは一事が万事なのです。経営者のやる気がなければ、それは社員にも伝わります。それが、こうした食べ物にも顕著に表れるのです」
横田はそこまで言って立ち上がると、勘定所に向かった。
ハンバーグの一片を口に持っていこうとしていた岩井が、フォークとナイフを置くと、コートを持って席を立った。それを見た留吉も致し方なく立ち上がった。テーブルには横田が一口食べたサンドイッチと、手がつけられていないステーキとハンバーグが残った。
「さて、口直しに街のラーメン屋にでも行きますか」
会計を済ませた横田が高笑いした。
Synopsisあらすじ
戦争が終わり、命からがら大陸からの引揚船に乗船した坂田留吉。しかし、焦土と化した日本に戻ってみると、戦後の混乱で親しい人々の安否もわからない。ひとり途方に暮れる留吉の前に現れたのは、あの男だった――。明治から平成へと駆け抜けた男の一代記「夢燈籠」。戦後復興、そして高度成長の日本を舞台に第2部スタート!
Profile著者紹介
1960年、神奈川県横浜市生まれ。早稲田大学卒業。『黒南風の海――加藤清正「文禄・慶長の役」異聞』で第1回本屋が選ぶ時代小説大賞を、『国を蹴った男』で第34回吉川英治文学新人賞を、『巨鯨の海』で第4回山田風太郎賞と第1回高校生直木賞を、『峠越え』で第20回中山義秀文学賞を、『義烈千秋 天狗党西へ』で第2回歴史時代作家クラブ賞(作品賞)を受賞。
Newest issue最新話
- 第51回2026.02.04
Backnumberバックナンバー
- 第50回2026.02.02
- 第49回2026.01.22
- 第48回2026.01.15
- 第47回2026.01.08
- 第46回2026.01.01
- 第45回2025.12.25
- 第44回2025.12.18
- 第43回2025.12.11
- 第42回2025.12.04
- 第41回2025.11.27
- 第40回2025.11.20
- 第39回2025.11.13
- 第38回2025.11.06
- 第37回2025.10.30
- 第36回2025.10.23
- 第35回2025.10.16
- 第34回2025.10.09
- 第33回2025.10.02
- 第32回2025.09.25
- 第31回2025.09.18
- 第30回2025.09.16
- 第29回2025.09.04
- 第28回2025.08.28
- 第27回2025.08.21
- 第26回2025.08.14
- 第25回2025.08.07
- 第24回2025.07.31
- 第23回2025.07.24
- 第22回2025.07.17
- 第21回2025.07.10
- 第20回2025.07.03
- 第19回2025.06.26
- 第18回2025.06.19
- 第17回2025.06.12
- 第16回2025.06.05
- 第15回2025.05.29
- 第14回2025.05.22
- 第13回2025.05.15
- 第12回2025.05.08
- 第11回2025.05.01
- 第10回2025.04.24
- 第9回2025.04.17
- 第8回2025.04.10
- 第7回2025.04.03
- 第6回2025.03.27
- 第5回2025.03.20
- 第4回2025.03.13
- 第3回2025.03.06
- 第2回2025.02.27
- 第1回2025.02.20