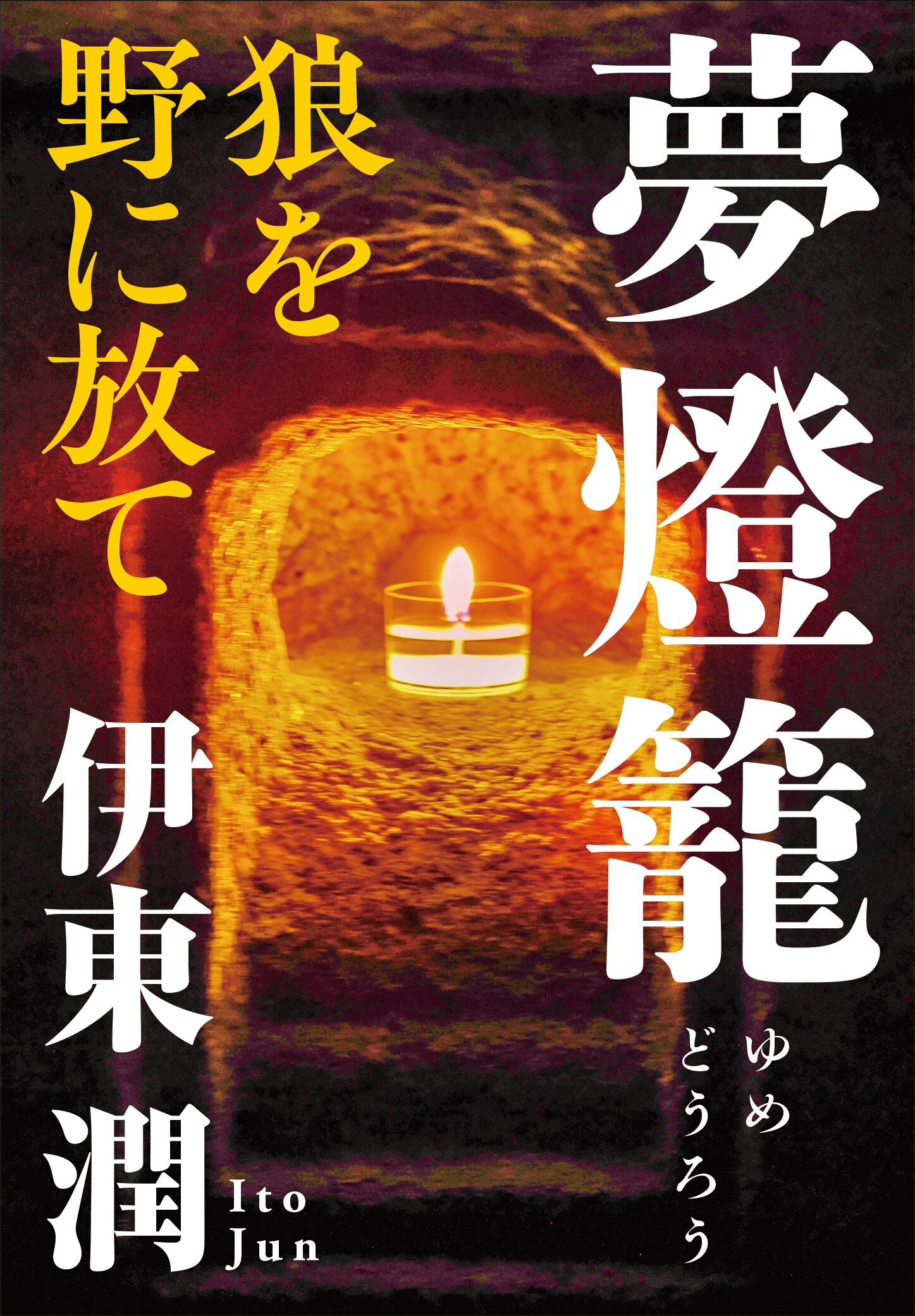夢燈籠 狼を野に放て第2回
二
船を降りても行くあてはない。一瞬、継母(ままはは)の弟の又吉健吉(またよしけんきち)の家まで歩こうかと思ったが、それでは厄介になるだけで、迷惑な話だと思い直した。学友の岩井壮司(いわいそうじ)の事務所に電話しようかとも思ったが、電話は全く通じていないと船内の噂話で聞いていたので、それもあきらめた。だいいち公衆電話が見当たらない。
――二人には、いつか挨拶に行かねばならないが、少し落ち着いてからにしよう。では、どうする。
その時、「東京方面に行きたい方は、横浜駅までバスが出ています」というアナウンスが聞こえた。それに応じて、ほぼ全員が立ち上がった。
――とりあえず東京に行くか。
何とはなしにそう思った留吉は、人の流れに乗るようにバス停に向かった。
何台かのバスは満員で乗れなかったが、どうにか最後の一台に乗れた。留吉は吊革に摑まって立っていたが、多くの人が所構わず座っている。そうした人々と荷物で、バスは満員にならずとも出発せざるを得ないのが原因だった。
横浜駅に着くと、駅前にはバラックの仮設店舗がずらりと並んでいた。その中の一軒のうどん屋に入り、腹ごしらえした留吉は、店主に聞いてみた。
「復員兵だが、どこの駅もこんな感じなのかい」
「ああ、どこもまだ仮設だよ。少し前までは闇市全盛だったけど、ようやく物資が出回るようになり、普通の店でも商いできるようになった」
「闇市というと、不法に仕入れたものを売る市のことかい」
「そうだよ。兄さんは大陸帰りかね」
うどんを出しながら、店主が留吉の全身を見回した。
「ああ、そうだ」
「だったら金は持っているね」
「そうでもない」
「東京に行くなら気をつけなよ」
「何に気をつけるんだい」
「何にでもさ」
丸眼鏡の店主が金歯を剝き出しにして笑う。
「どこに行けば、手っ取り早く稼げるんだい」
「今は戦後復興とかで、どこも人手不足さ。横浜でも労働力は引く手あまただけど、東京の方が多少日給がいいと聞いた」
「つまりドカチン(土方仕事)かい」
「そうだよ。兄さんは、それ以外のことができるのかい」
「いちおう大卒なんで――」
この時代、大卒は五パーセントを切っていた。
「だったら伝手を手繰りなよ。今なら大きな会社にも潜り込めるさ」
店主の高笑いが湯気にかき消された。
徐々に復興が進む風景を車窓から眺めつつ、新橋に着いた留吉は、まずは仕事を探そうと思った。ズボンのベルトやパンツの中に縫い込むなどして、多少の円を持ち帰ることはできたが、一カ月と食べていけない金額だ。そのためにはドカチンだって厭わないつもりだ。しかし、まずは求人をしている会社を探すことから始めようと思った。
――職安はどこにある。
交番にでも尋ねようと思ったが、なかなか見当たらない。駅員に聞けばよかったと後悔したが、雑踏に紛れてしまったので、駅まで戻るのもばかばかしい。
――どうしよう。
留吉は、いつの間にか闇市に足を踏み入れていた。
――これが闇市か。
そこは人の数といい、騒音といい、得体の知れない臭いといい、言葉では言い表せない熱気に包まれていた。
終戦直後の物資の欠乏は凄まじいもので、働き手を失った貧農の家庭などは、餓死者が出るほどだった。そのため政府は、戦中から続いていた配給制度によって何とか国民生活を維持させようとするが、米国からの援助物資はわずかで、とても国民全体には行き渡らない。しかも米軍にも支援物資を横流しする輩(やから)がおり、末端の配給量はさらに少ないものになっていた。そのため法を守る手本になろうとした裁判官の山口良忠は、配給物資以外を頑として口にせず、餓死するという有様だった。
東北の農村から作物を買ってきたり、米軍から支援物資を横流ししてもらったりした者たちは、それらを池袋、上野、新橋、新宿などで自然発生的に生まれた闇市で、公定価格の五~十倍の値段で販売した。それでも餓死するよりはましなので、誰もがなけなしの金を出して購入した。
これらの闇市は、後の暴力団となる的屋が仕切っており、闇市で商いをする者たちに対し、多額のみかじめ料を取っていた。
バラック造りの仮設店舗の間を歩いていると、日本軍の軍服や防寒着を売っている店があった。
――そうか。日本が崩壊する過程で、これらを管理していた連中が横流ししたんだな。
留吉はその節操のなさに呆れた。
――その時、一人の男の顔が脳裏に浮かんだ。
留吉はその店に入り、陸軍の略式制帽を購入した。復員兵を思わせた方が、少しは周囲のあたりがよくなると思ったからだ。
「こうしたものは、どこで仕入れたんだい」
代金を払いながら店主らしき男に尋ねると、とたんに嫌な顔をされた。
「あんたマッポか」
マッポとは、警察官になる者が多かった薩摩人を「薩摩っぽ」と呼んだことから派生した警察を表す隠語だ。
「復員したばかりだ。見れば分かるだろう」
「ああ、分かる。軍属だな」
「どうして分かった」
「兵隊さんが軍帽を買うわけがなかろう」
「尤もだ。それで質問だが――」
男が「ふん」と言うと啖呵を切った。
「口は割らねえよ!」
「そうかい」と答えて五円札を見せると、男の顔色が変わった。
「そいつをくれるのかい」
「ああ、教えてくれたらな」
男は左右を気にしつつ言った。
「横田商店、いや、今は横田産業だ」
「あ、あの横田英樹(よこたひでき)が社長をやっている会社か」
「何だ、知っているのか。でも五円はもらうぞ」
「ああ、やる。だが、もう一つ質問だ。横田商店はどこにある」
「なんだ、そんなことも知らねえのか。虎ノ門一丁目さ。焼け残ったビルは少ないんで、行ってみれば分かるよ」
「ありがとう」と言いながら五円札を渡すと、男が小躍りした。
「あんたも、こういう商いをやりたいんだな」
「まあな」
「だったら今は、食い物より衣類がいいぜ。終戦直後は食い物の方が断然景気がよかったが、食い物は持ちが悪いから、今は衣類の方がもうかる」
「親切にすまんね」
留吉が店を出ようとすると、男が古びた軍服を投げてよこした。
「こいつは贈り物だ。夜は冷えるからな。ここに店を出すなら、いつか飲もうぜ」
右手を挙げてそれに応えると、留吉は虎ノ門一丁目に向かった。
横田商店の社長は横田英樹といって、過去に留吉とかかわりのあった人物だ。横田は裸一貫で東京に出てきて、丁稚のような立場で繊維関連の会社に就職した。そこで仕事を覚えた横田は、自ら繊維製品の卸業の横田商店を開業した。しかし零細規模なので、金払いのいい軍部への伝手を探していた。そこでたまたま知り合ったのが留吉だった。留吉は石原莞爾中将に取り次ぎ、横田の事業を拡大させてやった。横田は大いに喜び、留吉のことを兄貴と呼ぶようになった。留吉は明治四十一年(一九〇八)生まれの三十四歳で、横田は大正二年(一九一三)生まれの二十九歳なので、留吉が五歳も年上だからだ。
しばらく二人で仕事をしていたが、留吉が満州に戻ったことで、横田とは音信不通になってしまっていた。
Synopsisあらすじ
戦争が終わり、命からがら大陸からの引揚船に乗船した坂田留吉。しかし、焦土と化した日本に戻ってみると、戦後の混乱で親しい人々の安否もわからない。ひとり途方に暮れる留吉の前に現れたのは、あの男だった――。明治から平成へと駆け抜けた男の一代記「夢燈籠」。戦後復興、そして高度成長の日本を舞台に第2部スタート!
Profile著者紹介
1960年、神奈川県横浜市生まれ。早稲田大学卒業。『黒南風の海――加藤清正「文禄・慶長の役」異聞』で第1回本屋が選ぶ時代小説大賞を、『国を蹴った男』で第34回吉川英治文学新人賞を、『巨鯨の海』で第4回山田風太郎賞と第1回高校生直木賞を、『峠越え』で第20回中山義秀文学賞を、『義烈千秋 天狗党西へ』で第2回歴史時代作家クラブ賞(作品賞)を受賞。
Newest issue最新話
- 第51回2026.02.04
Backnumberバックナンバー
- 第50回2026.02.02
- 第49回2026.01.22
- 第48回2026.01.15
- 第47回2026.01.08
- 第46回2026.01.01
- 第45回2025.12.25
- 第44回2025.12.18
- 第43回2025.12.11
- 第42回2025.12.04
- 第41回2025.11.27
- 第40回2025.11.20
- 第39回2025.11.13
- 第38回2025.11.06
- 第37回2025.10.30
- 第36回2025.10.23
- 第35回2025.10.16
- 第34回2025.10.09
- 第33回2025.10.02
- 第32回2025.09.25
- 第31回2025.09.18
- 第30回2025.09.16
- 第29回2025.09.04
- 第28回2025.08.28
- 第27回2025.08.21
- 第26回2025.08.14
- 第25回2025.08.07
- 第24回2025.07.31
- 第23回2025.07.24
- 第22回2025.07.17
- 第21回2025.07.10
- 第20回2025.07.03
- 第19回2025.06.26
- 第18回2025.06.19
- 第17回2025.06.12
- 第16回2025.06.05
- 第15回2025.05.29
- 第14回2025.05.22
- 第13回2025.05.15
- 第12回2025.05.08
- 第11回2025.05.01
- 第10回2025.04.24
- 第9回2025.04.17
- 第8回2025.04.10
- 第7回2025.04.03
- 第6回2025.03.27
- 第5回2025.03.20
- 第4回2025.03.13
- 第3回2025.03.06
- 第2回2025.02.27
- 第1回2025.02.20