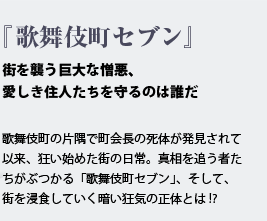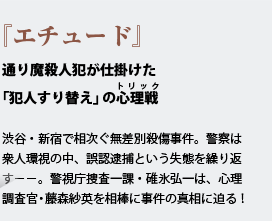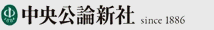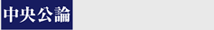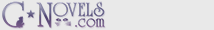小説の作法
-
誉田
そういえば今野さん、レコード会社にお勤めだったそうで。
-
今野
はい、いました。
-
誉田
 僕が音楽小説を書いた時に、別のレコード会社に取材させてもらったんですが、「事務所とアーティストとの間で、こういうことってありますかね」と聞いたら、「ああ、あるんじゃないですか」。何聞いても「あるんじゃないですかね」。何でもありの業界は、逆に書きづらいですねえ(笑)。
僕が音楽小説を書いた時に、別のレコード会社に取材させてもらったんですが、「事務所とアーティストとの間で、こういうことってありますかね」と聞いたら、「ああ、あるんじゃないですか」。何聞いても「あるんじゃないですかね」。何でもありの業界は、逆に書きづらいですねえ(笑)。
-
今野
そういう業界です(笑)。誉田さんはバンドやってたんですよね、ずっと。
-
誉田
はい。30歳までやりましたが、一銭にもならなかったです(笑)。
-
今野
最初に書いた小説の元が、ご自分の歌詞だったそうですね。珍しいタイプですよね、それ(笑)。
-
誉田
最初小説を書き始めた時、全然起承転結がつけられなかったんですよ。悩んでいたときに、自分の歌詞がちょっと物語風になってたので、「この歌詞を短篇小説にしてみよう」と思って、三つぐらい書いたらできるようになったんです。その最初の、生まれて初めて書いたやつをリライトして、「C☆NOVELS創刊25周年アンソロジー」に入れてもらったんです。
-
今野
最初にプロットを細かく決めるんでしょう? エクセルで人物の行動表を時系列で作るって聞きました。
-
誉田
はい、しますね。
-
今野
いや、俺はね、プロット立てられないの。
-
誉田
あ、そうなんですか?
-
今野
俺、大抵、タイトルが抽象的じゃないですか、漢字で二文字とか。あれ、連載始める時、ストーリーがどうなってもいいようにしてるんだ(笑)。毎回毎回、読者と一緒にハラハラしながら書いて、次どうしようかって。
- ――でも、結末は大体、決まってるんでしょう。
-
今野
いいや。
-
誉田
えー!
-
今野
決まってない。『エチュード』だって、最初は「てじな」っていうその三文字しか頭の中になかった(笑)。連載の時は、読者のために引きで終わるじゃないですか。次の日そこ読んで考えるんです、一生懸命。どうしようか、こんな引き作っちゃったけどって。
- ――でも、今野さんの小説は、けっこう最後にストンと着地しますよね。
-
今野
連載最後から二回目くらいのところから、自分の小説を頭から読み始めるんです。あ、これ拾える、これも拾える、よし着地できると。まあ、これが手品みたいなものですね(笑)。
- ――誉田さんは、きっちり最初に設計を。
-
誉田
そうですね、大体一節20枚でストーリーを割り、二十五節で一冊分、500枚くらい。20枚が割と書きやすい。
-
今野
あ、俺も一緒。一節20枚。20枚単位じゃないと書きにくいんだ。
-
誉田
だから、できるだけ1回50枚のお仕事は受けたくない(笑)。
-
今野
そうなのよ。50枚は中途半端だよね。共通点あったね(笑)。
- ――誉田さんは最初にプランを決めたとして、書いてるうちに登場人物の動きが変わってくるなんてことはありますか。
-
誉田
プランといっても、視点人物を決めて、だいたいの流れを押さえているだけなので、ふらっと別の人物が来たり、別の要素が入ってきたりして、予想しなかった場面になることはありますね。
-
今野
その視点の問題ってすごく大きくて、俺も若い頃は多視点で書いてたんですが、プロットをカチッと書いておかないと、視点人物が何を知っていて何を知らないか、だんだんわかんなくなるんですよね。今、割といい加減に書けるのは、単一視点にしているからです。
-
誉田
一つにした理由というのは何かあるんですか。
-
今野
年取ったからだと思う。多視点は面倒くさい(笑)。
- ――でも、『エチュード』の前に碓氷が登場する『パラレル』は完全に多視点でしたね。
-
今野
 あれはいろんな作品の登場人物を全部出しちゃえって思ったから。そういうのも、多視点で書いてた経験があるので苦ではないんです。年取ったからというのは冗談半分、本気半分で、なぜ単一視点になったかというと、小説と他メディアの違いというのを、ものすごく考えるようになったから。ドラマになった時の映像と小説がどう違うのかを考えた時、小説では心理描写しか勝てるものがない。ドラマもゲームも、そこはできないんですよね。で、そう書きたいという欲求が高まった時に、単一視点のほうが書きやすかったということです。そもそも、ハードボイルドというのは一人称が多いですよね。多分そういうのに慣れてたせいもあるんだと思うんです。
あれはいろんな作品の登場人物を全部出しちゃえって思ったから。そういうのも、多視点で書いてた経験があるので苦ではないんです。年取ったからというのは冗談半分、本気半分で、なぜ単一視点になったかというと、小説と他メディアの違いというのを、ものすごく考えるようになったから。ドラマになった時の映像と小説がどう違うのかを考えた時、小説では心理描写しか勝てるものがない。ドラマもゲームも、そこはできないんですよね。で、そう書きたいという欲求が高まった時に、単一視点のほうが書きやすかったということです。そもそも、ハードボイルドというのは一人称が多いですよね。多分そういうのに慣れてたせいもあるんだと思うんです。
 僕が音楽小説を書いた時に、別のレコード会社に取材させてもらったんですが、「事務所とアーティストとの間で、こういうことってありますかね」と聞いたら、「ああ、あるんじゃないですか」。何聞いても「あるんじゃないですかね」。何でもありの業界は、逆に書きづらいですねえ(笑)。
僕が音楽小説を書いた時に、別のレコード会社に取材させてもらったんですが、「事務所とアーティストとの間で、こういうことってありますかね」と聞いたら、「ああ、あるんじゃないですか」。何聞いても「あるんじゃないですかね」。何でもありの業界は、逆に書きづらいですねえ(笑)。
 あれはいろんな作品の登場人物を全部出しちゃえって思ったから。そういうのも、多視点で書いてた経験があるので苦ではないんです。年取ったからというのは冗談半分、本気半分で、なぜ単一視点になったかというと、小説と他メディアの違いというのを、ものすごく考えるようになったから。ドラマになった時の映像と小説がどう違うのかを考えた時、小説では心理描写しか勝てるものがない。ドラマもゲームも、そこはできないんですよね。で、そう書きたいという欲求が高まった時に、単一視点のほうが書きやすかったということです。そもそも、ハードボイルドというのは一人称が多いですよね。多分そういうのに慣れてたせいもあるんだと思うんです。
あれはいろんな作品の登場人物を全部出しちゃえって思ったから。そういうのも、多視点で書いてた経験があるので苦ではないんです。年取ったからというのは冗談半分、本気半分で、なぜ単一視点になったかというと、小説と他メディアの違いというのを、ものすごく考えるようになったから。ドラマになった時の映像と小説がどう違うのかを考えた時、小説では心理描写しか勝てるものがない。ドラマもゲームも、そこはできないんですよね。で、そう書きたいという欲求が高まった時に、単一視点のほうが書きやすかったということです。そもそも、ハードボイルドというのは一人称が多いですよね。多分そういうのに慣れてたせいもあるんだと思うんです。