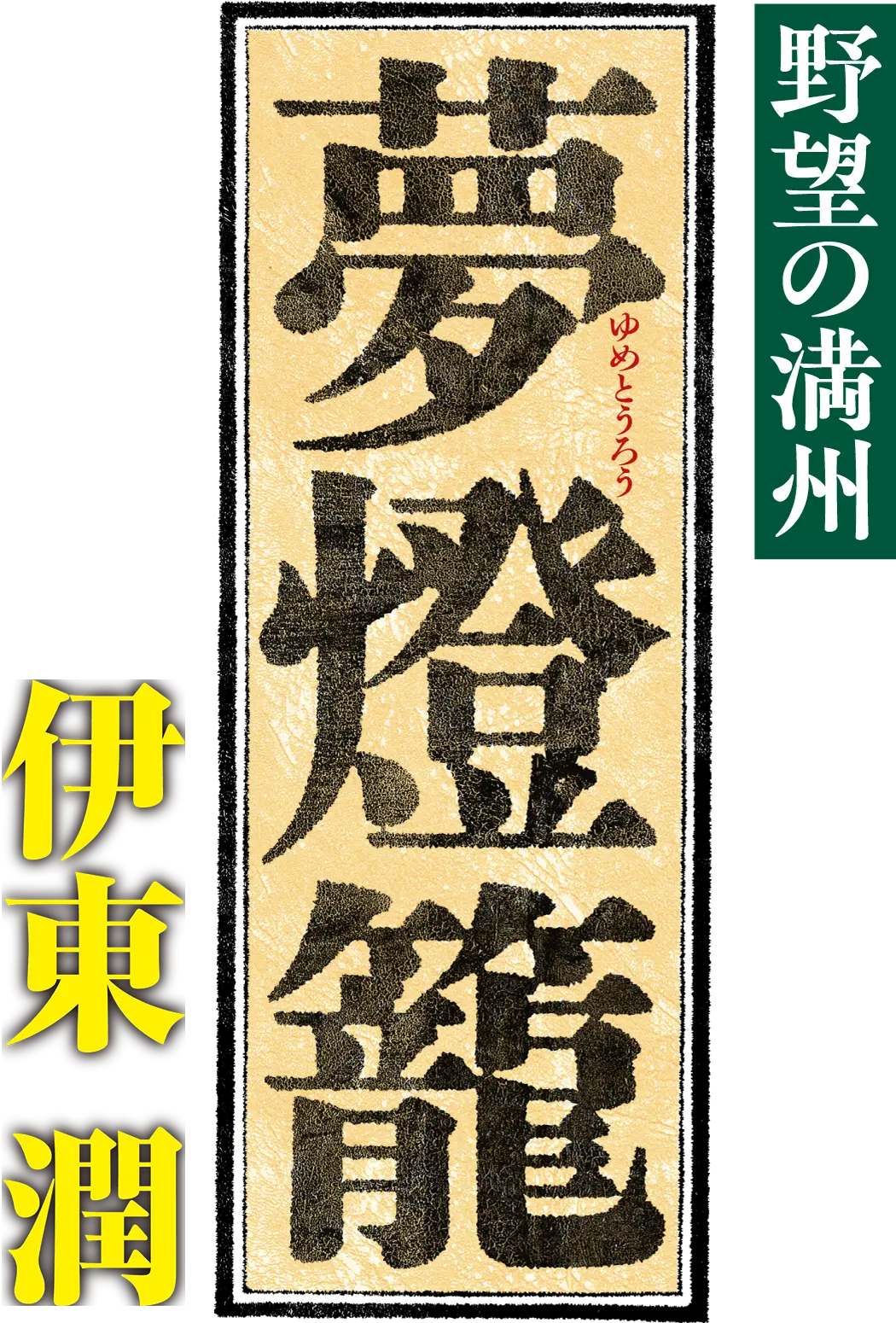
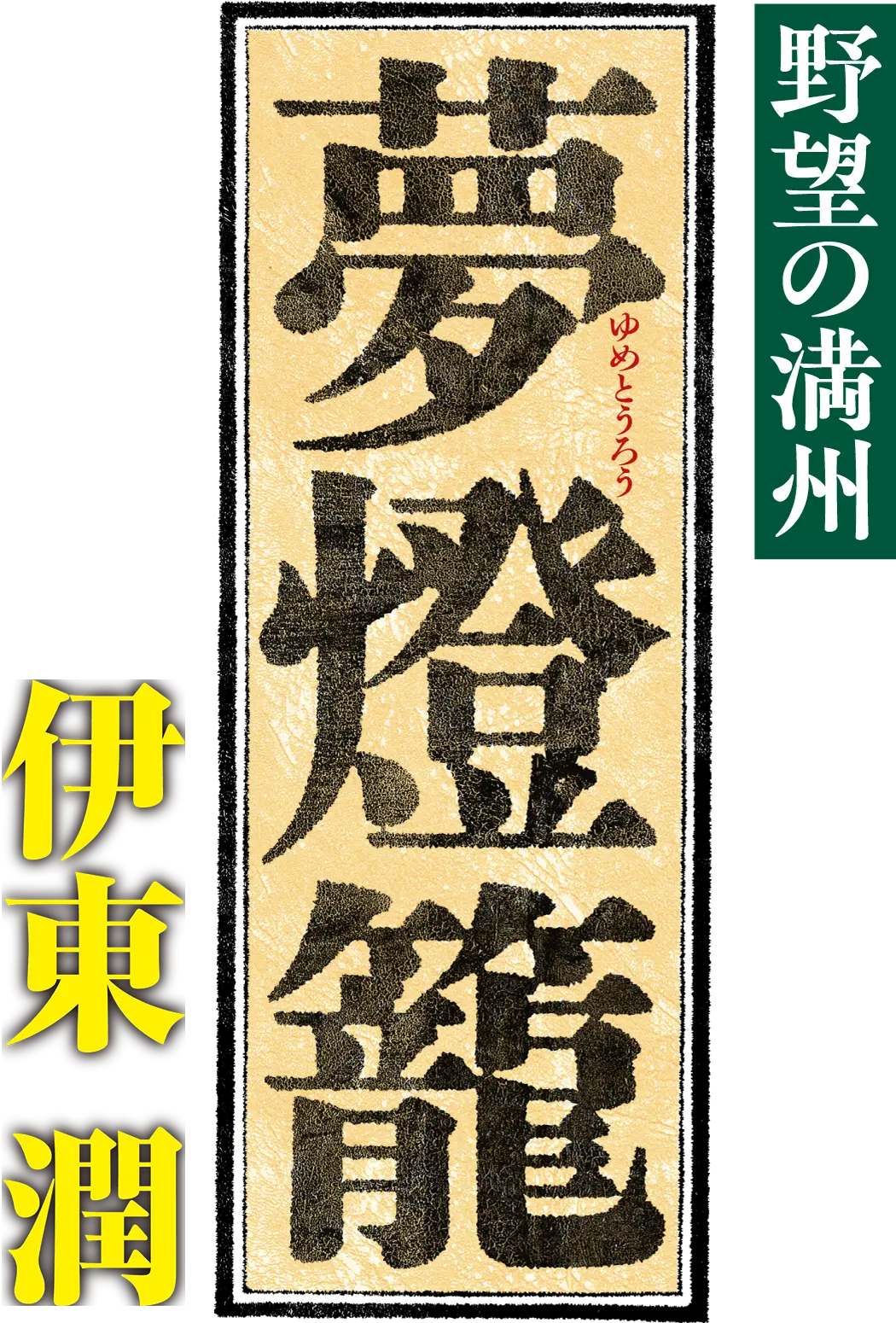
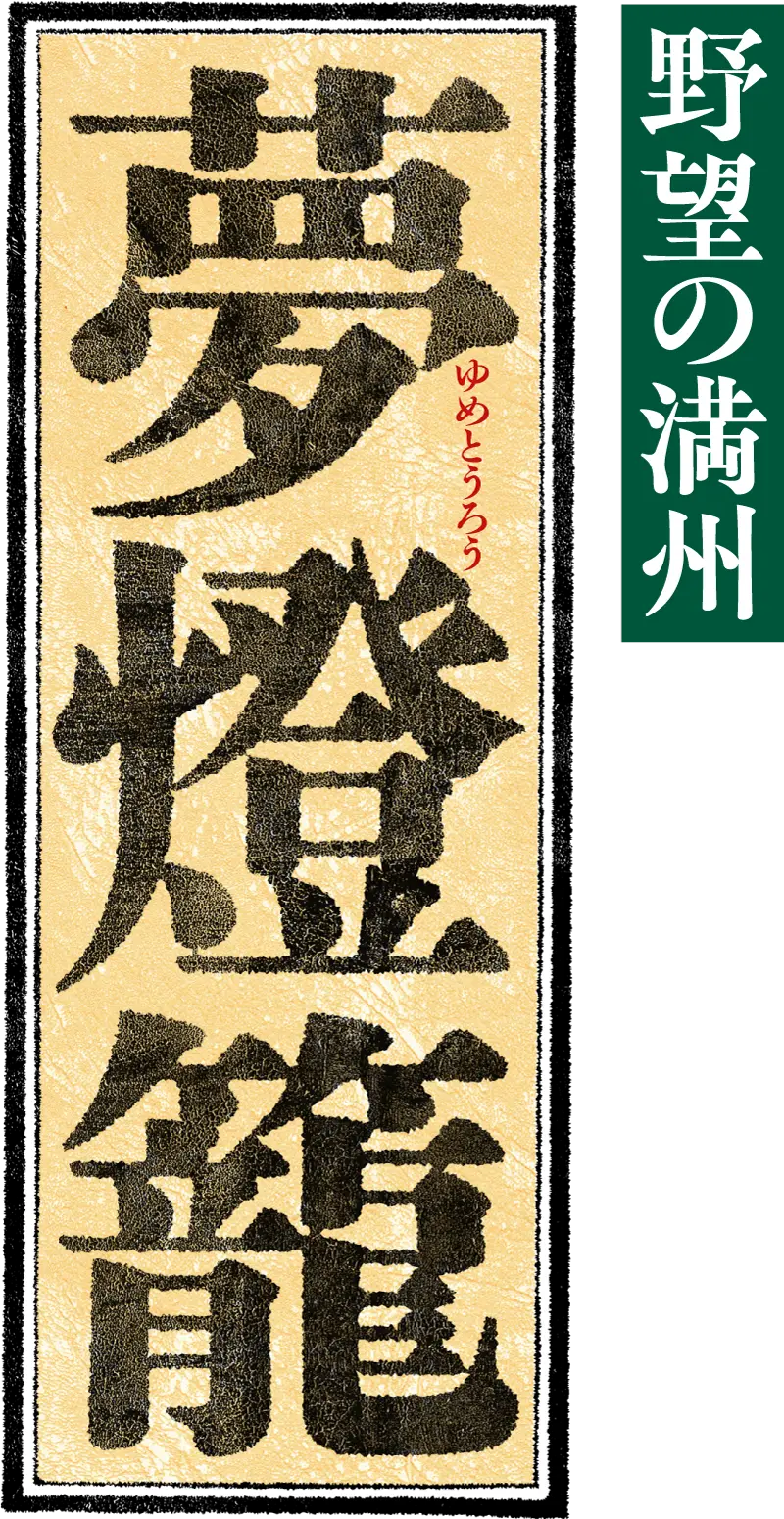

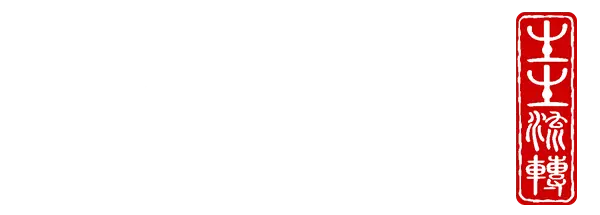






――満州を舞台にした『夢燈籠 野望の満州』は明治末から始まる大河ロマンです。読み終わって思ったのが、日本の近代史は日露戦争が頂点で、そこから下っていって昭和の軍部は最悪だったという司馬遼太郎の歴史観でした。ノモンハン事件を書く司馬さんの構想は実現しませんでしたが、伊東さんが満州を書いたのは司馬さんを意識されたからでしょうか。
伊東潤(以下:伊東) 多少は意識しました。司馬さんは『坂の上の雲』で近代に入り、山崎豊子さんも『不毛地帯』や『二つの祖国』で昭和史を掘り下げましたが、まだまだ近現代史の小説は、開拓の余地があります。本作では、近代史を点ではなく線で捉えるべく、大河小説という形式に挑みました。令和になって昭和の間に平成が挟まったことで、戦後昭和までが歴史小説の守備範囲になったと感じているので、こうした大河小説を出すにはいいタイミングだと思いました。それゆえ明治、大正、昭和、平成の四つの時代の移り変わりを、架空の人物である坂田留吉の目を通して一気に描こうと思ったのです。とくに意識したのは、なぜ小説なのか、なぜ架空の人物が主人公なのか、なぜ舞台が満州なのかという三点です。それはおいおい語っていきたいと思います。
――満州には以前から興味を持たれていたのですか。
伊東 満州は、日本が占領して傀儡国家を作ったといったネガティヴなイメージを持たれがちですが、進駐当初の日本人は、本気で理想国家を作ろうとしていました。満州国のスローガンだった五族協和も建て前に過ぎないと否定されがちですが、満州国建国の立役者の一人だった石原莞爾の本を読むと、本気で理想国家を築こうとしているんです。ですから、満州国に対するネガティヴなイメージを少し変えたいという思いはありました。最近は満州を舞台にした作品が増えているように感じていますが、それは理想国家、すなわち本来あるべきだった異世界に対する憧憬からだと思います。その意味で、満州は日本人のファンタジーなのかもしれません。
――日露戦争も満州利権と無関係ではないので、日本は明治からずっと満州を狙っていて、昭和の満州国建国に繋がります。満州を舞台にすると、日本の近代史がすべて描けることになりますね。
伊東 その通りです。満州にあったのは理想国家構築のロマンだけではありません。本作のもう一つのテーマは資源戦争です。第二次世界大戦は、資源に権益を持っている国と持っていない国が資源を奪い合った戦争です。国内に地下資源がなく、戦争にも産業にも必要な物資をアメリカからの輸入に頼っていた日本にとって、満州さえ手にすれば、資源問題はすべて解決すると思っていました。満州での資源採掘を進めたのが石原莞爾です。ただ資源開発には莫大な資金が必要で、地下資源そのものが予想より少なかったり、施設費や運搬費などの採算が合わなかったりするリスクがあります。それで東條英機らは、既に石油精製施設まであるスマトラのパレンバンやボルネオ島近くのタラカンといった地域を手に入れようとします。しかしそれはオランダの権益を奪うことになるので、列強の逆鱗に触れてしまうわけです。つまり列強が開発した東南アジアの資源を分捕ろうとした無謀な戦いが、先の大戦だったわけです。しかもそこには、東條英機と石原莞爾の感情的対立までありました。資源戦争という側面から見ていくと、太平洋戦争の実像が見えてきます。もちろん本書は小説なので、そのさわりの部分だけ描いたわけですが、関心のある方は参考文献を読んでいただきたいですね。
――作中では石原莞爾の評価が高かったですが、伊東さんはどのような人物だったと考えていますか。
伊東 私は石原を高く評価しています。石原莞爾が書いていることと実際の思惑は違うかもしれませんが、著作を読むと、五族協和という理想を本気で実現するつもりでいたと分かります。それゆえ石原にすべて任せておけば、満州国を傀儡国家から本物の独立国にしていたと思います。石原は賢明な人物なので、あのまま満州に留まっていたら、ゆくゆくは民間に下って、実業家として日満ないしは日中友好の懸け橋的存在になっていたと思います。また東條英機ではなく石原莞爾が総理大臣になっていれば、日本は戦争をしなかったのではないでしょうか。唯一、日本を救える石原を、陸軍は権力闘争で追い出しましたが、石原本人にも責任はあります。石原は頭の回転が速すぎて、周囲を馬鹿にするんです。作中では石原が四期も上の東條英機を「上等兵」と呼んでいますが、これは史実です。石原は、自分から見て能力のないと思う連中にゴマをすったり、おだててうまく付き合ったりすることができなかったんです。
――以前、国柱会から興味を持って石原莞爾を調べたことがあるのですが、伊東さんの評価と似ていて、彼は本気で五族協和を信じていて、あまりに理想主義者だったので現実主義者に満州を追われたように思えました。檀一雄『夕日と拳銃』の主人公のモデルになった伊達順之助も理想主義者だったので最後に酷い目に遭っているので、満州は理想主義者には居心地が悪かったように感じています。
伊東 当時も今もそうですが、理想主義者は現実主義者に淘汰される運命にあります。石原莞爾や伊達順之助しかりです。東條英樹は現実主義者で清濁併せ呑むことができたので、陸軍内で出世し、遂には総理大臣にまで上り詰めたわけですが、やはり理想やビジョンを持たないタイプの人なので、国家の舵取りには向いていませんでした。大切なのは理想主義者と現実主義者が折り合いつつ、うまく国家運営をしていくことです。この双方を一人で持っていたのが、政治家では大隈重信、実業家では渋沢栄一くらいだと思います。
――日本は欧米列強に差別され、それがコンプレックスになっていたので、アジアの共闘やアジア民族の平等はかなり本気で進めたと考えています。
伊東 全く同感です。その辺りは戦後の歴史観でずいぶん歪められてしまったので、夢を追っていた戦前の日本人を描くのは大切なことです。確かに、戦前も理想やビジョンを何も持たず、自分の利権の追求だけやっていた政治家や軍人もいました。しかも彼らは権力を握ることばかりを考え、短視眼的で大局観がありませんでした。その原因は軍部の人事制度にありました。海軍でいえばハンモックナンバーというやつですね。これである程度の出世が決定づけられるわけで、後で才能を開花させようと、若い頃の成績で決められた序列を覆せないのです。その逆に米国人は抜擢が多いです。チェスター・ニミッツの抜擢などは典型例ですね。学業成績がいい人は、与えられた課題をこなすのは実にうまいのですが、創造性に乏しく、不測の事態に対応する力にも乏しいように感じます。それはなぜかと言うと、目先の課題をうまく処理することで出世してきたという成功体験があるからです。
――長期的なビジョンがなく、目の前のことだけをひたすら処理しているというのは、現代の官僚組織と似ていますね。
伊東 政治家も同じで、学校教育でマークシートを重視してきたがために、解答を選ぶのはうまくても、創造性や大局観を持つ政治家が育たず、目先の利権構造をいかに守るかばかりを考えてしまうのです。私は外資系企業に二十二年もいたので分かるのですが、今の日本の教育では、世界に通用する人材は輩出できないと思います。大企業が衰退していくのは、次第にお利口さんばかりを採用してしまうことで同質化が進み、企業のダイナミズムが失われていくからです。しかも始末に悪いのは、マークシート教育の申し子ほど、自分だけは大局観も創造性もあると勘違いしていることです。
――興味深かったのは、張作霖爆殺事件の解釈でした。列車に乗っていた張作霖は、線路脇に仕掛けられた爆弾で暗殺されたとされていますが、実際、爆弾は別のところにあって、その計画に留吉の長兄の慶一がかかわったとされています。爆弾を仕掛けた位置が定説と違うというのは、伊東さんの独自の解釈なのですか。
伊東 その部分は、加藤康男さんの『謎解き「張作霖爆殺事件』(PHP新書)を参考にしました。河本大作大佐は線路に爆弾を仕掛けたのですが、写真を見ると、線路はそのままの状態で、列車の天蓋が破壊されています。これは証言と不一致なので不自然です。河本大佐は自分がやったと証言していますが、あれはソ連や中国共産党に言わされた感が強いと思います。当時、ソ連と中共は蜜月関係にあったので、日本の仕業にしようと口裏を合わせた可能性があるのです。ただ、日本にも張作霖を殺すとメリットがあったのは確かで、メリットがある以上は実行した可能性もあり得ます。ここだけでは新解釈を語り尽くせませんので、関心のある方は本文をお読み下さい。
――事件後に慶一は逃走して、兄を捜すため留吉が満州へ渡ります。留吉の調査を通して描かれる満州の描写には、リアリティがありました。
伊東 満州の本は昔から読んできたので、雰囲気を出すために阿片や馬賊なども細かく描写しました。特に大連は丁寧に書いたので、当時の満州に読者をお連れできると思っています。
――史実に沿っているので、石原莞爾は満州を追われ、資源開発も縮小されていきます。もし石原莞爾が満州にいたら、歴史は変わっていたと思いますか。
また、石原莞爾は、アジアを一つにして日本の国力を高め、最終的にアメリカと決戦する構想を持っていました。石原莞爾が健在でも、アメリカとの戦争は避けられなかったのでしょうか。
伊東 間違いなく変わっていたでしょうね。実は、戦後すぐに満洲で大慶油田が発見され、中国のエネルギー事情は一変します。それを戦前の日本が発見していたら、太平洋戦争はなかったわけで、実に無念なことです。またアジアが一丸になって米国に決戦を挑むという石原の構想は、満州国を理想国家にしようとしたこと以上に夢ですね。日本人のリーダーシップでは、中国はついてきません。アジアはヨーロッパ以上に文化圏が独立しており、互いに折り合える点を見つけて一致するなど困難を通り越して不可能です。とは言うものの、石原ならまとめ上げてしまったかもしれませんね。石原とは、それだけ器の大きな人物です。
――ヨーロッパの戦争は賠償金目的の小競り合いでしたが、総力戦だった第一次大戦で戦争が国家の命運を左右すると気付き、戦争が起こらないよう国際連盟を作りました。日本は第一次世界大戦に参戦しましたが、火事場泥棒的にドイツがアジアに持っていた土地と利権を手にしたくらいで、国家が存亡の危機に立つような戦争は経験していません。それが太平洋戦争に突入させたように感じています。
伊東 日本人は近代戦が総力戦であり、民間人まで戦渦に巻き込まれるとは思ってもいなかったはずです。つまり戦争をして負ければ、すべて失うという意識が、日本人には皆無だったのです。大隈重信を描いた拙著『威風堂々(上)幕末佐賀風雲録』『威風堂々(下)明治佐賀風雲録』(中公文庫)で、大隈は第一次世界大戦を見て、日本は傷ついていないから、ヨーロッパが立ち直る前に工業製品をどんどん売りつけようと言っているんです。他人の戦争につけ入ろうというのはさすが大隈ですが、彼や明治の元勲たちは、日本が第二次世界大戦の当事者になるなど考えもしなかったでしょうね。
――物語は、坂田留吉という架空の人物が歴史的な事件にかかわることで進んでいきますが、このスタイルを選ばれたのはなぜですか。
伊東 本作は、後景で歴史が流れ、前景で架空の人物が活躍し、その間で実在の人物と架空の人物が様々なかかわり方をするという小説ならではの形式です。こうすると架空の人物を自由に動かせるので、面白い物語になるんです。本作を書くにあたって、実は夢のお告げのようなものがあったんです。ある日、短い夢を見たんです。それは少年とおばあさんが黙って庭の燈籠を見つめているという構図だけなんです。しかしそれがなぜか江ノ島だと分かり、すると、どんどん物語の骨格ができていきました。いつか大河小説を書きたいと思ってきたのですが、漠然と思っていただけで、この夢をきっかけに一気に物語が膨らんでいきました。つまり移り変わる時代を睥睨する不変なものの象徴として燈籠を物語の中核に据え、主人公が自分の進むべき道や大局観を失いそうになるたびに燈籠と語り合い、正しい選択をしていくという設定ですね。それでタイトルを『夢燈籠』にしました。
――明治四十一年に生まれた留吉は、関東大震災、二・二六事件、満州での資源開発などにかかわります。学生時代は友人たちと馬鹿騒ぎをする学園ものですが、満州で行方不明になった兄を捜しに行くところはミステリー、石原莞爾に認められ満州の資源開発にあたったり、二・二六事件で重要な役を頼まれたりするところは経済小説、政治ドラマになっていました。作中に様々なジャンルを織り込むのは、最初から考えていたのですか。
伊東 ビルドゥングスロマン(成長物語)でスタートし、次第に歴史ミステリーや政治ドラマ的な要素を取り入れ、石油採掘のところは冒険小説風にしました。大河小説にするつもりだったので、歴史、冒険、サスペンス、ミステリー、経済、そして恋愛といった小説の諸要素をデパートのようにちりばめるというのは、構想段階から考えていました。また本作は、『青春の門』『しろばんば』『楡家の人々』『人間の条件』といった昭和の名作から影響を受け、それらを自分なりに消化した上で、作品に結実させた側面もあります。読んでいて、「あっ、ここがオマージュないしは本歌取りの部分か」なんて気づいていただければうれしいです。
――留吉は、悲惨な最後を遂げた母の出来事で「人生は自分で選び取る」との教訓を学び、それを実践しようとします。戦争へ向かう抗い難い大きな流れが出来ていた昭和初期に、自分で選択し人生を切り開こうとする留吉の姿は、現代人へのメッセージのように感じました。
伊東 戦後八十年が経過しようとしている今、日本だけでなく世界が羅針盤のない時代に突入したと思います。これからの日本は米国に追随せず、自分の運命を自分で選び取っていかねばならないのです。昭和二年に自殺した芥川龍之介は、「何か僕の将来に対する唯ぼんやりとした不安」という(久米正雄に宛てたとされる)遺書を残していますが、芥川はこれからの日本が戦争に向かっていくと予感し、それを漠然とした不安と表現したのではないでしょうか。これは現代の若者たちも同じで、将来への不安をいつも口にしています。こうした状況が芥川の感じていた不安と重なります。だからこそ誰もが不安を感じていた昭和初期に、自分で人生を選び取ろうとあがく留吉の生き方を描くことで、現代を生きる若者たちの羅針盤になるのではないかと思ったのです。
――学生時代の留吉は現代の若者と変わらない学校生活を送っていますが、関東大震災で被災し、二・二六事件に巻き込まれ、石原莞爾と親しくなり軍の派閥抗争の現実などを知ることで、平和な日常がいつ壊れるか分からないと知ります。ここにも、現代との共通点を感じました。
伊東 歴史小説は現代の映し鏡であらねばならないと常々思っていますが、まさに昭和初期は現代と同じで、大きな変化がめまぐるしく訪れた時代でした。3.11やウクライナ戦争で分かる通り、自然災害や国家間の軋轢によって、当たり前の日常が瞬時に失われるわけです。自然災害は致し方ないのですが、為政者たちの判断一つで自分たちの生活が一変させられるのはたまりません。しかし今の日本も安全圏に身を置いているわけではなく、権威主義国家の為政者たちの思惑一つで、ウクライナと同じ悲劇が起こるかもしれないのです。本作を通して、平穏な日常はそれほど堅固なものではないという現実を知っていただきたかったんです。
――関東大震災を大きく扱ったのは、そのためですか。
伊東 関東大震災は日本の近代史では外すことができない大きな事件です。こうした自然災害によっても人の運命は大きく変わります。個人ではどうにもならない、こうした事態に、われわれは巻き込まれることもあるんです。それでも運命を受け容れつつ最良の選択をしていく。そしてアゲインストな状況に立ち向かっていくことが大切だと訴えたかったんです。
――昭和八年に東京の千駄ヶ谷で一人暮らしを始めた留吉の部屋へ、酔った中原中也が入り込みます。この時期、留吉は帝都日日新聞で働いていて、留吉に中也が天才的な詩人だと教えてくれるのが文化部長で詩人でもある草野心平で、さらに留吉は中也と長谷川泰子の恋愛騒動に巻き込まれてしまいます。別のところでは、農商務省官僚の平岡が長男の公威(後の三島由紀夫)を連れているなど、近代文学の有名人が随所に顔を出しているのは、なぜなのでしょうか。
伊東 政治や軍事の話ばかりだと、読者が疲れるからです。昭和初期は軍人が威張っていて息苦しい時代と思われがちですが、常識にも倫理にも縛られない中原中也のような自由人もいて、そうした文人たちの無頼ぶりを読者に知ってほしいということもありました。私は中也の自由詩が若い頃から大好きで、その関係で多くの研究書も読んできました。実は、私は中也の帽子とマントのレプリカを持っているくらいの中也フリークなのです。中也を主役にした小説が書きたいと思っていたので、まずは本作で脇役として登場いただきました。最近知ったのですが、中也と小林秀雄と長谷川泰子の微妙な関係を描く「ゆきてかへらぬ」という映画が来年の二月から公開されるようですね。見るのが楽しみです。
――昭和九年頃に、弾圧で運動としてのプロレタリア文学が崩壊し、プロレタリア文学に批判されていた作家たちが息を吹き返して、いわゆる文芸復興が始まります。この時期は、モダニズムが最後に光を放っていて、カフェやダンスホールが人気でした。この時期の明るい一面が描かれていたのも興味深かったです。
伊東 戦前の昭和は暗い時代という誤解があるので、それを覆したいという思いはありました。今回の執筆にあたってプロレタリア文学も一通り学びましたが、当初の構想ほどは盛り込めませんでした。あれもこれもという感じにはできないですからね。日本におけるモダニズムの時代もいつか書きたい題材ですね。
――最後に、今後の展開を教えてください。
伊東 まだはっきりしていないので語りにくいのですが、戦後復興をどう描いていくかですね。その中でキーマンの一人が横田英樹です。今回、物語終盤から登場した彼のような成り上がりの人物が巨万の富を築けたのも、戦争によってすべてが覆った時代だからです。何が中心になるかと言えば、乗っ取りとか総会屋とかの経済戦争ですね。また東大生が闇金を経営した光クラブ事件、同じ東大出身で光クラブ事件をモデルにした『青の時代』を書いた三島由紀夫なども、時代を象徴する人として登場願おうかなと思っています。もちろん構想段階なので、まだどうなるかは分かりませんが、留吉が戦後の昭和の大きな事件とどうかかわっていくかを書きたいと思っています。そして留吉がどんな選択をして、どんな人物となっていくかは読んでのお楽しみとさせて下さい。
いずれにしても、短いもの全盛の現代において、読者と汗だくで格闘できるような二段組の大作を出せたというのは、作家冥利に尽きることです。長い小説が好まれなくなっている今だからこそ、長編小説の醍醐味を知ってほしいという思いが込められたこの大河小説を、令和の大衆文学を照らすような燈籠にしていきたいと思っています。



1960年、神奈川県横浜市生まれ。早稲田大学卒業。『黒南風の海――加藤清正「文禄・慶長の役」異聞』で第1回本屋が選ぶ時代小説大賞を、『国を蹴った男』で第34回吉川英治文学新人賞を、『巨鯨の海』で第4回山田風太郎賞と第1回高校生直木賞を、『峠越え』で第20回中山義秀文学賞を、『義烈千秋 天狗党西へ』で第2回歴史時代作家クラブ賞(作品賞)を受賞。近著に『江戸咎人逃亡伝』がある。