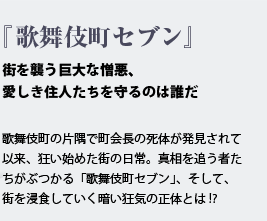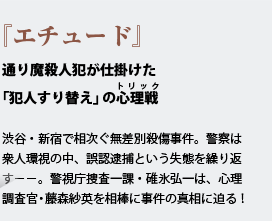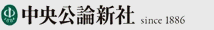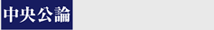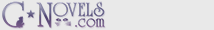警察小説ブーム
- ――『歌舞伎町セブン』は、警察官が重要なキャラクターのひとりですが、必ずしも「警察小説」のジャンルには収まらない作品ですね。
-
誉田
そうですね。三人の視点人物がいて、ひとりが地域課の警官なので、警察小説としての純度は33%くらいでしょうか(笑)。
- ――今、「警察小説ブーム」と言われ、今野さんは大ベテランとして、誉田さんは新風を吹き込んだ俊英として、それぞれ押しも押されもせぬ存在です。1988年から『安積班』シリーズを書かれている今野さん、ブームの理由は何でしょうか。
-
今野
 そのせいで、編集者が警察小説しか書かせてくれない(笑)。うーん、理由はちょっとよくわかんないんです。ブームといっても理由はないよね。
そのせいで、編集者が警察小説しか書かせてくれない(笑)。うーん、理由はちょっとよくわかんないんです。ブームといっても理由はないよね。
-
誉田
そうですねえ。今野さんがお書きになり始めた頃は、まだ警視庁に生活安全課とかない時代ですか。
-
今野
ないです。保安課とか保安部のころ。
-
誉田
僕はもう組対(組織犯罪対策課)ができている時代にスタートしてるので、ベースになっている警察組織自体がだいぶ違いますね。
-
今野
そうですね。で、ブームに理由はないと思うんですけど、例えば、バブルの時代とか景気のいい時代って、一匹狼、アウトローがウケるんです。会社員になることが簡単だった時代は、組織からはみ出すことがカッコよかった。でも今は、不景気で会社員になること自体が大変なんですよ。
-
誉田
ああ、確かにそうですね。
-
今野
だから組織から出たくないんですよ。なんとかしがみついて、組織の中でうまくやっていこうとする気持ちがサラリーマンの間で強い。警察は組織で動きますし、個人対組織という話がどうしても出てくるので、それがウケる要素の一つかなと思うんです。景気はけっこう反映しますね。大沢在昌さんの『新宿鮫』が一匹狼ですよね。90年、バブル崩壊の直前でした。
- ――誉田さんも『ジウ』や『ストロベリーナイト』などで一匹狼的な刑事を書きつつも、全体としてはチームという印象が強いですよね。
-
誉田
そうですね。やっぱり組織は、面倒くさいから面白いんだと思うんですよね。ひとりの刑事がいろいろな事件を担当できたら面白いけれど、組織の枠組み上できない。そうすると、別の事件はもう一人の刑事が担当して、ふたりの間でどう連絡をとらせるかとか、物語を作る上では制約なんですが、それを織り込んでいくことで人間味が出せる。
-
今野
 面倒くさいから面白いってのは、その通りですね。ゲームは制約が多いほど面白い。制約があったり問題が生じるから小説が書けるわけで(笑)。
面倒くさいから面白いってのは、その通りですね。ゲームは制約が多いほど面白い。制約があったり問題が生じるから小説が書けるわけで(笑)。
-
誉田
僕がいつも思うのは、警察官は本当は「ロボコップ」が一番だと思うんです。強くて正しくて平等で。だけど、人間である以上、そんなはずはないのであって。弱い市民をいじめる警官も、ヤクザに職務質問できない警官もたくさんいる。でも、それを「できてねえじゃねえかよ」ってつつくのではなくて「ああ、同じ人間なんだな」って見えたほうが面白いんじゃないかなと思いますけどね。
- ――誉田さんは、取材はどのようにしていますか。
-
誉田
細かいことはやっぱり警察関係者に聞かないとわからないので、「捜査本部が立った時、布団はどうするんですか」とか「女子寮ってどういう感じなんですか」とか(笑)。
-
今野
誉田さんの主人公は女性警察官が多いから、女子寮を書かざるをえない(笑)。
-
誉田
そうなんですよ(笑)。大まかな情報源は表に出てる資料とか書籍ですが、どうしてもわからないところは直接聞きます。
-
今野
その点、昔の警察小説は大ざっぱだったよね。捜査一課が5人しかいなかったりね(笑)。
-
誉田
それはすごい(笑)。
 そのせいで、編集者が警察小説しか書かせてくれない(笑)。うーん、理由はちょっとよくわかんないんです。ブームといっても理由はないよね。
そのせいで、編集者が警察小説しか書かせてくれない(笑)。うーん、理由はちょっとよくわかんないんです。ブームといっても理由はないよね。
 面倒くさいから面白いってのは、その通りですね。ゲームは制約が多いほど面白い。制約があったり問題が生じるから小説が書けるわけで(笑)。
面倒くさいから面白いってのは、その通りですね。ゲームは制約が多いほど面白い。制約があったり問題が生じるから小説が書けるわけで(笑)。