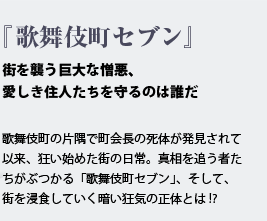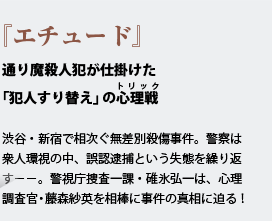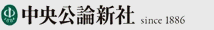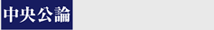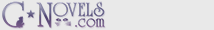大人と若者
- ――今回、『エチュード』で碓氷警部補は非常に家庭的な一面というか、よき父親の顔を見せますよね。
-
今野
そうなんですよ。最近は家庭を書かないとね、読者が文句言うんですよ(笑)。
- ――あ、そうなんですか(笑)。
-
今野
それは冗談ですけど、警察小説というのは長いあいだ「捜査小説」だったんです。その歴史がずっと長かったんですけれど、警察官をミステリーじゃなくて「小説」として描こうとした時、警察官にだって家族がいるわけで、それを描かないわけにはいかなくなってくるんですよね。
やっぱり若者と大人という対比がいつも気になっているんです。われわれの年になるとどうしても若者の素行が目につくわけで(笑)。社会に荒れた若者がいっぱいいるのは大人の責任なんですよ。それが凝縮された、社会の最小単位が家庭でしょう。犯罪にいつも仕事として関わっている警察官も、家に帰ると息子とか娘に向かい合わなければいけない。事件よりそっちのほうが面倒くさかったりするんですよね。そういう話はやっぱり書かざるをえなくなってきますよね。
- ――今野さんの小説には、大人がしっかりしないと子供はダメになるんだという視点が常にありますね。
-
今野
いや、親がしっかりしててもダメになる子供もいるけれど、あまりにも大人が無責任過ぎるなと感じることが多いので。現象を見て若者ばかり責めてもしょうがない。これはそういう社会作っちゃった俺たちの責任だってことを考えなきゃいけないんだね。
- ――誉田さんは、荒れる若者の心情みたいなものに共感しますか。
-
誉田
いや、そうでもないですね。実は、尾崎豊が好きじゃなくて、「この支配からの卒業」って、僕は若い頃も、別に支配されてるつもりはなかったし、多分向こうもしてるつもりないだろうなと思ってました。校舎の窓ガラス壊しても解決しないよって思っちゃうタイプなんで。大人に反抗するんじゃなく、ちゃんと大人になれよと思いますね。
- ――今回、誉田さんの『歌舞伎町セブン』にも、親子や家族というテーマが隠されていますよね。
-
誉田
僕の場合、なんでそういう人になっちゃったかという理由を、それまでの家庭環境や育ちに求めて、多視点で描くことが多い。『歌舞伎町セブン』もそうですね。年を重ねると若者の乱れが目につくというのはその通りですが、今の大人にも若い頃はあったはずで、繰り返しなんだろうなと思います。僕らの時はブームになるような若者文化は目立った形ではなかったですけど、もうちょっと上の世代だと竹の子族とか、今から見るとかなり恥ずかしい。常に若者は恥ずかしいもの、カッコ悪いものですよね。
-
今野
そうですね。今おいくつ?
-
誉田
41です。
-
今野
そうすると14歳、一回り以上違うんだねえ。俺なんかはすぐ上が全共闘世代なんです。あいつらがもう元気よく暴れてるのが楽しそうで......。
-
誉田
楽しそうなんですか、あれは。
-
今野
楽しそうでしたよ。あれ、だってブームですもん、全共闘ってお祭りですもん。
-
誉田
僕らなんかもう、ソ連が崩壊した後に全共闘のことを知ったので、この人たち何をやってんのかなと......。
-
今野
いや、当時『資本論』読んだ人はあの中の1%にも満たないと思う(笑)。後半は内ゲバになって、ちょっと怖いんですけど、その怖さもヒリヒリした感じで、楽しんでたんじゃないかな、みんな。
- ――最近、1968年の全共闘運動とか、70年安保についての本がずいぶん出てるし、注目されてますよね。
-
今野
その世代がちょうど定年を迎える頃なんですよね。世の中からリタイアしていくことへの郷愁が多分あるんだと思う。で、警察もそうなんです。全共闘世代ってやたら当時のことを懐かしがってしゃべるんですけど、当時、機動隊にいた人なんて元気でしょうがない。「俺たちはあのとき戦争してたんだ」みたいな話で。その人たちが現職のノンキャリアだと警部クラスで、一斉に退官する年になった。捜査能力がガタ落ちになるって、警察の「団塊問題」と言われているらしいです。