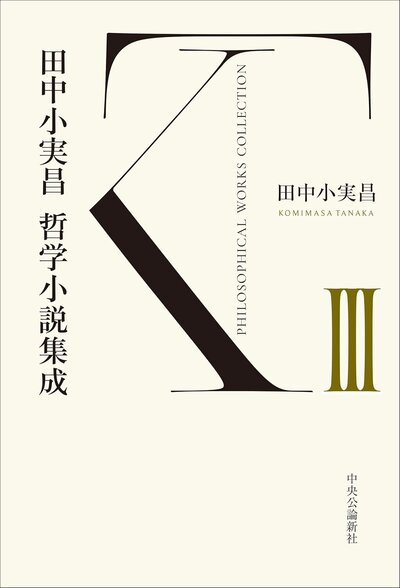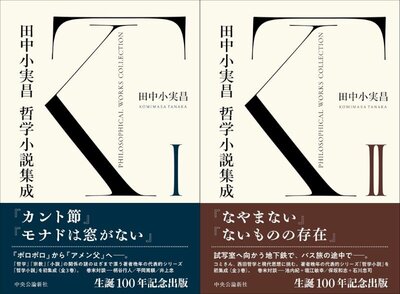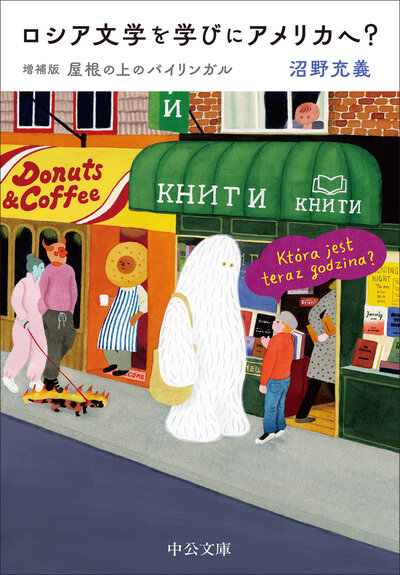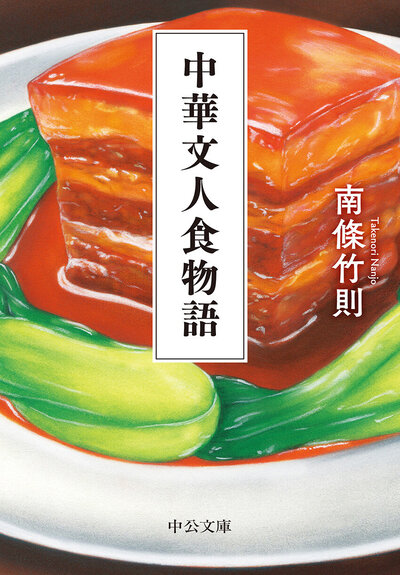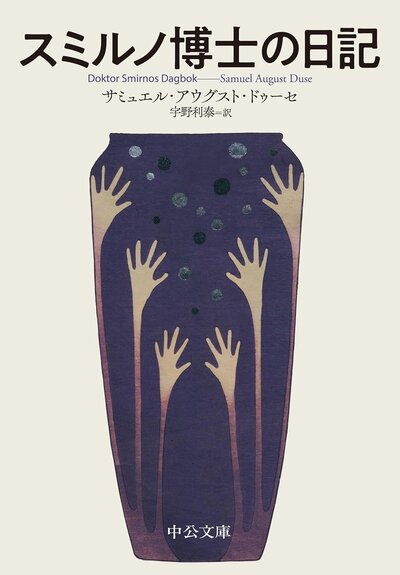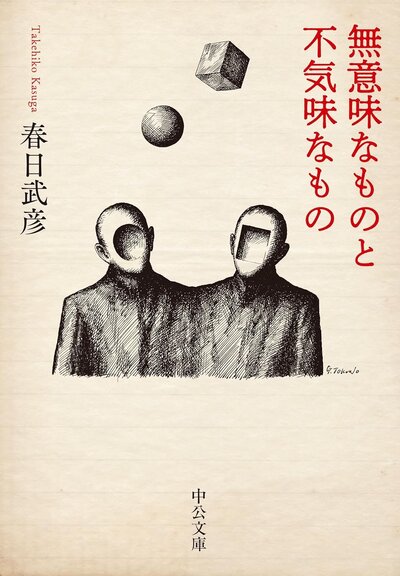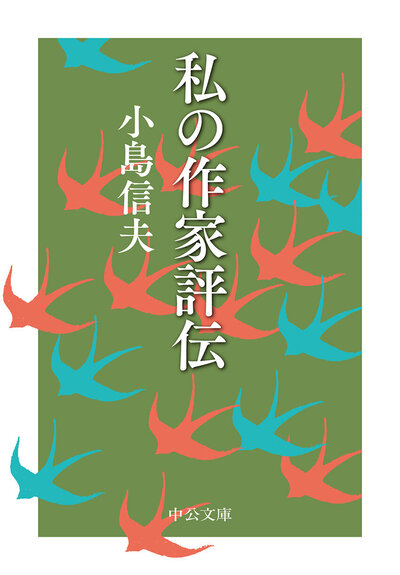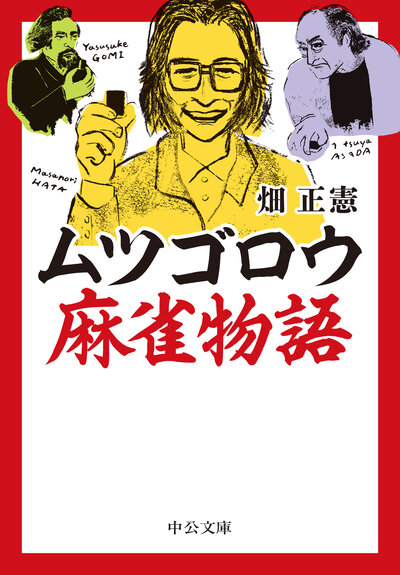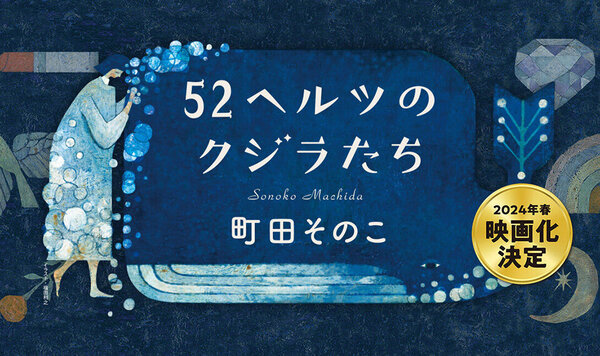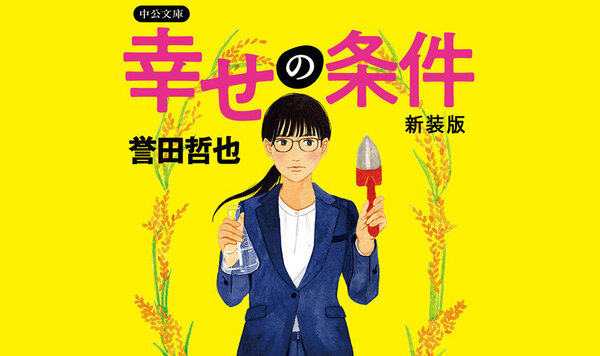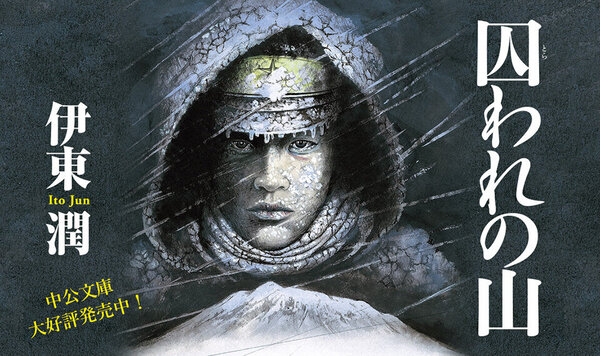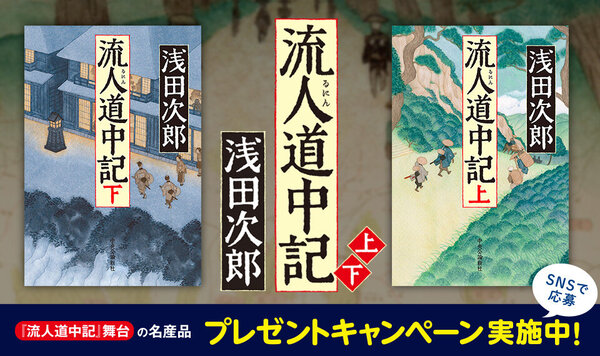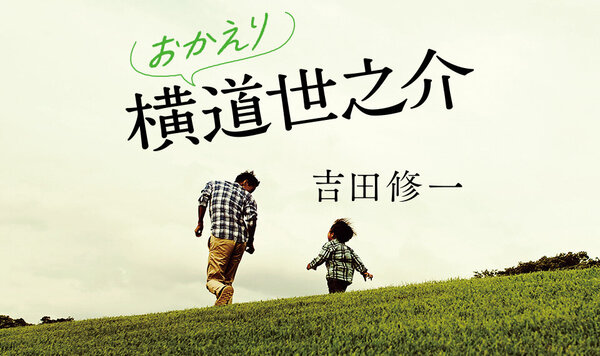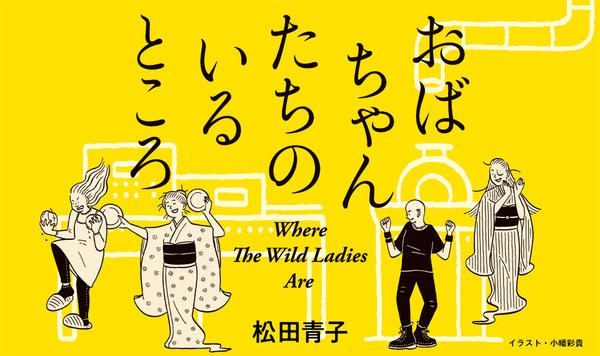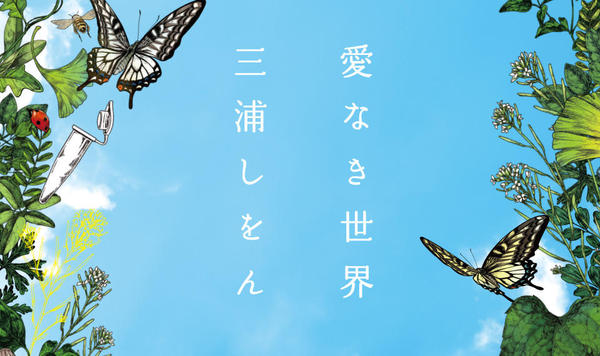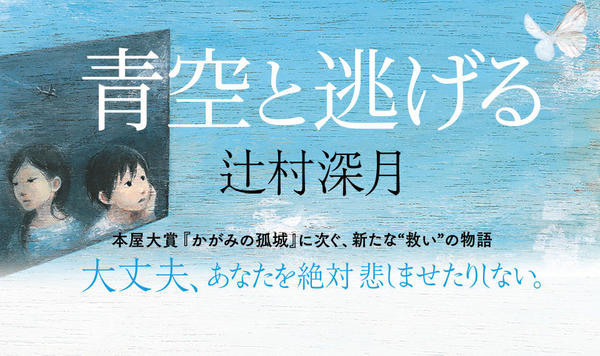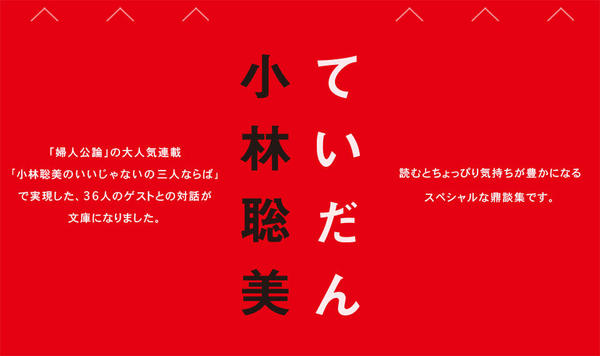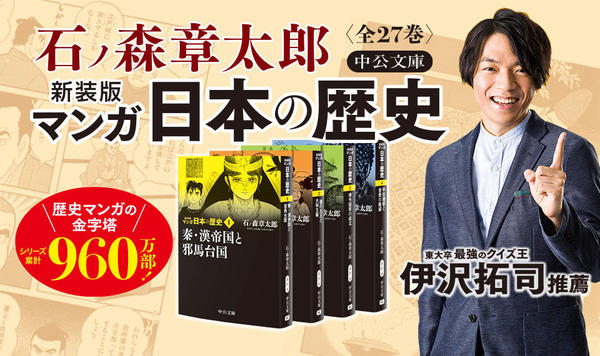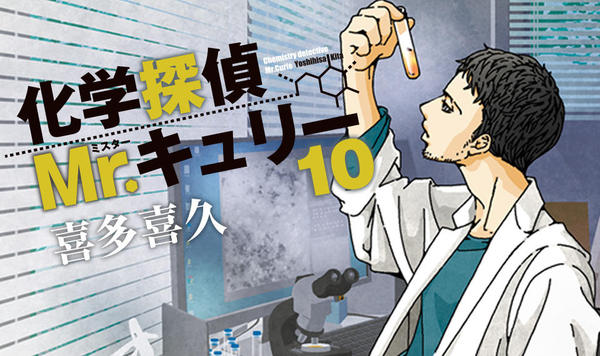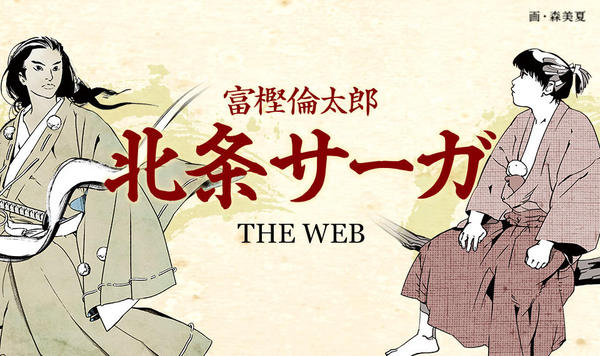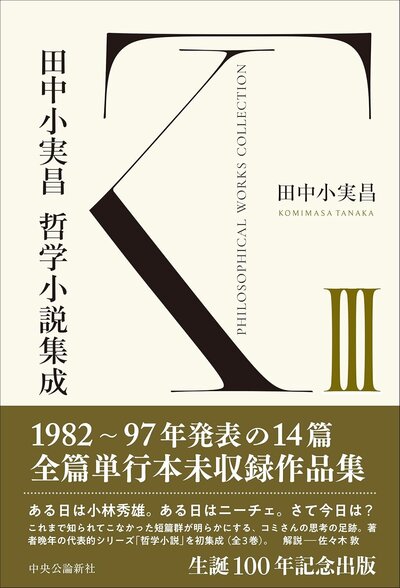
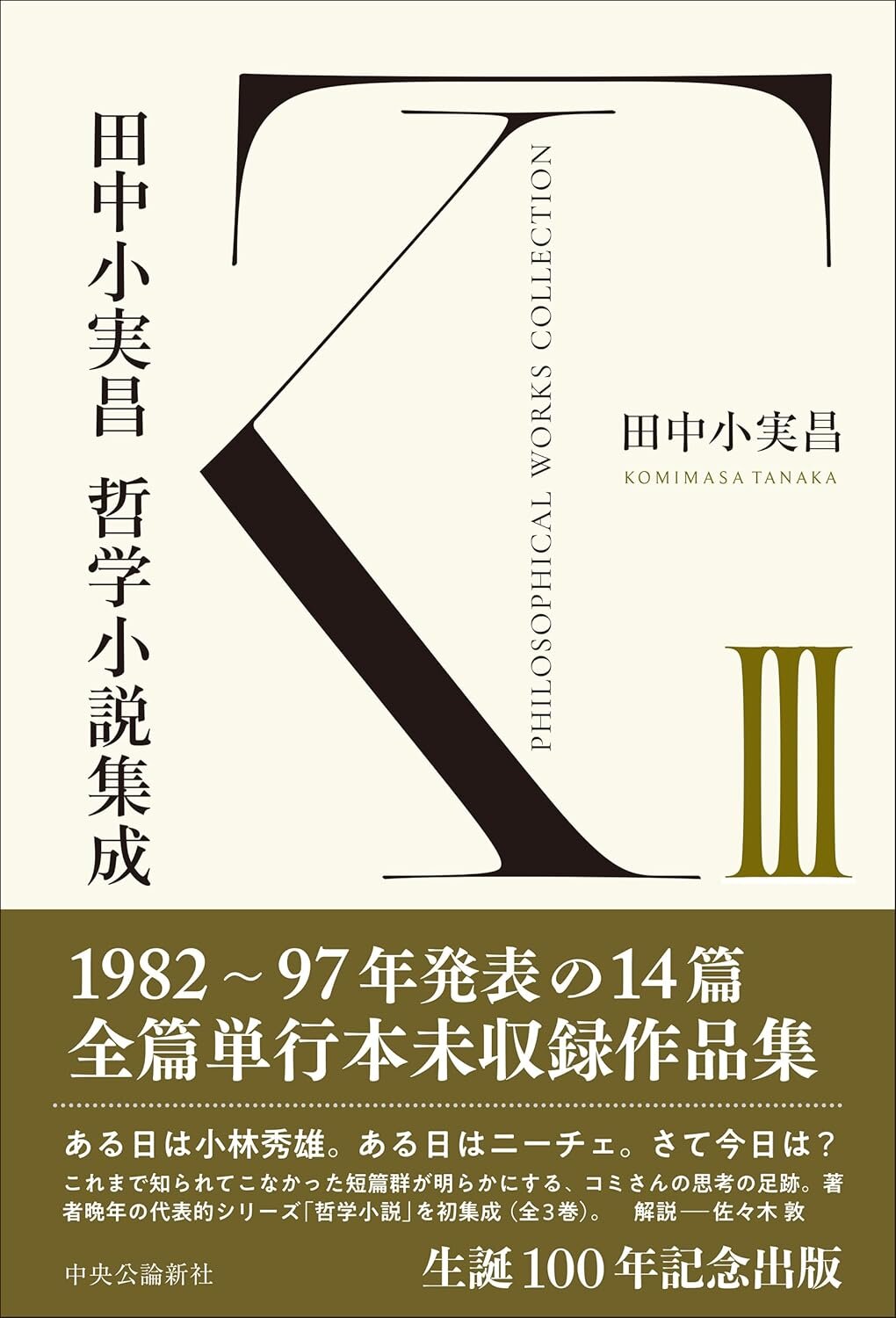
2025年3月、単行本新刊にて、『田中小実昌哲学小説集成 Ⅲ』を刊行しました。
著者晩年の代表的シリーズ「哲学小説」をまとめる生誕百年記念企画として、1月に刊行した同Ⅰ/Ⅱに続く、全三巻の最終巻です。
前の二冊とは違い、今回はすべて単行本未収録の14篇。いずれの短篇も、初めて読むという方が多いと思われます。
全三巻を通じて浮かび上がる、謎に満ちた「哲学小説」の姿とは......。
以下、担当編集者による紹介です。
企画のきっかけ
「哲学小説」というフレーズは元々、田中小実昌の短篇集『カント節』(福武書店、1985年)で用いられたキャッチコピーでした。
その概念を敷衍して、他の単行本未収録作品にも適用して編んだのが、今回の第Ⅲ巻です。
きっかけとなったのは、二つの短篇。
十年ほど前、古い文芸誌をめくっていたら、「あるかたち」(1993)という短篇に遭遇しました。小林秀雄の『本居宣長』を読んでいく、という、読書ノートのようなもの。(へー、コミさんも小林秀雄を読んだのか)ぐらいに当初は思っていました。
次に出会ったのが、「こころのコトバではなく」(1993)。同級生の哲学者・井上忠による当時の新著『超=言語の探究』を引用しながら感想を付していく、これも読書ノート型の一篇。
ここまでくると、(ははあ)と検討がつきました。そういえば、昔、「哲学小説集」と称された短篇集が何冊かあった。田中小実昌の単行本未収録作品の数は膨大だから、その中に、あの「哲学小説」系統の短篇も、きっといくつかあるのだろう。コミさんが『本居宣長』について語るっていうのは、なかなか新鮮だし、ほとんど知られていないはず。これは覚えておいたほうがいいかもしれないぞ――等々。
それから、ポツポツ短篇探しが始まりました。
「哲学小説」はいつ始まったのか?
では、「哲学小説」はいったい、いつ頃から書かれだしたのでしょうか。
一般的には、『カント節』の最初にある「ジョーシキ」(1983年6月)と見なされているかもしれません。実は、それ以前にも、父親の説教集をえんえん引用する「十字架」(1983年2月)という短篇があります(のち『なやまない』所収1988)。では、その頃なのか。
コミさんの作家的キャリアというと、最初は翻訳(と同時に同人誌に純文学を執筆)、そのあと娯楽雑誌に執筆、一方でしだいに純文学誌にも書くようになり、「ポロポロ」(1977年12月/単行本は1979年5月)以降はしだいに「コミマサ節」としかいいようのないエンターテインメントとも純文学とも括りがたい独自の路線へ......というふうに認識されているのではないかと思います。
実際、「ポロポロ」のような作品を書いてしまった後では、ふつうの意味のエンターテインメントは、作家としてもう書けないのではないか、とは誰もが思うところ。
ところが現実には、短篇集『ポロポロ』で谷崎賞を受賞(1979年)する前後にも、ミステリなどのエンターテインメント作品をコミさんは書いています(たとえば、その直前の1979年1月に発表された「叔父の日記ノート」という短篇[『ひとりよがりの人魚』所収]などは、かなりウェルメイドな――これぞエンターテインメントと断言できる――メタミステリ・ホラーの傑作です)。
最高傑作として絶讃されることの多い「ポロポロ」ですが、「地獄でアメン」(1985/『カント節』所収)によれば、実は、「作家自身の創作原理の種明かしであり、それを小説にするのはつまらない」と批判した作家がいたそうです。
都筑道夫です。
早川書房時代から仲の近い二人なので、コミさんも少しは気にしたかもしれません(だから「地獄でアメン」にも書いた)。しかし、「哲学小説」とは、いってみれば「ポロポロ」路線の継続ないし拡大ですから、ここに田中小実昌VS都筑道夫の作家的方針の違いを見ることもできそうです。
今回初収録した中で最も古い短篇は、「カント通りまで百メートル」(1982年3月)。その末尾に、最近〈小説が読めなく〉なった、とあります。そこから推測すれば、おそらく80年代初頭に、〈小説は読めないが、哲学書なら読める〉という状態になり......書く方面においても、それが晩年まで続いていったのではないか?
「哲学小説集成」への収録基準
さて、ひとくちに「哲学小説」といっても、その内容はバラバラです。先に挙げたような読書ノート型の作品を、仮に「純粋哲学小説」とすれば、ある時はその本を入手した状況や、読みながらの日常、旅先の光景などが入り......ある時はそれが全面化して、哲学書からの引用はほぼ消える......。
今回、収録にあたって頭を悩ませたのが、この基準です。読書ノート型はなるほどわかりやすい。しかし、私小説型、旅日記型で、ほんのわずかに哲学の話になる短篇も数多い。極論をいえば、コミさんの小説はぜんぶ哲学小説なのかもしれない。となると......どこまでを収録すればよいのか。
というわけで、比較的「哲学への言及の度合い」が高い方から順に選んでいったのが、第Ⅲ巻に収めた14篇。なので、近い内容の短篇は、他にもあります。皆さんもぜひ、「この短篇も哲学小説なんじゃないか」と思うものを、探してみてください。
最後に――小説の中に残された謎
最後に語っておきたいのは、コミさんの小説に残された謎についてです。一見、現実そのままを開けっぴろげに、無色透明に、謎などどこにもないように書いたかに見える文体ですが......しかし......。
小説の語り手は、大体毎回、旅先などで、女性と行動をともにすることが多いのですが、どうもその相手はいつも違います。
たとえば、第Ⅲ巻所収の二篇を比べてみましょう。
「海から海が」(1986)は、「あき子」という知り合いの女性が、神戸にある団地の四階に引っ越したので、「ぼく」が訪れる話。
のちに書かれた「団地の四階は海が見えた」(1995)を読むと、そこに出て来るのは、同じ団地としか思えません。ところが、「団地の四階~」で団地(明舞団地)に住んでいるのは、「マリ」という女性です。名前が違うだけならまだしも、人物の描かれ方(性格)はまったく違う。どう見ても、「あき子」と「マリ」は、違う人物という感じがする。
このあたりをよくよく検討すると、「田中小実昌の小説に出てくる〈ぼく〉の女性関係は、どうなってるんだ???」という疑問が生じるのですが......(誰かそれについてこれまで論じた人はいるのでしょうか)。
平岡篤頼との対談(「文学的ポロポロ」第Ⅰ巻所収)では、こうした「嘘」について、二人は次のような会話をしています。
平岡 そりゃね、嘘もついてますよ。嘘をついても、俺は嘘をついてる。こういう言い方はインチキだとか、自分でちゃんと白状してるわけですよね。こうやって喋っててもそうだけど、小説のなかでも、「そういう言い方には、なにかゴマカシがありそうだが」(「北川はぼくに」)だとか、「これはどうもインチキくさい」(「寝台の穴」)とか、絶えず自分のことばを疑っていらっしゃる。「ぼくは、自分に物語をしてるのではないか」(同)なんてね。(......)面白かったのはね、例の『香具師の旅』の中にいくつか短篇入ってますね。そのうちの二つか三つで、男と女のやることをしたのはこれが始めてだって書いてあるんですよ。ところがその度に相手の女が違っている。
田中 厚かましいねえ。そういうのは、厚かましいですねえ。
平岡 ぬけぬけと嘘ついてるわけ。これは知ってて嘘ついてるという感じが明らかなわけ。
田中 いや、言われて初めてわかりました、本当に。嘘をついている気がないんだね。
平岡 小説だから勿論かまわないですよ。ただ、いかにも正直に体験を書いたふりをしているので可笑しい。
田中 今初めて教えていただいてよくわかりましたけど......本当にどうもあいすみません(笑)。
「テラスに出たい」(1986/既刊および本企画未収録)という短篇は、「おれには創作力はないというのか」という、衝撃的な書き出しで始まります。
「物語」への疑いをたえず書き続けたコミさんが書かざるをえなかった「物語」とは、いったいなんだったのでしょうか?(編集部・N)
著者晩年の代表的シリーズとなった「哲学小説」を初集成(全三巻)。第一巻『カント節』『モナドは窓がない』/第二巻『なやまない』『ないものの存在』/第三巻 単行本未収録作品集