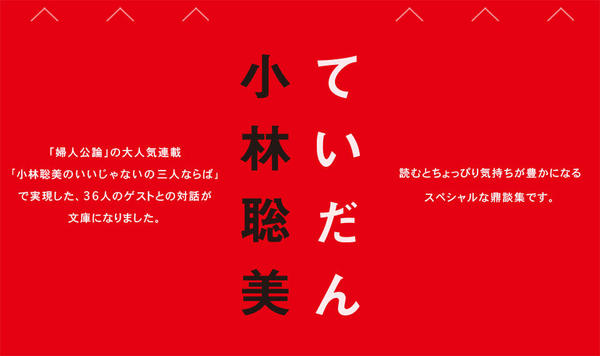あまり目立たない本......か?
小島信夫『私の作家評伝』が復刊されました。
中公文庫として小島の本は、創作指南をまとめたオリジナル編集の『小説作法』(2023年4月刊)に続き2冊目(保坂和志さんとの共著『小説修業』を含めると3冊目)です。

それで、なぜ今回、この本が復刊されたかといいますと。
20年ほど前、小説家の保坂和志さんが「小説論」シリーズで小島信夫作品を熱心にとりあげて以来、私の周囲の若い現代日本文学ファンの間で、小島信夫熱が高まりました。同時期、高橋源一郎さんや坪内祐三さんも小島作品について書かれていたので、俄然、気になる作品が増えました。
とはいえ、絶版が多くてなかなか読めなかった。長篇は『抱擁家族』、短篇集は『アメリカン・スクール』がロングセラーで、その二冊を別格とすると、古書価が高いし、なかなか見かけない。
中でもいちばん有名なのは、なんといっても『別れる理由』全3巻。「現代日本文学の最高傑作か、天下の奇書か!」(坪内祐三さんの評論『「別れる理由」が気になって』[2005]の帯文より)というような煽り文句を見ると、ますます集めたくなる。そんな私のような読者は多かったのではないでしょうか。
あれから20年。小島作品の復刊はだいぶ進みました。しかしその中でも、この『私の作家評伝』は、あまり評判を見かけなかった作品です。なぜでしょう。森田草平にはじまって宇野浩二に終わる16人の作品と人生を通して日本近代文学史をたどり直す、という内容が、良くいえばオーソドックス、悪くいえば地味に思われたのか(選書版で全3巻、という形態も、手に取りにくくさせた一因かもしれません)。
中公文庫では先に出た『小説作法』が好評だったので、次は『私の作家評伝』はどうか、と文庫編集長から潮文庫版(元本の全3巻を一冊にした、小島の批評作品で唯一文庫化されたもので、古書店でもほとんど見ない)を渡されたのきっかけに、私もそれまでつまみ読みだった本書を、初めからちゃんと通読することにしました。
そして、あることに気づいたのです。
10年以上、並行して連載された小説と評伝
この本の元になった連載(1969~80。74年分以降は『私の作家遍歴』として1980~81年刊)は、先述の『別れる理由』(1968~81)とほぼ重なっています。しかも、最初は数回で終わるつもりが、いつしか延々10年以上に及んでしまった、という成立事情も同じ。とすれば、両者には何かつながりがありそうだ。
やがて、過去の作家を登場人物として扱う「評伝」というスタイルで書き進むうち、自分自身をも小説の登場人物として扱うような術を身につけた、というような小島自身の発言を、エッセイや対談などに見つけました。なるほど。それで『別れる理由』はああいうメタフィクション展開になったのか。そういえば、これも同時期に後藤明生・古井由吉の依頼で「文体」に連載(1977~80)された長篇『美濃』は、まさに「評伝」そのものがテーマだった。
小島信夫は『別れる理由』と『私の作家遍歴』連載中に何か作風が根本的に変わったと巷間、いわれている。ならば、そのヒミツは、『私の作家評伝』の中にあるのではないか......。
「評伝」を通して日本の近代小説史をたどり直す
この連載は当初、三ヶ月に一作家の割合で書かれたそうです。三ヶ月で全集や評論を読んで誰か一人について書く、というのは、かなり大変そう、というか、実際大変でしょう。そういう切迫感が、文体にも出ています。
同じ岐阜出身の森田草平から、ある意味では日本の口語小説のパイオニアともいえる二葉亭四迷、漱石・鷗外、子規・虚子、徳田秋聲や近松秋江をへて、宇野浩二にたどりつく。
このぶあつい文庫本を最後まで読んで気づくのは、引用されている作家の文体と、それを評している地の文の文体が、だんだん似てくることです。たとえば、宇野浩二の章の最後のページ(p716)を見てください。引用文と地の文を読み比べると、ほとんどそっくりな息づかい、といえるでしょう。
この評伝のユニークさを、あえてひとくちでいうと、その作家の経歴を年譜的にたどりながら、「それを書いていた時の作者の気持ち」をアレコレと(あるいはズバリと)類推する、というものです。これは一般のテクスト論的な読み方からは絶対に出てこない読み方で、しかし明らかに、そこにこそ特色がある。
〈何しろ藤村は自伝的小説を書いているので、私の筆も小説の解説なのか、藤村自身のことなのか分らないように見えるが、いたしかたないところである〉(「島崎藤村」の章)とあるように、たしかにかつての(特に自然主義の)作家には、自伝的な、ないし私小説的な作品が多かった。かつ、それだけにとどまらず、漱石、鷗外、鏡花、といった作家にも、同じようにコジマは挑んでいく。するとどうなるか。
それを読んでいる「私」と、読まれている作家とが、同じ舞台に登場するように、だんだん近づいてゆくようになる。過去も現在も、生者も死者も入り混じった、狂騒的な、カーニヴァル的な空間が出現する。この盛り上がりは本書の醍醐味の一つです。そしてそこから、いま我々がこういうふうに読んだり書いたりしている、日本の小説というものがどういうふうに出来てきたのか、ということが、次第次第に明らかになっていく。
その観点からいえば、今回初書籍化となる柄谷行人・山崎正和との鼎談(1973。まだお二人は三十代)も、非常に面白く、身につまされるところの多いもの。特に柄谷さんの「夢」という語に着目してふりかえってみるならば、本書は別の貌を明らかにすることでしょう。
過去の作家を読むとはどういうことか。その付き合い方(交際術)を述べたものとして、ご覧になってみてください。(文庫編集部・N)

彼らから受け継ぐべきものとは何か――近代日本文学の代表的な文豪十六人の作品と人生を、独自の批評眼で辿る評伝集。〈巻末鼎談〉柄谷行人・山崎正和