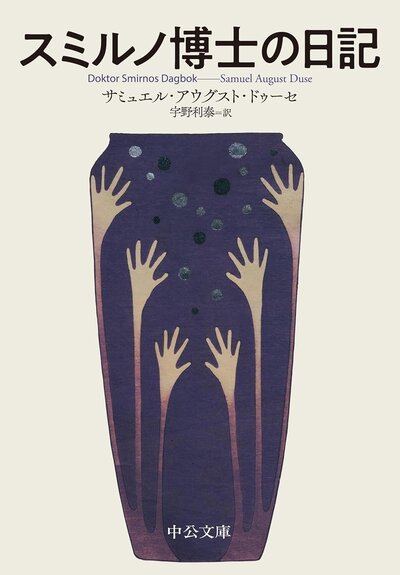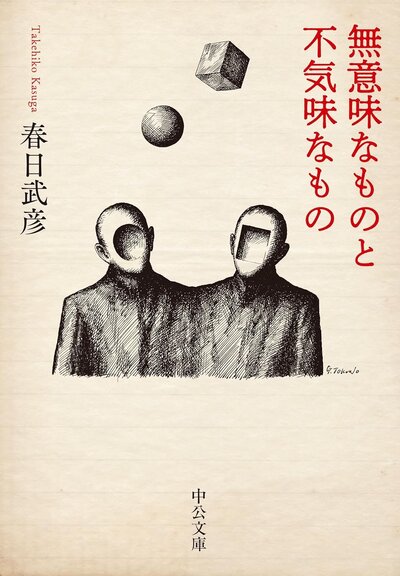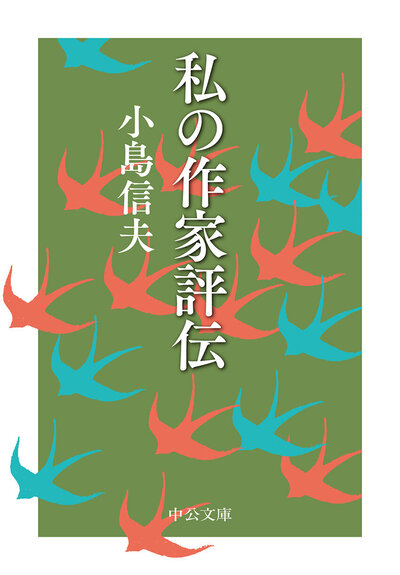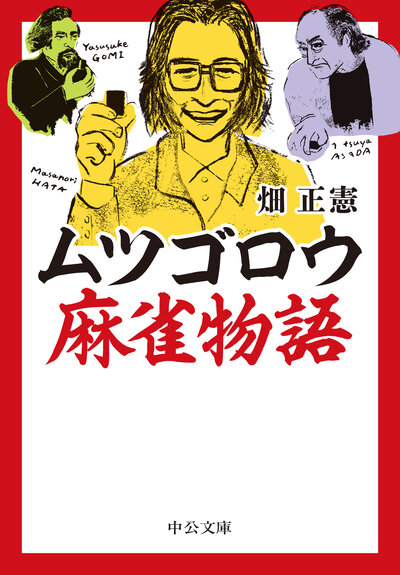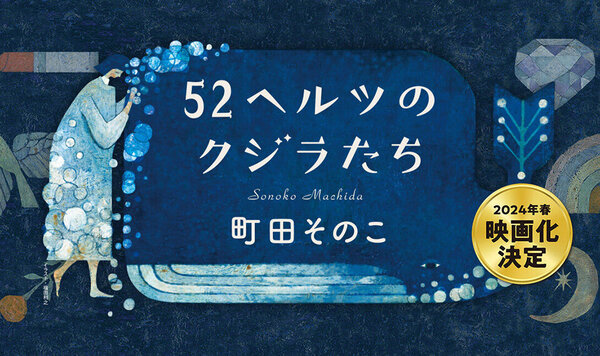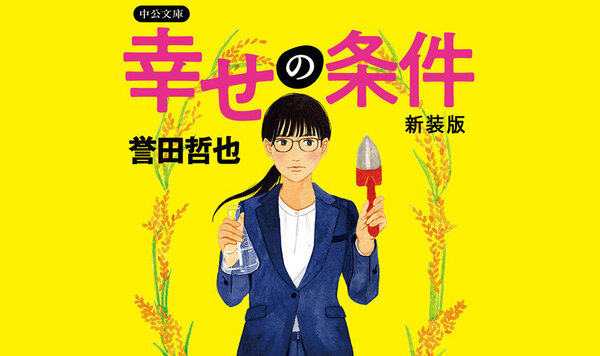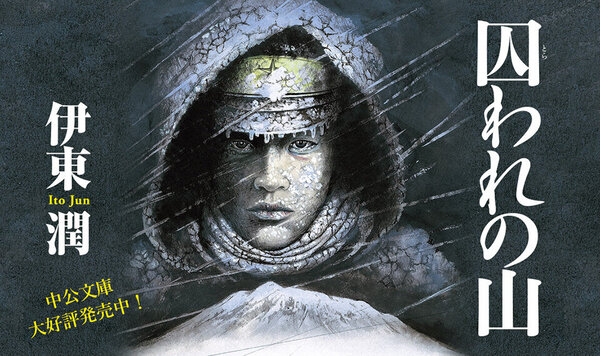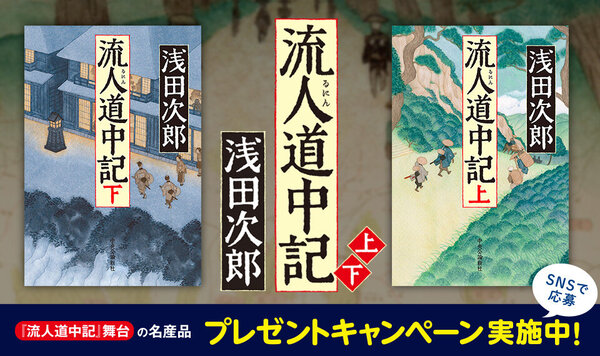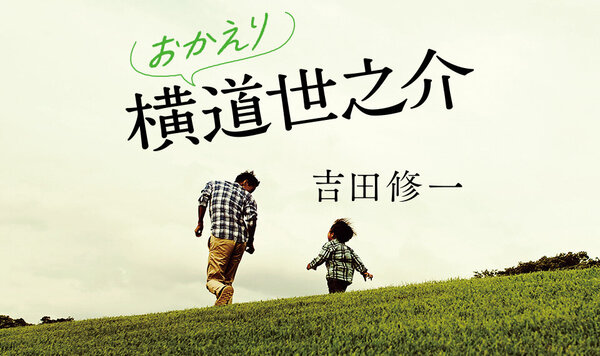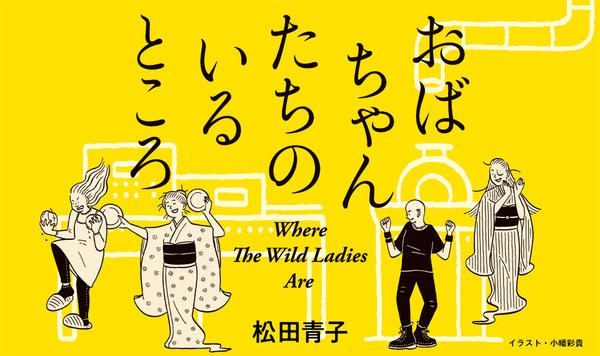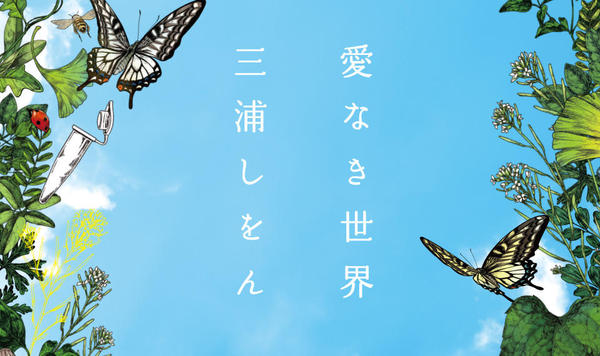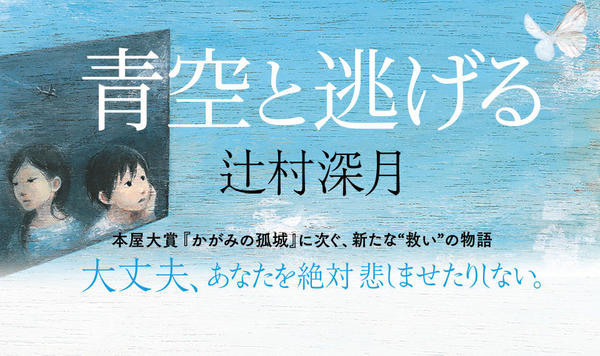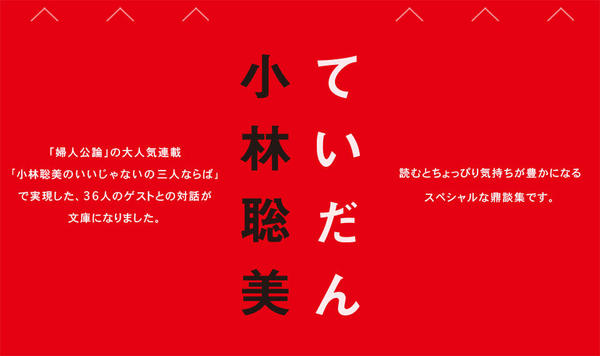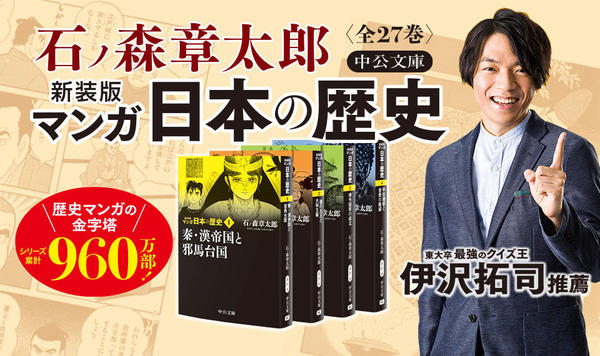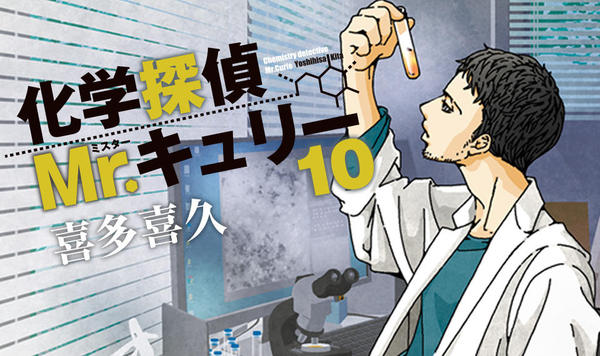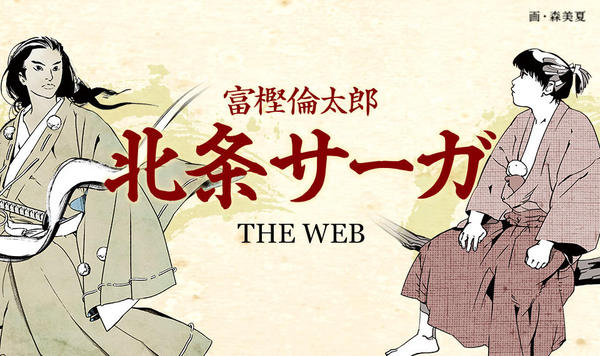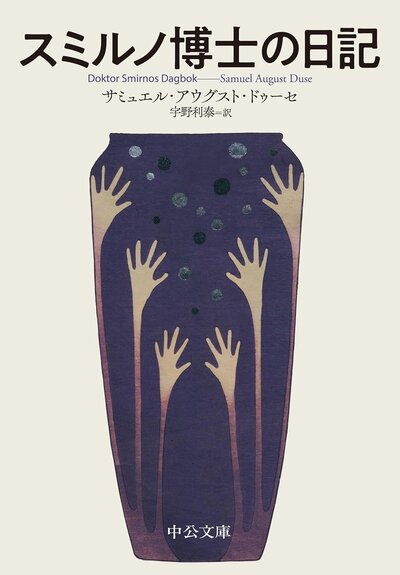
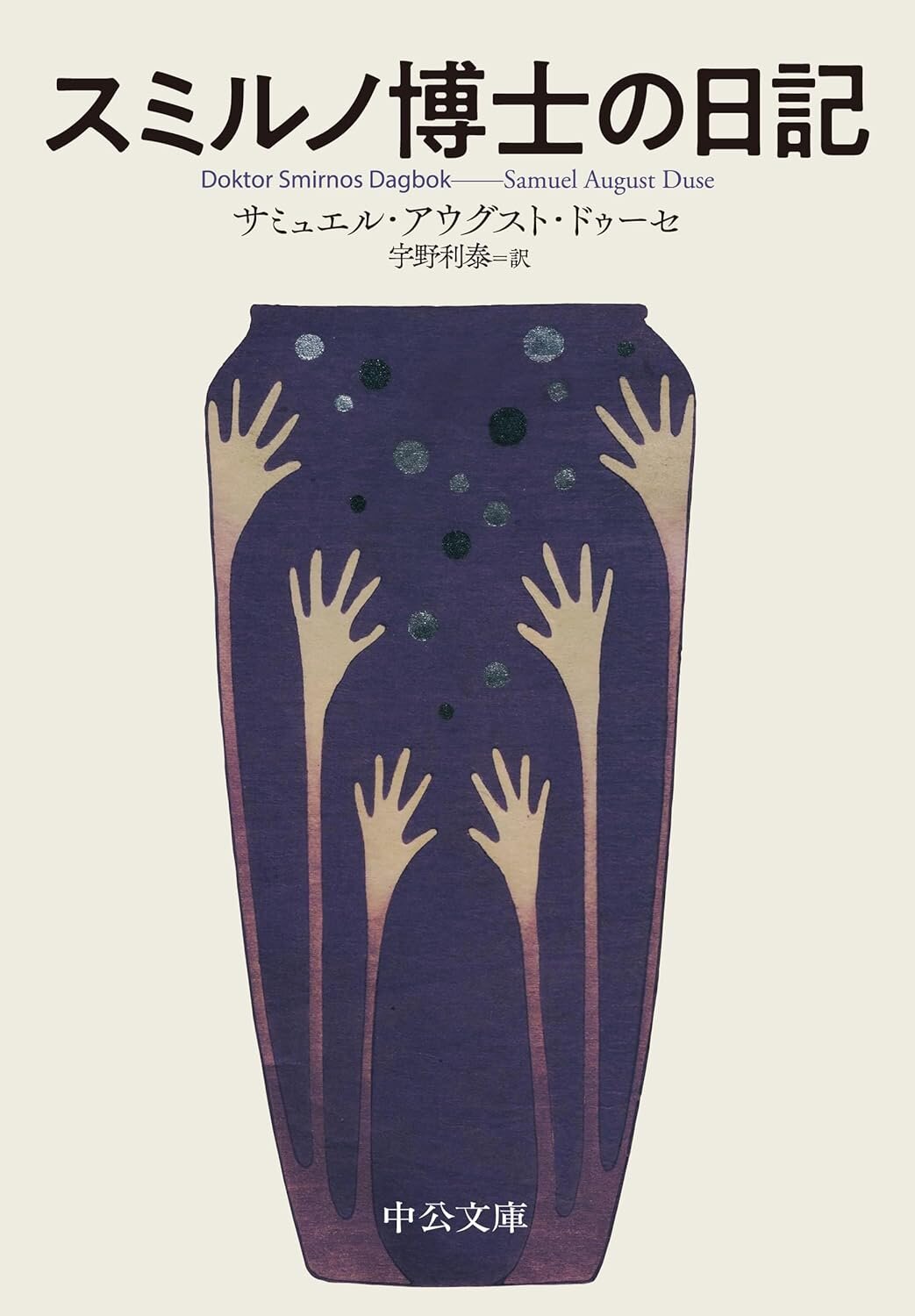
有名、だが読んだ人はほとんどいない......
サミュエル・アウグスト・ドゥーセ/宇野利泰訳『スミルノ博士の日記』を文庫版で復刊しました。
本作は、推理小説の好きな方にはある意味、非常に有名な作品です。しかし実際に読み通した人は少ない、という点でも、長らく有名でした。
なぜ有名なのか、を説明することは難しいので、以下、少し別の話をすることにします。
著者のサミュエル・アウグスト・ドゥーセ(1873-1933)はスウェーデンの作家。近年、へニング・マンケルやスティーグ・ラーソンなど、スウェーデンの翻訳ミステリは日本でも人気ですが、ドゥーセの活動時期は約100年前ですからだいぶ早い。本作にも登場する名探偵「レオ・カリング」の活躍するシリーズを14冊出していますが、元々は軍人で、1901~03年には南極探検に参加、その際の体験を元にしたノンフィクションや絵画も発表しており、かなり多才な人物です(江戸川乱歩『海外探偵小説作家と作品』に、より詳しいプロフィールが出ています)。
今回、編集を担当した私が本作の存在を知ったのはなんだったか、と思い返すと、たぶん、島田荘司さんと綾辻行人さんの対談『本格ミステリー館にて』(1992)だったのではないかという気がします。
1990年代当時すでに入手困難で、小酒井不木の旧訳(『小酒井不木全集』所収)か、東都書房版『世界推理小説大系5』(本書の底本)の宇野利泰訳を、古書か図書館で読むくらいしか、これまで手段がありませんでした。
私は前者でしたが、読む前に一つ失敗をしました。というのは、『(カタカナ)(漢字)の(漢字)』とタイトルをうろ覚えの状態で探してしまったので、誤って『ドウエル教授の首』(アレクサンドル・ベリャーエフ著)という長篇SFを読んでしまい、「これはミステリじゃないじゃないか!」と頭を抱えたのです。
それくらい、この小説は、存在自体あまり表に出されず、知っている人だけの間でヒッソリ語り継がれる――そういう状態が、長く続いていました。
意外(?)にしっかり本格ミステリ
さて、私も『不木全集』でようやく読むことができました。これは原著の発表年(1917年)を考えると、当時の日本としてはかなり早く、1923年に「新青年」で連載されたもの(ただしドイツ語版からの重訳)。
探偵役のレオ・カリングはデュパン/ホームズ以来の奇矯なキャラクターで、それもさることながら、時計と銃弾をめぐるアリバイのロジカルな推理過程、語り手を襲う数々の不可解な現象――など、本格ミステリとしての構造や中盤のサスペンスは予想以上にしっかりしていて、古典作品としてはかなり満足感があったのを覚えています。
ただ、抄訳だからか、ところどころ駆け足の印象はありました。それに、いわゆる「旧字旧かな」なのも、敷居が高い感じがする。
宇野利泰訳(1963)の存在を知ったのは、しばらく後でした。
ただ、宇野訳も不木訳同様、ドイツ語版を元にしたものでした。その後、宇野自身によるスウェーデン語原典からの新訳として創元推理文庫が企画されていた、というエピソードを知ったのは、元東京創元社・戸川安宣さんのコラム「翻訳家交遊録」(2015)によってです。
本作の文庫版を今回企画した際、そのエピソードのことを思い出しました。かつての新訳企画はいったいなぜ実現しなかったのだろう? 何か難しい問題があったのか――不思議に思い、戸川さんにお尋ねしてみました。
すると、実際には宇野利泰さんも乗り気だったものの、死去によって実現しなかった、という事情を伺いました(詳しくは本書巻末の解説を御覧ください)。
スウェーデン語原典からの新訳は今後、新しい訳者によって別の版元から出るかも知れない、という情報も昨今、耳にしていたので、ここはかつての宇野訳を文庫復刊しよう、という運びとなりました。
といっても、それだけではさすがに、新味に欠けます。スウェーデン語専門の方にご協力いただき、原語版を参照した上で注釈を付すことにしました。また小酒井不木・宇野利泰両氏が依拠したドイツ語訳原本(江戸川乱歩旧蔵図書として立教大学・大衆文化研究センターに所蔵)、近年リリースされた英訳電子版も結果的に確認することになり、日独瑞英の言語で同じ小説を比べる、という、珍しい編集体験となりました。
そのまま読んでください
そしてようやく、中公文庫版『スミルノ博士の日記』が完成しました。
この紹介記事をここまで読んできた方は、もしかすると、私が小説の内容にほとんど触れていないことに、お気づきではないかと思います。
余計なおしゃべりはここまでにします。
もし本作について、見たことも聞いたこともない、初めて知った、という場合は、そのまま小説の本文に進んでください。
ミステリを読む際、ある種の幸福というものは、一生にそう何度も味わえるものではありませんから――。
(文庫編集部・N)