ホーム > 検索結果
発行された時期:1973年1月からを含む書籍一覧
全10808件中 10785~10800件表示
-
中公新書
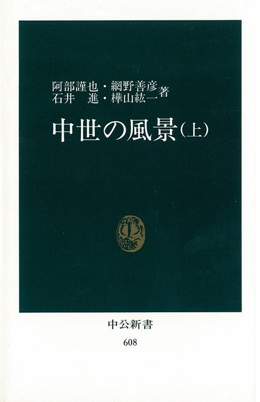
中世の風景(上)
阿部謹也/網野善彦/石井進/樺山紘一 著
これまで私たちにとって、中世の明瞭なイメージを結ぶことはむずかしかった。しかし、近年の中世史研究の新しい動向はめざましいものがあり、具体的な中世の諸相が浮かび上がってきた。本書は、四人の中世史家による中世についての活発な討論の記録である。上巻は、「海・山・川」などの縁辺に暮らす民の文化、社会に独自の地位をしめはじめる多種多様の「職人」、中世の忘れられない点景である「馬」、そして「都市」がテーマとなる。
1981/04/23 刊行
-
中公新書
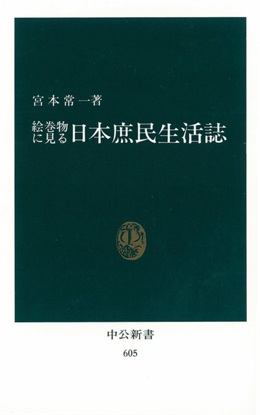
絵巻物に見る
日本庶民生活誌
宮本常一 著
日本の絵巻物は、時代の民衆生活を知る貴重な宝庫でもある。民衆の明るさを語る「陽気な日本人」から始まり、次いで「人生」「農耕」「人間と動物」「海の生活」「工匠と民具」「旅と交易」「住居」「火と生活」「衣生活」「飲食と生活」「信仰と生活」といった民俗誌的な章立てで、絵巻物に描かれた庶民の生活とさまざまな習俗を読みとる。本書は、多年全国の田舎を隈なく歩き回り、庶民と民俗に愛情深い眼を注ぎつづけた著者の遺著となった。
1981/03/23 刊行
-
中公新書
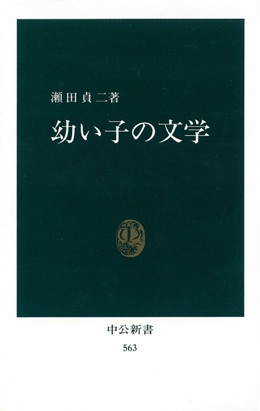
幼い子の文学
瀬田貞二 著
子どもと子どもの本の世界を愛しつつ逝った著者の真骨頂を伝える連続講話。東西のなぞなぞ、わらべ唄、民話についての造詣を自在に語り、確かな目で選ばれた詩や物語を朗読し鑑賞するなかで、幼い子どもの心を深くゆさぶり、そして大人の読者も惹きつけずにはおかない、本当の幼年文学の姿がありありと浮かびあがる。楽しい作品、数々の優れた翻訳によって日本の児童文学を豊かにした著者ならではの道案内。
1980/01/23 刊行
-
中公新書
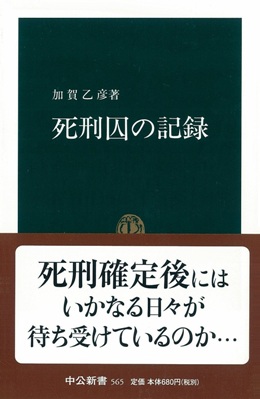
死刑囚の記録
加賀乙彦 著
一九五四年、松沢病院の医師として一人の殺人犯を診察したときが、著者の死刑囚とのはじめての出会いであった。東京拘置所の精神科医官となってから、数多くの死刑囚と面接し、彼らの悩みの相談相手になることになる。本書では著者がとくに親しくつきあった人たちをとりあげてその心理状況を記録する。極限状況におかれた人びとが一様に拘禁ノイローゼになっている苛酷な現実を描いて、死刑とは何かを問いかけ、また考える異色の記録。
1980/01/23 刊行
-
中公新書

明治六年政変
毛利敏彦 著
明治六年十二月、西郷隆盛は、板垣退助ら四参議とともに、自らの手でつくった政府を去った。西郷はなぜ野に下ったのか。征韓論に敗れたからという。また不平士族の棟梁として殉じたのだともいう。当時の内政外交の激動の過程を先入見を去って正確にたどってみると、驚くべき事実が浮かび上がってくる。――西郷は、日本への法治主義導入をめぐる深刻な政争の犠牲者だった。「征韓論」政変の名の下に隠されていた事件の真相に迫る。
1979/12/18 刊行
-
中公新書
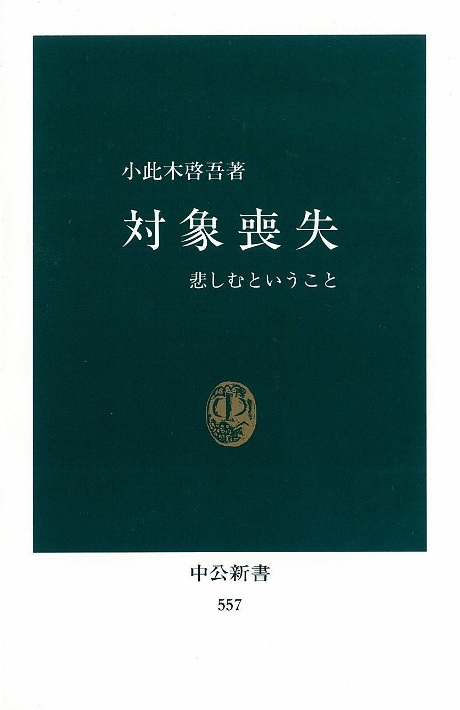
対象喪失
悲しむということ
小此木啓吾 著
肉親との死別・愛の喪失・転勤・浪人等々、日ごろ馴れ親しんだ対象を失ったとき、その悲しみをどう耐えるかは、人間にとって永遠の課題である。ところが現代社会はいつのまにか、悲しむことを精神生活から排除してしまい、モラトリアム人間の時代を迎えて「悲しみを知らない世代」が誕生し、いたずらに困惑し、絶望にうちひしがれている。本書は具体例によって悲哀の心理過程と悲哀の意味を説き、自立することへの関係に及ぶ。
1979/11/21 刊行
-
中公文庫
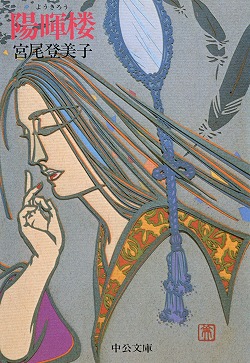
陽暉楼
宮尾登美子 著
土佐随一の芸妓房子が初めて知った恋心ゆえに、華やかな人生舞台から倖薄い、哀れな末路をたどる悲愴な若き生涯を描く感動の長篇。〈解説〉磯田光一
1979/09/10 刊行
-
中公新書
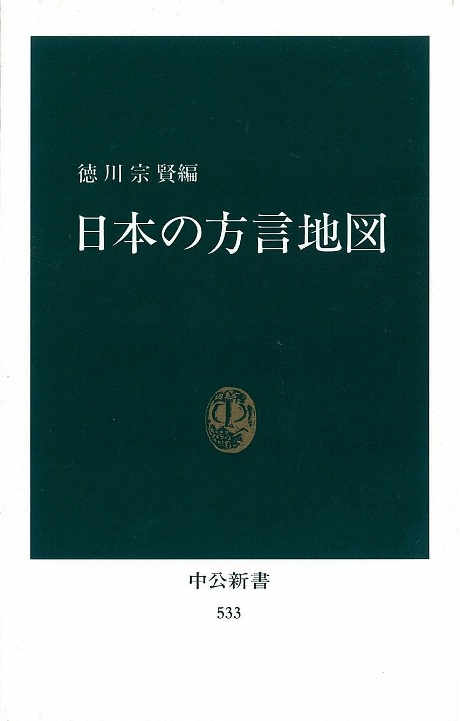
日本の方言地図
徳川宗賢 著
相手の出身地も知らずに「シアサッテに会おう」などと約束するのは危険であろう。西日本と東日本では、その意味内容が同じでない。このようなことばの地域差を分布図に読み取る方法は、柳田国男の『蝸牛考』にはじまる。以来、約半世紀の空白時代を経て、国立国語研究所の行なった全国的な言語調査の成果『日本言語地図』(全六巻)の中から代表的な五〇枚を選び出して略図化し、そこに投影されたことばの生成・発展・衰滅を明らかにする。
1979/03/22 刊行
-
中公新書
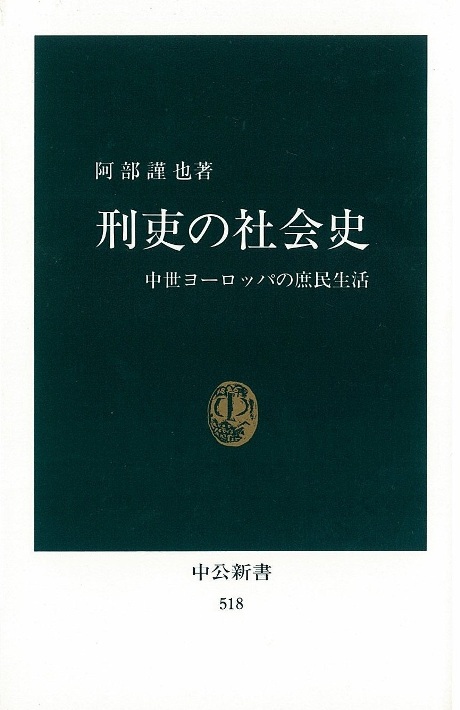
刑吏の社会史
中世ヨーロッパの庶民生活
阿部謹也 著
かつて社会にとって最も神聖な儀式であった「処刑」は、十二、三世紀を境にして、〝名誉をもたない〟刑吏の仕事に変っていった。職業としての刑吏が出現し、彼らは民衆から蔑視され、日常生活においても厳しい差別をうけた。都市の成立とツンフトの結成、それにともなう新しい人間関係の展開、その中で刑罰観はどう変化していったか。刑罰観の変遷と刑吏差別の根源を追究する中で、庶民生活の実態を明らかにし、民衆意識の深層に迫る。
1978/10/23 刊行
-
中公新書
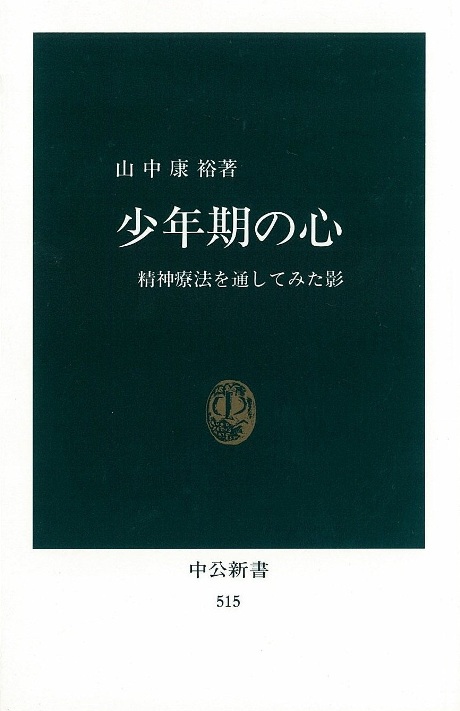
少年期の心
精神療法を通してみた影
山中康裕 著
一歩家を出ると一言も口をきかない太郎君、不登校を続ける庭子さん、自分の母親が母親と分からなくなった霧子さん、執拗な心気症から自殺まではかった誠君......。ごく当り前の小学生・中学生を辛い危うい淵に追いやった原因は何か。「箱庭療法」はじめ、イメージの世界で彼らととことんつきあうことを通じその心の治療に取組んできた著者が、一つ一つのケースを如実に描きだし、親が、教師が忘れてはならないことを愛情をこめて説く。
1978/09/21 刊行
-
中公新書
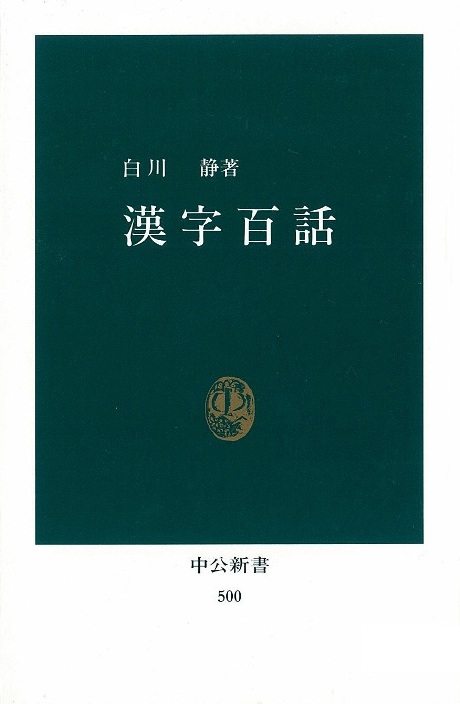
漢字百話
白川静 著
漢字の伝統は、中国では字形を正す正字の学として、わが国ではその訓義を通じて漢字を国語化する問題として存在した。中国が正字を捨て、わが国で訓義的使用を多く廃するのは、それぞれの伝統の否定に連なる。また、両国の文字改革にみる漢字の意味体系の否定は、その字形学的知識の欠如に基づく。甲骨・金文に精通する著者が、このような現状認識から、漢字本来の造字法やその構造原理に即しつつ、漢字の基本的諸問題を考察する。
1978/04/21 刊行
-
中公新書
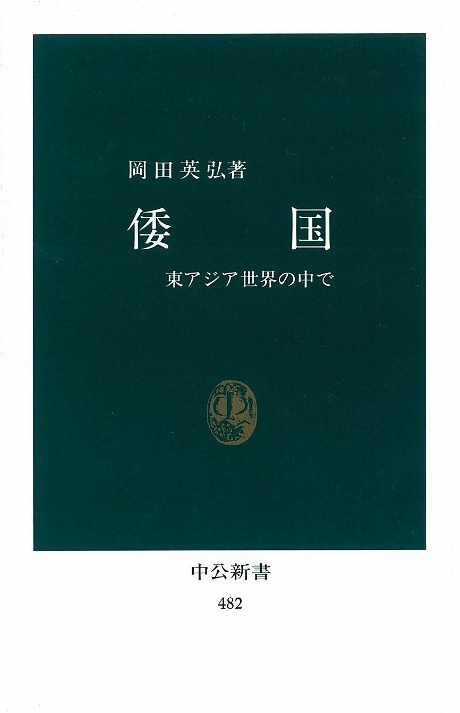
倭国
東アジア世界の中で
岡田英弘 著
本書は中国の史料を基礎に、確実な事実を積み重ねて、日本をとりまく国際情勢を把握し、東アジア全体の民族の興亡と政治の動態、大陸から日本にまで及んだ壮大な商業ルートを明らかにし、華僑の来日とその背景、卑弥呼の王権がどのような状況で成り立ちえたかなど、意外なドラマを展開する。大きな流れを踏まえた視点で『日本書紀』の伝承に新たな光をあてて日本古代史の謎に大胆な解釈を加え、日本民族と国家の誕生過程を描く。
1977/10/22 刊行
-
中公新書
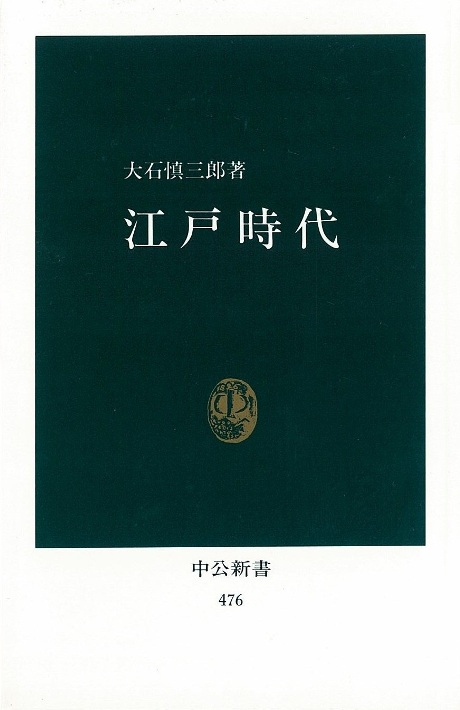
江戸時代
大石慎三郎 著
小説・映画・演劇が作りあげた江戸時代のイメージは、歴史学の研究成果と合致しないものが少なくない。また膨大な史料や事実の中で、全体像を見失った歴史書もある。あるいは、近代社会が前の近世社会をことさら古く見せようとした傾向もなくはない。本書は、二五〇年あまり内外ともに戦争のなかった時代、しかも今日の一般庶民大衆の歴史が直接始まった時代の全体的特徴を、捉え直す。江戸時代イメージを一新する通史である。
1977/08/25 刊行
-
中公新書
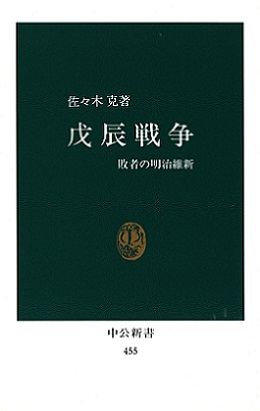
戊辰戦争
敗者の明治維新
佐々木克 著
戊辰戦争に勝利することによって薩長討幕派は明治政権の主体となりえた。だが幕藩制国家にかわる統一国家の構想は討幕派だけがもっていたのではない。徳川慶喜、榎本武揚、河井継之助、そして会津、庄内および奥羽越列藩同盟も自ら描いた国家像があった。彼らは「朝敵」とされながらも何故に、何を求めて戦い、敗北したのか。敗者に負わされたマイナスの遺産はなにか。敗者の側に分析の視座を置いて戊辰戦争に新たな照明をあてる。
1977/01/25 刊行
-
中公新書
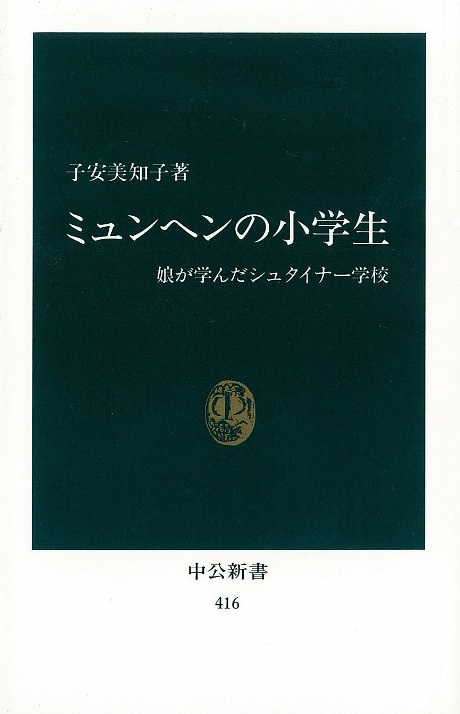
ミュンヘンの小学生
娘が学んだシュタイナー学校
子安美知子 著
学者夫妻がミュンヘンに留学して、娘さんを入学させた学校のユニークな教育――〝詰め込み〟をさけて授業を進めて行き、落第もさせないし、能力による選別もやらない。しかし十二年間の一貫教育のあとでは、 実力が身についている。 「エポック授業」「オイリュトミー」など子どもの能力発達に適した方法も……。日本の教育が直面している難問題を解決している学校を、娘の生活を通して母親が綴る。毎日出版文化賞受賞。
1975/12/20 刊行







