- 2020 04/23
- 著者に聞く
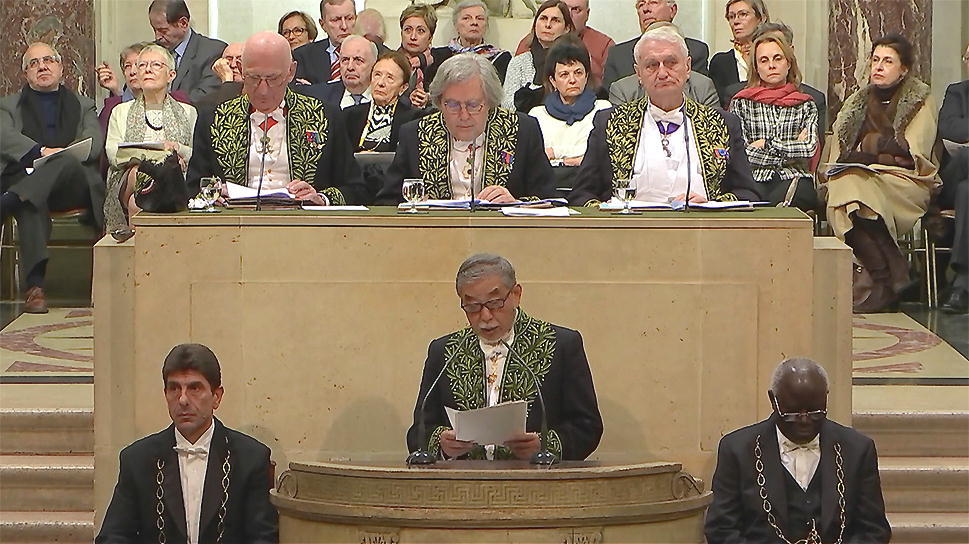
2014年に刊行した『禁欲のヨーロッパ』以来、『贖罪のヨーロッパ』、『剣と清貧のヨーロッパ』、『宣教のヨーロッパ』と、佐藤彰一先生はヨーロッパの修道制、さらにはその精神・社会について一貫して執筆・刊行されてきました。5冊目の『歴史探究のヨーロッパ』で本シリーズが完結したことをふまえて、お話を伺いました。(既刊刊行時のインタビューは、『贖罪のヨーロッパ』、『剣と清貧のヨーロッパ』、『宣教のヨーロッパ』をご覧下さい。)
――本書は「歴史探究のヨーロッパ」という大きなタイトルですが、本書で取り扱う時代、つまり宗教改革からルネサンスや人文主義が花開いた時代、さらにフランス革命に至る時代に、ヨーロッパの歴史学の考え方が大きく変わったのですか?
佐藤:学校の教科書では、よく紀元前5世紀のギリシア人ヘロドトスが「歴史の父」と形容され、この分野の始祖とされています。
この呼び名は古代ローマの弁論家キケロが奉ったものですが、ヘロドトスの有名な著作『歴史』の表題となっている「歴史」という言葉は、古典ギリシア語で「調査」、「探求」を意味していて、私たちが「歴史」という言葉で普通考えるような、過去の出来事を語ったり、書き記したりすることとは少し違っています。実際ヘロドトスのこの作品は、自分が見聞した事柄を伝説なども含めて書き記したもので、見聞録的な性格が濃厚で、歴史といっても同時代的な性格が強いのが特徴です。
ヘロドトスから20年ほど後に生まれたトゥキュディデスが、ヘロドトスが自分の著作を公開の場で朗読したのを聞いて、触発されたというのは有名な話ですが、そのトゥキュディデスが書き記したアテネとスパルタとの戦争を記録した傑作『戦史』もまた「ヒストリア」と題され、叙述の性格こそ大いに異なるものの、自らが見聞するか、他から情報を得て記した同時代的な記述です。
ところで、やや乱暴に単純化することになりますが、これに対して、ローマでは歴史叙述はむろん同時代的な作品にも事欠かないものの、普通にかなり時代を遡って過去の出来事、歴史を叙述した作品も数多く見られるようになります。
リヴィウスの『ローマ建国以来の歴史』やポリビュオスの『歴史』などは、著者が直接体験した出来事ではなく、様々の記録をもとにして、ある視点から過去の出来事を再構成し、時間の中での物事の展開を書き記した作品です。叙述の対象と作者とは直接の関係を持たない、そうした性格の叙述です。私たちが読み慣れている多くの「歴史書」は、こうした著作の部類に属すると言ってよいでしょう。
そしてキリスト教が公認宗教となり、ついでヨーロッパ世界の唯一の宗教として君臨し始めると、それは歴史叙述にも大きな影を落とすことになります。キリスト教は、原初の天地創造から、救済者としてのキリストの誕生を経て、最後の審判にいたるまですべてが必然的な出来事の経過のなかで位置づけられるところからうかがえるように、徹頭徹尾歴史的な宗教であると言ってよいと思います。したがって歴史の語りと救済の世界観は、中世を通じて一体とは言わないまでも極めて強く結びついていました。
フランスの中世史家ベルナール・グネの『西洋中世における歴史叙述と歴史的教養』(1980年)が出て、その多くが修道士を含めた教会人によって中世に書かれた歴史作品を、単純にキリスト教的歴史観を過去に投影するような著作と見るそれまでの見方が間違いであることが明らかになりました。
しかしそれだからと言って、過去の歴史の再構成にあたって、残された記録を精査して「事実」を汲み上げ、それに基づいて過去を再構成するという遣り方が一般的であったわけではありません。歴史の展開を相変わらず、キリスト者共同体の運命を語るものとして構成する精神は強靭な力をもって君臨していました。
誤解を避けるためにあらかじめ指摘しておきたいのですが、私がこの書物で論じたことは「歴史観」の変化ということではありません。「歴史的事実」とは何か、それを確定するにはどのような作業が必要かという、いわば歴史を再構成するための素材をいかに客観的なものとして抽出するか、その方法の発展を明らかにしようと意図したものです。
仮に客観的に「歴史的事実」が確定できたとしても、それを歴史の語りに昇華するためには、歴史の意味論、認識論という要素が絡んできますから、ことはそれほど単純ではありません。それでも過去の事実を客観的な方法で確定できることは根本的に重要です。13世紀後半にイタリアで始まった文献学研究、そして15世紀後半フランスで始まるブルージュ学派の文献学・古典学研究が、17世紀のサン・モール会の歴史研究や、イエズス会(ボランディスト)の聖人伝研究、イタリアでの修史事業に流れ込んだのです。残された記録から何がどのような方法で読み取れ、何が読み取れないかの方法的基準が確立されたのです。
こうした潮流の精華が、ジャン・マビヨンが著した『文書の形式について』でした。この書物が現れた1681年を、フランスの中世史家マルク・ブロックが「人間の知性の歴史において真に偉大な日付である」と述べたのは、史料から事実を確定する客観的方法の基準が確立されたことの重大性を強調したかったからに他ならないのです。歴史を叙述する基礎となる土台を、客観的に固める作業は、その上に構築する歴史の叙述そのものにも影響を与えずにはおきません。その意味で歴史学の考え方にも大きな変化をもたらしたことは否定できないと思います。
――なぜマビヨンをはじめとする修道士や修道院はその役割を果たすことになったのでしょうか。
佐藤:マビヨンが活動したサン・ジェルマン・デ・プレ修道院は、サン・モール会に属していて、歴史研究と史料編纂の拠点でした。
初代のサン・モール会総会長のグレゴワール・タリスが、会士一人ひとりが能力に見合った知的活動に勤しむよう督励したのは、宗教改革の後、修道士という存在に対する社会の視線が厳しくなり、何らかの知的生産活動に従事させるのが得策と判断したからでした。功利主義思想はもっと時代を下ってから前面に出てきたのですが、教会の旧体制と結びついているかのようにみなされた修道院、修道士への世間の風当たりは次第に厳しくなる現実はありました。
タリス師が歴史研究に肩入れした理由は、宗教改革以来ことあるごとに続いた新教勢力との論争でした。教会の堕落し、腐敗したありようを批判するプロテスタントに対して、「歴史的事実」に基づいてこれを反駁することは、カトリック側にとって極めて重要な課題でした。
日々信徒の魂の導きに多くの時間を費やさざるを得ない在俗聖職者にこうした任務を期待することは困難であり、必然的にその課題は修道院と修道士に委ねられることになったのです。
――この時代に生まれた歴史探究、あるいは文献学や考証学は、現代の私たちにも影響を与えているのでしょうか。
佐藤:私はこの著書のなかで、「考証学」という用語を初めて使いました。そこでまずこの用語について一言説明しておかなければなりません。
考証、考証学という用語は、フランス語「erudition」の訳語です。この時代の歴史研究を論ずる書物のなかで、しばしばこの用語がでてきます。辞書的には「博学」、「学殖」といった意味ですが、これでは余りに抽象的すぎて何のことやらわかりません。それで散々悩み抜いた末に、本書で使ったポール・アザールが書いた『ヨーロッパ精神の危機』を訳した野沢協氏が、「エリュディシオン」を「考証学」と訳しているのに気がつき、それを拝借しました。「考証学」というとわが国では中国の清朝考証学が有名ですが、それとは別に史料解釈の帰納法的手続きの仕組みをとらえて、そのように命名したのです。
つまり史料を「観察」し、それを帰納(induction)する、例えば「ミシェルというフランス人は背が高い」という観察から、「全てのミシェルというフランス人は背が高い」という命題を帰納する。そしてそれが常に成り立つか否かを「検証」することで完結する思考法です。むろんミシェルというフランス人には背がそれほど高くない人がいますから、これは成り立ちません。すなわち偽の命題ということになります。
実際の歴史研究で重要なのは、この検証部分です。つまり命題の真偽は、検証の対象にすべきフランス人のミシェルをどれだけ数多く知っているかにかかっているのです。たまたま自分が知っている2、3人のミシェルというフランス人が皆高身長であれば、この命題を真と判断しかねません、しかしミシェルというフランス人を1000人知っている人は、そのなかに背が低いフランス人ミシェルがいることを知っていて、偽であると判断するかもしれません。ことは検証の段階でのデータの量によるわけで、検証の対象となる事例の数が多ければ多いほど、その判定の信頼性が高いことになります。
Erudition、「博識」とはそのことを指す言葉なのです。史料所見の量の多さです。それを帰納的論理操作の部分を含めて表現したのが「考証学」という言葉と考えてください。
なおこの時代に考証学者として卓越していたのは、サン・モール会士やボランディストなどの学僧だけではありませんでした。サン・ジェルマン修道院に火曜日と日曜日ごとに集い意見をたたかわせた「サン・ジェルマン修道院協会」のメンバーであったシャルル・デュ・カンジュやエティエンヌ・バリューズらの民間の考証学者も、「碩学」の名をほしいままにした大学者でした。
さて肝心のご質問ですが、私は文献学も考証学も共に、私たちの日常生活においても、非常に重要な思考のツールであると考えています。
文献学的思考は、職業的シーンや生活の場で、書かれた文章を読み解き、書き手の真意を理解し、あるいは推測する訓練をさせてくれます。なぜAではなくて、同義語のBという表現を用いたか、その理由を探り、書き手の真意を知る上で大事な思考を鍛えてくれます。
また考証学的思考は、いわばビッグデータを基礎にして、作業仮説を篩い分ける訓練になります。それはこれからのビジネス・シーンには重要な思考様式を育ててくれるでしょう。
学問の愉しさは註を読む愉しさだとは、私を名古屋大学に慫慂して下さった碩学の古代史家故長谷川博隆先生の口癖でしたが、考証学的指向が端的に現れるのが註であり、その分量です。この点で徹底しているのは、ドイツの学問的伝統で、脚注がそのページで消化できず、次ページをまるまる費やしてしまう例も珍しくありません。2019年暮れにテュービンゲン大学のミーシャ・マイヤー教授が『民族移動:西暦3世紀から8世紀までのヨーロッパ、アジア。アフリカ』と題する1532ページの大著を出版しましたが、本文が1104ページ、巻末の註と文献リストが390ページという構成で、膨大な量の註がこの斬新な民族移動期史の価値をうらなうものになっています。
――『禁欲のヨーロッパ』以来、全5冊にわたってヨーロッパの修道制の変遷とそれが社会に与えた影響について叙述されましたが、通して叙述することによって気づかれた新たな発見がありましたらお教えください。
佐藤:本書の結びの文章でも書いたことですが、古代末期から18世紀までの修道院の歴史を通観してみて、修道院という組織が、自ら社会からの切断という「孤立」的な存在を基本様式としながらも、各時代の特徴的な活動の様式が、いわば時代の要請を受けとめる柔軟性を具えていたことが見てとれ、執筆前には考えもしなかった側面に気づかされことです。それは驚きでした。
それが本来のあるべき修道院の姿からの逸脱であるのか、それとも人の世の「成層圏」にありながら、薄い大気の層の拍動を通じて励起された感覚が、共同体内部に作り出さずにはおかない人性の根本に根ざした現象であったのかは、にわかに判断できないのですが、おそらく後者であろうと考えています。
そのことは、功利主義思想や啓蒙主義思想の社会への浸透で生産活動に携わらない組織である修道院に逆風が吹いた時期に、様々の慈善活動、救済事業に乗り出すことで、新たな展開を見たところにも見て取れます。現在開発途上国で活動する修道士、修道女は多くがこうした分野で行動し、今でも修道制の精神を守り続け、そしてさらに展開しているように思われます。
――同様に、ご執筆にあたってのご苦労がありましたら。
佐藤:第4弾の『宣教のヨーロッパ』と第5弾の『歴史探究のヨーロッパ』は、中世史を専攻領域にしている私にとって、未知の分野でした。「未知」という意味は、その歴史を知らないというのではなく、研究対象として、論文を執筆した経験がないということです。そのことと関連しますが、手元にこの分野の専門研究書の蓄積があまり無くて、情報の蒐集に苦労したことです。
もっとも新しい分野を学ぶことはそれ自体愉しいことですから、少しも苦にはなりませんでした。未知の領域であればあるだけ、最新の研究が必要になり、フランス・アマゾンやドイツ・アマゾンを含め書籍販売業者には大いに世話になりました、というか利益を上げる機会を提供したと思います。ですからこの2冊は近代史を専門にする同輩に対する「道場破り」的な挙措であったと思っていますし、それだけに彼らの反応には興味があります。
――最後に、これからは何について研究されようと思っていらっしゃいますか。
佐藤:私の専門領域のフランク史に戻ります。ただ今度は先史学者や古代史家の方々への「道場破り」的な行動を取ることになりますが、お許し願いたいと思っています。
ヨーロッパを含めた、少なくとも西ユーラシアでは紀元前1200年頃に、後期青銅器時代のシステムが崩壊するという事態が起こったことは先史学者共通の認識になっています。この時代を起点として、地中海世界から離れた大西洋東部世界と北海・バルト海地域を表舞台として進行する歴史過程が出発点となっています。このなかでゲルマン民族の幾つかの部族が再編され、フランク人という名前で歴史に登場する歴史的経過を再構成し、初期フランク王権をめぐる王統の起源をめぐる謎や彼らが作ったメロヴィング国家の独創的な仕組みを解明しようと考えています。
目下ローマ人のエルベ川流域への進出まで筆を進めています。これは註を施した書物で、できるだけ1巻でまとめたいと思っていますが、正直まだ分かりません。

