- 2016 11/30
- 著者に聞く
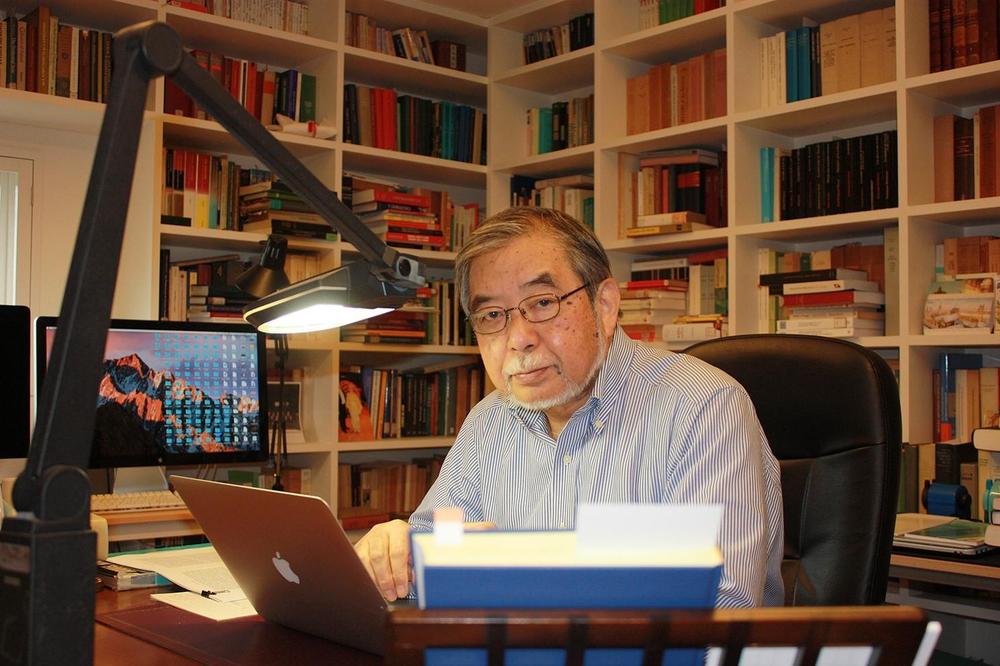
前著『禁欲のヨーロッパ』に続き、『贖罪のヨーロッパ』を上梓された佐藤彰一さん。千年に及ぶヨーロッパ古代の思想史に取り組んだ背景などをうかがった。
――本書を執筆した動機を教えてください。
佐藤:少し長くなります。1997年に出版した『修道院と農民』(名古屋大学出版会)は、主に経済史の問題関心からする研究の成果でした。この著作を準備しながら、魂の陶冶と霊的修行の場としての西洋の修道院そのものへの関心が大きく膨らんで行きました。1984年から2年間パリで研究生活を送る機会があったのですが、その折に中古のアウディを駆ってフランスを中心に、イタリア、スペイン、英国の中世初期に創建された修道院を訪れ、実地に見聞を広めることができました。そうしたなかでキリスト教修道院の歴史を、西洋の精神史の一部としてヨーロッパ史全体を通して見てみるという構想が自然に生まれて来たように思います。
我が国の中世修道院を研究する歴史家は、その多くがクリスチャンですが、私の場合は家の伝統のうえで禅宗の仏教徒です。キリスト教信仰をもった先学の著作とは異なる視点で、西洋の修道院史を語ることができるのではないかという自負も作用したかもしれません。
2014年2月に出版した前著『禁欲のヨーロッパ』(中公新書)は、修道士の厳しい修行生活を支える自ら進んで行う禁欲実践の起源を、キリスト教以前の古代ギリシアの市民の徳目であり、養生法でもあった「自己への配慮」の思想と、これを継承した古代ローマのエリート層に育まれた禁欲の思想のうちに求めた内容でした。その意味で、修道思想の社会的起源の探究とも呼べるものでした。
それに対して、本書『贖罪のヨーロッパ』は、キリスト教以前の古典古代の身体思想の系譜に立ちながら、その延長線上にキリスト教の救済思想と深く結びついた贖罪の観念を展望しようとしたものです。贖罪と救済とを結びつけるうえで、最も重要な思想は聖アウグスティヌスが生み出したのですが、これが一種の社会思想としてヨーロッパキリスト教世界に浸透するうえで最大の功績を果たしたのは、アイルランドの修道士たち、なかでも聖コルンバヌスでした。
彼らは、大陸からアイルランドに持ち込まれた様々の教父の作品や教義関連の著作で学び、一世紀以上にわたって沈滞していた大陸の修道制に、いわば原初の息吹を再びアイルランドから吹き込んだのです。同時に「リュクスーユ読誦集」で用いられている新たな書体を創りだし、やがてはカロリング朝期に頂点に達した写本文化繁栄のきっかけをつくりました。修道院の歴史的役割として、古典古代の作品を筆写し、それを後世に残したその功績は決して忘れてはならないものです。
このように、宗教・精神世界と書物文化両面にわたる中世修道院が果たした巨大な役割を、自分なりにしかも現在の研究動向もまじえて述べて見たいというのが動機でした。
――執筆中に何か苦労したことがありますか。
佐藤:私が書物を書く時は、第1ページ目から書き始めるというやり方を取っています。人によっては途中の章から書き出したり、構成が出来上がっている部分を先行して書いたりと様々のようです。手帳を見ると2015年8月3日に本書の「はじめに」の部分を書き出し、2016年3月20日に最初の稿を書き終えています。約7ヵ月を要したことになります。特に早くも遅くもない標準的なスピードだと思います。苦労したことと言えば構成上のことで、「あとがき」にも書いたように、叙述上の多くのトピックは常に研究の進展の嵐に曝されていますから、そうした新説をどの程度叙述に反映させるか、純粋の学術書とは違いますから、そのサジ加減を塩梅するのに苦心したと言えば言えるかもしれません。
――前著『禁欲のヨーロッパ』と本書で描かれる内容で、とくに異なっている点はどのようなところでしょうか。
佐藤:どの時代、どのような主題でも構いませんが、およそ歴史記述を実践するにあたって、叙述の内容は「意味」を持たなければなりませんが、意味は論理と一体です。のっけから小難しい言い回しになってしまいましたが、『禁欲のヨーロッパ』で展開した論理は、自己の欲望を統制する技法が古典古代と末期ローマでどのように展開したかを探究する論理でした。
しかし本書『贖罪のヨーロッパ』の舞台となったのは、すでにキリスト教が社会にかなり浸透した時代のヨーロッパです。そこでは古典古代のストア的禁欲思想とは根本的に異なる、罪障の贖いが信徒すべてに求められた世界です。「欲望」は贖罪の対象である「罪」のなかに解消され、贖うべき「罪」の一部と化してしまったのです。「禁欲」の論理は、6世紀以後はより広範な「罪」の論理として展開して行くというのが私の考えです。
――修道生活にかかわる事柄と現在のヨーロッパ人の日常生活とには、どんな繋がりがあるでしょうか?
佐藤:これはなかなか答えるのに難しい問題です。修道生活の根底にある霊的希求や贖罪意識などは、キリスト教精神の総体的ありようですから、人々の日常生活の根底を規定している要素とは言えるにしても、それが修道院からの影響であるとは言えないでしょう。修道士も一般信徒もキリスト者として、もともと共有していた「価値」ですね。
むしろもっと瑣末な日常的な振る舞いに現れていると言えるかもしれません。例えばヨーロッパ人がレストランに一人でいるとき、しばしば書物を読みながら食事をしている光景に出会います。おそらく我が国の礼儀作法では無作法な振る舞いとみなされるのでしょうが、彼の地では日本ほどに無作法とは思われないのではないでしょうか。中世の修道院では、一日に一度の食事は貴重な口福の機会ですから、食べる楽しみについつい精神が弛緩し、お喋りに興ずる気持ちに誘われます。これは人間として自然な振る舞いですが、沈黙を旨とする修道院では駄弁は忌むべき行動です。そのために食事の折には当番の読師がいて、大きな声で聖書を読み上げ、食事中に修道士たちが無用のコミュニケーションを取らないようにしたり、また食事中に書物を読むことを推奨したりしたと言われています。確か中世ドイツの修道院におけるこうした振る舞いを「Essenlektur」と表したと思いますが、それが正確に食事中の個別の読書を指したものか、それとも読師による読み上げを指しているかは、専門家の間で議論があるようですが。
――本書にはさまざまな修道院が登場しますが、先生ご自身が実際に訪ねてとくに気になった修道院などはありますか?
佐藤:フランスを中心にして中世初期に創建された修道院は、かなり見て回りました。12~13世紀に建てられたものならともかく、7~8世紀の創建になる修道院の多くは廃墟になっているか、単なる教会堂になっていて、往時を知るよすがさえ残っていないことも珍しくありません。第6章や第8章で紹介した現在ルクセンブルクに属しているエヒテルナハ修道院は、アングロ・サクソン人の宣教師ウィリブロードが7世紀末に建立した修道院で、現在の建物は近代になって再建された施設ですが、ここは中世初期の修道院の多くが廃棄されたローマ時代のヴィラの敷地を利用したことを示す典型的な場所で、機会があればぜひ訪ねてください。それと言うのも広大なヴィラ遺構が全面的に発掘され、宏壮な敷地に配置された東屋(あずまや)の遺構や、噴水施設などが忠実に復元されているからです。当時の修道院の立地場所を脳裏に思い浮かべるのに格好の例です。
自分で言うのもなんなんですが、私は地理、地名などにかなりこだわります。地名が出てくれば、必ずその現在地がどこかを調べないと落ち着かないのです。中世初期を研究領域にしていますから、この時代の土地売買関連の文書などを史料にすることも頻繁にあるのですが、例えば売却される土地が一体どこに当たるのか、その広さがどれくらいなのかを具体的に知ることは非常に大事です。問題なのは土地の名称がラテン語で表記されていて、それが現在どういう名前で呼ばれているのか、そもそもその土地が地名としても消失してしまっているかが分からないことです。現在地が特定されている場所の近辺で、そのラテン語が地名として、フランスであればフランス語のどのような綴り字になっているか、決まった法則があって変化するわけではないので、その特定に頭を悩ませます。
フランス国土地理院の10万分の1地図とか、『Index Atlas de France』という、フランス全県の地名を網羅した千ページの地図帳――ここには戸数30~40くらいの小集落まで収録されていて、フランスの宅配業者の標準ツールだと聞いたことがあります――などを参考にして、ああでもないこうでもないと頭をひねった挙句、「現在地不明」とするか、あるいは一つの仮説として特定の地名に同定することになるわけです。海外領土を除いて、フランスにある95県の『県別地誌辞典Dictionnaire topographique du department de ….』というシリーズがツールとして存在するのですが、企画の開始から100年にもなるのに、刊行済みの県は10前後という有様です。
――本書には写本もさまざま紹介されていますが、先生ご自身が実際に御覧になって感銘を受けた写本などはありますか?
佐藤:美術史家ではないので、いわゆる美麗な写本を目にする機会を持ったことはほとんどありません。いつも、あまり流麗ではない筆致で書かれた証文の類です。しかし歴史家にとって、それはどんなに美しい写本を目にするよりもエキサイティングです。それは歴史のナマの声がそこから聞こえてくるからです。
歴史家にとっての写本と接することの魅力は、一種の手触り感とでも言うのでしょうか、そんなものが感じられるからです。校訂され印刷された刊本で史料を読むときと、長い年月の経過のなかで茶褐色に変色し、インクの薄れがところどころ見られる写本で同じテクストを読むときでは、事柄の切迫感がまるで違います。印刷本ではテクストはある種抽象的な言説の表示でしかないのに対して、写本では書き手と読み手のあいだの時間の隔たりが消失し、抜き差しならない直接的な関係に陥ります。例えば印刷本の場合は措辞の連なりは不動のものと映りますが、写本では文字を構成する微妙な線の動きから、次に来る言葉が今現在目にしているのとは違った単語を書くつもりがあったのではないかと、ふと思ったりするわけです。現に在った歴史と異なる歴史、いわば可能態の歴史が、読み手の脳裏に一瞬よぎる思いがすること。これは歴史家の想像力の涵養にとても大事であると思います。
中世写本のもう一つの魅力は、写本そのもと言うより、その伝来の歴史を調べることです。7世紀のトゥールのサン・マルタン修道院で制作されたある文書が、そのあと反故紙となりカロリング朝期に、豪華写本の肉厚の表紙を仕立てる用紙として使われ、その豪華写本がフランス革命の混乱の中で解体され、その折に反故紙が独立に競売の対象になって、英国のインド植民地支配で財をなした伝説の愛書家トマス・フィリップス卿が落札。一族の没落を機に再び競売にかけられ、やがてこれを入手した出版業者がこの反故紙の故郷であるフランスの国立図書館に寄贈するという顛末は、写本が紡いだ歴史そのものと言えなくありません。その変遷の段階、段階が歴史研究の対象になり得る深さを持っているのです。
――執筆中に印象に残った出来事をお聞かせください。
佐藤:私にとって生涯忘れることができない二つの大きな出来事がありました。一つは2015年11月30日に、私の古希を記念してフランス、イギリス、ドイツ、日本の中世史家たちが寄稿した論文集がパリのDe Boccard書店から出版されて、忘れもしない13日のテロから2週間しか経っていないパリのフランス学士院でその贈呈式を行なってもらったこと。
もう一つは本書の第6章で論じた、修道院による古典作品の筆写保存の問題を主題に選び、2016年1月12日に皇居松の間において「西洋中世修道院の文化史的意義」と題して、御進講役を仰せつかったことです。天皇皇后両陛下、皇族の皆様方、陪聴の皆様の前で進講を務める場面を写した写真が後日宮内庁から戴いたのですが、写真を見たパリのピエール・トゥベール先生には、皇帝に進講するアルクイヌスを彷彿とさせると、嬉しいお褒めの言葉を頂戴しました。
――本書と関連するおすすめの本や映画など何かありますか。
佐藤:少し古くなりますが、本も映画も極めつきは惜しくも先年他界したウンベルト・エーコの『薔薇の名前』に指を屈するでしょうね。映画はお気に入りのジャン=ジャック・アノーが監督で、ショーン・コネリーが演ずるバスカヴィルのウィリアムは、彼独特の少し舌足らずの英語の発音が、いかにもイングランドから到来したカミソリの頭脳を具えた壮年の修道士の風格を漂わせて秀逸でした。修道士の不可解な連続死が、修道院の謎めいた大図書室の深奥に密かに蔵されているアリストテレスの一作品で、現在まで伝来していない『笑いについて』――本当に書かれたかどうかも定かではないのですが――の写本を読んだ者が被害者になるという、中世写本の研究者には堪えられない構成で、世界的なベストセラーになりました。お読みでない方にはぜひお勧めします。
――今後の課題、テーマを教えてください。
佐藤:本書の続きとなる1冊を、仮の題ですが「托鉢修道会と騎士修道会――都市化と膨張時代の中世ヨーロッパ修道制」というタイトルで書こうと考えています。13世紀から15世紀が時代枠となるでしょう。
その後は宗教改革の時代に入り、イギリスの修道院のように、国王による強権的な解散措置の対象になるものも出てきます。また、トリエント公会議という、カトリックの側からする対抗宗教改革の動きのなかで、施設としての修道院を持たず、ローマ教皇に直属するイエズス会や、それより1世紀ほど遅れてフランスの旧ベネディクト派修道院がサン・モール会に結集します。イエズス会が新大陸や、日本を初めとするアジアの布教に務めたことは知られていますし、サン・モール会は、歴史学や神学などの学問研究の面で大きな業績を挙げました。これらを「バロック時代の修道制」として、16世紀と18世紀の修道制を考えて見たいと思っています。
その後に、できれば19世紀から20世紀までを植民地における修道士、修道女の活動を主題にした1冊を書きたいと思っています。そうすれば、西洋の修道制をその起源から現在まで辿ったことになりますから。
西洋の修道制についての通史の仕事とは別に、フランク史の分野での著作を考えています。こちらは注付きの学術書の体裁となります。フランク人の起源の問題に取り組む予定なので、北西ヨーロッパの青銅器時代にまで論が及ぶことになるでしょう。考古学を主力とする先史学と、文字記録を素材とする歴史学をどのように結びつけるか、方法論の上でも工夫をしなければならない著作になると踏んでいます。
――最後に読者へのメッセージを一言いただけますか?
佐藤:人文科学、なかでも歴史学の醍醐味は、それまで定説とされていた事実や解釈が、常に新しい主張や、新しい史料の発見によって覆され、再解釈の対象になるところにあります。知の大いなる躍動の舞台である歴史の書物を、お愉しみください。

