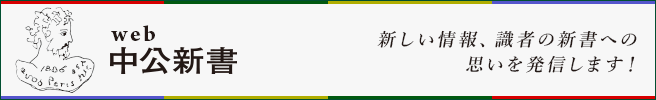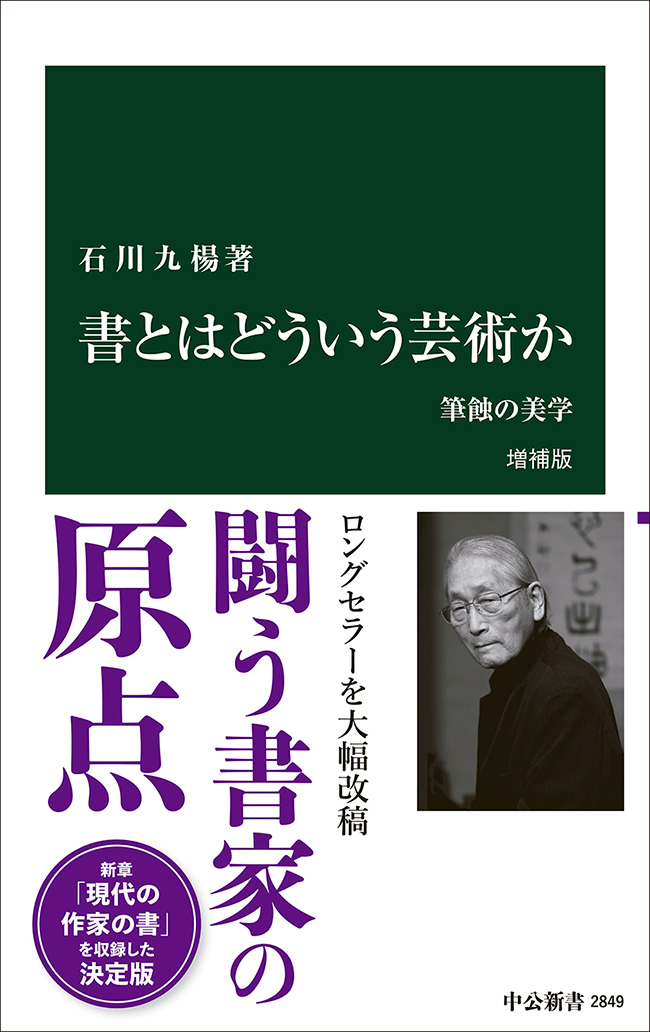
書とはどういう芸術か 増補版筆蝕の美学
石川九楊 著
書は紙と筆と墨の芸術である。墨跡には深度・速度・角度と力が秘められている。書の美は草書体に萌芽し、楷書体とその基本運筆「三折法」の成立により完成したが、そこには石と紙の争闘史があった。筆と紙の接点に生じる力(筆蝕)こそ書の美の核心で、文字でなく言葉を書くところに書の価値はある。甲骨文から前衛書道までを読み解き、書の表現を歴史的、構造的に解明したロングセラーに、新章「現代の作家の書」を収録。
目次
- 増補版発刊にあたって
- はじめに
- 序章 書はどのようなものと考えられてきたか
- 「書は美術ならず」論争/「書は文字の美的工夫」/「書は文字の美術」/「書は線の美」/「書は人なり」/その他の書論/従来の書論を超えて/書は筆跡、書字跡である/書は肉筆である
- 第一章 書は筆蝕の芸術である―書の美はどのような構造で成立するか
- 肉筆と筆蝕/筆蝕とは何か/書は「深度」の芸術である/書は「速度」の芸術である/書は「角度」の芸術である/深度と速度と角度のからみ合い/書は「力」の芸術である/構成
- 第二章 書は紙・筆・墨の芸術である―書の美の価値はなぜ生じるのか
- 紙・筆・墨の前史/抽象的表現空間、「白紙」の発見/抽象的刻具、毛筆の発見/楷書体の成立/抽象的刻り跡、墨の発見/紙が石に勝利する条件/草書体、行書体、楷書体/三折法の逆襲/つながる草書、狂草/顔真卿「顔勤礼碑」の意味/黄庭堅「李太白憶旧遊詩巻」の革命/書の芸術性の根拠
- 第三章 書は言葉の芸術である―書は何を表現するのか
- 書は漢字文明圏の芸術である/日本の書と中国の書/日本の書と背景/書は文学である
- 第四章 書は現在の芸術でありうるだろうか―書の再生について
- 書の近代/現代の書/近代詩文書/伝統書道の変貌/素人の書/書の再生
- 第五章 現代の作家の書
- 戦後の書の語られ方/作家たちの書をどう見るか/岡本かの子の書/川端康成の書/松本清張の書/三島由紀夫の書/中上健次の書
- あとがき
- 増補版あとがき
- 図版出典
書誌データ
- 初版刊行日2025/3/24
- 判型新書判
- ページ数272ページ
- 定価1100円(10%税込)
- ISBNコードISBN978-4-12-102849-5
書店の在庫を確認
- ❑紀伊國屋書店 ❑丸善&ジュンク堂書店
- ❑有隣堂 ❑TSUTAYA ❑くまざわ書店
書評掲載案内
・metropolitan2026年1月号・朝日新聞(朝刊)2025年4月26日/中村佑子(作家・映像作家)