ホーム > 検索結果
発行された時期:1973年1月からを含む書籍一覧
全10808件中 345~360件表示
-
電子書籍
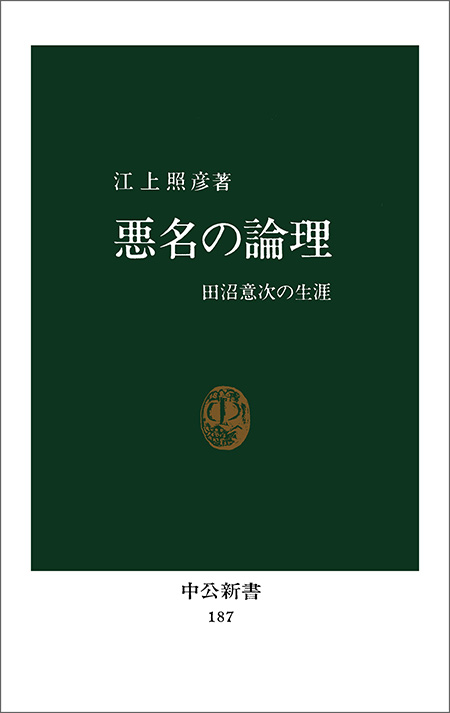
悪名の論理
田沼意次の生涯
江上照彦 著
ナポレオンはメッテルニヒを「世紀最大の嘘つき」と呼んだ。一度はその愛人だったこともあるリーフェン公爵夫人さえも、「世にも稀れな偽善者」とののしった。田沼意次の場合も嫌われかたがよく似ている。徳川の為政者中、彼ほど世間から口汚く罵倒され、あげくは汚辱の淵に蹴落されて深く沈淪しているものはない。東西をとわず悪名高い為政者には共通の政治的性格の特徴があるが、不評の条件とは何か。意次の生涯をたどって追究する。
2025/04/22 刊行
-
電子書籍
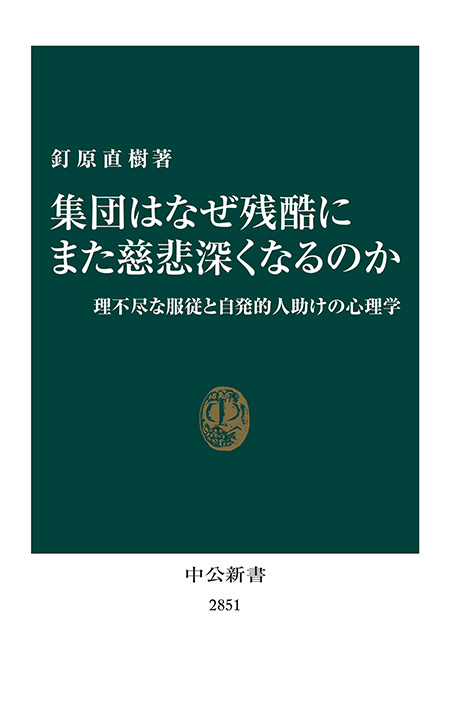
集団はなぜ残酷にまた慈悲深くなるのか
理不尽な服従と自発的人助けの心理学
釘原直樹 著
組織の不祥事が報道されると「自分なら絶対にやらない」と思う。だが、いざ当事者になると、個人ならしない悪事でも多くの人は不承不承、あるいは平気でしてしまう。なぜ集団になると、簡単に同調・迎合し、服従してしまうのか。著者は同調や服従に関する有名な実験の日本版を実施し、その心理を探る。一方でタイタニック遭難など、緊急時に助け合い、力を発揮するのも集団の特性である。集団の光と闇を解明する試み。■□■ 目 次 ■□■はじめに――集団心理の光と影序章 集団とは何か第1章 わが国で行われた服従実験で明らかになったことは何か1 責任を「人」に押し付ける2 服従実験と悪の凡庸性3 筆者が行った服従実験4 日本での服従実験の結果は?第2章 服従の理由は? 第三者の感想は? 実験の問題点は?1 なぜ参加しようと思ったのか2 服従を促進する要因は何か3 なぜ離脱できないのか4 服従実験の観察者は実験をどのように見るのか5 服従実験の問題点①――生態学的妥当性の問題6 服従実験の問題点②――方法論と倫理の問題第3章 同調行動はなぜ起きるのか1 同調とは何か2 同調の分類3 無意識に影響を受ける4 緊急事態で大きくなる影響5 集団規範による影響第4章 現代日本人の同調の特色は何か1 同調行動に影響する要因2 筆者が実施した同調実験第5章 同調行動はどのように拡散するのか1 ロジスティック・モデル2 同調の広がりに関する実験3 大集団での同調は?第6章 緊急事態では人は理性的に振る舞うのか1 集団のネガティブな側面の研究2 緊急事態では人は理性を失うのか?3 実際の緊急事態の行動と意思決定の研究4 9・11同時多発テロ時の世界貿易センタービルからの避難第7章 航空機事故発生時の機内で人々はどのように行動したのか1 ガルーダ・インドネシア航空機福岡空港離陸失敗事故2 事故発生時の客室内3 乗客の認識4 脱出時の行動5 調査のまとめ終章 集団の光と影に何が影響するか1 社会の価値観2 加害者と被害者の視点の違い3 内集団と外集団4 行為者と観察者の認識の食い違い5 光と影の非対称性(影が光より強いのか)あとがき
2025/04/22 刊行
-
電子書籍
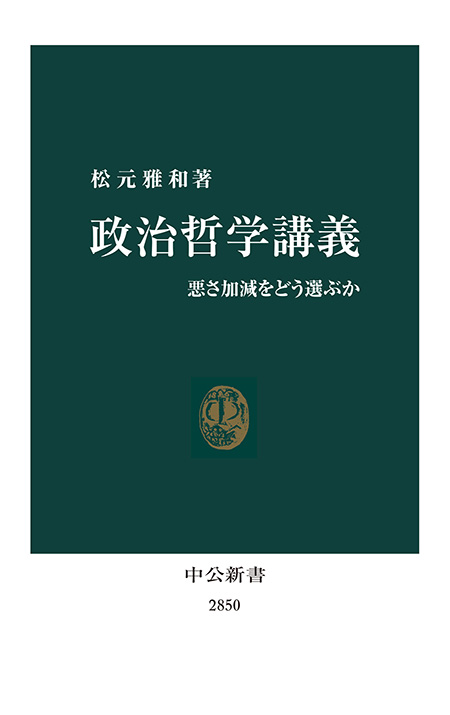
政治哲学講義
悪さ加減をどう選ぶか
松元雅和 著
正しさとは何かを探究してきた政治哲学。向き合う現実の世界は進むも退くも地獄、「よりマシな悪」を選んでなんぼの側面をもつ。命の重さに違いはあるのか。汚い手段は許されるか。大義のために家族や友情を犠牲にできるか。本書はサンデルの正義論やトロッコ問題のような思考実験に加え、小説や戯曲の名場面を道しるべに、「正しさ」ではなく「悪さ」というネガから政治哲学へいざなう。混迷の時代に灯火をともす一書。【目次】はじめに正義論に残された問い 作品で読み解く第1章 「悪さ加減の選択」―?ビリー・バッドの運命1 選択のジレンマ性ジレンマとは何か 損失の不可避性 損失の不可逆性2 政治のジレンマ性政治とは何か 公共の利益 利害の対立3 マシな悪の倫理マシな悪とは何か 三つの特徴 行為と結果の組み合わせ4 まとめ――政治の悲劇性第2章 国家と個人――アンティゴネーとクレオーンの対立1 偏向的観点と不偏的観点偏向的観点 不偏的観点2 不偏的観点と政治法の下の平等 具体例① 政治腐敗 具体例② 国連活動3 不偏的観点と個人インテグリティと政治 国家と個人・再考4 まとめ――クレオーンの苦悩と悲嘆第3章 多数と少数――邸宅の火事でフェヌロンを救う理由1 数の問題規範理論① 功利主義 特徴① 総和主義 特徴② 帰結主義2 総和主義の是非人格の別個性 権利論 権利は絶対的か3 帰結主義の是非規範理論② 義務論 マシな悪の倫理・再考 義務論的制約4 まとめ――ゴドウィンの変化第4章 無危害と善行――ハイジャック機を違法に撃墜する1 トロリーの思考実験具体例ドイツ航空安全法 「問題」前史2 消極的義務と積極的義務義務の対照性 優先テーゼ3 トロリー問題「問題」の発見 手段原理 航空安全法判決4 まとめ――制約をあえて乗り越える第5章 目的と手段――サルトルと「汚れた手」の問題1 汚れた手という問題理解①マキァヴェリの場合 理解② ウォルツァーの場合2 いつ手は汚れるか印としての罪悪感 罪の内実3 いつ手を汚すか指針①絶対主義 指針② 規則功利主義 指針③ 閾値義務論 制度化の問題4 まとめ――サルトルと現実政治第6章 自国と世界――ジェリビー夫人の望遠鏡的博愛1 一般義務と特別義務不偏的観点・再考 偏向的観点・再考 偏向テーゼ2 特別義務の理由理由①道具的議論 理由② 制度的議論 理由③ 関係的議論3 特別義務の限界不偏テーゼ 消極的義務・再考 積極的義務・再考4 まとめ――慈悲は家からはじまり……第7章 戦争と犠牲――ローン・サバイバーの葛藤1 民間人と戦闘員民間人の保護 戦闘員の保護2 民間人への付随的損害二重結果説 民間人か自国民か 具体例 ガザ紛争3 民間人への意図的加害個人が陥る緊急事態 国家が陥る緊急事態 偏向的観点・再再考4 まとめ――戦闘員の信念と部族の決意第8章 選択と責任――カミュが描く「正義の人びと」1 選択を引き受ける規範理論③ 徳倫理学 インテグリティと政治・再考 心情倫理と責任倫理2 責任を引き受ける指針①メルロ=ポンティの場合 指針② カミュの場合3 「悪さ加減の選択」と私たち民主的な汚れた手 責任を政治的に引き受ける 具体例 アルジェリア問題4 まとめ――サルトル=カミュ論争終 章 政治哲学の行方AIと「悪さ加減の選択」 AI時代の政治哲学あとがき読書・作品案内引用・参考文献
2025/04/22 刊行
-
電子書籍
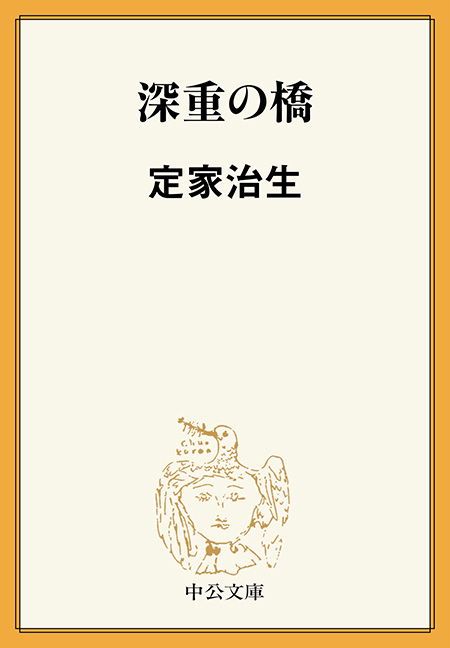
深重の橋
定家治生 著
本作品は著者名を澤田ふじ子から定家治生に変更いたしました。京を焦土と化す応仁・文明の大乱の足音が刻々と迫るなか、15歳の少年〈牛〉が人買い商人の手で湯屋(風呂屋)へと売り飛ばされた。狡猾な主が課す苛酷な労働に耐え、牛は逞しい男へと成長する。そして一緒に人買い市から売られてきた女と心を寄せ合うのだった。やがてその才を見込まれ牛は、武具屋に引き取られる。激化する守護大名家の勢力争い、度重なる凶作と飢饉、頻発する土一揆。そして、日本の文化を誕生させたといっても過言ではない、足利義政の為政――。牛は応仁・文明の大乱の渦中へ身を投じるが、そこには悲劇の邂逅が待ち受けていた……。巻末に短編小説「はぐれの茶碗」を収録。
2025/04/22 刊行
-
電子書籍
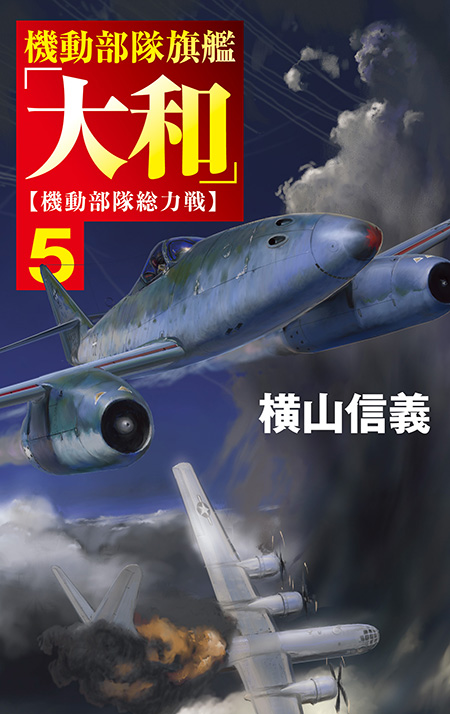
機動部隊旗艦「大和」5
機動部隊総力戦
横山信義 著
豪州を連合国から脱落させる日本の戦略は頓挫する。連合艦隊司令長官近藤信竹大将はソロモン諸島とニューギニアの兵力を引き上げラバウルの防備を固めて迎え撃たんとするが、米海軍は手薄となっていたカビエンを奇襲。トラックとの連絡を絶たれたラバウルは敵中に孤立し、トラック諸島も空襲にさらされ艦隊泊地としての機能を喪失してしまう。豪州を守り切った米軍が次に狙ってくるのは、マリアナ諸島である。ここに基地が構築された場合、日本本土が重爆撃機B29の攻撃圏内に入ってしまう。新鋭エセックス級空母10隻を押し立てて迫りくる米海軍に対し、連合艦隊も空海の総力を挙げて立ち向かうが――。「米軍は十中の十までマリアナに来る。GF司令部は、そのように判断している」
2025/04/22 刊行
-
電子書籍
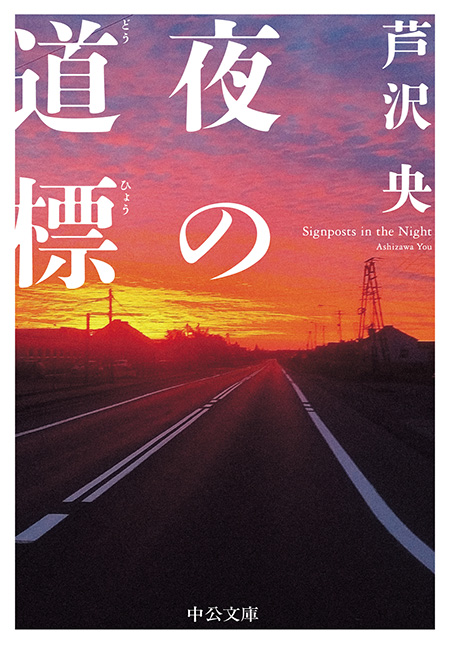
夜の道標
芦沢央 著
1996年、横浜市内で塾経営者が殺害された。事件発生から2年、被疑者である元教え子の足取りは今もつかめていない――。殺人犯を匿う女、窓際に追いやられながら捜査を続ける刑事、そして、父親から虐待を受けている少年。それぞれの守りたいものが絡み合い、事態は思いもよらぬ展開を迎える。日本推理作家協会賞受賞作。(解説)山田詠美
2025/04/22 刊行
-
電子書籍
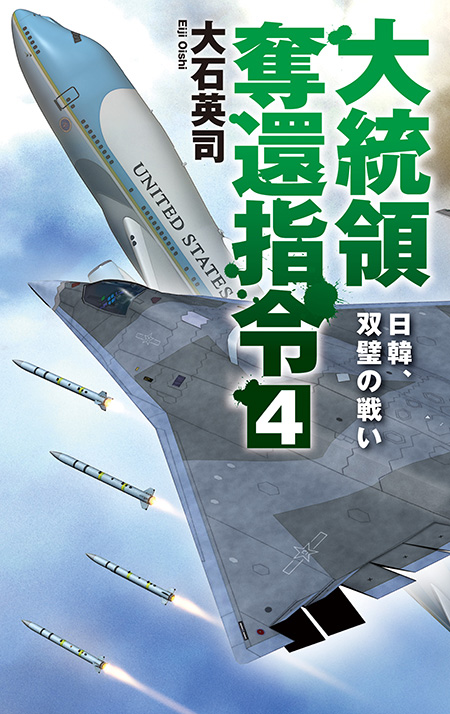
大統領奪還指令4
日韓、双璧の戦い
大石英司 著
米国内の混乱に乗じ、アラスカ・アンカレッジへの上陸を果たした中国人民解放軍。そこには、ロシアの魔の手も迫っていた!一方の自衛隊は夥しい犠牲を払いつつも、シアトルに留まる。未曾有の危機に日韓の特殊部隊が手を結ぶ、激動の第4巻。〈目次〉プロローグ第一章 踏み留まる決意第二章 英雄の帰還第三章 特殊戦司令官第四章 語学の達人第五章 J‐36戦闘機第六章 父と娘第七章 日韓、それぞれの戦い第八章 幽霊退治エピローグ
2025/04/22 刊行
-
電子書籍
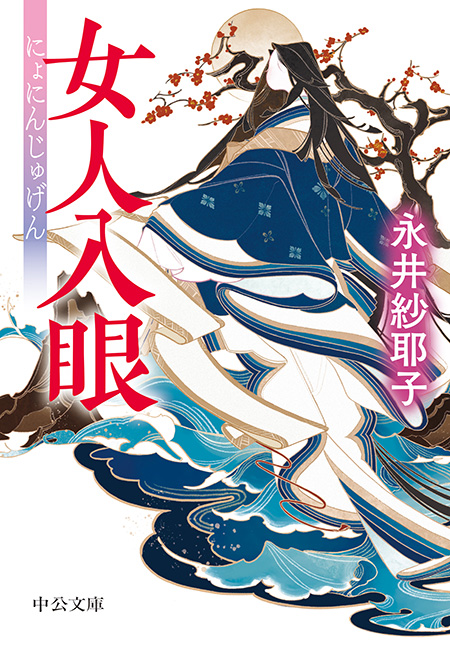
女人入眼
永井紗耶子 著
第167回直木賞候補作、待望の文庫化!「鎌倉幕府最大の失策」と呼ばれる謎多き事件・大姫入内。その背後にあったのは、国の実権をめぐる女たちの政争。そしてわかり合えない母娘の悲しい過去だった。「大仏は眼が入って初めて仏となるのです。男たちが戦で彫り上げた国の形に、玉眼を入れるのは、女人であろうと私は思うのですよ」建久六年(1195年)。京の六条殿に仕える女房・周子は、宮中掌握の一手として、源頼朝と北条政子の娘・大姫を入内させるという命を受けて鎌倉へ入る。気鬱の病を抱え、繊細な心を持つ大姫と、大きな野望を抱き、それゆえ娘への強い圧力となる政子。二人のことを探る周子が辿り着いた、母子の間に横たわる悲しき過去とは――。「鎌倉幕府最大の失策」と呼ばれる謎多き事件・大姫入内。その背後には、政治の実権をめぐる女たちの戦いと、わかり合えない母と娘の物語があった。
2025/04/22 刊行
-
電子書籍
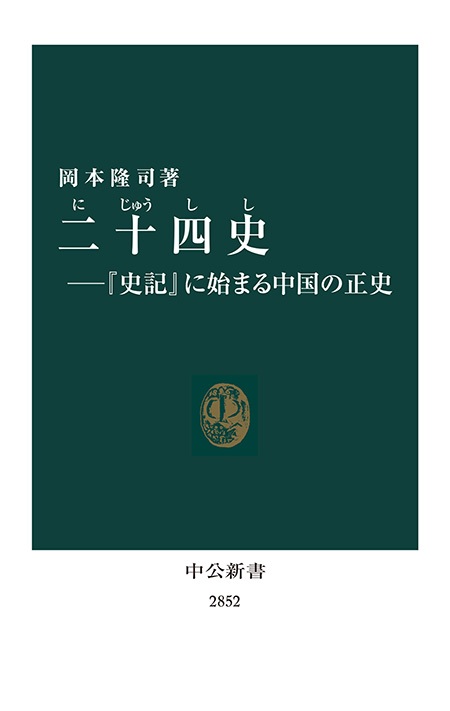
二十四史―『史記』に始まる中国の正史
岡本隆司 著
史記、漢書、三国志、後漢書……元史、明史。中国では、前王朝の歴史を次の王朝が国家をあげて編纂することが多かった。これらは「正史」とされ、統べて二十四史と呼ぶ。中国史の根本史料であり、ここから歴史が記されてきた。 本書は、正史の起源から現代まで、各書の特徴や意義、歴史を追う。さらに、日本の史書との差異や、清史をめぐる中華民国と中華人民共和国の編纂方針の対立など、時の政治の影響を受けた問題を記す。
2025/04/22 刊行
-
電子書籍
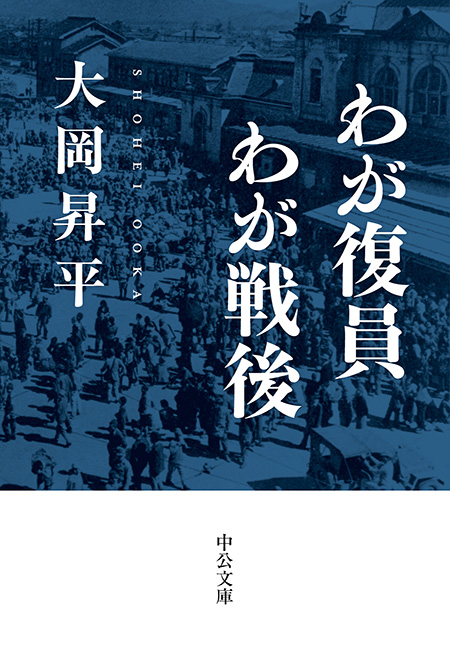
わが復員わが戦後
大岡昇平 著
1945年12月、復員船は博多に着いた──。戦争末期、一兵士としてフィリピンのミンドロ島の警備にあたり、一年弱の俘虜生活を送った復員兵を待っていた、戦後社会の混乱、家族や旧友との再会……。戦争と戦後体験から生まれた名作を集成。遺稿となったエッセイ「二極対立の時代を生き続けたいたわしさ」を付す。〈解説〉城山三郎 〈巻末エッセイ〉阿部昭
2025/04/22 刊行
-
電子書籍
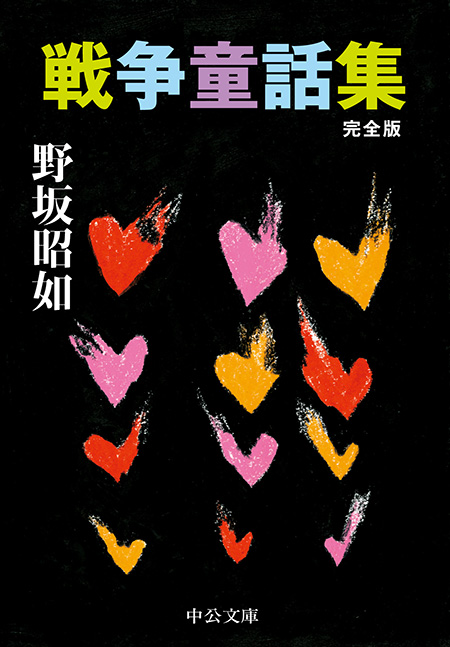
戦争童話集
完全版
野坂昭如 著
「あの夏から80年。野坂さんの思いを、私は語り継ぐ」 吉永小百合さん推薦昭和20年、8月15日――すべて同じ書き出しで始まるのは、忘れてはならない物語。空襲下の母子を描く「凧になったお母さん」をはじめ、鎮魂の祈りをこめて綴られた12篇に、沖縄戦の悲劇を伝える「ウミガメと少年」「石のラジオ」を増補した完全版。野坂昭如没後10年。【目次】小さい潜水艦に恋をしたでかすぎるクジラの話青いオウムと痩せた男の子の話干からびた象と象使いの話凧になったお母さん年老いた雌狼と女の子の話赤とんぼと、あぶら虫ソルジャーズ・ファミリーぼくの防空壕八月の風船馬と兵士捕虜と女の子焼跡の、お菓子の木改版のためのあとがき沖縄篇ウミガメと少年石のラジオ
2025/04/22 刊行
-
電子書籍
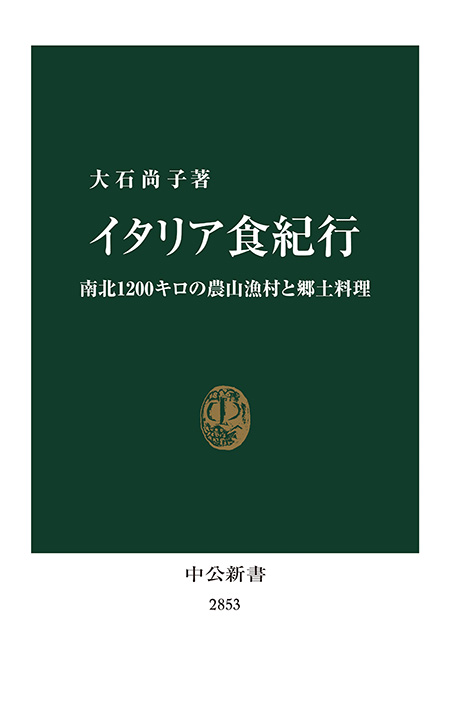
イタリア食紀行
南北1200キロの農山漁村と郷土料理
大石尚子 著
隣町に行けば言葉もパスタも変わる――。イタリア料理は味わいのみならず、多様性が魅力。地域の風土・歴史に根ざした食材や伝統料理法が受け継がれているのだ。著者は南・北・中央・島々をめぐり、ポベラッチャ(貧乏食)の知恵を足と舌で探る。またアグリツーリズムや有機農業、スローフード運動など、地域再生のソーシャル・イノベーションにも注目。人口減少が進む日本の地方にとって、有益なヒントが満載。写真多数。はじめに―食と社会の未来を求めて世界初・食をテーマにしたミラノ万博 日本とイタリアの類似性 農村が未来を切り拓く第1章 身土不二―地域に根ざした食の多様性ランチは家でマンマの手づくり まちにあふれるメルカート―野菜・畜産・魚介 隣町に行けば言葉もパスタも変わる ハレとケ―イタリア料理の誕生と南北問題 資本主義競争に打ち勝ってきたブランド力 知と融合するスローフード運動 よみがえる農業/農村―その背景 第2章 北イタリア―トリノ・ヴェネト州・ボローニャ1 アルプス(山)とパダーノ(平野)が育む芳醇な食自治都市国家の形成と経済発展 アルプスの麓・丘陵地帯の極上食材 全世界から若者が集まる小さな田舎町・ブラ エトルリア時代から伝わるポー平原の食文化2 伝統×若者―食の新たな価値創造へ過疎地のワイナリーで景観を守る二人の若者 伝統手法によるシャンパーニュよりも上品に―プロセッコ 暮らしの質を保障するスローシティ 肥沃な土地が極上生ハムを生み出す伝統 食のテーマパークFICOと食問題を解決するボローニャの企業 障がい者雇用と廃棄食削減に挑戦する世界的シェフ 脱工業から持続可能な都市へ第3章 中央イタリア ―ローマ、トスカーナ、ウンブリア州1
2025/04/22 刊行
-
電子書籍
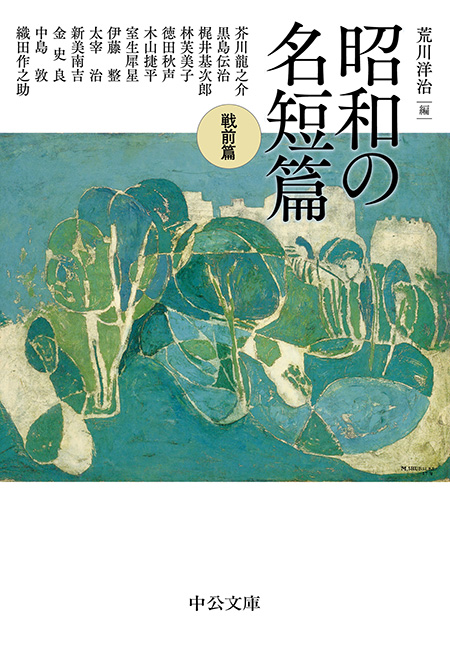
昭和の名短篇
戦前篇
荒川洋治 編
激動の昭和・戦前戦中期、作家たちはみずからの限界点を見つめながら、文学を愛する人たちの期待に応えようとした。そこから忘れがたい多くの名編が生まれた――。芥川龍之介から中島敦、織田作之助まで現代詩作家・荒川洋治が厳選した全十三篇を発表年代順に収録。解説では昭和の名長篇も紹介する。文庫オリジナル。〈編集・解説〉荒川洋治【目次】玄鶴山房/芥川龍之介冬の日/梶井基次郎橇/黒島伝治風琴と魚の町/林芙美子和解/徳田秋声一昔/木山捷平あにいもうと/室生犀星馬喰の果て/伊藤整満願/太宰治久助君の話/新美南吉コブタンネ/金史良名人伝/中島敦木の都/織田作之助
2025/04/22 刊行
-
電子書籍
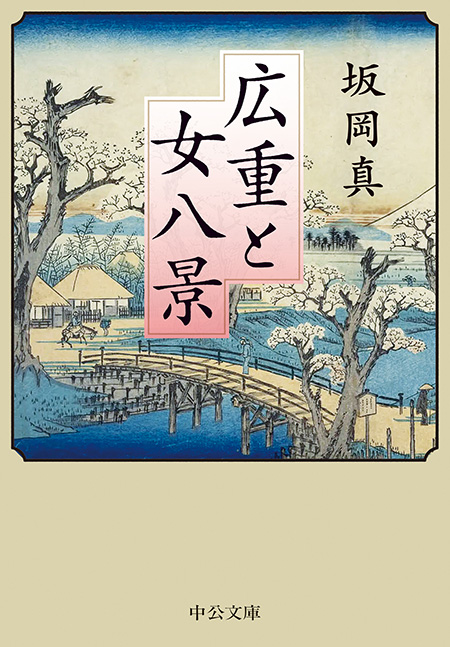
広重と女八景
坂岡真 著
「七夕の晩、また君恋橋で逢おう」と男から錦絵を渡された女。その話を聞いた絵師は、落款から己の描いた絵だと気付き、二人の邂逅を見届けたいと二十数年ぶりに彼の地へ向かう(「小金井橋夕照」)。名所絵の依頼を受けた歌川広重が「江戸近郊八景」を描く道すがら、人々の抜き差しならぬ恋模様を覗く傑作八篇。『恋々彩々』改題。〈解説〉細谷正充
2025/04/22 刊行
-
電子書籍
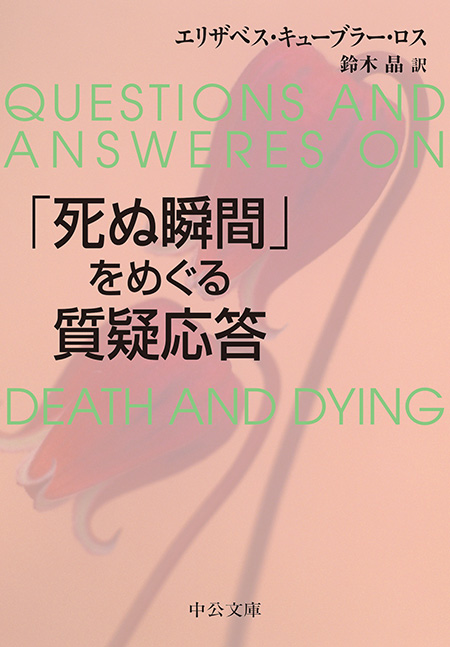
「死ぬ瞬間」をめぐる質疑応答
エリザベス・キューブラー・ロス 著 鈴木晶 訳
死を告知された患者と、介護する家族の心構えを、簡潔な質疑応答のかたちでまとめた必読の書。「どうして私が」という当惑と悲しみをいかに克服するのか。
2025/04/22 刊行







