ホーム > 検索結果
発行された時期:1973年1月からを含む書籍一覧
全10812件中 4590~4605件表示
-
中公新書
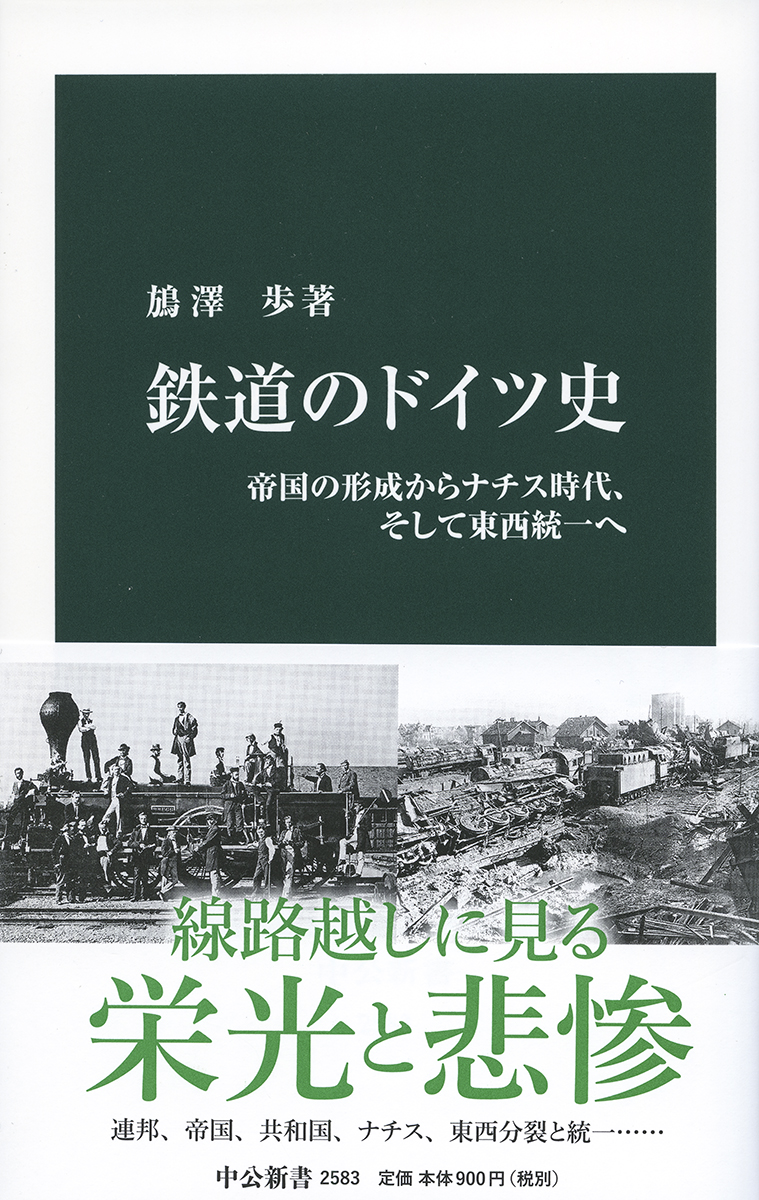
鉄道のドイツ史
帝国の形成からナチス時代、そして東西統一へ
?澤歩 著
1815年、大小さまざまな主権国家の集合体・ドイツ連邦が誕生。以降、ドイツは帝国、共和国、ナチス、東西分裂、そして統一へと、複雑な軌道を疾走した。本書は、同時代に誕生した鉄道という近代技術を担った人びとと、その組織からドイツを論じる。統一国家の形成や二度の世界大戦などの激動に、鉄路はいかなる役割を果たしたのか。「富と速度」(ゲーテ)の国民経済を模索した苦闘とともに、「欧州の盟主」の実像を描き出す。
2020/03/18 刊行
-
中公新書
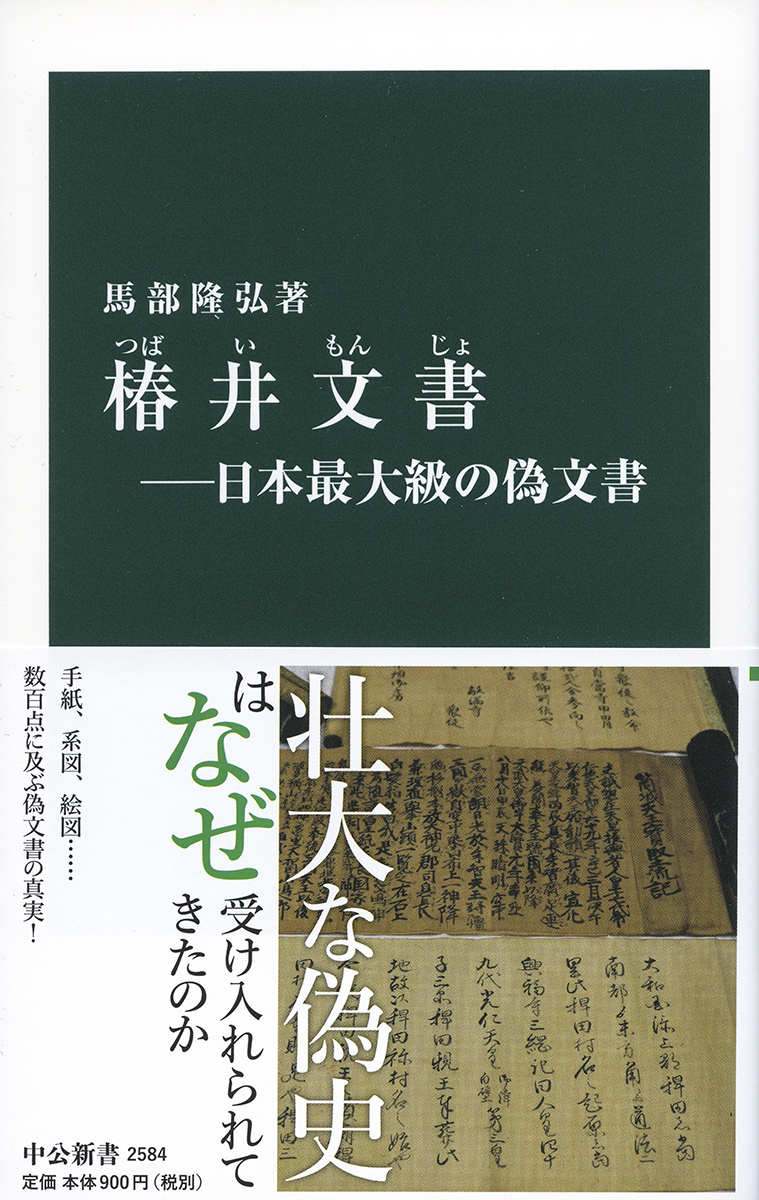
椿井文書―日本最大級の偽文書
馬部隆弘 著
中世の地図、失われた大伽藍や城の絵図、合戦に参陣した武将のリスト、家系図......。これらは貴重な史料であり、学校教材や市町村史にも活用されてきた。しかし、もしそれが後世の偽文書だったら? しかも、たった一人の人物によって創られたものだとしたら――。椿井政隆(一七七〇~一八三七)が創り、近畿一円に流布し、現在も影響を与え続ける数百点にも及ぶ偽文書。本書はその全貌に迫る衝撃の一冊である。
2020/03/18 刊行
-
中公新書
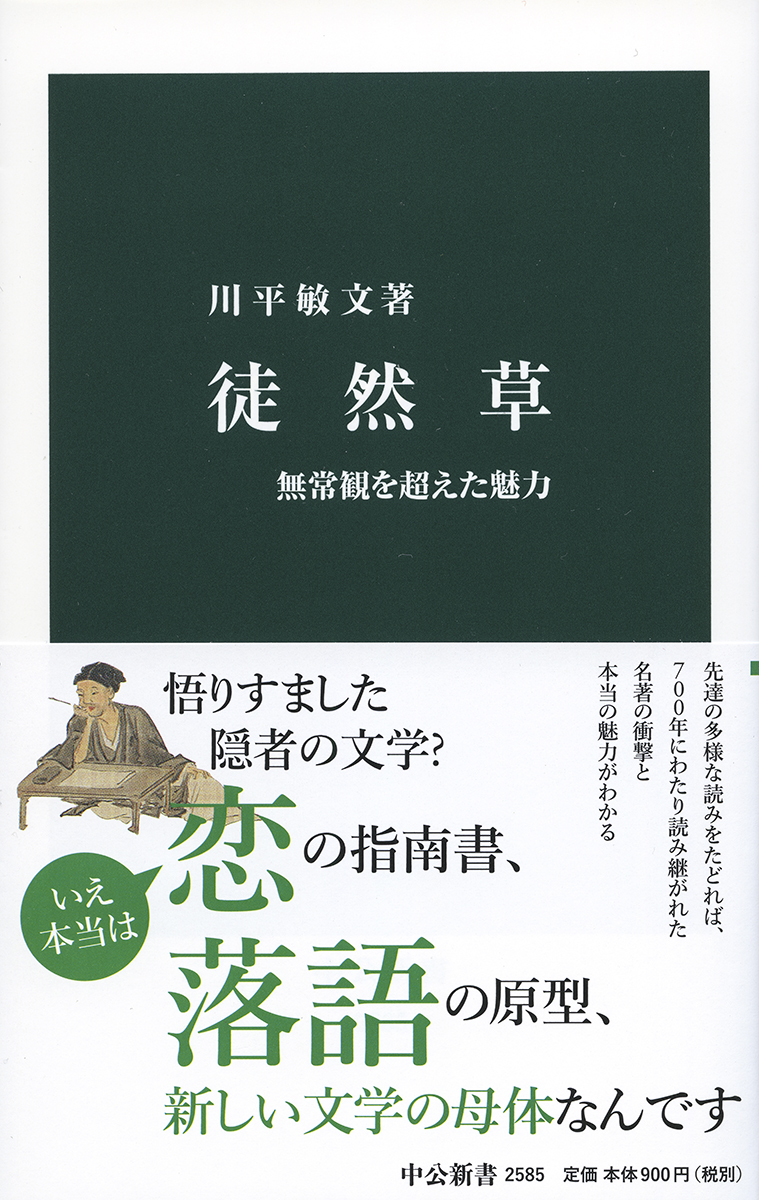
徒然草
無常観を超えた魅力
川平敏文 著
鎌倉時代末期、兼好法師が著した日本文学屈指の古典『徒然草』。自然の移ろいに美を見いだし、死や老いが主題の随想を含むため「無常観の文学」という理解が主流だ。しかし、ベストセラーだった江戸時代には多様な読み方がなされた。江戸幕府に仕えた儒者の林羅山は儒教に基づく注釈書を作り、近松門左衛門は浄瑠璃で兼好を色男として描いた。本書は『徒然草』の知られざる章段や先達の読みを通して奥深さと魅力に迫る。
2020/03/18 刊行
-
中公新書ラクレ
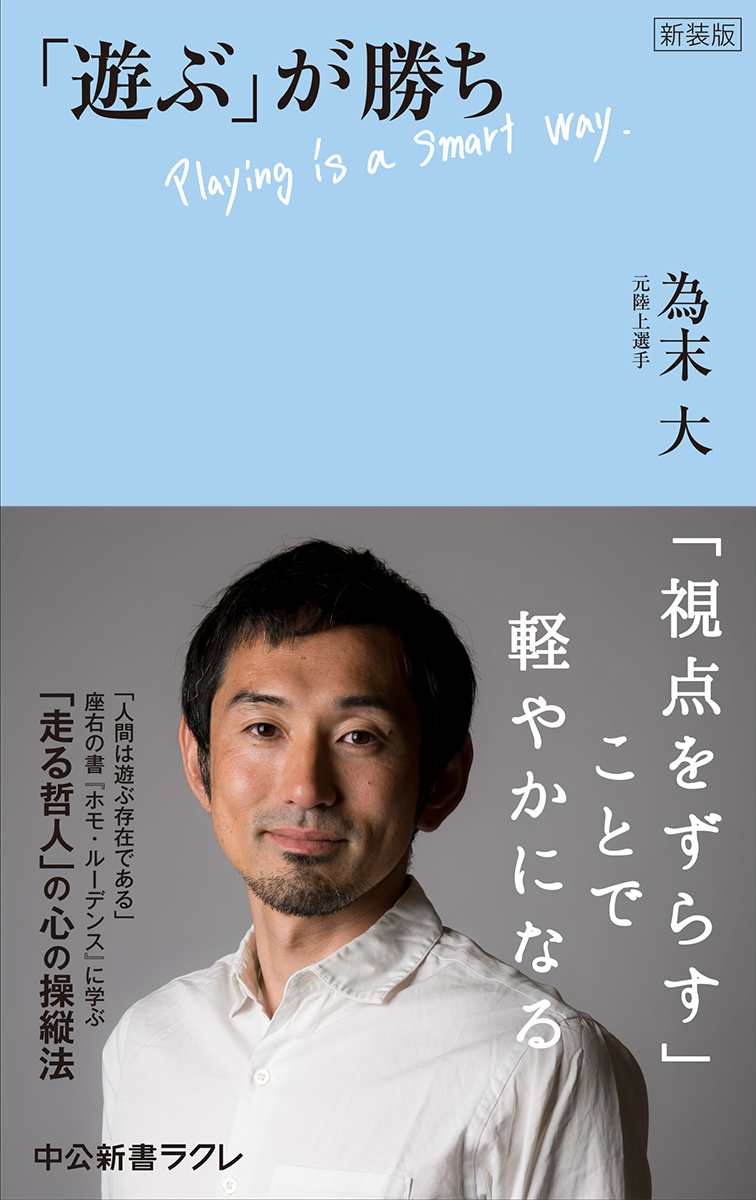
新装版
「遊ぶ」が勝ち
為末大 著
世界陸上選手権のハードル競技で銅メダルを2度勝ち取り、オリンピックにも3度出場。引退後はスポーツと教育に関する活動を行い、ビジネスの世界に挑戦している「走る哲学者」の原動力とは何か? 競技生活晩年、記録が伸びず苦しかったときに出会った名著に重要なヒントがあった――「人間は“遊ぶ”存在である」。世界の第一線で闘った競技生活を振り返り、「遊び」という身体感覚を言語化したロングセラーの新装版。「努力が報われない」と悩む人たちへ贈る心の操縦法。
2020/03/18 刊行
-
中公新書ラクレ
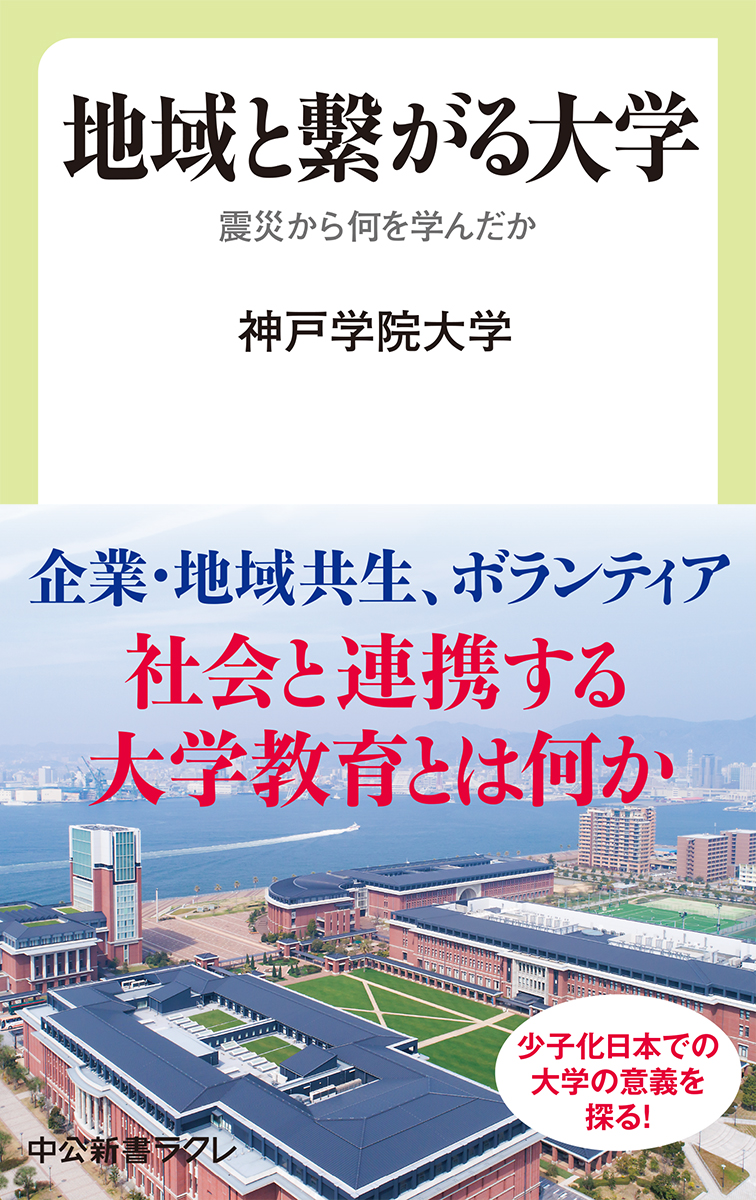
地域と繋がる大学
震災から何を学んだか
神戸学院大学 著
1995年(平成7年)阪神・淡路大震災が直撃した神戸市。その後、国内外からの支援を受け復興の道を歩む。震源地に一番近い総合大学として、神戸学院大学は「社会との絆」「いのちの大切さ」を教育指針に地域の復興に尽力し、防災やボランティアなど教育活動を展開。産業界、自治体、地域との連携で新しい大学の価値を創り上げることを目指した。本書では、大学の取り組みを紹介し、今後の大学教育が進むべき新しい方向性を問う一冊である。
2020/03/18 刊行
-
電子書籍
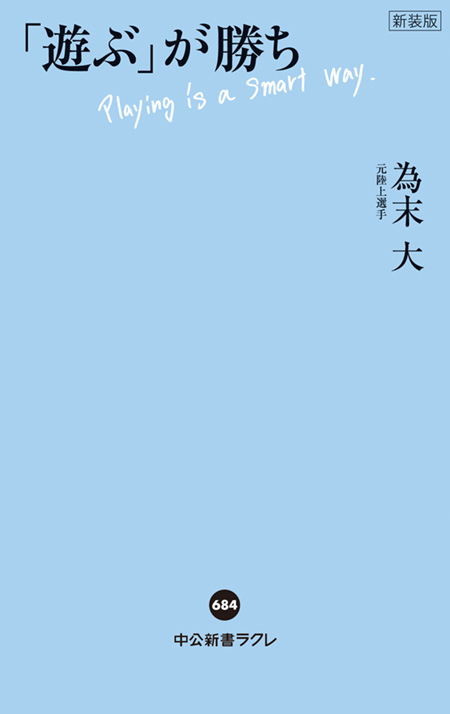
新装版
「遊ぶ」が勝ち
為末大 著
世界陸上選手権のハードル競技で銅メダルを2度勝ち取り、オリンピックにも3度出場。引退後はスポーツと教育に関する活動を行い、ビジネスの世界に挑戦している「走る哲学者」の原動力とは何か? 「人間は“遊ぶ”存在である」――競技生活晩年、記録が伸びず苦しかったときに出会った名著に重要なヒントがあった。世界の第一線で闘った競技生活を振り返り、「遊び」という身体感覚を言語化したロングセラー新装版。「努力が報われない」と悩む人たちへ贈る心の操縦法。
2020/03/18 刊行
-
電子書籍
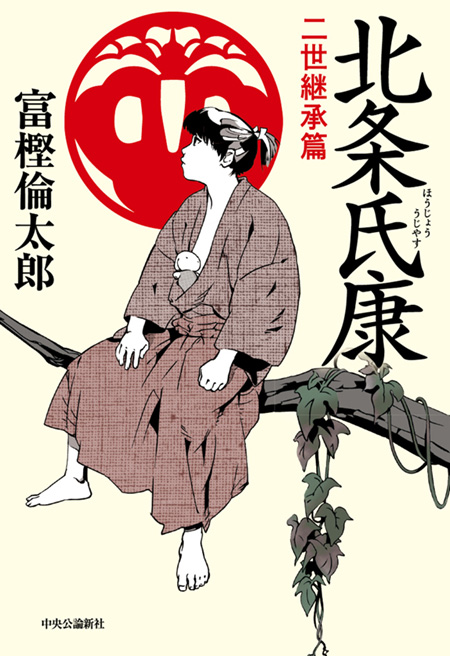
北条氏康
二世継承篇
富樫倫太郎 著
〈北条サーガ〉に待望の新シリーズ富樫倫太郎が、今度は北条家3代目の生涯を描き出す!「北条早雲」と「軍配者」――ふたつの人気シリーズを受け継ぐ壮大なストーリー「北条氏康」が幕を開ける祖父・早雲に可愛がられた伊豆千代丸は、やがて3代目・氏康として立つ。関東全土の支配を目指す氏康の生涯には、今川義元との対立、河越夜襲、そして武田信玄や上杉謙信との死闘……幾多の試練が待つことに。新シリーズ第一弾は、早雲に可愛がられた伊豆千代丸時代から、軍配者・風摩小太郎との出会い、小沢原の初陣まで!
2020/03/18 刊行
-
電子書籍

覇権交代8
香港ジレンマ
大石英司 著
海南島制圧を目指し北上していた日米は、都市ゲリラ戦へ突入したことで進行が停滞していた。一方、韓国では反日を叫ぶ釜山市長が解任され、香港では自由を叫ぶ学生たちが続々と獅子山に集結する――。これまでに無い兵器や情報を駆使する新時代の戦争は最終局面を迎え、各国・各軍がそれぞれの思惑で動く中、中国軍の最後の反撃により、水陸機動団長になった土門に最大の危機が迫る!?ハワイから続くこの戦いの勝者は?〈サイレント・コア〉のメンバーは、無事日本に帰ることができるのか――。大人気「覇権交代」シリーズ完結!
2020/03/17 刊行
-
電子書籍
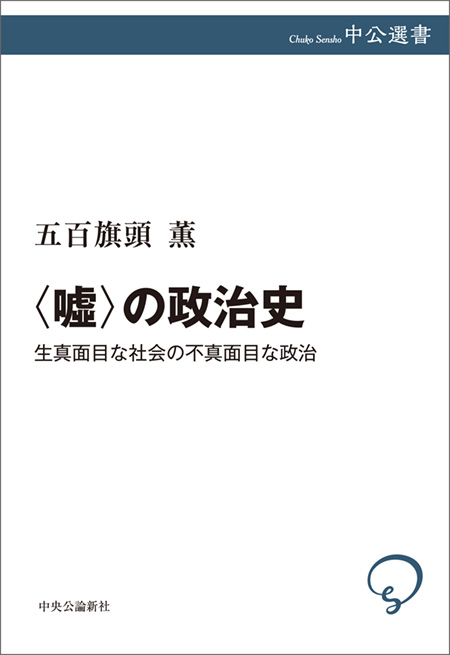
〈嘘〉の政治史
生真面目な社会の不真面目な政治
五百旗頭薫 著
政治に〈嘘〉がつきものなのはなぜか。絶対の権力というものがあるとすれば、嘘はいらない。それなりの反対勢力野党や異議申し立てがあるからこそ、それを迂回するために嘘が必要となり、反対する野党や異議申し立ての側も、権力と闘うために嘘を武器にするのだ。もちろん嘘には害があり、特に危険な嘘もある。世界中に嘘が横行する今、近現代の日本の経験は、嘘を減らし、嘘を生き延びるための教訓への対応策と対抗策の格好の素材となるはずだ。複数政党政治が成立するための条件と地域社会のあるべき未来像も、そこから見えてくる。目次はじめにⅠ 〈嘘〉の起源――生真面目な社会 歴史をとらえる第1章 職分から政党への五〇〇年Ⅱ レトリックの効用――〈嘘〉の明治史 横着な〈嘘〉への対処法第2章 福地櫻痴の挑戦 第3章 循環の観念 第4章 五/七/五で嘘を切る Ⅲ 野党 存続の条件 政党の〈嘘〉の功罪第5章 複数政党政治を支える嘘Ⅳ 地方統治の作法 〈嘘〉のある号令と、呼応する人々第6章 人類を鼓舞してきたもの 第7章 受益と負担の均衡を求めて――近現代日本の地域社会 補章 昆虫化日本 越冬始末
2020/03/13 刊行
-
電子書籍
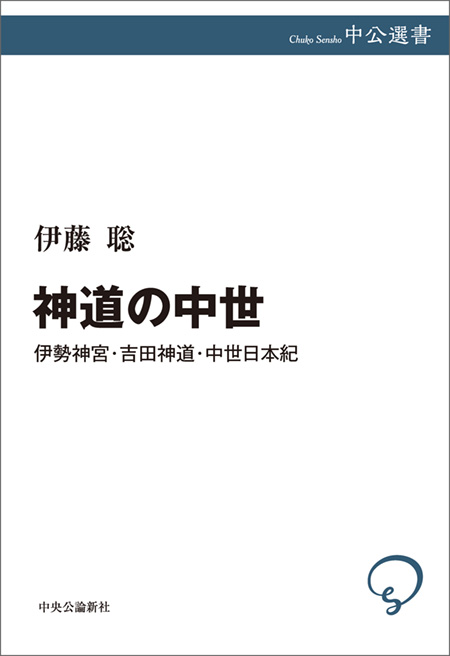
神道の中世
伊勢神宮・吉田神道・中世日本紀
伊藤聡 著
神道という言葉が信仰・宗教を指すようになるのは中世であり、仏教の一派ではない独立した神道流派は応仁期の吉田神道に始まる。神仏習合や密教、当時渡来した禅思想を基に続々と神道書が編まれ、神と仏を巡る多様な解釈が生み出された。『古今和歌集』注釈や能などの文芸世界とも相互作用を起こし、神道は豊穣な中世文化の一翼を担っていく。成立時から融通無碍に変化し続けた神道の本質とは何か。最新の研究からその姿に迫る。
2020/03/13 刊行
-
電子書籍
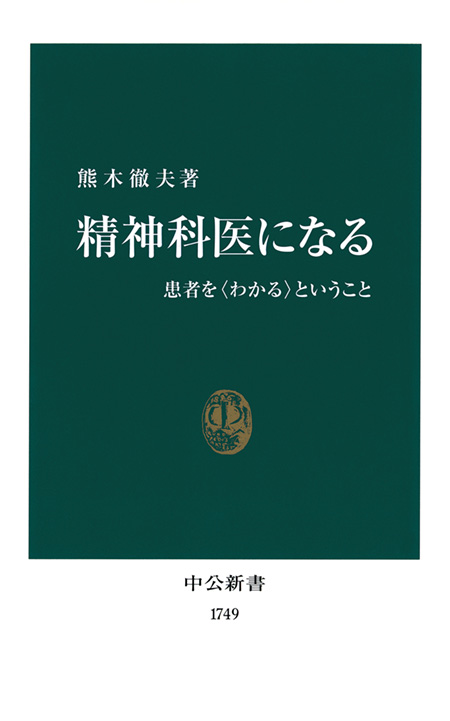
精神科医になる
患者を〈わかる〉ということ
熊木徹夫 著
精神科医は患者が病気であることを本当に証明できるのか。病気か〈甘え〉かをどこで見極めるのか。精神科医療において一人の患者にカウンセリングと薬を処方しての治療が同時に行なわれるのはなぜか。本書は精神科に勤務する著者が、臨床の現場で行き当たった疑問に一つ一つ立ち止まり、本当の「精神科医」になるために重ねた思索の結晶である。現代の精神科医療が抱える問題を掘り起こし、対人関係の原点を見つめる。
2020/03/13 刊行
-
電子書籍
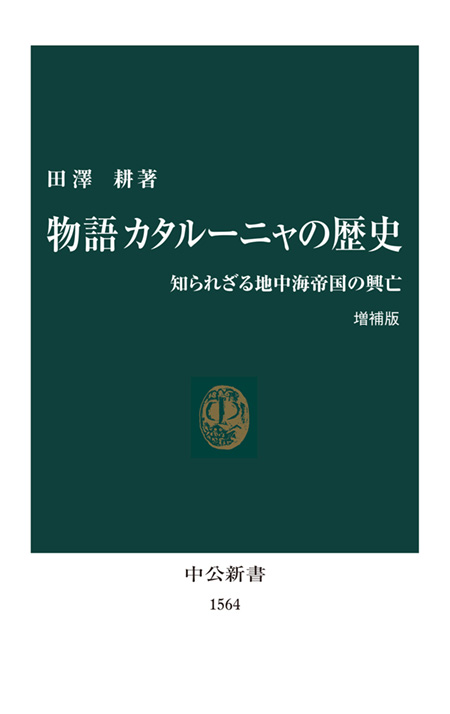
物語 カタルーニャの歴史 増補版
知られざる地中海帝国の興亡
田澤耕 著
バルセロナを中心にスペイン随一の繁栄を誇るカタルーニャ。かつてイタリアや遠くギリシャまで地中海全域を支配した大帝国だった。建国の父・ギフレ毛むくじゃら伯、黄金時代のジャウマ征服王や、騎士・錬金術師・怪僧らが地中海狭しと活躍する栄光の中世から、長い衰退期と混乱を経ながらも再生への努力を続ける現代へ。20世紀初頭のバルセロナの繁栄、スペイン内戦、21世紀の独立運動までを増補した決定版!
2020/03/13 刊行
-
電子書籍
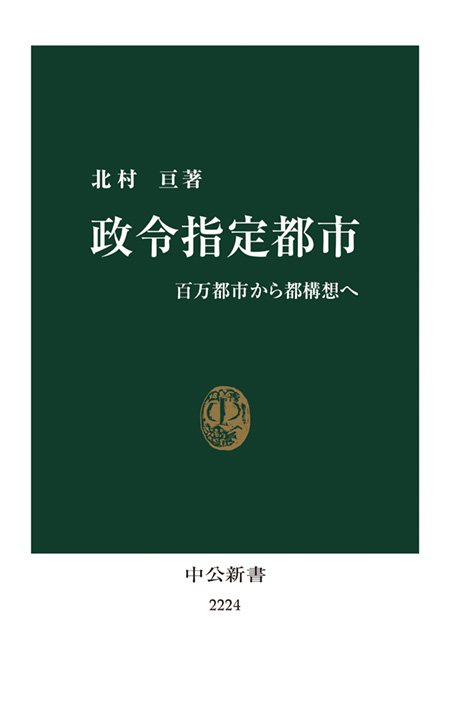
政令指定都市
百万都市から都構想へ
北村亘 著
かつて政令指定都市といえば、横浜や京都など日本を代表する「華やかな百万都市」を意味した。しかし市町村合併推進のため、従来のイメージからほど遠い都市が次々移行した結果、その数は二〇に達した。一方、近年の経済的停滞により税収は激減し、老朽化した施設や生活保護への対応が重荷となっている。「大阪都構想」などの改革で大都市は甦るのか――。歴史や統計、インタビューから、日本の大都市統治を問い直す。
2020/03/13 刊行
-
電子書籍
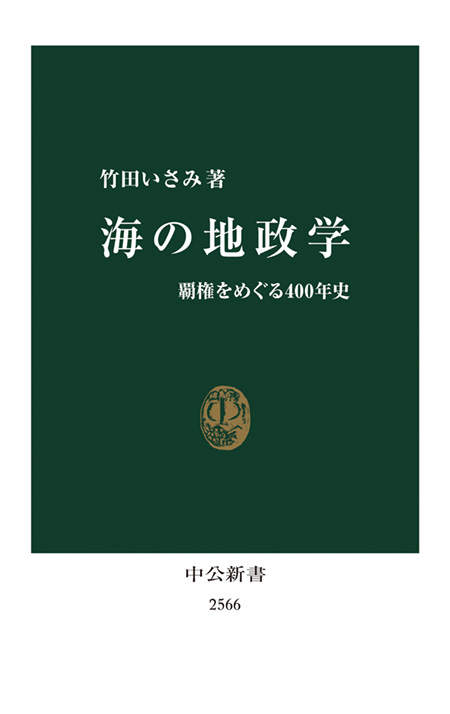
海の地政学
覇権をめぐる400年史
竹田いさみ 著
地球の面積の7割以上を占める海。大航海時代以来、その覇権をめぐって、多くの国々が鎬を削ってきた。スペイン、オランダ、イギリス、二度の大戦を経て頂点に君臨するアメリカ。そして国際ルールへ挑戦する中国……。本書は、航路や資源、国際的な法制度など多様な論点から、400年に及ぶ海をめぐる激動の歴史を描き出す。各国の思惑が交錯し、形作られてきた海洋秩序を前にして、海に囲まれた日本はどう向き合うべきか。
2020/03/13 刊行
-
電子書籍
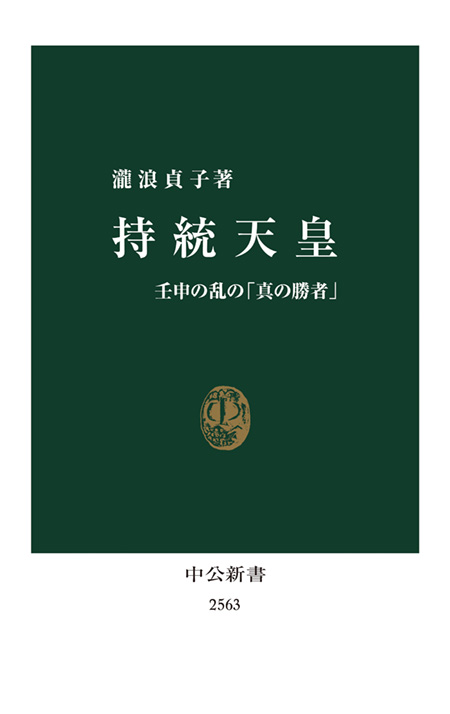
持統天皇
壬申の乱の「真の勝者」
瀧浪貞子 著
後の天智天皇の子として大化改新の年に誕生した少女は、五歳のときに祖父が自害し、心痛の余り母が没するという悲劇を体験する。十三歳で叔父の大海人皇子(後の天武天皇)と結婚。有間皇子の謀反や白村江の戦いの後、二十七歳のとき、古代最大の争乱である壬申の乱を夫と共に起こし、弟・大友皇子に勝利する。その後は中央集権化に邁進し、兄弟継承だった皇位を父子継承に転換させた。古代国家を形作った女帝の実像とは。
2020/03/13 刊行







