ホーム > 検索結果
発行された時期:1973年1月からを含む書籍一覧
全10813件中 3390~3405件表示
-
中公新書ラクレ
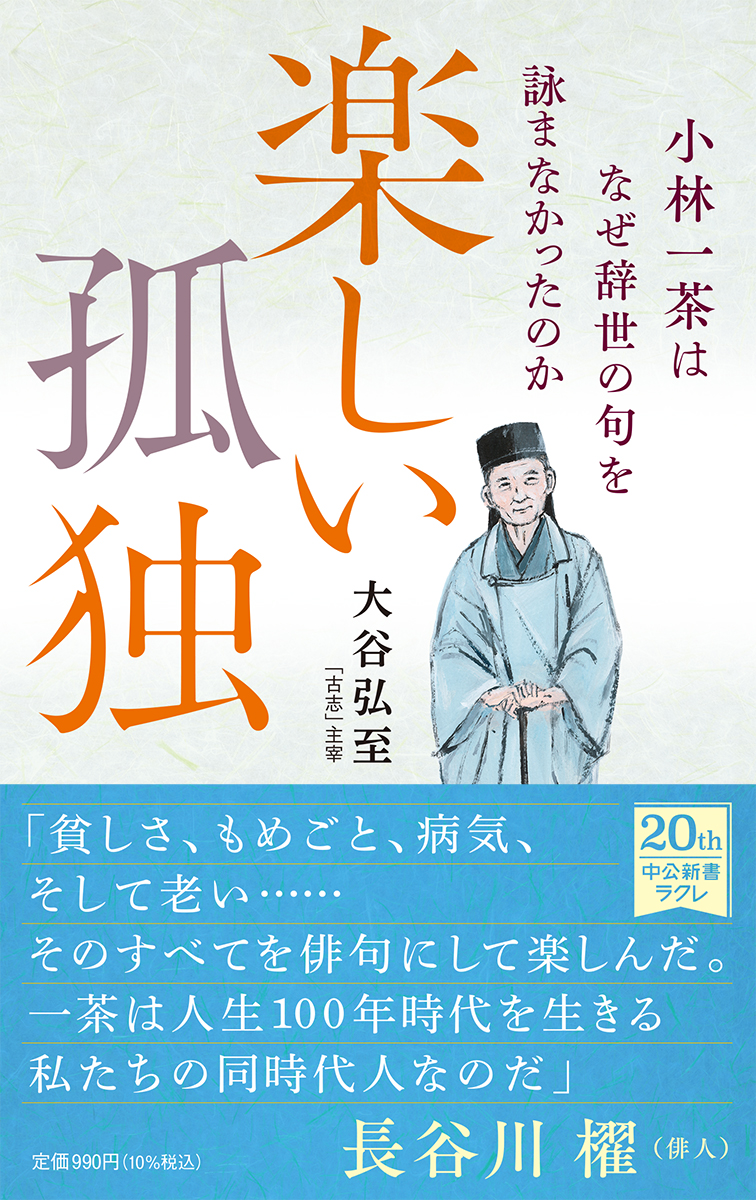
楽しい孤独 小林一茶はなぜ辞世の句を詠まなかったのか
大谷弘至 著
老(おい)が身の 値(ね)ぶみをさるるけさの春 一茶「値踏みをする」は「値段を見積もる」という意味です。老人である一茶に対して、世間の目はあたかも商品の値段を付けるかのようであるというのです。一人住まいの貧しい老人である自分は価値のない存在としてみられている……一茶は、そんな世間の冷酷な視線ですら面白がり俳句にしてしまいます。いったいどうやったら、そんなことができるのでしょうか。 本書は、一茶の生涯をたどり、彼が遺した俳句を味わいながら、つらいことばかりが多い人生と向き合い、世間という荒波の中でどのように暮らしていけばよいのか、生きるヒントを探る旅のガイドブックのようなものなのかもしれません。
2021/11/09 刊行
-
中公新書ラクレ
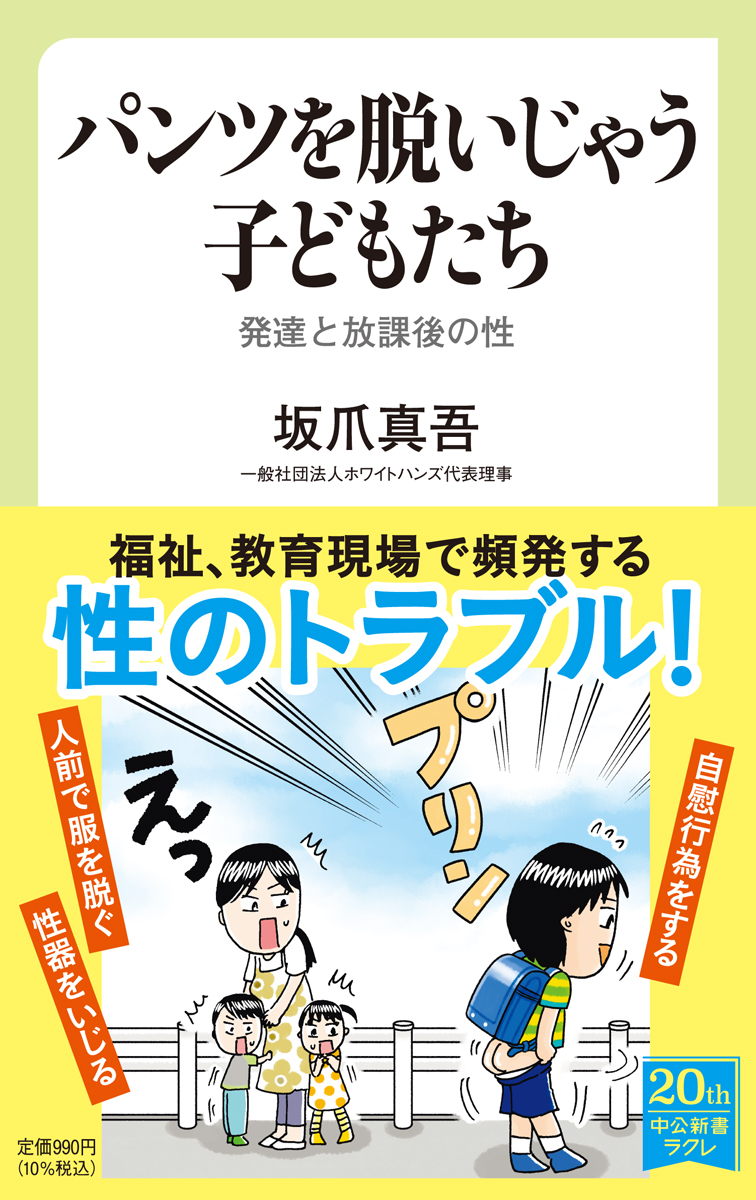
パンツを脱いじゃう子どもたち
発達と放課後の性
坂爪真吾 著
人前で服を脱ぐ、性器をいじる、自慰行為をする――。障害のある子どもや発達に特性のある子どもが通う「放課後等デイサービス」。その現場で問題になっているのが、子どもたちの性に関するトラブルだ。長年障害者の性問題に取り組んできた著者が、放課後等デイサービスの現場の声を集め、障害のある子どもたち、そして私たちが自分自身や他人の性とうまく向き合っていくための方策を探る。
2021/11/09 刊行
-
中公選書
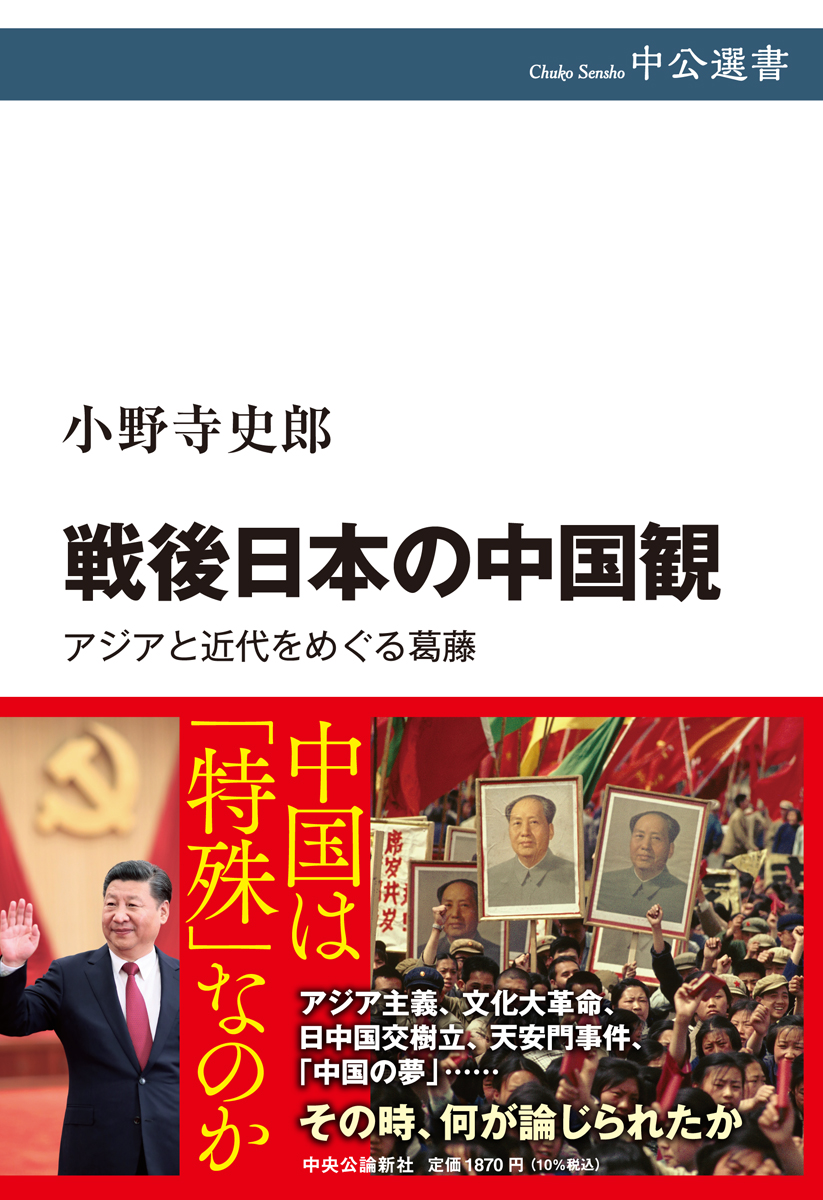
戦後日本の中国観
アジアと近代をめぐる葛藤
小野寺史郎 著
巨大な隣国、中国。その政策、対外行動、国内で起こる事件は時に理解しがたいものと映る。私たちは、この隣国をどのように捉えるべきか。本書は戦後の中国近現代史研究の歴史をひもとき、日本の中国観に迫る。敗戦や文化大革命は、日本の中国研究にどのような影響をもたらしたか。共産党政権の成立、日中国交樹立、改革開放、天安門事件、反日デモ、「一帯一路」などをどう論じたのか。膨張を続ける中国を、冷静に見つめるために。
2021/11/09 刊行
-
中公選書
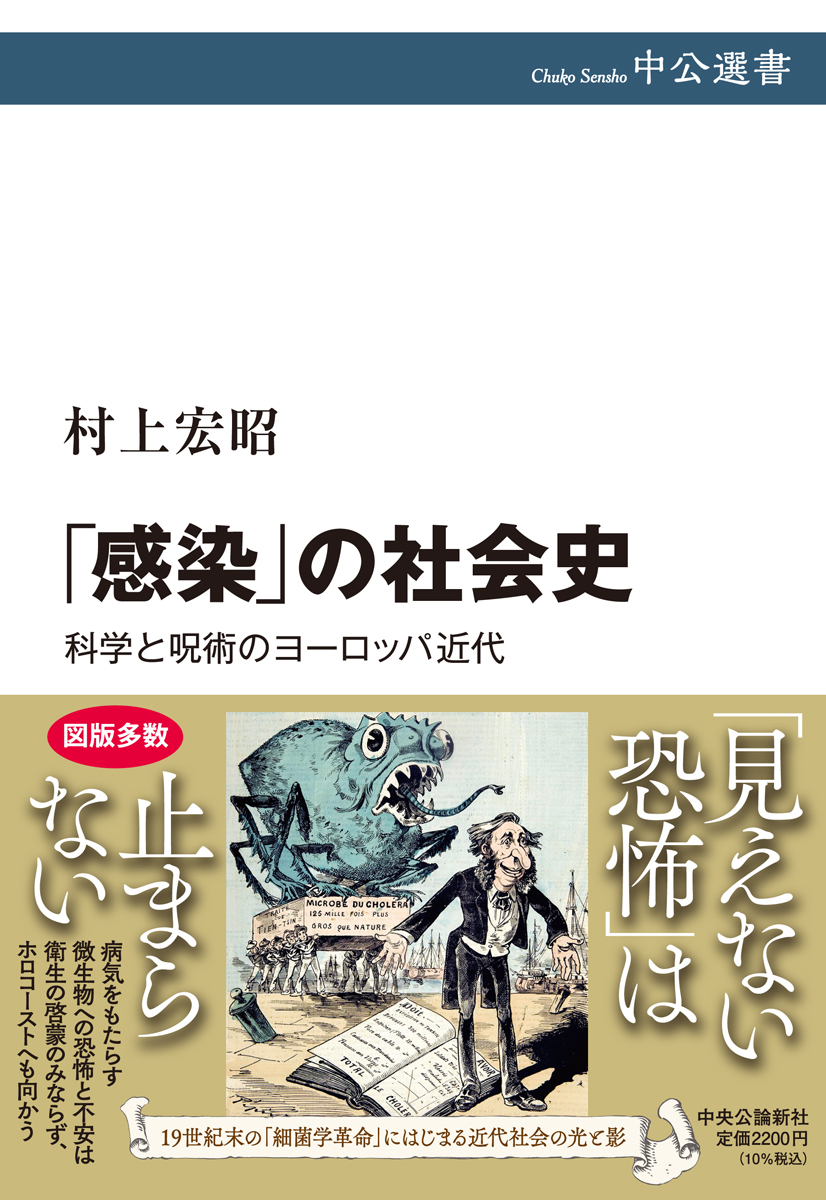
「感染」の社会史
科学と呪術のヨーロッパ近代
村上宏昭 著
2021/11/09 刊行
-
電子書籍
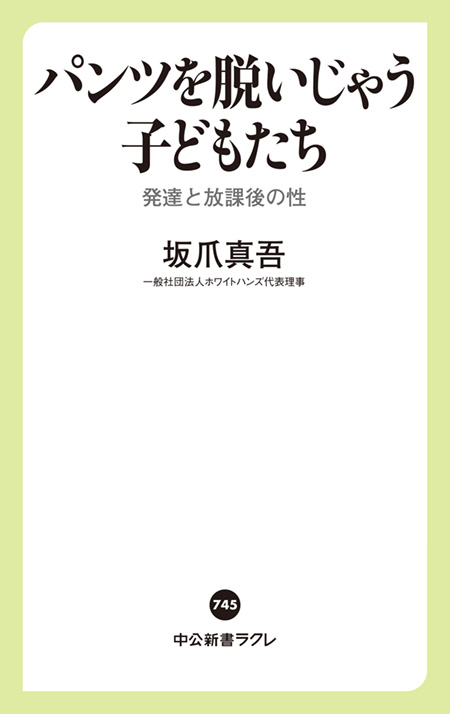
パンツを脱いじゃう子どもたち
発達と放課後の性
坂爪真吾 著
「性の公共」をテーマとする著者の、書き下ろし新刊。新型コロナの影響で学童保育に注目が集まる中、この数年間で、飛躍的に利用者数を伸ばしたサービスがある。それは「放課後等デイサービス」である。放課後等デイサービスとは、障害のある子どもや発達に特性のある子どものための福祉サービスで、現在の利用者数は20万人を超えている。その放課後等デイサービスの現場で問題になっているのが、子どもたちの性に関するトラブルだ。特に多いのが「人前で服を脱いでしまう」という行為。ほかにも、人前で性器をいじる、自慰行為をしてしまうなど、様々な問題が起こっている。本書は、放課後等デイサービスの現場で起こっている性に関する問題を分析した上で、障害のある子どもたち、そして私たちが自分自身や他人の性とうまく向き合っていくための方策を探る。
2021/11/09 刊行
-
電子書籍
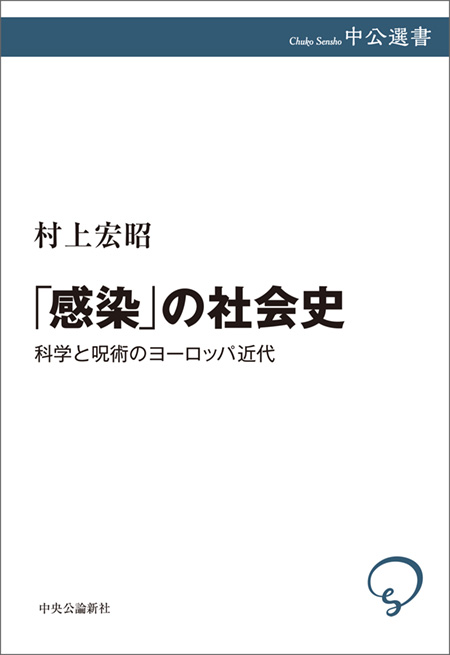
「感染」の社会史
科学と呪術のヨーロッパ近代
村上宏昭 著
「見えない恐怖」は止まらない――。コレラなどの疫病が「感染」するものと認識されてから、たかだか一五〇年ほどにすぎない。だが病気をもたらす不可視の微生物への恐怖と不安は、呪術的思考と絡み合いながら、人と人とのつながりや社会のあり方を一変させた。それは効果的な感染予防の福音を伝えた一方で、ジェノサイドを招く火種ともなった。本書は十九世紀末の「細菌学革命」にまつわる光と影、その後のヨーロッパ世界の激動を、臨場感溢れる多数の図版と共に追う。
2021/11/09 刊行
-
電子書籍
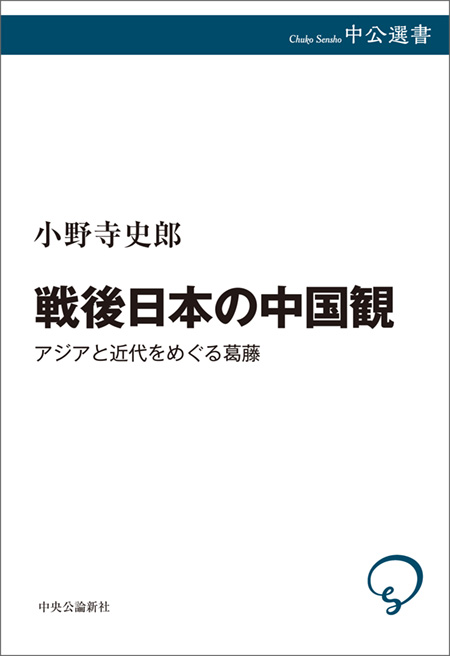
戦後日本の中国観
アジアと近代をめぐる葛藤
小野寺史郎 著
巨大な隣国、中国。その政策、対外行動、国内で起こる事件は時に理解しがたいものと映る。私たちは、この隣国をどのように捉えるべきか。本書は戦後の中国近現代史研究の歴史をひもとき、日本の中国観に迫る。敗戦や文化大革命は、日本の中国研究にどのような影響をもたらしたか。共産党政権の成立、日中国交樹立、改革開放、天安門事件、反日デモ、「一帯一路」などをどう論じたのか。膨張を続ける中国を、冷静に見つめるために。
2021/11/09 刊行
-
電子書籍
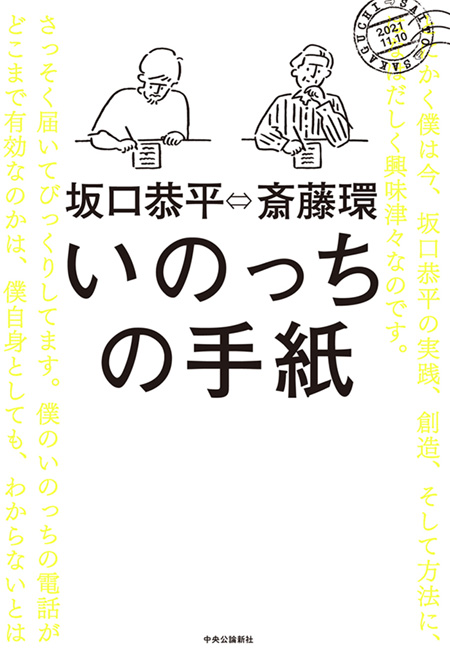
いのっちの手紙
斎藤環/坂口恭平 著
《目次》はじめに 斎藤環Ⅰ 傾聴/境界【第一信】斎藤環→坂口恭平様 恭平さんの方法論は、「とんでもない」【第二信】坂口恭平→斎藤環様 死にたい人に死なない方法を伝えているわけではないんですⅡ 治療/フィールドワーク【第三信】斎藤環→坂口恭平様 どのくらい「技法」として意識していますか?【第四信】坂口恭平→斎藤環様 苦しさや悩みには、一〇種類くらいのパターンしかありません 46Ⅲ 脆弱さ/柔らかさ【第五信】斎藤環→坂口恭平様「活動処方療法」の効果を共同で研究してみたい【第六信】坂口恭平→斎藤環様 今までの人生の中で一番マシだったことを聞いてみますⅣ 自己愛/承認欲求【第七信】斎藤環→坂口恭平様 相談者とともに欲望を作り出しているようにも見えます【第八信】坂口恭平→斎藤環様 自分の欲望ってのが、実は一番、どこにもない答えなんですよねⅤ 流れ/意欲【第九信】斎藤環→坂口恭平様「所有欲」について、どう考えていますか?【第十信】坂口恭平→斎藤環様 創造するという行為が、至上の愛よりも強い喜びですⅥ 悟り/変化【第十一信】斎藤環→坂口恭平様 恭平さんの境地は、幸福であり究極の自由であるように思います【第十二信】坂口恭平→斎藤環様 人々もまた幸福のことを知っていると僕は確かに感じていますおわりに 坂口恭平
2021/11/09 刊行
-
電子書籍
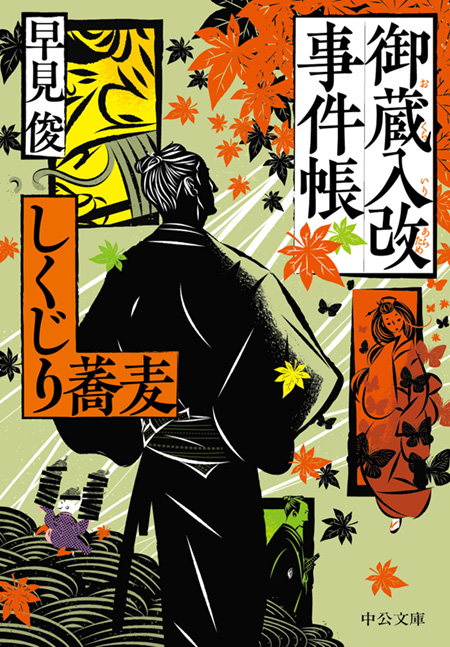
御蔵入改事件帳
しくじり蕎麦
早見俊 著
町奉行所や火付盗賊改が取り上げない訴えや未解決事件を探索する御蔵入改。元長崎奉行でサーベルの遣い手・荻生但馬をはじめ、必殺剣を持つ一徹者の元定町廻り同心、六尺棒を振り回す将棋好きの元臨時廻り同心、長い薬指でどんな財布でもすり取る洗い髪が艶やかな女すり、桃色地の小袖と真っ赤な股引姿で愛想を振りまく禿頭の幇間という、個性豊かな五人組だ。南町奉行所元臨時廻り同心の大門武蔵は、御蔵入改の同僚である幇間・喜多八に唆され、蕎麦の大食い大会に出場することになった。大会は薬種問屋が軒を連ねる日本橋本町の蕎麦屋で開催され、賞金は十両。蕎麦っ食いとして有名な「蕎麦圭」こと薬売りの圭太郎、薬種問屋太田屋の放蕩息子・伊之助、薬種問屋大塚屋の看板娘・お千津らと対決することになった武蔵だったが……(「しくじり蕎麦」)。表題作を含む痛快&人情時代小説全四篇。文庫書き下ろし【目次】第一話 しくじり蕎麦第二話 しくじり幇間第三話 しくじり忠臣蔵第四話 しくじり同心
2021/10/29 刊行
-
電子書籍
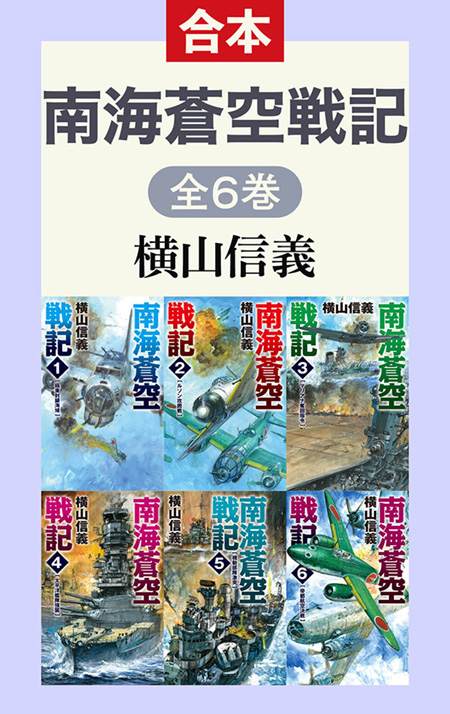
南海蒼空戦記(全6巻合本)
横山信義 著
〈ありえたかもしれないもう一つの世界大戦――人気シリーズ一気読み!〉欧州で始まった第二次大戦より4年。中立を保つ日本はドイツから流出したクルト・タンク、エルンスト・ハインケルらの頭脳を得て、軍用機の開発に注力していた。さらに、広島を襲った地震により海軍が建造中だった「大和」の廃艦が決定。連合艦隊はこれを機に航空主兵に舵を切ることに。一方、陸軍は、大戦の混乱に乗じて蘭印の保護国化に成功した。日本の領土的野心を懸念する米軍の挑発行為が激化し、南洋の緊張が高まる中、遂にB25の奇襲で開戦の火蓋が切られる。日本軍は零戦を中心とした戦闘機でこれを迎え撃つ!
2021/10/29 刊行
-
電子書籍
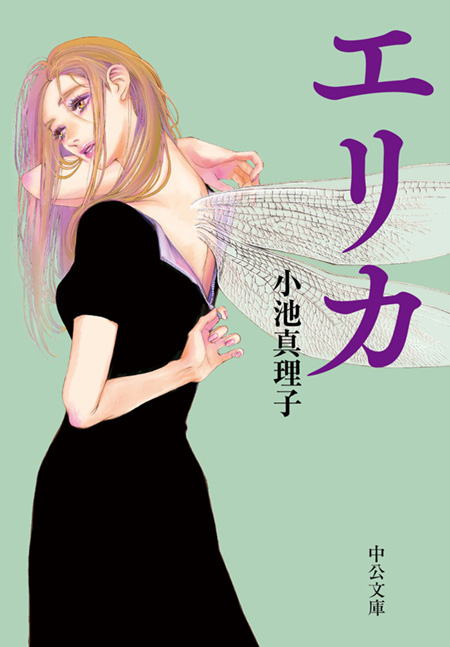
エリカ
小池真理子 著
急逝した親友の告別式の夜、その不倫相手と二人で飲んだのをきっかけに、エリカはいつしか彼との恋愛にのめり込んでいく。逢瀬を重ねていった先には何が……。高ぶるほど空虚、充たされるほど孤独。現代の愛の不毛に迫る長篇。
2021/10/29 刊行
-
電子書籍
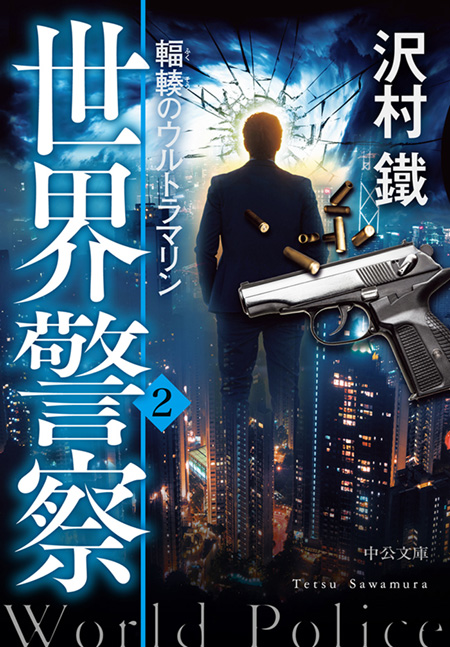
世界警察2
輻輳のウルトラマリン
沢村鐵 著
凶悪犯罪を防ぐため、日本警察は世界へ。警察小説史上最大スケール。圧巻のシリーズ第二弾。日本を襲った軍事蜂起を鎮圧した警視庁。現場から逃亡したテロリストが謎の地下兵器産業の一員であることを知った刑事たちは足取りを追って世界へ飛ぶ。一方、国連事務総長のソフィアは世界各地の軍事指導者の横暴に頭を悩ませていた。囚われた仲間、世界中で続発するテロ行為。全ての鍵は「平成」に起きた事件に隠されていた。
2021/10/29 刊行
-
電子書籍
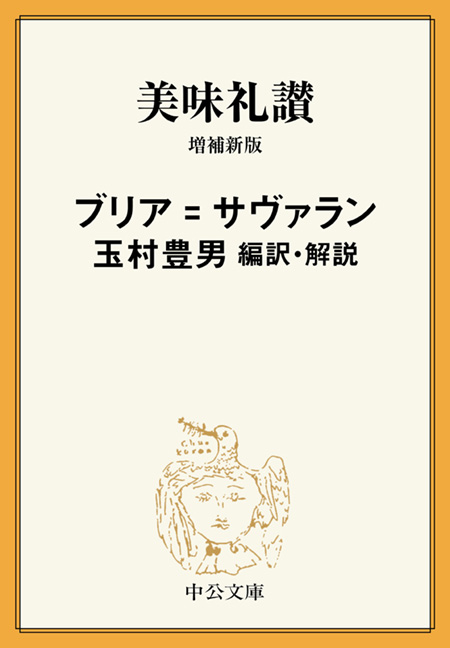
美味礼讃
増補新版
ブリア=サヴァラン 著/玉村豊男 編訳・解説
新しい料理の発見は人類の幸福にとって天体の発見以上のものである――。1825年に刊行された『味覚の生理学』は、日本では『美味礼讃』の訳書名で知られてきた。美食家としての情熱と蘊蓄を科学的知見をもとに掘り下げ、食べることが人間と社会にとっていかに重要であるかを説いた美味学の古典。大胆な編集にもとづき、平易な訳文・親しみやすい解説を施した新版。
2021/10/29 刊行
-
電子書籍
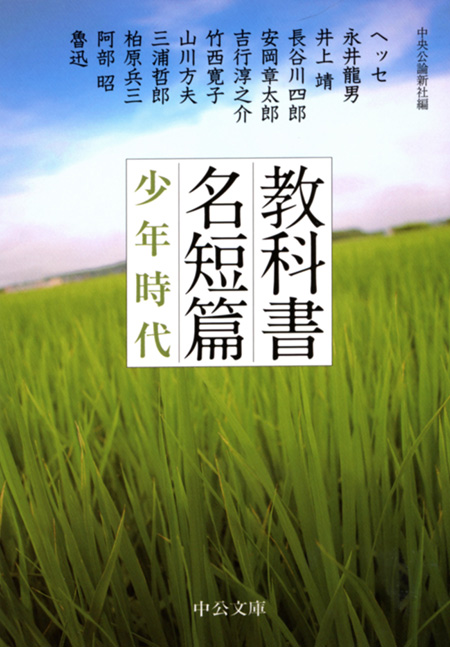
教科書名短篇
少年時代
中央公論新社 編
ヘッセ、永井龍男から山川方夫、三浦哲郎まで。少年期の苦く切ない記憶、淡い恋情を描いた佳篇を中学教科書から精選。珠玉の12篇。文庫オリジナル。 【目次】 少年の日の思い出/ヘルマン・ヘッセ(高橋健二訳) 胡桃割り/永井龍男 晩夏/井上靖 子どもたち/長谷川四郎 サアカスの馬/安岡章太郎 童謡/吉行淳之介 神馬/竹西寛子 夏の葬列/山川方夫 盆土産/三浦哲郎 幼年時代/柏原兵三 あこがれ/阿部昭 故郷/魯迅(竹内好訳)
2021/10/29 刊行
-
電子書籍
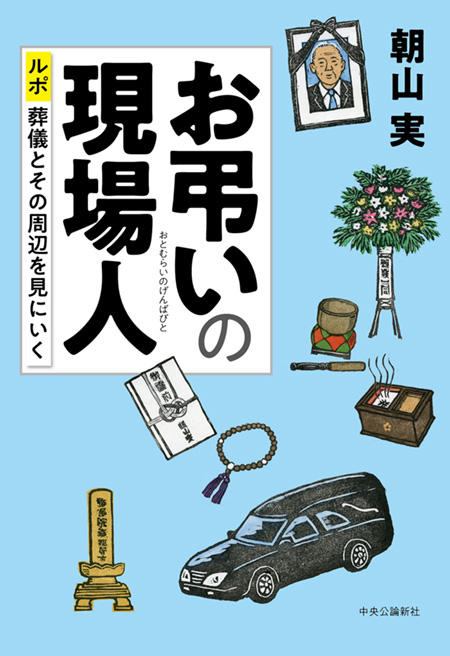
お弔いの現場人
ルポ 葬儀とその周辺を見にいく
朝山実 著
前作『父の戒名をつけてみました』で、父の葬儀、遺産「争」続、さらには現代の「弔い」についての考察を執筆した著者。あれから5年。現在は、父から相続した一軒家を、「葬儀会館」として貸し出している。貸している相手は、父の葬儀で出会った、霊柩車の運転手――。元・霊柩車の運転手が葬儀会社を起業、その人柄と経営姿勢に共感し、ビジネスパートナーとなったのだ。派遣僧侶、自宅葬、遺品整理、墓じまい、身よりのない人のお葬式……。変わりゆく葬儀とその周辺の今を、業界の最先端をゆく人びとへの取材・インタビューを軸に描き出す。
2021/10/29 刊行







