- 2025 07/23
- まえがき公開
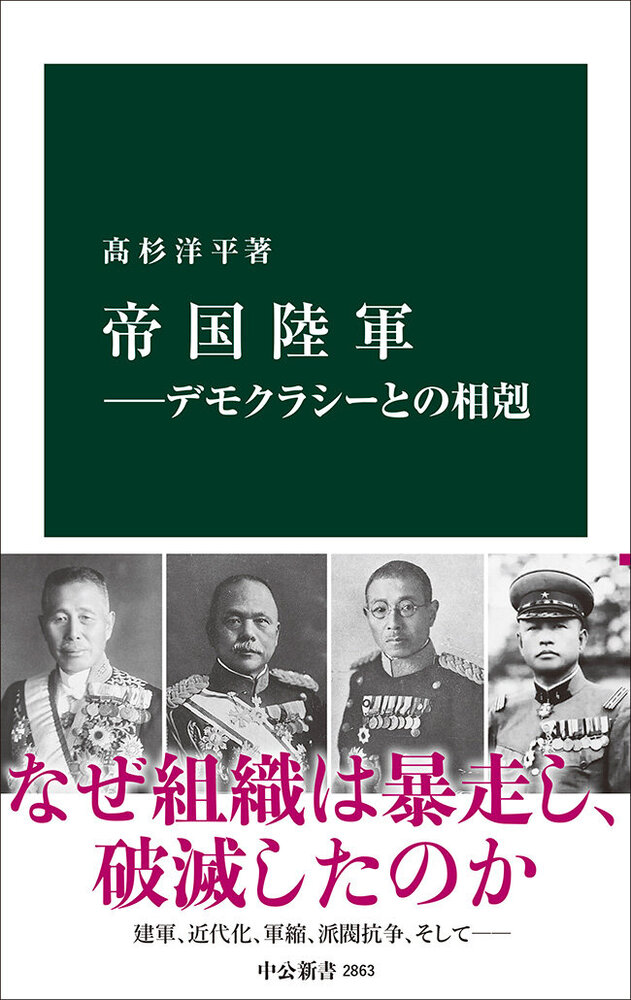
陰湿、粗暴、狂信的……と語られてきた大日本帝国陸軍。しかし実際には、建軍当初から、国際的視野を持つ開明的な将校などは多く存在していた。1945年の解体までの七十余年で、何が変化したのか――。本書は、日露戦争勝利の栄光、大正デモクラシーと軍縮、激しい派閥抗争、急速な政治化の果ての破滅まで、軍と社会が影響を与え合った軌跡を描く。陸軍という組織を通し、日本の政軍関係を照らす、もう一つの近現代史。 『帝国陸軍―デモクラシーとの相剋』の 「はしがき」を公開します。
大日本帝国陸軍と聞いて、我々は何を想像するだろうか。
科学と人命を軽視し、精神力と銃剣突撃に固執した蒙昧な軍隊。「皇国史観」で神懸かりとなった狂信的将校。アジア侵略と対米戦争に狂奔した軍事指導者。一切の自由が許されない陰湿な内務班(一般兵士の生活班)。古参兵からの理不尽な暴力。散々にいびられ殴られた初年兵は、南方のジャングルで飢えとマラリアに苦しみ、最後は軍事的合理性を欠いた玉砕突撃で全滅する。こうした軍隊生活が存在したことは厳然たる事実だが、しかし、次のような証言もある。
京都帝国大学を卒業した政治記者で、のちに立命館大学教授となる前芝確三の回想である。
前芝が二等兵として入営(徴兵されて軍隊に入隊すること)した昭和改元(1926年)前後の陸軍(大阪歩兵第八連隊)は、ひどくのんびりしていた。暇を持て余した前芝が、フランス語の独習をしようと参考書の持ち込み許可を願い出ると、士官学校でフランス語を専修した中隊長は、「わからんことがあったら聞きにこい」と大いに激励した。中隊長と仲良くなった前芝は、仏語参考書だけではなく、社会思想の書物も持ち込んで大いに勉強した。前芝の所属した連隊ではスポーツも奨励していた。フランス帰りの連隊長(香月清司。のち中将)自ら、兵隊に野球チームやラグビーチームを作らせていた。チームの中核となったのは、旧制中学や大学で運動部に所属していたインテリ・スポーツマンである。前芝も、野球とラグビー両チームに所属して民間チームとの対外試合に励んだ。八連隊チームは強豪として鳴らした。
新兵の思想問題に対する態度も柔和なものであった。当時は左翼思想、進歩思想の全盛期であり、兵隊にも左翼運動に関わりのある人物がたくさん入営してきた。そうした新兵の一人が、軍人の宣誓(服従義務の宣誓)を拒むと、ある上官は、なんとか穏便に翻意させようと1週間くらい説得に努め、ついには兵隊を説得するため、まずは自分自身が兵隊の思想を理解しなければならないと、マルクス主義の勉強を始める者もいたという(前芝『体験的昭和史』)。
これらは少し特殊な例なのかもしれないが、しかし、帝国陸軍のある一面での実像なのは間違いない。太平洋戦争期の陸軍最晩年の記憶に上書きされて忘れ去られがちだが、明治の末から昭和の初めにかけて「大正デモクラシー」と称された時代に、陸軍がこのような姿を見せた瞬間もあったのである。
そもそも、陸軍士官学校は旧制第一高等学校と並び称される超難関校の一つであり、入校してくる候補生は各地の旧制中学でトップクラスの成績を誇る秀才だった。もちろん、士官学校での普通学教育は旧制高校や帝国大学には劣るものであったが、帝大出のインテリ兵にフランス語を教えることができるほどの頭脳の持ち主も確かに存在したのである。
そうした士官学校出の将校のなかから、さらに進んで高級将校になろうとすれば、普通は陸軍大学校(陸大)も卒業せねばならなかった。陸大への入学試験も難関であり、進学率は士官学校卒業者の10%程度である。
中等教育機関(旧制中学、高等女学校、実業校など)への進学率が20%前後、高等教育機関(旧制高校、専門学校、大学など)への進学率が10%前後の時代にあって(大学進学率に限れば1%程度に過ぎない)、彼らは間違いなく社会のスーパー・エリートであった。そして陸大を優秀な成績で卒業した者は数年間の海外留学を経験し、その後も折に触れて海外勤務を命じられた。日本人の大半にとって、海外旅行や外国人との交際など夢物語であった時代である。
総じて、彼らは広範な知識と緻密な思考能力を持った国際人であったと考えてよい。こうした彼らの知的レベル、国際経験を考慮するならば、前芝が出会った理知的で開明的な将校の存在も、違和感なく肯首しうるだろう。
では、なぜ帝国陸軍は変わってしまったのだろうか。最も単純でかつ説得力を持つ回答は、太平洋戦争が「負け戦だったから」というものであろう。人であれ組織であれ、落ち目になれば非合理と内輪揉めの隘路に迷い込むのは普通の現象だろう。「窮すれば濫す」である。
しかし、この回答は太平洋戦争の開戦以降に起きた変化の説明には便利だが、それ以前から起きていた変化を説明することはできない。たとえば、二・二六事件に代表される軍人によるテロ事件の頻発や、非論理的な国体明徴運動の興隆のような変化は、どう説明するのだろうか。満洲事変や日中戦争のような対外武力進出にいたる変化は、どう説明するのだろうか。対米開戦という無謀な国策決定にいたる変化は、どう説明するのだろうか。
それらは負け戦の結果ではもちろんないし、むしろそれらの変化が負け戦を誘引したのであろう。では、一体なぜ、前芝の出会った魅力的な大正デモクラシーの陸軍将校たちは消えてしまったのだろうか。
そもそも、もう少し突き詰めて考えると、帝国陸軍は大正デモクラシーを経験したのにもかかわらず変わってしまい、ついには戦争を選択したのだろうか。それとも大正デモクラシーを経験したからこそ変化し、最終的に戦争を選択したのだろうか。どちらにせよ興味深い現象だろうが、もし後者だとすれば意味深長だろう。なぜなら「民主主義」と「平和主義」が軍部の「暴走」を生んだことになるからである。
本書の構成を簡単に紹介しておこう。
まず第1章では、日露戦争に勝利し、栄光の頂点に上り詰めた陸軍が直面した新たな「戦い」が描かれる。それは急速に台頭してきた政党勢力との政治対立であった。軍拡予算をめぐって、陸軍と政党内閣は政治闘争を繰り広げる。この戦いは、陸軍にとって、ある意味では日露戦争以上に困難なものとなっていく。
第2章では、第一次世界大戦を契機に生じた軍事技術や社会風潮の急激な変化が描かれる。大戦は日本陸軍の装備、戦術を一夜にして陳腐化し、近代化は急務の課題となった。他方で、社会では大正デモクラシーと称される風潮が興隆しつつあった。特に、大戦を契機として勃興した平和主義やアンチ・ミリタリズムの世論は、陸軍への強烈な逆風として吹きつける。
第3章では、大正デモクラシーのなかで興隆した軍縮要求に対して、陸軍が如何に対応したかが描かれる。宇垣一成というカリスマの下、陸軍は政党や世論との対立ではなく、自己変革を選択し、「政軍協調路線」という新たな政軍関係を生み出す。そして軍縮と近代化を両立させた「宇垣軍縮」を実行する。
第4章では、政軍協調路線の行き詰まりと国際環境の変動によって、陸軍内に既存の政軍関係への不満と社会改革への欲求が興隆する過程が描かれる。大正デモクラシーの爛熟のなかで陸軍は急速に変質していく。「昭和陸軍」は大正デモクラシーの「落とし子」として誕生するのである。
第5章では、軍事と政治の抜本的改革を目指す陸軍革新運動の実態と、その帰結である満洲事変が描かれる。宇垣軍政を否定する革新派軍人たちは結集し、軍隊内のヘゲモニー(政治的主導権)を掌握すると、満洲事変を決行する。満洲事変は甘美な成功体験として、陸軍軍人の記憶に刻み込まれることになる。
第6章では、陸軍革新運動が熾烈な派閥抗争へと発展する過程が描かれる。革新派軍人たちは「統制派」と「皇道派」に分裂し、血で血を洗う苛烈な闘争を展開する。激しい派閥対立はなぜ生まれ、陸軍に何をもたらすのだろうか。
第7章では、二・二六事件後に加速する陸軍による政治干渉が描かれる。広田弘毅(こうき)内閣の組閣に陸軍は露骨に干渉し、部内ヘゲモニーを掌握した石原莞爾は、世界最終戦争を見据えて国家改造を試みる。クーデターという不祥事にもかかわらず、なぜ露骨な政治干渉は止まらなかったのだろうか。そして陸軍は政治を支配することに成功したのだろうか。
第8章では、日中戦争の勃発と太平洋戦争への発展が描かれる。石原に代わる新たな実力者となった武藤章は、日中戦争拡大を主導し、後には、その終結と対米戦回避に奔走する。
なぜ陸軍は泥沼化する日中戦争に突き進んだのだろうか。そして、なぜ対米戦争へと続く歴史の隘路にはまってしまったのだろうか。
(まえがき、著者略歴は『帝国陸軍―デモクラシーとの相剋』初版刊行時のものです)
