ホーム > 検索結果
発行された時期:1973年1月からを含む書籍一覧
全10813件中 9660~9675件表示
-
中公文庫
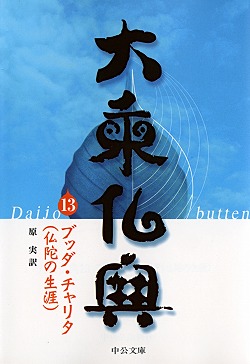
大乗仏典13
ブッダ・チャリタ(仏陀の生涯)
原実 訳
世の無常を悟った王子シッダルタを出家させまいと誘惑する女性の大胆かつ繊細な描写を交え、人間仏陀の生涯を佳麗に描きあげた仏伝中白眉の詩文学。
2004/08/23 刊行
-
中公文庫
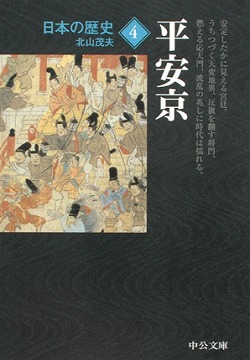
日本の歴史4
平安京
北山茂夫 著
坂上田村麻呂の蝦夷平定後、平安京の建設が始まる。律令国家没落の傾斜は深まり、将門の乱をへて摂関藤原氏の全盛時代へと移る経過をさぐる。〈解説〉佐藤宗諄
2004/08/23 刊行
-
中公文庫
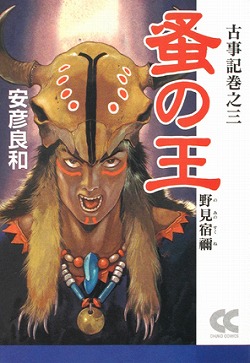
古事記巻之三
蚤の王
野見宿禰
安彦良和 著
四世紀初め、第十一代垂仁天皇の治世下、土師氏の開祖・野見宿禰の一代記。宿禰は殉死をやめ、土人形(埴輪)の埋葬をもって、殉死にかえることを提案した。
2004/08/23 刊行
-
電子書籍
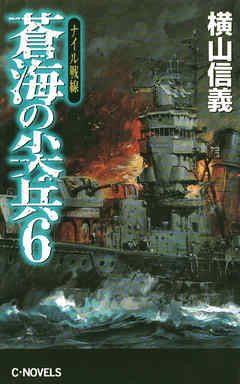
蒼海の尖兵6
ナイル戦線
横山信義 著
仏戦艦によるスエズ閉塞を許した日米連合軍。地中海目前にして主力艦隊は足踏みを余儀なくされた。この現状を打破すべく日米精鋭で編成された「挺身隊」が送り込まれたが……!?
2004/08/13 刊行
-
電子書籍
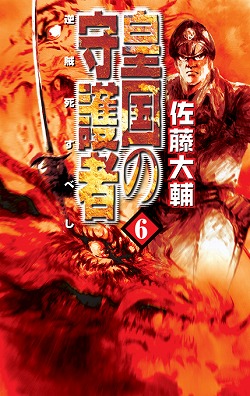
皇国の守護者6
逆賊死すべし
佐藤大輔 著
予期せぬ帝国軍の冬季攻勢に崩壊寸前の虎城戦線。居合わせた新城は防戦に奮闘する。だが一少佐の巨大すぎる救国の戦果が猜疑と妬をよび、 皇都では新城抹殺のクーデタ計画が……!!
2004/08/13 刊行
-
中公クラシックス
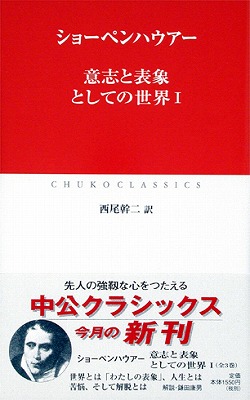
意志と表象としての世界Ⅰ
ショーペンハウアー 著 西尾幹二 訳 鎌田康男 解説
ショーペンハウアーの魅力は、ドイツ神秘主義と18世紀啓蒙思想という相反する二要素を一身に合流させていたその矛盾と二重性にある。いまその哲学を再評価する時節を迎えつつある。
2004/08/10 刊行
-
中公新書
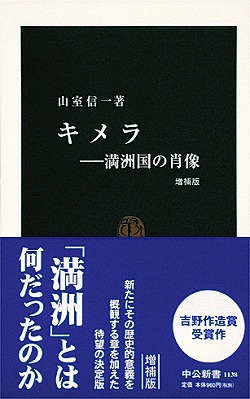
キメラ―満洲国の肖像 増補版
山室信一 著
一九三二年三月、中国東北地方に忽然と出現し、わずか一三年五カ月後に姿を消した国家、満洲国。今日なおその影を色濃く残す満洲国とは何だったのか。本書は建国の背景、統治機構の特色を明らかにし、そこに凝縮して現れた近代日本の国家観、民族観、そしてアジア観を問い直す試みである。新たに満洲・満洲国の前史と戦後に及ぼした影響など、その歴史的意義を想定問答形式によって概観する章を増補した。
2004/07/25 刊行
-
中公新書
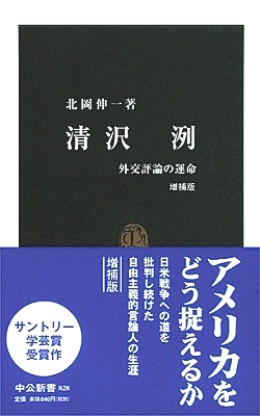
清沢洌 増補版
外交評論の運命
北岡伸一 著
『暗黒日記』の著者として知られる清沢洌は、戦前期における最も優れた自由主義的言論人であり、その外交評論は今日の国際関係を考える上で、なお価値を失っていない。石橋湛山、馬場恒吾ら同時代人のなかでアメリカに対する認識が例外的に鋭くあり得たのはなぜか。一人のアメリカ移民が邦字新聞記者となり、活躍の舞台を日本に移してから、孤独な言論活動の後に死すまでの軌跡を近代日本の動きと重ねて描く唯一の評伝。サントリー学芸賞受賞作。
2004/07/25 刊行
-
中公新書
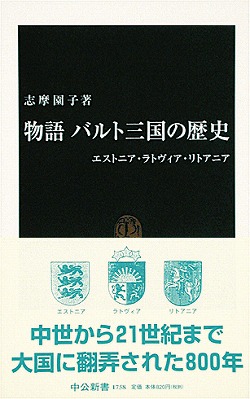
物語 バルト三国の歴史
エストニア・ラトヴィア・リトアニア
志摩園子 著
二〇〇四年五月、エストニア、ラトヴィア、リトアニアは念願だったEUへの加盟を果たした。これまで三つ子のように扱われてきた三国は、なぜ「バルト」と一括されるのか。その答えは、中世から東西南北の交易の十字路として注目されたバルト海東南岸地域でくりひろげられた歴史の中にある。周辺大国ドイツ、ロシアの狭間にあって、それぞれの民族のまとまりを失うことなく、二〇世紀にやっと建国した三国の道のりを辿る。
2004/07/25 刊行
-
中公新書
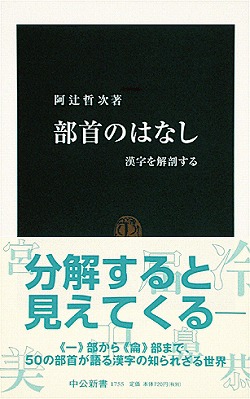
部首のはなし
漢字を解剖する
阿辻哲次 著
なぜ「卍」は《十》部6画なのか?「巨」はなぜ《工》部なのか? なぜ女ヘンがあって男ヘンはないのか……。漢字が誕生して三千年、漢字の字体はさまざまに変化していった。そのなかで、多くの部首が生まれ、消えていった。所属する部首を移動したり、部首が分からなくなってしまったものも多い。漢字を分解してみると、その合理性と矛盾がはじめて見えてくる。50の部首ごとにたどる楽しい漢字エッセイ。
2004/07/25 刊行
-
電子書籍

蒼海の尖兵5
スエズ進攻
横山信義 著
インド洋の事実上の制海空権を握った、日米連合軍の次なる目標はスエズ運河。ここを突破できれば地中海への進攻ルートが確保できる。だが、その前には強大な敵が……!?
2004/07/25 刊行
-
電子書籍
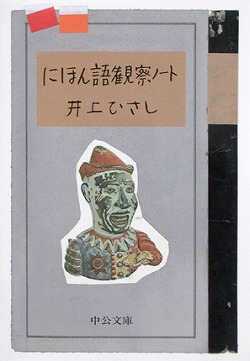
にほん語観察ノート
井上ひさし 著
お役所言葉はなぜ難しい? 必ず笑える駄洒落のコツとは? ふだんの言葉の中にこそ、日本語のひみつは隠れているのです。「言葉の貯金がなにより楽しみ」という筆者のとっておき。持ち出し厳禁、言葉の見本帳。
2004/07/25 刊行
-
電子書籍
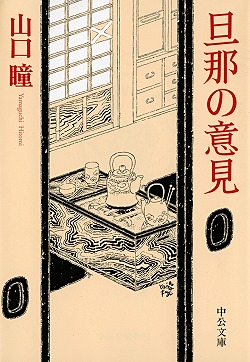
旦那の意見
山口瞳 著
この頃、電車で席を譲らなくても気が咎めなくなった。志ん生晩年のかすれ声に涙を流す。角栄に義憤を感じつつも父の面影を重ねる。――『男性自身』で大好評を博した著者が「最初の随筆集」と断じてはばからぬ珠玉の自選名文集。
2004/07/25 刊行
-
中公文庫
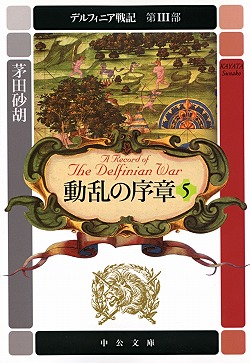
デルフィニア戦記
第Ⅲ部 動乱の序章5
茅田砂胡 著
隣国の版図拡大をおそれる両国王からの暗殺依頼により、コーラル城の喧噪にまぎれ、巧妙に、精緻に張りめぐらされる暗殺の罠。リィに最大の危機が迫る!
2004/07/23 刊行
-
中公文庫
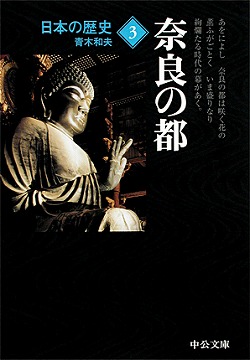
日本の歴史3
奈良の都
青木和夫 著
古代国家の到達した一つの展望台。律令制度はほぼ整い、国富は集中されて華麗な奈良の都が出現する。大仏開眼、古事記が誕生した絢爛たる時代。〈解説〉丸山裕美子
2004/07/23 刊行







