ホーム > 検索結果
発行された時期:1973年1月からを含む書籍一覧
全10812件中 5820~5835件表示
-
中公文庫
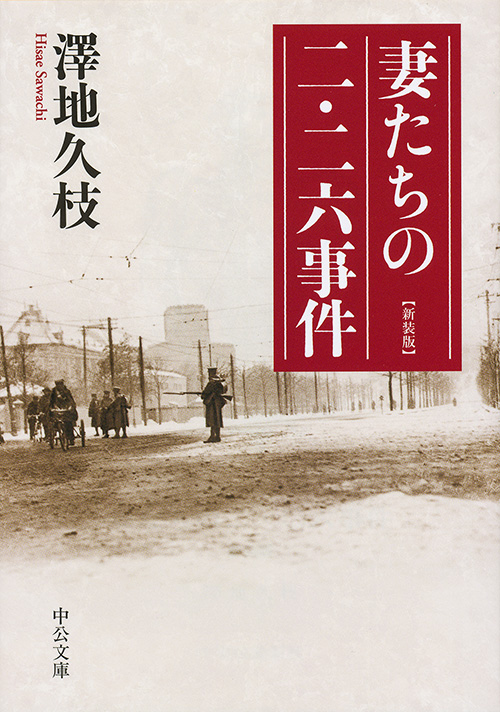
妻たちの二・二六事件
新装版
澤地久枝 著
〝至誠〟に殉じた二・二六事件の若き将校たち。彼らへの愛を秘めて激動の昭和を生きた妻たちの三十五年をたどる、感動のドキュメント。〈解説〉中田整一
2017/12/22 刊行
-
中公文庫
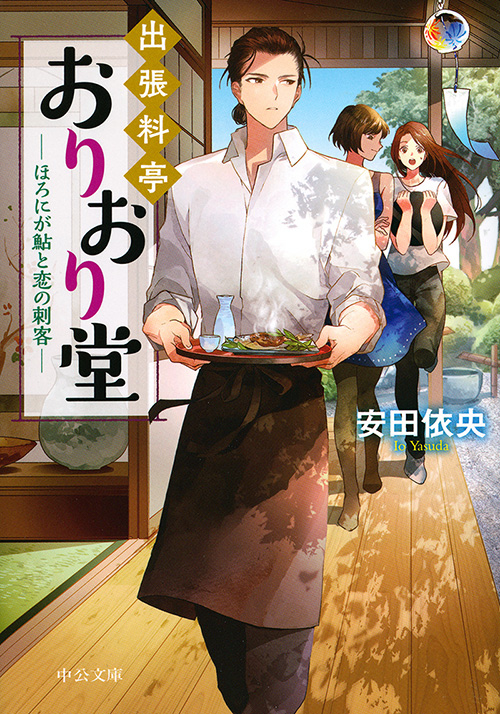
出張料亭おりおり堂
ほろにが鮎と恋の刺客
安田依央 著
仁さんの胸に飛びこむ可憐な娘。立ち尽くす澄香……! 突如現れたライバルが語る、仁さんの秘められた過去とは? 早くも波瀾のおいしいラブコメ、第二弾!
2017/12/22 刊行
-
中公文庫
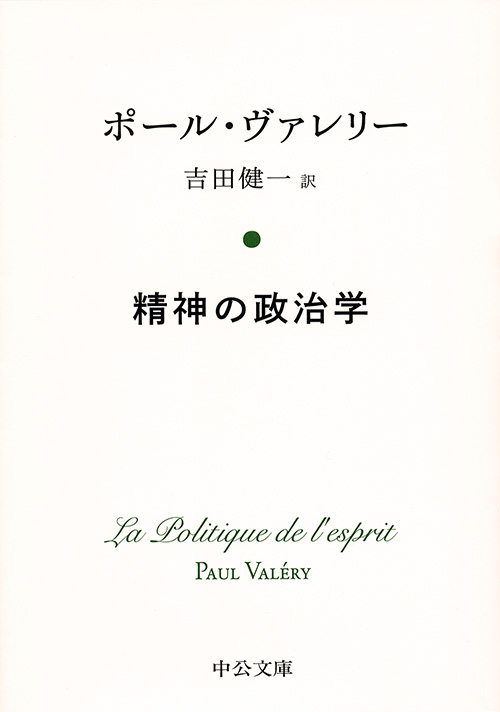
精神の政治学
ポール・ヴァレリー 著 吉田健一 訳
表題作ほか「知性に就て」「地中海の感興」「レオナルドと哲学者達」の全四篇を収める。巻末に吉田健一の単行本未収録エッセイを併録。〈解説〉四方田犬彦
2017/12/22 刊行
-
中公文庫
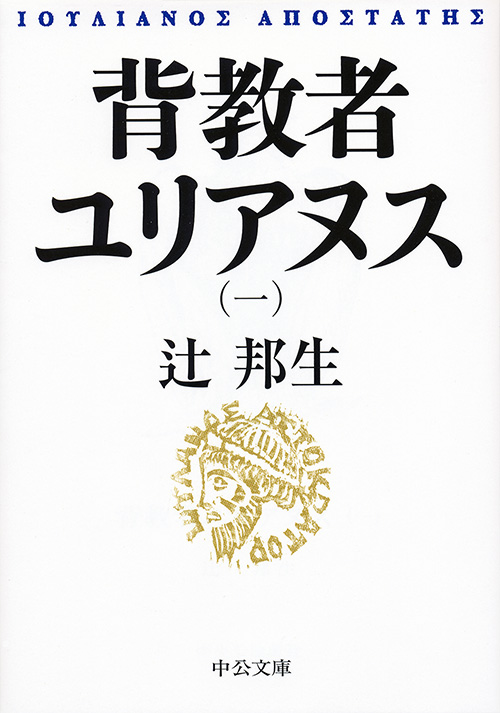
背教者ユリアヌス(一)
辻邦生 著
血で血を洗う政争のさなかにありながら、ギリシア古典を学び、友を得て、生きることの喜びを見いだしていくユリアヌス――壮大な歴史ロマン、開幕!
2017/12/22 刊行
-
中公文庫
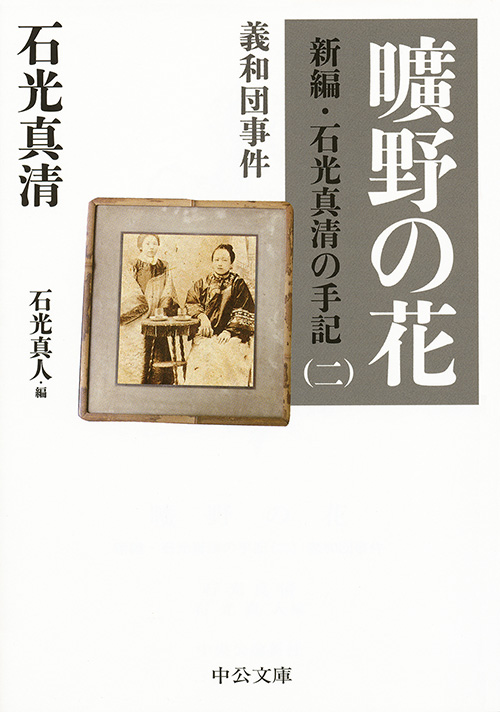
曠野の花
新編・石光真清の手記(二)義和団事件
石光真清 著 石光真人 編
明治三十二年、ロシアの進出著しい満洲に、諜報活動に従事すべく入った石光陸軍大尉。そこで出会った中国人馬賊やその日本人妻との交流を綴る。
2017/12/22 刊行
-
中公文庫
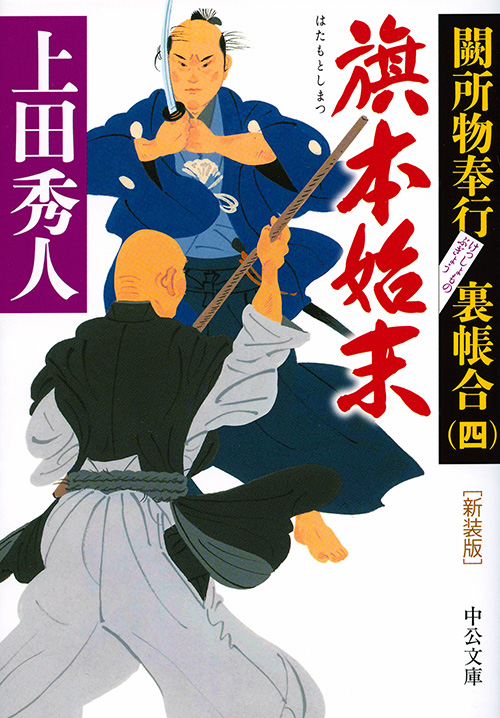
新装版
旗本始末
闕所物奉行 裏帳合(四)
上田秀人 著
失踪した旗本の行方を追う扇太郎は借金の形に娘を売る旗本が増えていることを知る。人身売買禁止を逆手にとり吉原乗っ取りを企む勢力との戦いが始まる。
2017/12/22 刊行
-
中公新書
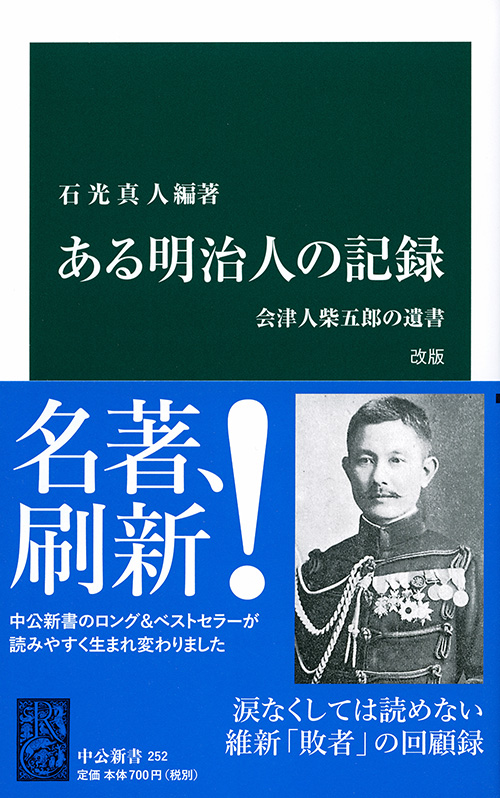
ある明治人の記録 改版
会津人柴五郎の遺書
石光真人 編著
明治維新に際し、朝敵の汚名を着せられた会津藩。降伏後、藩士は下北半島の辺地に移封され、寒さと飢えの生活を強いられた。明治三十三年の義和団事件で、その沈着な行動により世界の賞讃を得た柴五郎は、会津藩士の子であり、会津落城に自刃した祖母、母、姉妹を偲びながら、維新の裏面史ともいうべき苦難の少年時代の思い出を遺した。『城下の人』で知られる編著者が、その記録を整理編集し、人とその時代を概観する。
2017/12/21 刊行
-
中公新書
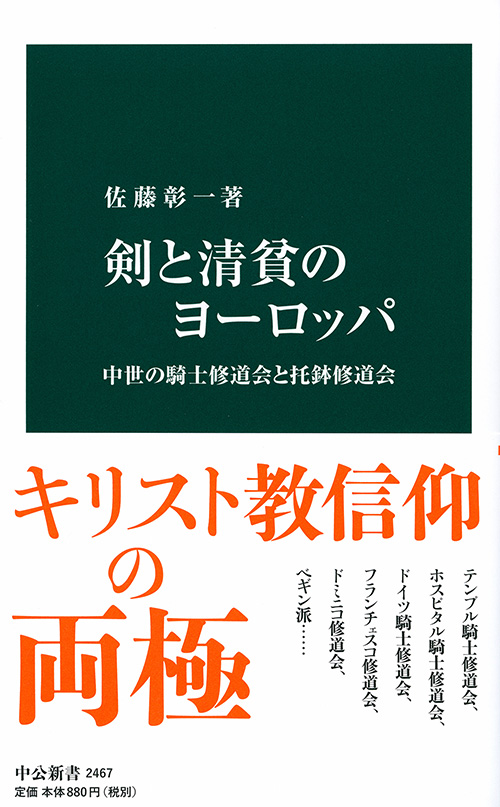
剣と清貧のヨーロッパ
中世の騎士修道会と托鉢修道会
佐藤彰一 著
俗世間を離れ、自らの心の内を見つめる修道院。だが12世紀、突如その伝統から大きく離れた修道会が生まれた。騎士修道会と托鉢修道会である。かたや十字軍となって聖地エルサレムやイベリア半島、北方で異教徒と戦い、かたや聖フランチェスコらが都市のただ中で民衆の信仰のあり方をラディカルに変革した。これら〝鬼子〟ともいうべき修道会の由来と変遷を、各修道会の戒律や所領経営などにも注目しながら通観する。
2017/12/21 刊行
-
中公新書
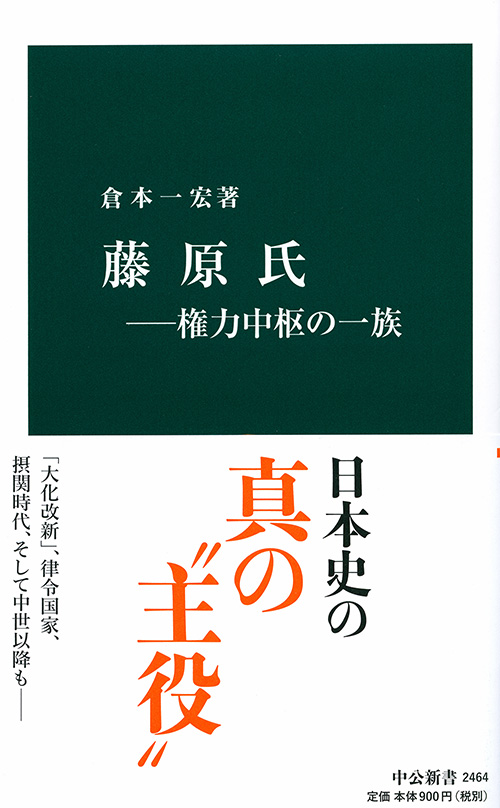
藤原氏―権力中枢の一族
倉本一宏 著
「大化改新」で功績を残したとされる鎌足に始まる藤原氏。律令国家を完成させた不比等から四家の分立、ミウチ関係を梃子に天皇家と一体化した摂関時代まで権力中枢を占めつづける。中世の武家社会を迎えても五摂家はじめ諸家は枢要な地位を占め、その末裔は近代以降も活躍した。本書は古代国家の成立過程から院政期、そして中世に至る藤原氏千年の動きをたどる。権力をいかにして?み、後世まで伝えていったかを描く。
2017/12/21 刊行
-
中公新書
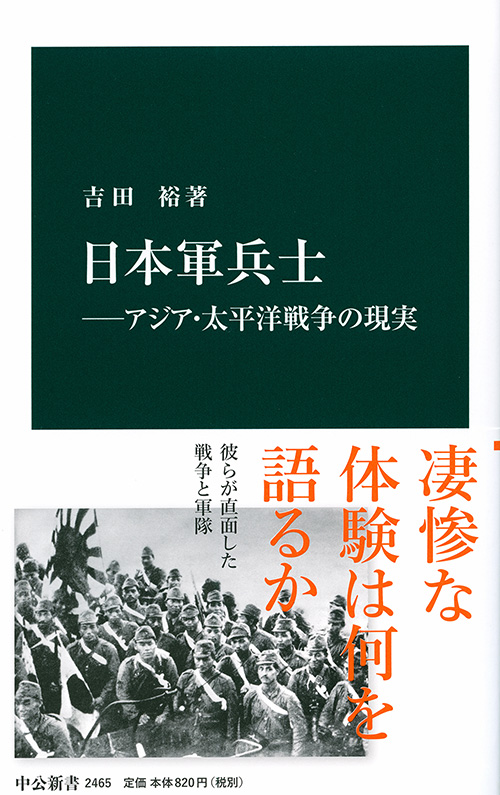
日本軍兵士―アジア・太平洋戦争の現実
吉田裕 著
310万人に及ぶ日本人犠牲者を出した先の大戦。実はその9割が1944年以降と推算される。本書は「兵士の目線・立ち位置」から、特に敗色濃厚になった時期以降のアジア・太平洋戦争の実態を追う。異常に高い餓死率、30万人を超えた海没死、戦場での自殺と「処置」、特攻、体力が劣悪化した補充兵、靴に鮫皮まで使用した物資欠乏......。勇猛と語られる日本兵たちが、特異な軍事思想の下、凄惨な体験を強いられた現実を描く。アジア・太平洋賞特別賞、新書大賞受賞
2017/12/21 刊行
-
電子書籍
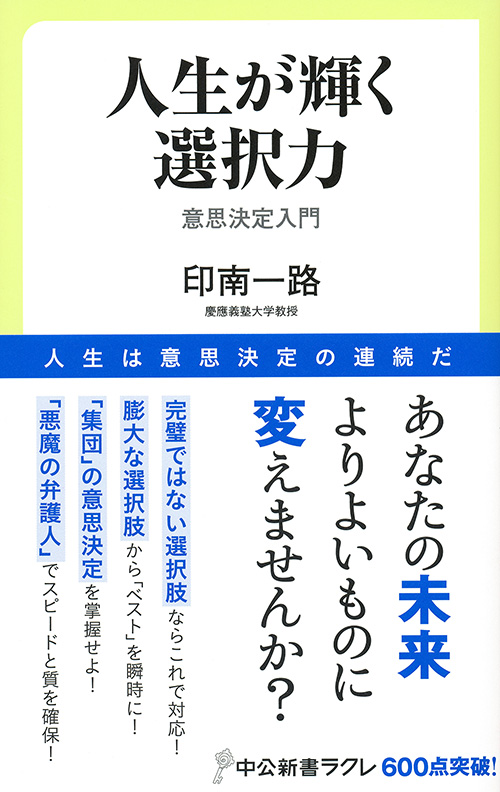
人生が輝く選択力
意思決定入門
印南一路 著
就職・転職に仕事や買い物、さらには恋人選びなど「正しい選択をしたい」と思いつつも、「誤った選択をした」「後悔している」という経験は誰でもあること。そこで慶應義塾大学教授で、意思決定論の権威である筆者に依頼。悩みがちな場面において、限りなく「正しい選択」をするための技法を伝授! 完ぺきな選択肢が無いときにどう選ぶ? 膨大な情報が入手できる昨今、必要なものを瞬時に選び出すには? 集団の意思決定を掌握する方法とは? 人生は「意思決定」の連続だ!
2017/12/08 刊行
-
電子書籍
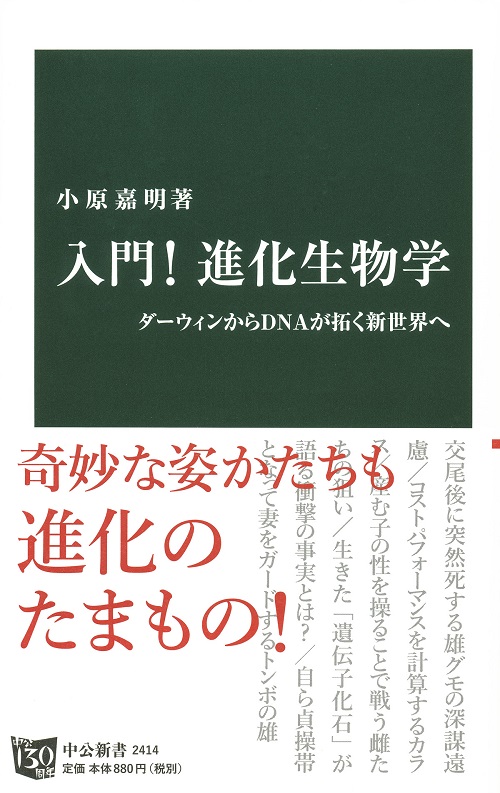
入門! 進化生物学
ダーウィンからDNAが拓く新世界へ
小原嘉明 著
生物はなぜこんなに多様なかたちをしているのか? 餌の種類に応じてくちばしの形を変えた鳥、雄が交尾後の雌に貞操帯でフタをするトンボなど、多様な姿や驚きの行動が、どのようにして生起したのかを解説。さらに中立進化説、分子遺伝学や行動生物学といった最新の知見を紹介し、「挑戦する雄」が新たな種を生み出すとの新説や、過剰な適応は絶滅への道であることを提唱する。知的興奮に満ちた生き物好き必読の書。
2017/12/08 刊行
-
電子書籍
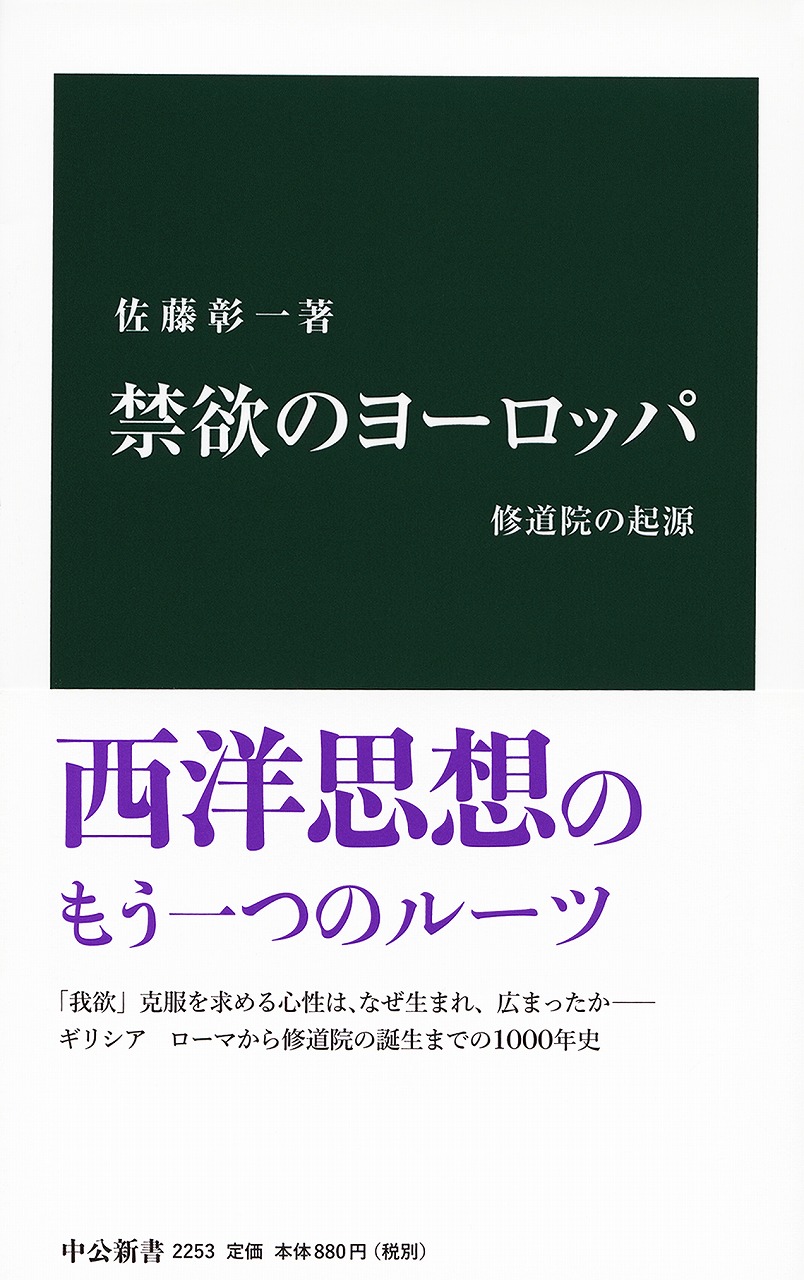
禁欲のヨーロッパ
修道院の起源
佐藤彰一 著
多くの宗教で、性欲・金銭欲などの自らの欲求を断ち切り、克服することが求められる。キリスト教も同様だが、それではヨーロッパにおける「禁欲の思想」はいつ生まれ、どのように変化していったのか。身体を鍛錬する古代ギリシアから、法に縛られたローマ時代を経て、キリスト教の広がりとともに修道制が生まれ、修道院が誕生するまで――。千年に及ぶヨーロッパ古代の思想史を「禁欲」という視点から照らし出す意欲作。
2017/12/08 刊行
-
電子書籍
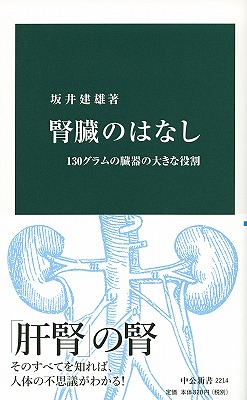
腎臓のはなし
130グラムの臓器の大きな役割
坂井建雄 著
一つ減っても大丈夫。そう軽視できるほど、腎臓の人体における役割は小さくない。主な働きは尿を作ることだけだが、それがなぜ生命の維持に必須なのか? 一日二〇〇リットル作りその九九%を再吸収する尿生成の方法から全身の体液バランス調整のしくみ、脳と同じくらい複雑で繊細かつ壊れにくい構造、一三〇〇万人以上と推計される慢性腎疾患の治療まで。背中に収まるソラマメ型の臓器について、第一人者がすべてを解説。
2017/12/08 刊行
-
電子書籍
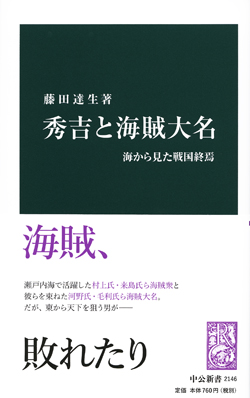
秀吉と海賊大名
海から見た戦国終焉
藤田達生 著
信長・秀吉・家康が天下統一をめざした時、鍵となった地域が瀬戸内である。とくに伊予(現在の愛媛県)は中国・四国・九州を結ぶ「かなめ所」(秀吉の朱印状より)であった。瀬戸内海で活躍した村上氏・来島氏ら海賊衆と彼らを束ねた河野氏・毛利氏ら「海賊大名」は、秀吉など東国勢力との衝突を余儀なくされる。信長が始め、秀吉・家康が引き継いだ「革命」は、地方の人々をいかに翻弄したか。愛媛出版文化賞第1部門受賞。
2017/12/08 刊行







