ホーム > 検索結果
発行された時期:1973年1月からを含む書籍一覧
全10812件中 5775~5790件表示
-
中公文庫
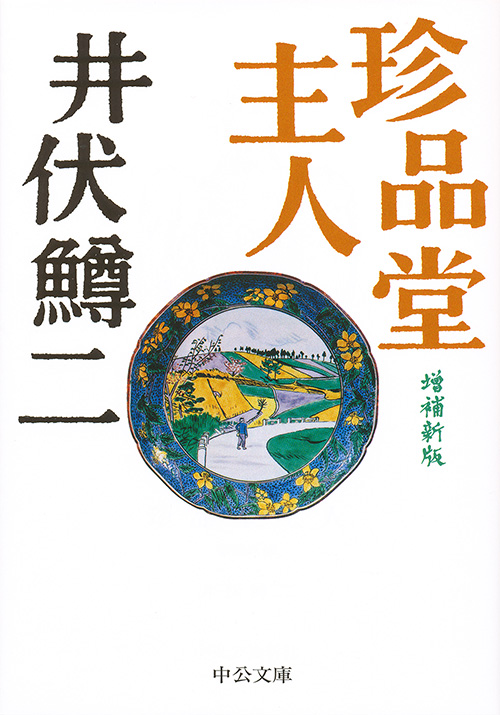
珍品堂主人
増補新版
井伏鱒二 著
風変わりな品物を掘り出す骨董屋・珍品堂を中心に善意と奸計が織りなす人間模様を鮮やかに描く。関連エッセイを増補した決定版。〈巻末エッセイ〉白洲正子
2018/01/23 刊行
-
中公文庫
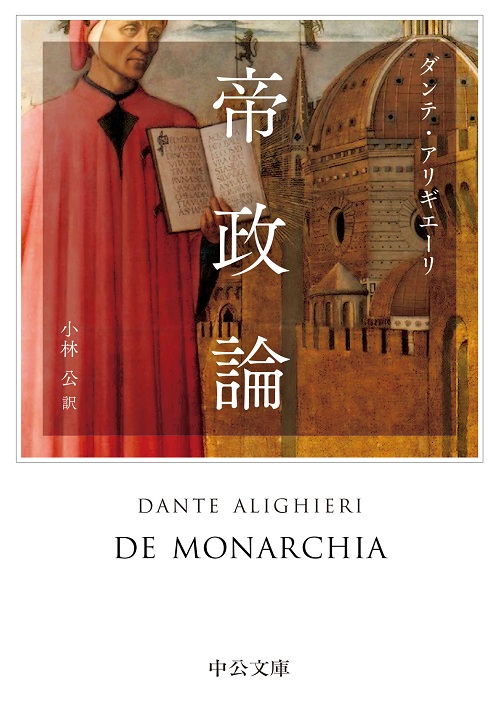
帝政論
ダンテ 著 小林公 訳
人間に平和、正義、自由をもたらす政体とは何か。教皇派、皇帝派入り乱れ抗争する状況の中、哲学、論理学を駆使して、霊的統治と世俗的統治の分離を行う。
2018/01/23 刊行
-
中公文庫
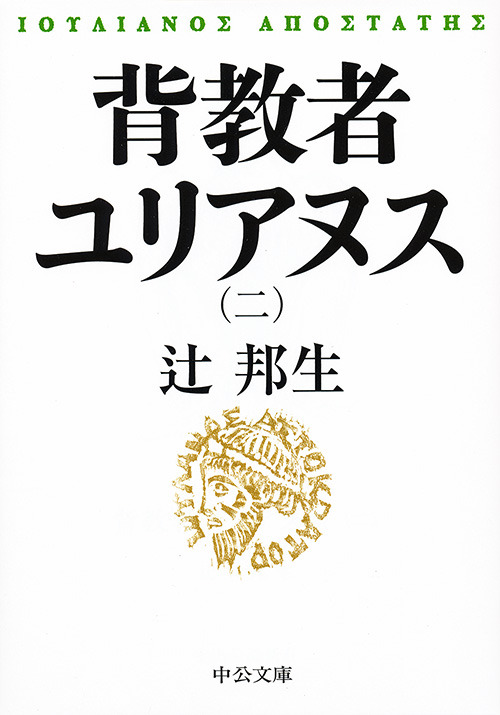
背教者ユリアヌス(二)
辻邦生 著
学友たちとの平穏な日々を過ごすユリアヌスだったが、兄ガルスの謀反の疑いにより、宮廷に召喚される。皇后との出会いが彼の運命を大きく変えて……。
2018/01/23 刊行
-
中公文庫
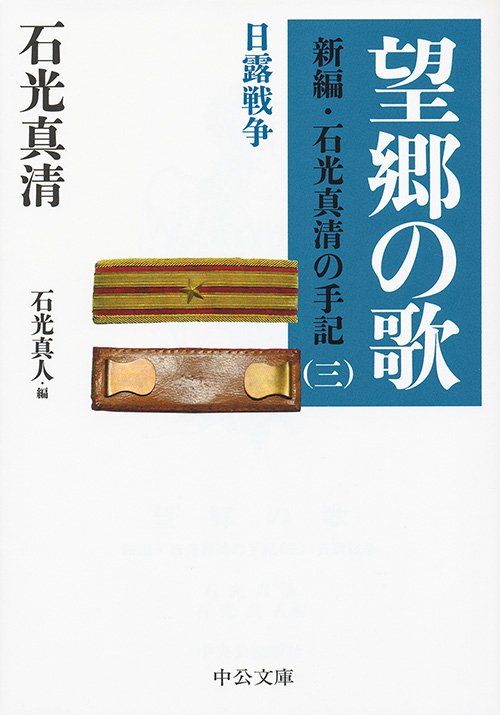
望郷の歌
新編・石光真清の手記(三)日露戦争
石光真清 著 石光真人 編
日露開戦。石光陸軍少佐は第二軍司令部付副官として出征。終戦後も大陸への夢醒めず、幾度かの事業失敗を経てついに海賊稼業へ。そして明治の終焉。
2018/01/23 刊行
-
中公文庫
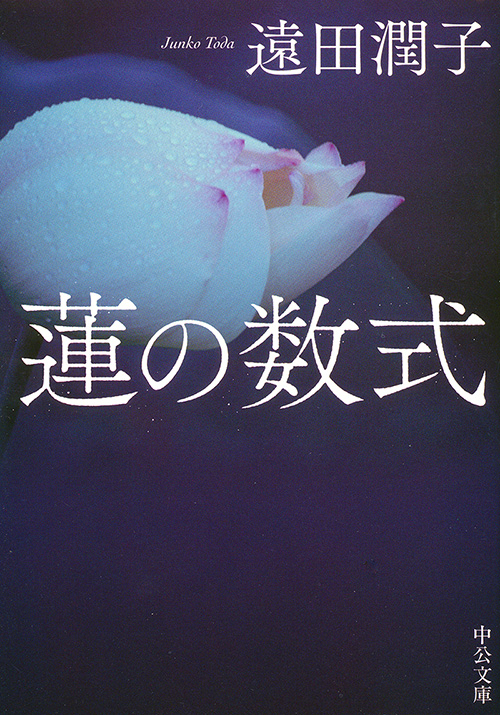
蓮の数式
遠田潤子 著
婚家から虐げられ孤立する女が出会ったのは、自らの生い立ちと算数障害に苦しむ男。愛を忘れた女と愛を知らない男が向かう先には、何が待っているのか――。
2018/01/23 刊行
-
中公文庫
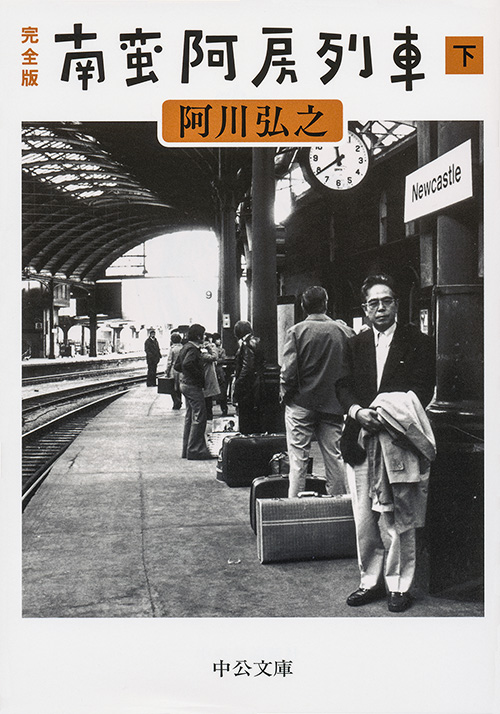
完全版
南蛮阿房列車(下)
阿川弘之 著
ただ汽車に乗るためだけに、世界の隅々まで出かけた紀行文学の名作。下巻は「カンガルー阿房列車」から「ピラミッド阿房列車」までの十篇。〈解説〉関川夏央
2018/01/23 刊行
-
中公文庫
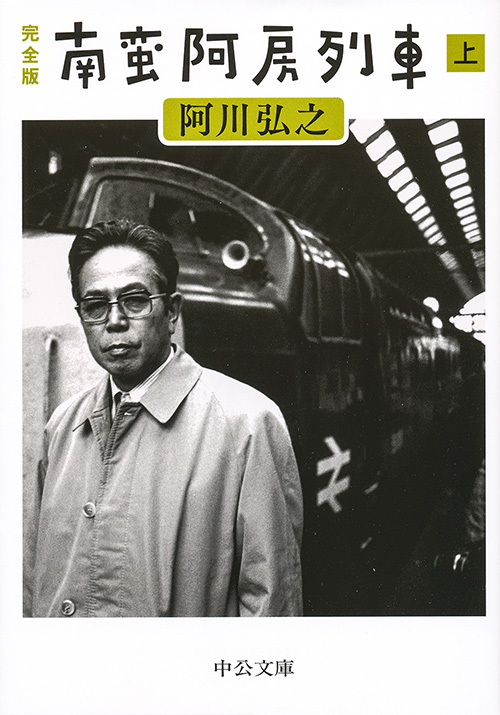
完全版
南蛮阿房列車(上)
阿川弘之 著
北杜夫ら珍友・奇人を道連れに、異国の鉄道を乗りまくる。ユーモアと臨場感が満載の鉄道紀行。上巻は「欧州畸人特急」から「最終オリエント急行」までの十篇。
2018/01/23 刊行
-
中公文庫
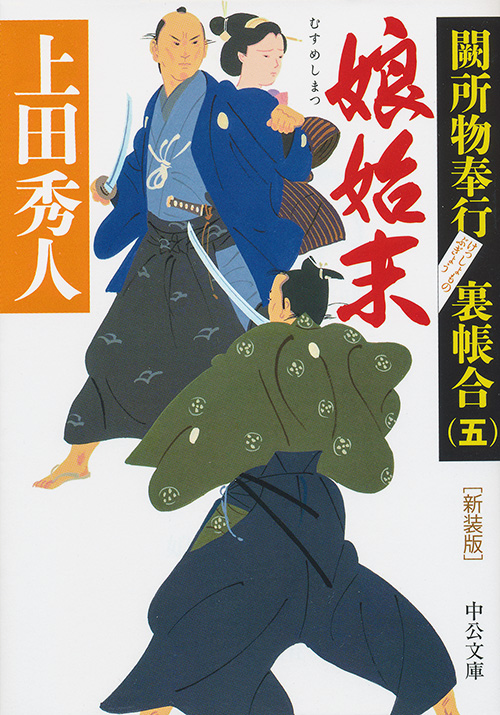
新装版
娘始末
闕所物奉行 裏帳合(五)
上田秀人 著
借金の形に売られた旗本の娘が自害。扇太郎の預かりの身となった元遊女の朱鷺にも魔の手がのびる。江戸闇社会の掌握を狙う一太郎との対決も山場に!
2018/01/23 刊行
-
単行本
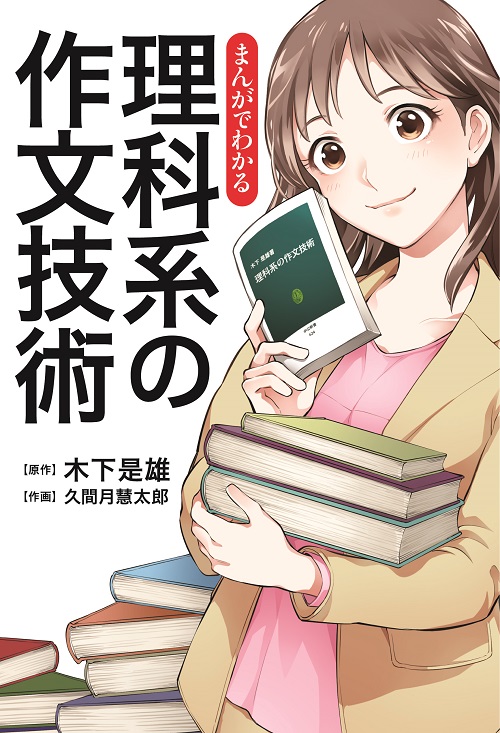
まんがでわかる 理科系の作文技術
木下是雄 原作 久間月慧太郎 作画
論文、レポート、ビジネス文書など、あらゆるシーンで求められる「明快・簡潔な表現」を追求し、100万部越えを果たした大ベストセラー新書『理科系の作文技術』が、ついにまんが化。「本当に役に立つ文章術」と評される本書のエッセンスを、まんがで手軽に習得できる!
2018/01/22 刊行
-
中公新書
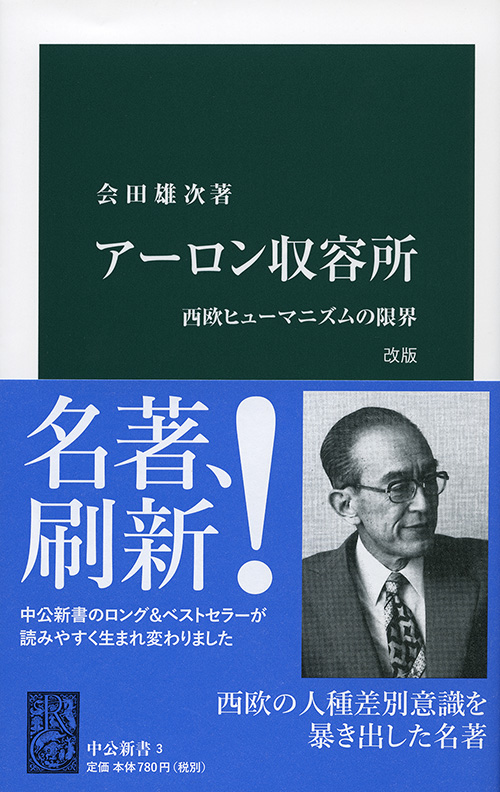
アーロン収容所 改版
西欧ヒューマニズムの限界
会田雄次 著
英軍は、なぜ日本軍捕虜に家畜同様の食物を与えて平然としていられるのか。女性兵士は、なぜ捕虜の面前で全裸のまま平然としていられるのか。ビルマ英軍収容所に強制労働の日々を送った歴史家の鋭利な筆はたえず読者を驚かせ、微苦笑させつつ西欧という怪物の正体を暴露してゆく。激しい怒りとユーモアの見事な結合がここにある。強烈な事実のもつ説得力の前に、私たちの西欧観は再出発を余儀なくされるだろう。
2018/01/22 刊行
-
中公新書
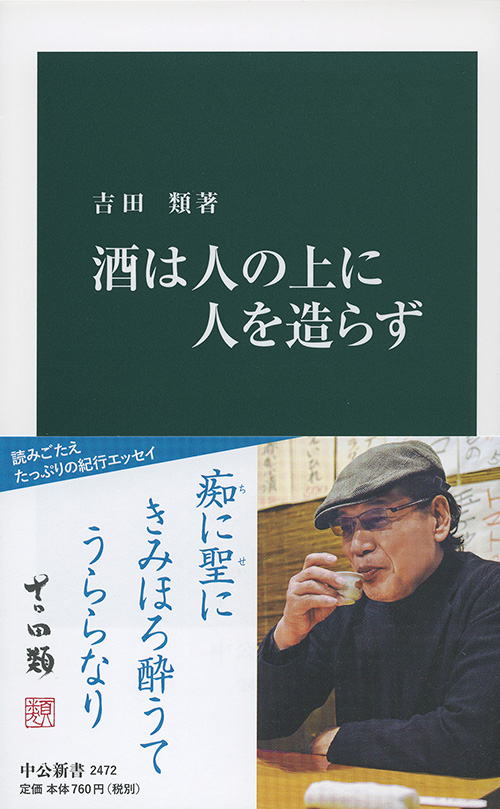
酒は人の上に人を造らず
吉田類 著
『土佐日記』の作者・紀貫之は、国司の任を終えた送別の宴で連日、熱烈に歓待された。酒好きが多く、酔うほどに胸襟を開く土地柄なれば、開放的な酒宴は今なお健在、と高知出身の著者は言う。福沢諭吉の名言ならぬ「酒は人の上に人を造らず」を地でいく著者は、東京の下町をはじめ、北海道、福島、京都、愛媛、熊本など各地を訪ね、出会った人たちと縁を結ぶ。酒場の風情と人間模様を描く、読みごたえたっぷりの紀行エッセイ。
2018/01/22 刊行
-
中公新書
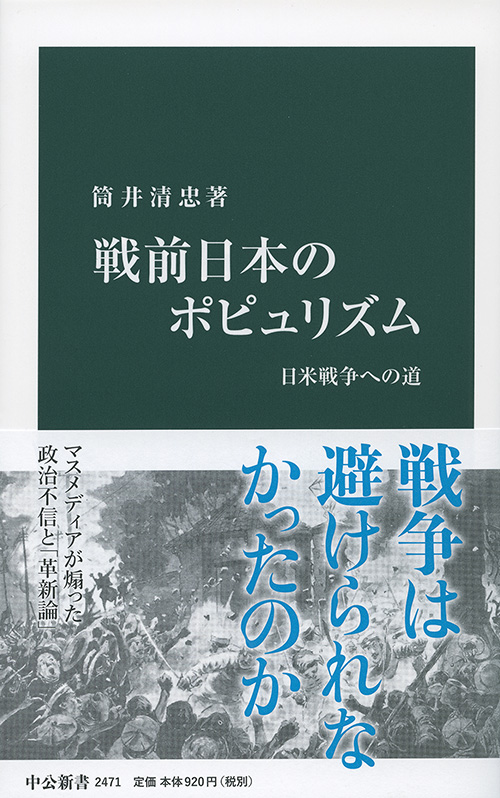
戦前日本のポピュリズム
日米戦争への道
筒井清忠 著
現代の政治状況を表現するときに用いられる「ポピュリズム」。だが、それが劇場型大衆動員政治を意味するのであれば、日本はすでに戦前期に経験があった。日露戦争後の日比谷焼き打ち事件に始まり、怪写真事件、満洲事変、五・一五事件、天皇機関説問題、近衛文麿の登場、そして日米開戦。普通選挙と二大政党制は、なぜ政党政治の崩壊と、戦争という破滅に至ったのか。現代への教訓を歴史に学ぶ。
2018/01/22 刊行
-
中公新書
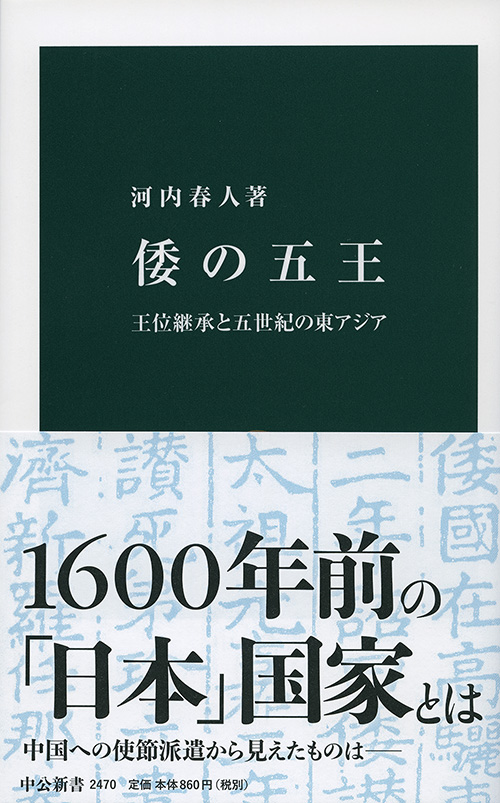
倭の五王
王位継承と五世紀の東アジア
河内春人 著
倭の五王とは、中国史書『宋書』倭国伝に記された讃・珍・済・興・武を言う。邪馬台国による交信が途絶えてから150年を経て、5世紀に中国へ使者を派遣した王たちである。当時、朝鮮半島では高句麗・百済・新羅が争い、倭もその渦中にあった。本書は、中国への〝接近〟の意図や状況、倭国内の不安定な王権や文化レベル、『古事記』『日本書紀』における天皇との関係などを中国史書から解読。5世紀の倭や東アジアの実態を描く。古代歴史文化賞優秀作品賞受賞
2018/01/22 刊行
-
電子書籍
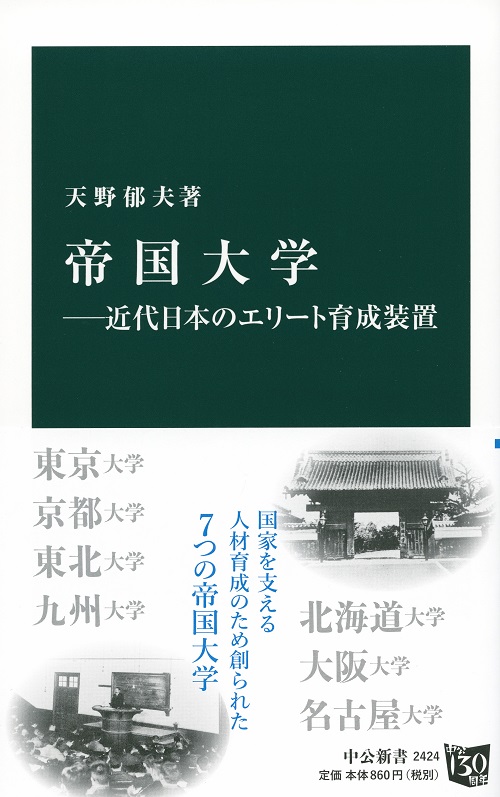
帝国大学―近代日本のエリート育成装置
天野郁夫 著
今なお大きな存在感を持つ旧七帝大。明治維新後、西欧の技術を学ぶため、一八八六年の帝国大学令により設立が始まった。本書では、各地域の事情に応じて設立・拡充される様子、帝大生の学生生活や就職先、教授たちの研究と組織の体制、予科教育の実情、太平洋戦争へ向かう中での変容などを豊富なデータに基づき活写。建学から戦後、国立総合大学に生まれ変わるまでの七〇年間を追い、エリート七大学の全貌を描く。
2018/01/12 刊行
-
電子書籍
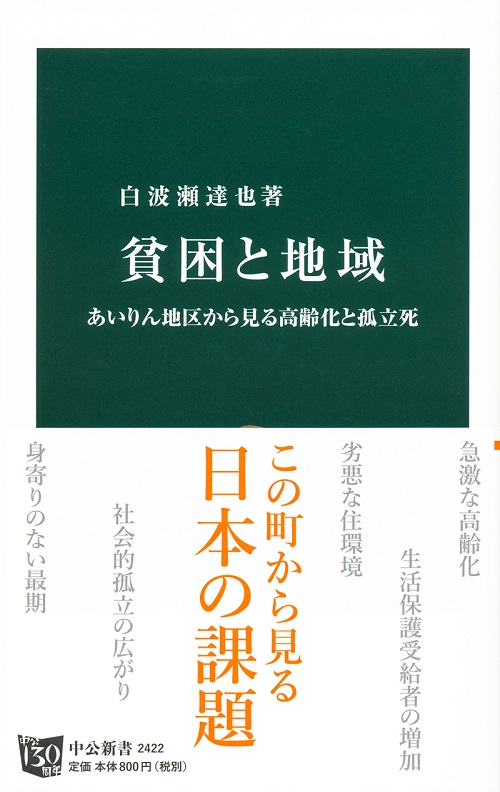
貧困と地域
あいりん地区から見る高齢化と孤立死
白波瀬達也 著
「日雇労働者の町」と呼ばれ、高度経済成長期に頻発した暴動で注目を集めた大阪のあいりん地区(釜ヶ崎)。現在は高齢化が進むなか、「福祉の町」として知られる。劣悪な住環境、生活保護受給者の増加、社会的孤立の広がり、身寄りのない最期など、このエリアが直面している課題は、全国の地域社会にとっても他人事ではない。本書は、貧困の地域集中とその対策を追った著者による現代のコミュニティ論である。
2018/01/12 刊行







