- 2025 06/14
- まえがき公開
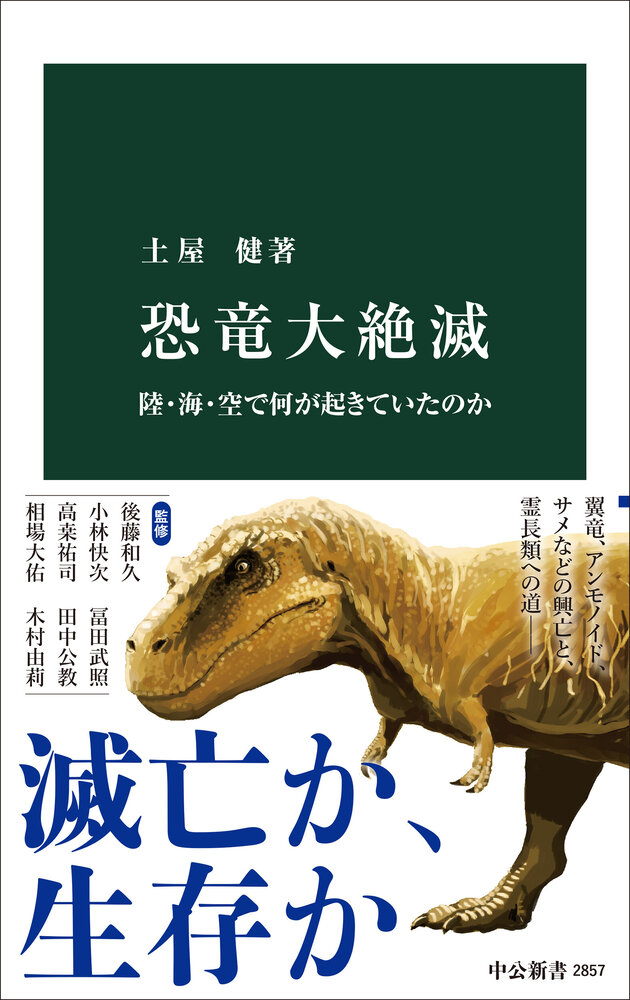
6600万年前、生態系の頂点を極めた恐竜類が地球上から姿を消した。大量絶滅事件の原因は、隕石だとするのが現在の定説である。ただ、その影響は一様ではなかった。突然のインパクトを前に、生存と滅亡の明暗は、いかに分かれたのか? 本書は、恐竜、翼竜、アンモノイド、サメ、鳥、哺乳類などの存亡を幅広く解説。大量絶滅事件の前後のドラマを豊富な図版とともに描き出し、個性豊かな古生物たちの歩みを伝える。
『恐竜大絶滅 陸・海・空で何が起きていたのか』の 「はじめに」を公開します。
はじめに――食と社会の未来を求めて
それは、今から約6600万年前の話だ。
一つの巨大隕石が、メキシコのユカタン半島の先端付近に落下した。この巨大隕石の衝突をトリガーとして、「衝突の冬」と呼ばれる大規模な寒冷化が発生。地球の平均気温は、約6℃も下がったといわれている。
気候の変化についていくことができず、「滅びの連鎖」が始まった。生命史に残る大量絶滅事件の勃発だ。
陸では、恐竜類が大打撃を受けた。1億6000万年以上の長きにわたって地上に君臨し、空前の大帝国を築き上げていた恐竜類は、その構成員の一つである鳥類を残し、他はすべて姿を消した。空では翼竜類が滅び、海でもアンモナイト類をはじめ、事件の発生直前まで生態系に君臨していた海棲爬虫類たちが姿を消した。
一方で、大量絶滅事件を乗り越えたグループもある。
生き残りの代表は、私たち哺乳類だ。哺乳類の〝始祖〟は、恐竜類とほぼ同時期に出現し、ともに多様化し、大量絶滅事件前には恐竜類を捕食する種も、空を飛ぶ種も、水中を泳ぐ種も出現していた。こうした多様な種は滅んだ。しかし、一部の種が命脈をつないだ。
海の生き残りの代表を一つ挙げるとすれば、サメの仲間を挙げることができる。サメ類は大量絶滅事件よりも1億年以上前に出現し、海棲爬虫類と熾烈な生存競争を繰り広げた。大量絶滅事件によってライバルたちは姿を消したが、サメ類は現在まで子孫を残している。
約6600万年前に何があったのか? それは、地球科学の最前線で、多くの研究者が挑み続けている「大きな謎」だ。
1980年にアメリカの物理学者が提唱した「隕石衝突説」は、今やこの事件の「起点」を説明する定説となっている。今、学界の最前線では、「何が原因だったのか」ではなく、「隕石衝突によって何が変化したのか」という〝物語の細部〟の解明に関心が移行しつつある。
この事件で滅んだ動物たちも、もちろん生き残った動物たちも、「約6600万年前にだけ」生きていたわけではない。グループによっては、数千万年、数億年にわたる連綿と続く進化の果てに大量絶滅事件に遭遇し、あるものは滅び、あるものは、かろうじて生き残ったのだ。
この本では、約6600万年前の大量絶滅事件と︑その事件で滅び、あるいは生き残った動物たちに至る「物語」に焦点を当て、さまざまな研究成果を紹介しながら綴っていく。本書を読み終えたとき、「約6600万年前の大量絶滅事件が意味すること」が、より鮮明にみえてくるはずだ。
(まえがき、著者略歴は『恐竜大絶滅』初版刊行時のものです)
