- 2018 04/09
- 著者に聞く
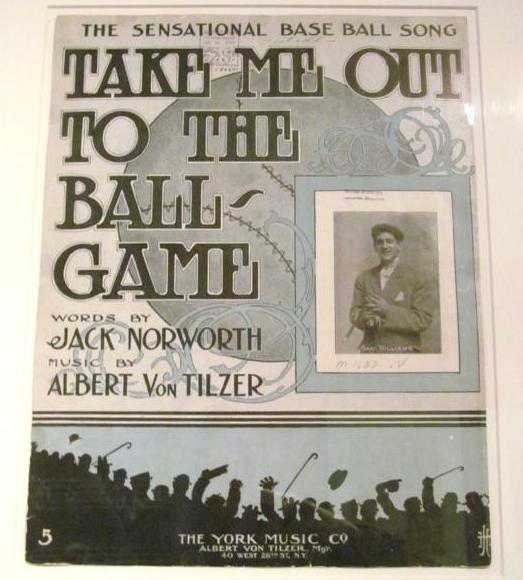
アメリカ発祥競技の成立過程やスポーツにまつわるさまざまな事件、出来事、ビジネス、選手などからアメリカの特殊性、原理を浮かび上がらせた『スポーツ国家アメリカ』を刊行した、アメリカ研究者の鈴木透さん。執筆のエピソードなどをうかがいました。
――アメリカとスポーツへの関心は、いつごろから、どういったきっかけがあったのですか。
鈴木:私は小学校一年生をアメリカですごしましたが、当時日本ではまだ影が薄かった大学アメリカンフットボールの試合を実際に観る機会がありました。これが、アメリカのスポーツとの関わりの始まりです。
小さいころからスポーツ中継を観るのは好きでした。野球、サッカー、ラグビー、アメリカンフットボール、バレーボール、アイスホッケーなどはよく観ていましたね。
その後、高校時代、米軍放送の番組を片っ端から聴くようになりました。当時の日本のテレビではアメリカのスポーツの生中継などなかったので、米軍放送で流されるアメリカのラジオの実況を通じて、アメリカの四大プロスポーツや大学スポーツに触れました。
ですから、アメリカのスポーツは、日本のプロ野球を観るのと同じように、自分の日常生活の一部にごく自然に組み込まれている存在です。
――中公新書の前著『性と暴力のアメリカ』(2006年)の発売から10年以上経ちました。前著と今回の『スポーツ国家アメリカ』で描いたアメリカについて、共通している問題意識について教えてください。また、アメリカへの見方が当時と変わっているようであれば、理由なども教えてください。
鈴木:「人為的集団統合の実験の途中の国」というのが、アメリカに対する私の一貫した視点です。前作では、人為的集団統合の宿命ゆえに性や暴力の問題がアメリカでは重要な社会的争点になりやすいことに焦点を当てたわけですが、今回は人為的集団統合のツールには何があるのかという観点へと議論を進めて、スポーツを論じています。その意味では、本書は前作の議論の延長線上にあると言えますね。実際、本書でも、スポーツにおける性や人種をめぐる問題がかなり出てきます。
また、この国の実験性という側面に加えて、先進国らしからぬいわば前近代的(ないし反近代的)ともいえる傾向がいかにアメリカという国を特徴づけているかという点を前作でも強調したつもりです。そうした視点は、スポーツの純粋さを志向するアマチュアリズムと一線を画してプロスポーツ大国への道を歩み、中世的祝祭に通ずる地域ぐるみのイベントとしてスポーツを活用するという、「スポーツの近代化に逆行する部分を持ちながらもスポーツと社会形成とを結びつけていったアメリカの軌跡」という本書の視点にも流れていると思います。
前作から10年以上が経過しましたが、基本的には「人為的集団統合の実験の途中の国」という本質は失われたとは思いません。トランプ政権の発足でアメリカが一変したかのように思われる方もあるかもしれませんし、表面的には従来と異なる社会的潮流が浮上しているのも確かですが、政治経験のない人間に大統領を任せるのも、これもまた実験の一つであるわけで、むしろそこには「試行錯誤をしながらもがき続けるアメリカ」という、従来からのこの国の特質が如実に表れているとさえ見ることができるかもしれません。
世間では、アメリカでおかしなことが起こると、「アメリカの時代はもう終わった」といった論調に傾きやすいですが、実験国家である以上、実はこの国に失敗はつきものなのです。むしろ、失敗したなと思ったらそれを修正しようとするベクトルが生まれてくるところに、この国の底力があります。トランプ政権に対する反発や、社会問題に対する様々な異議申し立てが噴出している現代アメリカの状況は、混沌としているようでいて、実験国家としてある意味では健全ともいえるのです。ただし、そこにもどのような落とし穴があるのかという点に、今回はスポーツというレンズを通して言及したつもりです。
――アメリカのスポーツの観る上で、これから着目すべき点はどこでしょうか。
鈴木:個人的には、アメリカのスポーツビジネスと女性の団体競技との関係が今後どうなっていくのかに注目しています。本書にも記した通り、サッカーやバスケットボールなど競技水準の高い女子の団体競技がアメリカには存在するのに、それらのプロ化は必ずしも順調とは言えません。
その点、男性優位の「観る」スポーツというコンセプトと一線を画した、女性たちによる「する」スポーツとしてのアマチュアのローラーダービー(ローラーゲーム)の復活が今後どうなっていくのか、とても関心があります。詳しくは本書を読んでいただきたいのですが、ローラーダービーの未来は、男性優位のアメリカのスポーツビジネスへの対抗モデルとしての意味を持ちうると思いますし、それが世界中に普及していくことは、女性の自己実現や社会の女性観を刷新していく力にもなるのではないかと感じています。
昨年、この話を大学の講義でしたとき、もし君たちの中で女子のローラーダービーのサークルを作りたいという人がいれば、私は喜んでその顧問になる、と言ったのですが、まだオファーはありませんね。
また、本書では言及しませんでしたが、これと関連して、男子と女子という区分そのものを超越するような競技のあり方、つまり、男女混合の競技形式が今後どう普及していくかという点もスポーツの未来を考えた時に注目すべき動向だと思っています。ローラーダービー自体、男女混成の開催形式もかつてあったわけですが、テニスやカーリング、フィギュアスケートなどに見られる男女ペアのような、男女が一緒に戦うというコンセプトとそれが持ちうる社会的意味について、もっと私たちは真剣に考えるべきではないでしょうか。
――特に好きなスタジアムや選手がいれば理由も合わせて教えてください。
鈴木:アメリカで最もユニークなスポーツ施設だと思うのは、ボストンのTDガーデンです。ここは、NHL(プロアイスホッケー)とNBA(プロバスケットボール)の試合に使われるほか、コンサートなどの各種イベント会場にもなるのですが、なんとノースステーションという通勤電車の発着するターミナル駅のホームの真上にあるのです。町の中心部の敷地不足からこうなったのでしょう。ニューヨークのマディソンスクエアガーデンもペンステーションという巨大な鉄道駅の上に立地しているのですが、ホームはすべて地下に埋設されているので、あまり駅の上という感じはしません。ところがこちらは、ホームが地上にあり、それに覆いかぶさるようにスポーツ施設が作られているのです。スポーツの博物館も併設されていて、なかなか見ごたえがあります。
日本では駅の上は商業施設が普通だし、耐震性の問題もあるかもしれませんが、人の集まりやすい駅とスポーツ複合施設をセットにしてみるのは、地域の活性化やポーツ振興、都市空間の有効活用といった見地から、日本でも考えてみる価値のあるモデルだと思います。
――執筆中のエピソードがあれば。
鈴木:スポーツのことを知っているとアメリカ人とのコミュニケーションが円滑になるという例を「あとがき」にも記しましたが、同じようなことが執筆中にもありました。
ニューメキシコ州のアルバカーキという町に行ったときのことです。その日私は、100キロほど離れた州都サンタフェの州立歴史博物館に用事があって、10人ほどの客とともに早朝アルバカーキの駅で電車を待っていました。すると、サンタフェの近くで電車が車と衝突し、死者も出ているので、夕方まで運休だ、というのです。困った私は、何とかサンタフェまで行く方法はないか駅員にかけあいました。すると同じように困っていた女性がいて、とうとうその駅員さんは、なら、30キロほど離れた途中のベルナリオという駅まで車で送ってあげよう、そこには電車が立ち往生していて、そこからサンタフェまで何らかの振り替え輸送をすることになるだろうから、と言ってくれたのです。
私たち二人は工事用のトラックに乗せられました。するとその駅員さんは、私たちが何者なのか、いろいろと質問し始めました、ちょうどその日は、NFL(プロフットボール)のシーズンが始まった翌日で、フットボールは好きかと聞いてきました。私は本書の「あとがき」にも記したようにデンバー・ブロンコスの長年のファンなので、そう答えると、なんと彼もそうだというではありませんか。デンバーのあるコロラド州はニューメキシコ州の隣で、ニューメキシコ州にはNFLのチームがないため、ここの人は、デンバーか、やはり隣のテキサス州のダラス・カウボーイズのファンだというのです。彼は、デンバーまで車で片道6時間以上かけて試合を見に行くほどの筋金入りのファンでした。
それからはもう一人の女性そっちのけで、彼と私との間でブロンコス談義が始まりました。往年の名選手や監督、今シーズンはどうなりそうか、などといったことで盛り上がってしまったのです。もう一人の女性はシカゴの人で、最近ここに引っ越してきたらしく、明らかにフットボ-ルの知識は私より貧弱でした。
そうこうするうちに、ベルナリオという町まで来ました。ところが彼は、どうせ夕方まで電車はこないし、このままサンタフェまで送ってやる、と言い出したのです。サンタフェまで行けば往復で2時間は軽くかかるのですが、彼は外国からやってきたブロンコスファンとの会話を続けたかったのでしょう。ブロンコス談義はさらにサンタフェまで続きました。
アメリカで困った時に親切にしてくれた人は他にもいますが、彼は破格のことをしてくれました。それも、同じチームのファンという親近感のなせる業だったのだと思います。アメリカにおけるスポーツの存在感の大きさをあらためて感じました。
――本書を通して伝えたかったことはなんでしょうか。
鈴木:この本で伝えたかったのは、スポーツという視角からでも本格的なアメリカ研究ができる、そして、むしろそこからこそ、アメリカ的創造力の本質がより鮮明に見えてくるということです。競技理念やルールがその競技を生み出した社会や文化を実際にはどう反映しているのか、また、スポーツの世界が現実の社会の出来事とどうリンクしているのかに着目することで、一味違う読みごたえのあるアメリカ論を提示したつもりです。この本は大学での私の講義ノートを基にしているのですが、講義の時の学生の反応も良かったですね。
本書では、スポーツ史とアメリカ研究という異なる領域を結びつけたわけですが、特定の分野に閉じこもるのではなく、むしろ越境していくことが新たな観点を創出する重要な糸口なるということを感じていただきたいですね。アメリカンフットボールと独占禁止法とか、バスケットボールと宗教とか、それまで無関係に見えていた事柄がつながるときというのが、学問をしていて最も知的興奮を覚える瞬間の一つです。
さらに、越境することの魅力は、それまで別々の世界に見えていたものがつながることで、両方とも前よりも鮮明に見えるようになるということです。スポーツ史とアメリカ研究を結びつけた本書をお読みいただければ、スポーツとアメリカの両方に対する見方が変わってくるはずです。
そして最終的には、アメリカと日本の境目も越境して、アメリカの教訓を日本という文脈にフィードバックする発想を読者の皆さんには持ってほしいですね。外国研究とは、究極的には自分が住んでいる社会を相対化し、身の回りの世界を見つめ直すことにつながっているわけですから。本書が、ラグビーのワールドカップや東京オリンピック・パラリンピックを機に、今後スポーツというものを日本社会はどう位置づけていくべきかという議論の糧になることを望みます。
――『スポーツ国家アメリカ』をどのような人に読んでほしいですか。
鈴木:本書の最もコアな読者は、当然アメリカなり、スポーツやスポーツビジネスに関心のある人ということになるでしょうが、本書の中身が分野横断的な越境の精神でできているように、読者層も様々な人たちが混在するといいですね。とりわけ、企業の社会的責任とか地域振興、文化政策やグローバル化、女性の地位の向上やメディアの倫理といった問題に関心のある人にも読んでもらい、スポーツという身近な事柄がこれらの問題と実は密接につながっていることを再認識してもらえたらと思います。また、日本人選手の活躍で、アメリカのスポーツに関心を持ち始めた人もいるかと思いますが、本書を一読いただけると、アメリカのスポーツがいっそう身近になるでしょう。
一般的には、読書好きの人はスポーツに疎く、スポーツが好きな人は逆にあまり本は読まない、といった傾向があるかもしれません。本書を通じて、そうした普段はあまり接点のない人たちが知的興奮を共有し、互いの距離感が一歩でも縮まるといいですね。スポーツは縁遠い、あるいはアメリカ史はよく知らないという人にも十分わかるように、競技のルールやアメリカの成り立ちを説明してあります。
社会の力とは、その構成員がどれだけ問題意識を共有できるかにかかっているのだと思うのですが、比較的手ごろな読書体験としての新書は、それに貢献できる媒体だと思っています。終章にも記したように、近代産業社会の能率至上主義は、専門化と分業化のジレンマを抱えています。一方的に専門化を推し進めるのではなく、個と全体の連関を生み出す作業を大切にしたい――本書を専門書というよりは新書の形で書きたかった理由もそこにあります。
ただ、本当のことを言うと、この本を真っ先に読んでほしいと思う人は、もはやこの世にはいません。それは、序章で言及した、本書の着想の出発点にもなっている、『オフサイドはなせ反則か』の著者、中村敏雄さんです。実は、私は中村さんと面識がありません。中村さんをよく知っている、という人も知りません。言ってみれば、赤の他人です。でも、中村さんの著作を読んで、これはアメリカ研究に応用できるヒントを含んでいると確信し、彼の視点を私なりに発展させたつもりです。この本をもし読んでくださったら、どんな感想が返ってきただろうと思わずにはいられません。
学問の世界の素晴らしいところは、このように自分が直接教わった先生以外にも、著作を通じて多くの先生に出会えるということですね。ですから、今度は私の著作を読んでくれた見ず知らずの人が、それをさらに別の仕事へと応用するようなことをしてくれるなら、うれしい限りですね。
――最後に、今後のお仕事について教えてください。
鈴木:本書では、スポーツという切り口から「アメリカ的創造力とは何か」という問いに迫っています。そして、近代社会の限界を超えようとする、異種混交的世界への志向や、資本主義と民主主義を両立させるために時間・空間・行動をコントロールしようとする発想が、アメリカ的創造力の根幹に深く関わっている可能性を提起しました。私自身は、こうしたアメリカ的創造力の特徴がどのようにして形成され、それが現在いかなる状況にあるのかを、スポーツ以外の事例からも検証する必要性を感じています。目下、私が注目しているのは、次の四つのテーマです。
一つ目は、アメリカ食文化史。アメリカ型競技の出現が、産業社会における健康不安と関係していることは本書にも記した通りですが、こうした健康不安は、他方では食の変革という流れにもつながっています。アメリカと言えば、ハンバーガーとフライドポテトしか思い浮かばない人も多いかもしれませんが、実際にはアメリカの食文化は、先住インディアンや黒人奴隷、様々な移民集団といった異種混交的な基層を持ち、そこに産業社会がもたらした食の変革が絡み合う形で成立しています。なので、食の歴史は、人為的集団統合と産業社会の在り方という、本書でスポーツを通じて検証しようとした図式とも重なる、魅力的なテーマなのです。
二つ目は、アメリカにおける人工楽園の系譜。本書でもスポーツがアメリカの都市の形成に深く関わっている点に触れましたが、アメリカ的創造力は、ある種の空間形成を志向するところがあると感じています。それは、本書でも指摘したような、時間・空間・行動をコントロールするという、アメリカ型競技の根底に流れている発想ともつながっています。アメリカは理想の空間をどのように創出しようとしてきたのか、植民地時代の都市計画から現代のテーマパークやゲイテッド・コミュニティに至るまで、アメリカン・ユートピアの文化史をたどってみると、アメリカ的創造力の現在がより鮮明に見えてくるでしょう。
三つ目は、南西部論。トランプ政権の発足で、アメリカ南西部のメキシコとの国境に壁を作る話が話題になっていますが、アメリカ的創造力の重要な要素であると私が考える異種混交性への志向をこの国が育む上で非常に重要なインスピレーションの源となってきた地域は、実はほかならぬ南西部なのです。ここは、先住インディアンとメキシコ(スペイン)の文化が混ざり合い、グランドキャニオンのような太古の大自然が残る地域で、西洋近代とは異なる世界として、アメリカの芸術、建築、宗教、映画などの大衆文化に大きな影響を与えてきました。国境警備という大義名分があるにしても、アメリカ文化の活力がいわばこうした異界への越境の精神にあると考えるなら、移動を阻止する壁の建設は、それに逆行する、いわば自らの異種混交的成り立ちを否定する象徴的意味も持っています。南西部はあまり日本でもなじみがない地域かもしれませんが、この地域が果たしてきた役割をあらためて振り返ることは、現代アメリカに警鐘を鳴らす意味でも、アメリカ研究者が取り組むべきテーマだと思います。
四つ目は、三つ目と少し関係しますが、現代アメリカが共有すべき記憶の問題。本書でもスポーツイベントが現代アメリカにおける記憶の民主化と結びつきつつあるとことを記しましたが、非ワスプ多数派時代に向けて、従来のワスプ中心主義的歴史観をアメリカがどう修正できるかは、今後のアメリカの行方を大きく左右すると思います。人為的集団統合の完成度が上がるのか、それとも分断が加速するのかを見極める上で、アメリカ社会の様々な領域、例えば、史跡保存、博物館展示、映画における過去の描き方などを幅広く見渡しながら、記憶表現の動向を注視していくのはとても有効な作業だと思っています。
以上のテーマについては、すでに講義をしたり、論文に書いたりと手はつけていますが、アメリカ文化研究と現代アメリカ論を主たる専攻領域としている身としては、早いうちにこれらのテーマにはまとまった形でけりをつけたいですね。

