- 2025 07/25
- まえがき公開
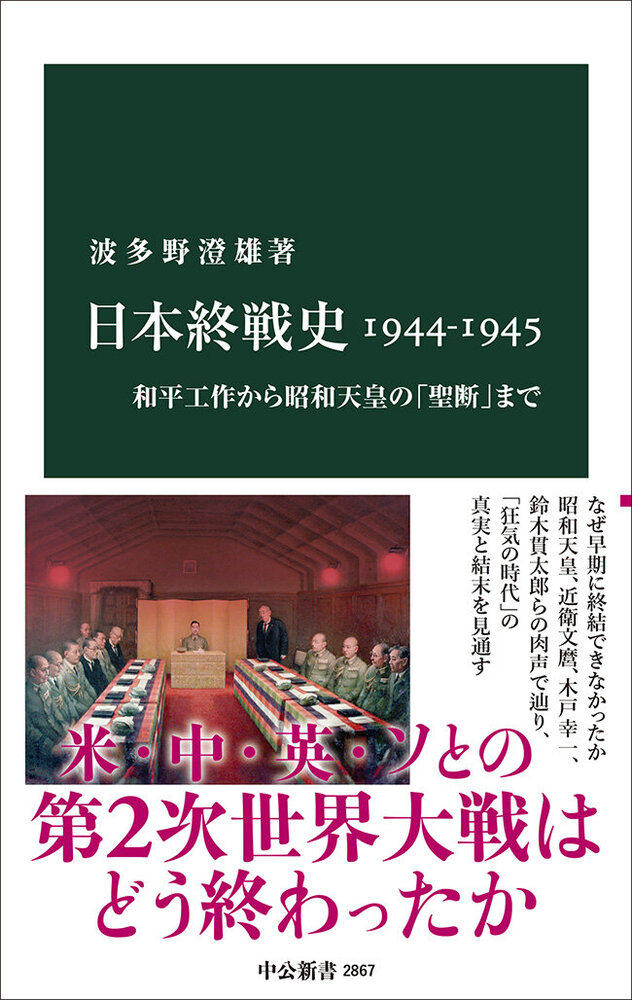
泥沼化する日中戦争、太平洋を挟んだ日米戦争、東南アジアでの日英戦争、原爆投下、敗戦前後の日ソ戦争。米中英ソとの複合戦争はいかに推移し、幾多の和平・収拾策にもかかわらず、なぜ早期に終戦できなかったか。他方、本土決戦を目前に、なぜ「聖断」で終戦が可能となったか。最新研究を踏まえ、昭和天皇・近衛文麿・木戸幸一・鈴木貫太郎らの肉声で辿り、第2次世界大戦の結末を巨細に描く。「狂気の時代」の真実に迫る。 『日本終戦史1944-1945 和平工作から昭和天皇の「聖断」まで』の 「まえがき」を公開します。
今から70年近く前、ロバート・ビュートー教授が著した『日本降伏の決定』(英文版1954年、邦訳『終戦外史』1958年)に序文を寄せたエドウィン・ライシャワー教授(元駐日アメリカ大使)は、こう述べている。
「あの降伏の時機が、実際よりわずか二週間をはさんで早められたか遅れたかだけでも、戦後の世界の情勢は著しく違ったものになっていたであろう。二週間前に降伏していれば、原爆投下もなかったし、ソ連の参戦も起こらなかった。二週間降伏がのびていたらロシア軍の極東進撃はさらに進んでいただろうし、日本の破壊も回復できぬものとなっていたであろう」
このライシャワー教授の問いかけは、議論が尽きることなく現在でも続いている。1945年8月15日の降伏・敗戦(終戦)をはさむ「二週間前」といえば、アメリカ・イギリス・中国の三国首脳名によるポツダム宣言 降伏勧告から約一週間後である。他方、「二週間後」といえば、日本占領が始まり降伏文書の調印もまもない頃である。
確かに、2週間早ければ数十万人の日本人の命が救われたであろうし、2週間遅ければ犠牲と破壊はさらに膨らんだことは想像にかたくない。こうした事態にとどまらず、2週間の違いは戦後世界の姿を大きく左右したであろう、とライシャワー教授は指摘している。それほど1945年7月から8月にかけては重大な一時期であり、日本と連合国の指導者の決定や決断に大きな注目を集めるのである。
さて、筆者の理解では、「大東亜戦争」は、真珠湾攻撃に始まる「日米戦争」、おもに東南アジアを舞台とした「日英戦争」、1937年に始まる「日中戦争」、終戦前後の「日ソ戦争」という、四つの戦場の「複合戦争」であった。米英中ソの四大連合国の結束は辛うじて維持されたが、それぞれが担った戦場の様相も、今に残る傷痕もそれぞれ異なる。
確かに、おもに太平洋を舞台とした日米戦争は、戦域の広さと伸縮性において他を上回る。ペリリュー島や硫黄島のように、戦線の後退によって孤島に取り残され、絶望的な戦いを強いられた日本軍兵士は数十万にも及ぶ。さらに沖縄戦は多数の非戦闘員を巻き込み、20万人以上が犠牲となった。
しかし、こうした激戦にもかかわらず、戦後の日米間には、両国関係を揺るがすほどの歴史問題が噴出することはなかった。深化する戦後の日米同盟がそれを抑えてきたからである。
日米戦争は50万人以上の戦死者を出したが、これに次ぐ40万人以上の戦死者を出したのが日中戦争である。他国民に与えた被害という点では、日中戦争は日米戦争をはるかに上回る。
本書は、これらの戦争のうち、太平洋における日米戦争と大陸における日中戦争という二大戦争を、どのような展望のもとに、どのように終わらせようとしていたのか、それぞれの過程をたどったものである。その過程では、日中戦争や日英戦争の行方は定まらず、結局、日米戦争をいかに終結させるかに、指導者の関心は集約されていく。
その一方、日中戦争(支那事変)は、他の戦場から切り離され、犠牲の拡大にもかかわらず、その解決策や収拾策が見出せないまま終息する。二つの戦争はどのような関係にあったのか、なかったのかが、本書のテーマの一つである。
また、ひと握りの指導者による終戦決定は、原爆とソ連参戦という二つの外圧との関連が重視されがちである。本書は、これらの外圧を軽視するものではないが、終戦を左右した要因として、米側の本土侵攻作戦計画やその前段階における空襲・封鎖、これに対峙する日本側の本土決戦構想、決戦の柱とされた特攻や本土に張り巡らされた防備体制にも注目した。
日本にとって原爆は突発的なものであり、ソ連参戦もその時期を正確に把握していたわけではない。そう考えると、本土を最終決戦の場として死に物狂いで抗戦体制の形成に躍起となる日本人と、指導者たちの戦争の収拾のための努力は、終戦や戦後を考えるうえで見逃せない側面であろう。
ライシャワー教授が指摘するように、ポツダム宣言の発表から2度目の「聖断」まで、きわめて重大な2週間余りのあいだに、なぜ最高指導者は戦争終結の決断ができなかったか。これも重要な問いであるが、もう一つの問いは、「徹底抗戦論」が国内に横溢するなか、なぜ2度の「聖断」で終戦が可能であったか。2度の「聖断」による終戦は、国内戦場化や政府の崩壊、さらにソ連の本土進出が避けられたという意味で、むしろ早期終戦として評価することも可能である。本書は二つの問いを念頭においている。
私の答えをあらかじめ示しておけば、「複合戦争」の収拾が対米戦争の終結に絞られたことで早期の終戦が可能となり、戦後の日米同盟を導く伏線ともなるのだ。こう考えると、あの時点での「聖断」の意味はきわめて大きいのである。
本書は9章構成であるが、内容的には3部に分かれている。
第一章〜第三章(第一部)は、戦争の主軸であった太平洋戦線と大陸戦線における戦略と政略、そして戦争収拾のための指導者の努力を大きく拘束することになった内外の要因に眼を向けている。
第四章〜第六章(第二部)は、小磯国昭内閣と鈴木貫太郎内閣におけるさまざまな「和平論」が行き詰まり、1945年6月下旬に意を決した木戸幸一内大臣が、「時局収拾試案」をもって指導者の説得にあたるまでの指導者の動きを取り上げている。中心人物の一人は、重臣・近衛文麿である。近衛は重臣のなかでは比較的明瞭に戦後を見通しつつ、米英との直接和平の必要をとなえていたからだ。
第七章〜第九章(第三部)では、45年7月下旬のポツダム宣言の発出、8月の原爆とソ連参戦という「二つの外圧」のもと、2度の「聖断」によって決着せざるえなかった指導者たちの動きに眼を向けた。東郷重徳外相や阿南惟幾陸相などがその中心である。
また、最後の第九章は、「聖断」が実質的に、太平洋戦線「日米戦争」の終結であったことを踏まえ、大陸における「日中戦争」と「日ソ戦争」の収拾のあり方を取り上げている。
三つの戦争がいかに相互に切り離され、それぞれ異なる結末を迎えたかを理解できるはずだ。
本書はおおむね以上のような構成であるが、それぞれの章のまとまりを重視したため、各章の記述は必ずしも時系列の順に配置されていないことをお断りしておきたい。
なお、本書が重点を置くのは、マリアナ諸島が奪われた1944年夏から1945年夏までのほぼ1年間である。とくに同諸島のサイパン陥落で軍事的敗北は決定的となったが、日本はすぐには戦争終結には向かわなかった。国体という中核価値を護るため、朝野をあげて特攻兵士の「殉国」を称賛し、本土決戦を叫ぶという、近代日本の歩みのなかでは稀にみる「狂気の時代」に突入する。この1年間の出来事をたどることは、敗戦と復興の意味を考えるための手がかりとなろう。
(まえがき、著者略歴は『日本終戦史1944-1945』初版刊行時のものです)
