- 2025 02/21
- まえがき公開
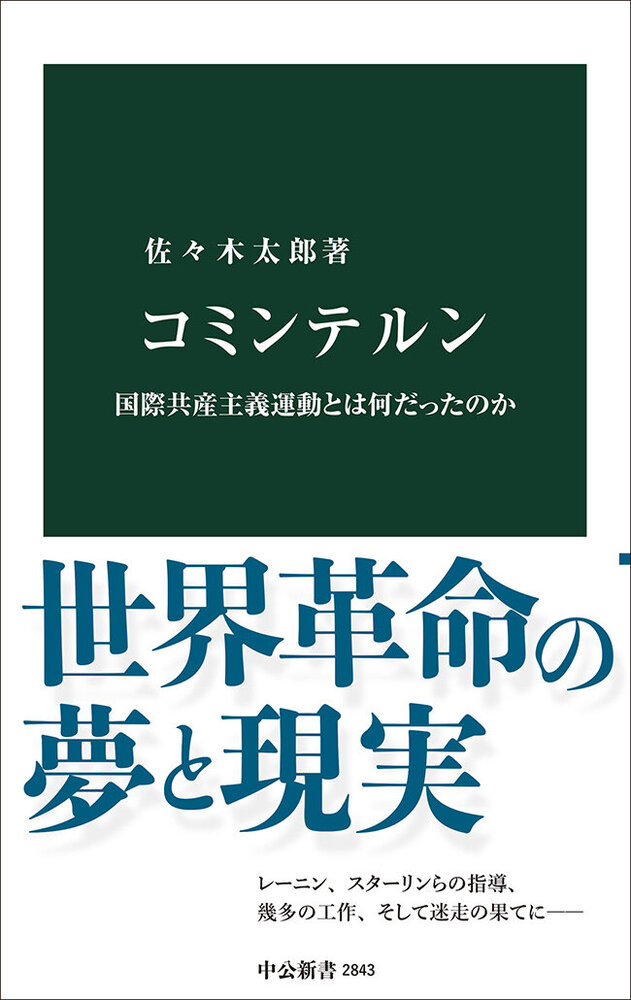
ロシア革命後の1919年、コミンテルン(共産主義インターナショナル)は、世界革命のために誕生。各国共産主義政党の国際統一組織として、欧州のみならずアジアなど各地に影響を及ぼすべく、様々な介入や工作を行った。本書は、レーニンやスターリンら指導者の思想も踏まえ、知られざる活動に光をあてる。1943年の解体にいたるまで、人々を煽動する一方、自らも歴史に翻弄され続けた組織の軌跡を描き出す。 『コミンテルン 国際共産主義運動とは何だったのか』の 「はじめに」を公開します。
1919年3月初旬、まだ春の兆しの遠いモスクワ。
ロシア革命後に始まった内戦と諸外国からの干渉によって混乱の続く国内情勢のさなか、壮麗な旧ロシア帝国宮殿クレムリン内の小さなホールに、国内外の共産主義者が集った。
ホールは、政権を奪取したレーニン率いるボリシェヴィキ、すなわちロシア共産党が、革命裁判のために使っていた場所であり、帝政派に対する最初の死刑宣告が出されたことでも知られる。しかし、このとき会した、19ヵ国の共産党組織などの代表者ら五十余名は、死の宣告ではなく、産声を聞くことになった。否、ある意味では、その両方であったのかもしれない。
第二次世界大戦中の1943年5月にスターリンが解散するまでの約四半世紀にわたり、国際共産主義運動の司令塔として現代史に大きな影響を及ぼす「共産主義インターナショナル」、略称「コミンテルン」が創立されたのだ。
世界中の無産階級すなわち土地や資本といった生産手段をもたない人びと、いわゆる「プロレタリアート」を蜂起させ、有産階級すなわち「ブルジョアジー」の支配を打ち破り、各国の国家権力を次々と転覆することで、資本主義世界を根底から破壊しつくし、この地上を共産主義の理想で塗り替える――文字通り世界革命の実現を使命とするコミンテルンは、イデオロギーの世紀たる20世紀を象徴する存在であった。
各国の共産党を支部として統括し、革命的なインターナショナリズムを追求したこの巨大組織については、これまで多様な立場からさまざまなことが語られてきた。
とくに東西冷戦時代までは、ソ連や各国の共産党から発信された、いわば公式史のようなものから、反共主義者の手による批判の書まで、数多くの言説が生み出された。なかには、コミンテルンの活動の実態についてはっきりとした証拠のないまま、無数の政治現象や社会的混乱と結びつけて論ずるような、いわゆる陰謀論に類するものも見られる。
たしかに、コミンテルンが多岐にわたる秘密の活動を実施し、ロシアの国益の追求にも深く関わっていた面があったことは紛れもない事実である。ソ連崩壊後、新たに陽の目を見るようになった史料の数々は、そのことを明瞭に示している。こうした点から言っても、共産勢力側の公式史観がいかに現実から遊離したものであったかは論を俟たない。
ただし、厚いヴェールに閉ざされていた秘密の側面が徐々に明らかになってきたとはいえ、それを過度に強調したり単純化したりして、史料から実証的に把握できる以上のことを論じようとする姿勢も厳しく排されなくてはならない。しかし残念なことに、実態が見えにくいこともあってか、コミンテルンに関しては巷間で誤解されている面も多いように感じられる。
かつてマルクスとエンゲルスは、共産主義という妖怪が徘徊しているとの有名な一文を物したが、今ではコミンテルンの亡霊がさまよって人びとに幻影を見せているのかもしれない。コミンテルンが結成されて約百年を経た節目にある今こそ強く求められるのは、バランスを欠いた極端な史観に囚われず、等身大の姿を描く努力である。革命の時代である20世紀はもちろん、グローバル資本主義と排他的なナショナリズムを特徴とする21世紀のあり様を深く見据え、また現在のロシアや東欧のみならず世界各地で大きく変化を起こしている国際秩序の動きについてその歴史的な淵源を探るうえでも、この特異な国際組織に対する正確な知識は少なからず必要であろう。
コミンテルンの歴史は、そのインターナショナリズムが諸外国のナショナリズムと衝突したきた歴史であると同時に、ソ連のナショナリズムとの葛藤の歴史でもあった。当然、クレムリンのなかで生まれ、その後もモスクワに本部が置かれたコミンテルンにとって、革命ロシアの党や政権との関係は切っても切れないものである。その関係が時代を追ってどのように変化していったのかは、研究者にとって大きなテーマであり続けてきた。
加えて、単一の「世界共産党」たるコミンテルン自体、モスクワにある本部機構、各国の共産党指導部、一般党員、さらには「フロント組織」、つまりコミンテルン本体との関係を偽装するなどして活動した外郭団体など、多層的な構造になっている。それらの関係性をも含めていくと、コミンテルン史の解明は複雑な連立方程式を解くことにほかならない。
本書は、こうした課題に改めて向き合い、等身大のコミンテルン像の一端に迫ろうとする試みである。もちろん、この小著で巨大組織のすべてを描き尽くすことはとうてい不可能である以上、目指すべきはコミンテルンがたどってきた道程を歴史的・思想的に俯瞰するマクロな視点に立脚しつつ、ときにミクロな視点を織り交ぜながら、その本質に迫ることだろう。
その際、コミンテルン内部の動向だけに終始するのではなく、ロシアの政治や外交、さらには他国の動向や国際関係の歴史的な変遷をもできる限り視野に入れ、コミンテルンを立体的に描き出すことを目指したい。それゆえ、本書は未公刊史料を縦横に駆使するというよりも、ソ連崩壊後に公刊された諸史料はもちろん、幅広い分野における研究者たちがこれまで積み重ねてきた成果にも目を配って吸収しつつ、コミンテルンを中心とした国際共産主義運動の実際について像を結ぶことに重心を置く。
なお本書では、コミンテルンを取り上げるに当たって、その前身であり、マルクスが深く関わった「第一インターナショナル」や、その後継組織である「第二インターナショナル」などの国際組織についても簡単に概観する(なお、「インターナショナル」は名詞として用いられるとき、国境を越えてさまざまな国の人びとが参加する国際組織を指す場合がある。また、「インター」と略されることもある)。言うまでもなく、マルクス主義の始祖であるマルクスの思想と行動への理解は、コミンテルンを読み解くうえで、欠かせないものだからだ。
マルクスが理論と実践の狭間で格闘した軌跡は、その後のマルクス主義者たちに多大なインスピレーションを与え続けた。もちろんマルクスの時代には存在しなかったような複雑な事象が20世紀に立ち現れることになっても、彼の弟子たちは師の教えを自分なりに解釈し、ときには大胆なアレンジを施しながら、目の前に広がる世界を根底から変革しようとした。
そうした19世紀以来の社会変革をめぐる長い試行錯誤の歴史のなかにおける、ひとつの壮大な「実験」としてコミンテルンを適正に位置づけることで、激動の20世紀を形づくった革命運動の一端がはっきりと姿を現すだろう。
ここで本書の構成について述べておきたい。
序章では、第一及び第二インターを経て、第三インター、すなわちコミンテルンが誕生するまでの経緯を追う。そのうえで、第1章では産声を上げたコミンテルンがヨーロッパ各国の労働運動に対して第二インターとの決別を迫り、各地に共産党が結成されていく様子をたどる。それとともに、本来は特定の加盟団体による全体の統治を認めないはずのインターナショナルの理念を外れて、コミンテルンが早々にロシア共産党の強い影響下のもと「ロシア化」を起こし、同党をヒエラルキーの頂点とするきわめて中央集権的な組織体制が姿を現し始めるまでを追う。
第2章は、ロシア十月革命に刺激を受けてヨーロッパ各地で発生した革命が次々と頓挫するなか、レーニンがヨーロッパとアジアを結びつける形で構想した独自の国際革命理論を取り上げる。そしてこの理論に基づいてコミンテルンが乗り出した最初期の東方革命、つまり1920年代初頭の中東での革命の顛末を俯瞰する。
第3章は、第一次世界大戦中にレーニンが19世紀ドイツの思想家ヘーゲルの哲学に接近したことなどに注目し、彼の革命思想の深層に迫る。そのうえで、とりわけ1920年のコミンテルン第2回大会以後、ロシア内外で革命が行き詰まりを見せるなか、レーニンが厳しい現実との格闘を通じて自らの思想をいかに適用したのか、またそれが以後の革命運動に与えた影響についても見ておきたい。
第4章は、20年代の初頭から後半にかけてヨーロッパで実践された「労働者統一戦線」戦術を中心に、当時のコミンテルンの動向を取り上げる。まず、この戦術の本質的な意義が、蜂起に逸る共産党左派の動きや、社会民主主義――議会制民主主義を通じた穏健な社会変革を追求する社会主義思想及び運動の一派であり、とりわけ19世紀末以降、ドイツ社会民主党を中心にヨーロッパにて大きな勢力を成す――への強い敵意、あるいはロシアの国益重視などによって当初から揺らいでいたことを確認する。
そのうえで、24年1月のレーニン死去によって本格化した党内での後継者争いが世界各地の統一戦線を激しく揺さぶった様子などを含め、最終的にこの戦術が放棄されるまでの過程を描く。加えて、この統一戦線の時期に、コミンテルンとロシアの諜報機関との協力関係が生まれ、また前者のフロント組織による大規模な活動が始まった様子にも触れる。
第5章は、党内闘争を制し共産主義世界の最高指導者に上り詰めるスターリンが、若かりし頃から取り組んできた民族論などに目を配りつつ、彼とコミンテルン及び国際共産主義運動の関係性がどのように形成されたかを探る。また、彼が20年代後半に主導した中国での革命の失敗や、ポーランドやイギリスとの関係悪化、あるいはウクライナ政策をめぐるコミンテルン内の混乱などといったソ連内外での緊張の高まりが、各国共産党にソ連防衛を第一の任務とする傾向を強めさせた経緯をたどる。
第6章は、1931年の満洲事変や33年のヒトラー政権誕生など、30年代に入ってソ連を取り巻く国際環境が一層緊迫するなか、コミンテルンが着手した大規模なフロント組織活動を取り上げる。また、コミンテルン第7回大会で採択された「人民戦線」戦術の成り立ち及びフランスやスペインや中国での適用の様子、さらには37年ごろから本格化したスターリンの「大粛清」によってコミンテルンが深甚な打撃を受けるまでを見ていく。
第7章は、39年の独ソ不可侵条約締結や41年の独ソ戦勃発など、独ソ間をはじめとする国際関係の激変に翻弄されるコミンテルンの姿を追う。そして、スターリンがコミンテルンの解散を決断した顛末とともに、その後のソ連のインターナショナリズムについても一瞥する。
それでは早速、コミンテルンをめぐる歴史のダイナミズムに迫ってみよう。
(まえがき、著者略歴は『コミンテルン』初版刊行時のものです)
