- 2025 02/06
- まえがき公開
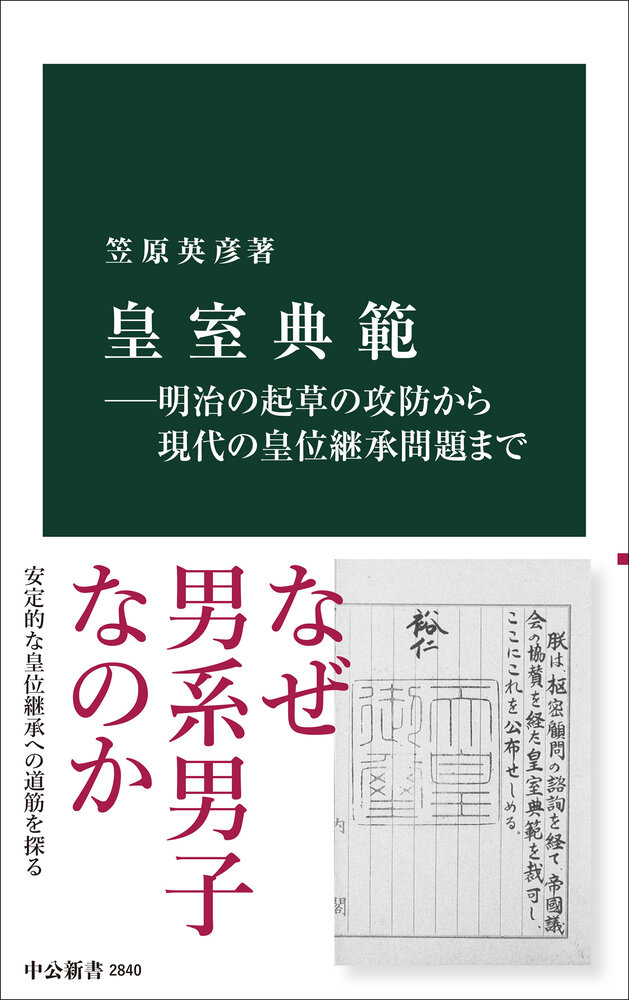
伊藤博文の主導で制定された明治の皇室典範。女帝・女系容認の可能性もあったが、皇位継承資格は「男系の男子」限定で、退位の規定もない。その骨格は戦後の皇室典範でも維持された。皇族男子の誕生は極めて稀で、皇族数の減少も続き、制度的矛盾が顕在化して久しい。小泉内閣時代に改正の検討が始まるも、進展はいまだ見えない。本格的議論の再開に向けて、皇室制度の専門家が論点を整理し、法改正への道筋を探る。 『皇室典範―明治の起草の攻防から現代の皇位継承問題まで』の 「はじめに」を公開します。
2001年12月、成婚9年目にして、皇太子夫妻(現在の天皇、皇后)に待望の第一子、愛子内親王が誕生した。ついで06年9月には、秋篠宮家に悠仁親王が誕生。皇位継承資格を有する皇族男子の誕生は、秋篠宮文仁親王以来41年ぶりのことであった。1990年代頃から、日本でも少子化に伴う人口減少が表面化し、皇室でもまた皇族の減少が顕著となった。
しかも戦後、皇位継承資格を嫡出に限定したうえ、皇室典範がそれを男系男子に限定したため、皇位継承資格者の確保は容易でなくなった。こうした現行の皇室典範は、明治の中頃に制定された皇位継承など皇室に関するわが国最初の成文法、明治皇室典範をおおむね踏襲し、戦後も半世紀以上にわたり維持されてきた。
ようやく今世紀を迎え、皇室典範の矛盾は皇位継承問題などとして議論されるようになったが、いまだ法改正に向けた見通しは立っていない。
古くは飛鳥時代から江戸時代まで、わが国史上には10代8人の女帝が在位した。しかし明治以降今日に至るまで、皇室典範は皇位継承資格を男系男子に限定し、いまだ安定的皇位継承に向けた道筋はつけられていない。また、古代より近世まで長らく認められてきた譲位の慣行は明治皇室典範において否定された。戦後、現行皇室典範もこれを引き継ぎ、終身在位制は比較的最近まで維持されてきたのである。
明治憲法(大日本帝国憲法)により、「皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ継承ス」と定められた。ここにいう「皇男子孫」とは、男系の男子のことであり、非嫡出子も含まれていた。男系男子に加え退位を認めない皇位継承ルールの変更は、伊藤博文の強力な政治指導の下に、1887(明治20)年の高輪会議で決定された。その歴史的経緯や政治的背景については第一章で詳しく述べたい。
しかしこれはあくまで政権中枢での決定であった。明治典範が起草された明治の前半においても、依然として官民双方に女帝容認を唱える意見が多く聞かれた。政府系新聞の記者として知られる福地源一郎は、多くの女帝誕生の歴史をふまえ、積極的に女帝容認論を展開した。民間の私擬憲法の多くも、女帝容認の立場をとっていた。
こうして1885(明治18)年末に宮内省が立案したとされる皇室法草案「皇室制規」には、「皇族中男系絶ユルトキハ皇族中女系ヲ以テ継承ス」と女系拡大論が説かれていた。もっともこれに対し、井上毅は翌86年に「謹具意見」を提出し、女帝容認論を一蹴した。そのため、つづく典範の草案、「帝室典則」以降、女帝容認論は姿を消した。
井上によれば、民権派の中にも女帝容認に批判的な意見は珍しくなかった。井上も注目した論客の島田三郎は、日本の女帝制には中継ぎとしての役割が期待されたのであり、西欧の女帝制とは本質的に異なるとしたのである。また島田は、女帝に一生独身を貫かせるというのは情理に反するが、皇婿(女性皇族の配偶者)を求めるとなると、人臣たる「女帝の夫」の存在はどうもわが国古来の夫婦観念になじまないとする。
井上がいうように、歴史上即位した女帝はいわば代理者の地位であって、一時の執政にすぎない。女系の天皇というのは、皇族女子が婚姻によりもうけた皇子女によって皇位が継承されることを意味する。女系天皇については、女帝の生んだ皇子女が夫の姓をつぎ、皇統が他に移ると認識されかねなかった。
このように、「謹具意見」に民権派の島田らの言説を引用した井上も、とりわけこの皇婿の問題に重大な関心を寄せた。いつの時代にも保守派により女系継承が警戒されるのは、まさに皇婿の問題がついて回るからにほかならない。近時も、政府の有識者会議が提示した選択肢に対して、自民党が婚姻後も皇族女子が皇室に残ることを認めながら、配偶者が皇族になることを認めないのは、そのためである。
明治皇室典範の起草に際して重要な皇位継承をめぐる論点とされたのは、皇位継承資格のほかに譲位の可否があった。実際の典範起草作業にあたった井上毅や柳原前光が譲位を規定すべきとしたのに対し、ときの最高権力者である伊藤博文がこれに強く反対したため、譲位の制度化は見送られた。
伊藤が皇室典範の注釈書としてまとめた『皇室典範義解』には、皇極天皇(7世紀に在位した女帝)に始まる「女帝仮摂」の慣行である譲位を、神武天皇から舒明天皇まで34世つづいた終身在位の「恒典」(不変の規則)により改めた、との解釈が記された。
戦後、現行皇室典範の起草過程においても、政府関係者や専門家により退位の可否が議論された。制度上、天皇が退位を欲した場合は摂政設置をもって代えるとされた。皇室典範の実質的な起草にあたった臨時法制調査会第一部会では、宮沢俊義ら憲法学者や法制局関係者により、退位制度を設けるべきとの見解が表明された。
一方、天皇側近や宮内省は、退位規定を設けることに反対した。同部会に参加していた宮内官僚の高尾亮一が著書『皇室典範の制定経過』に記したように、退位の問題は昭和天皇の戦争責任と密接に関連していたからにほかならない。宮内省は、昭和天皇が戦争責任を負って退位することだけは避けたかったのである。
GHQ(連合国最高司令官総司令部)は憲法とは異なり、皇室典範の起草については日本の主体性を認めていた。よってGHQは、憲法が規定する象徴天皇制との関連においてまず、皇室典範の起草に関心を寄せたのである。
GHQ民政局のサイラス・ピーク博士は、日本の歴史上に女帝は存在したが、女系は存在しなかったことに理解を示した。またピークは天皇の国政関与に結びつきかねない退位についても関心を寄せ、退位の制度化が昭和天皇に及ぼす影響にも言及した。
このように、皇室典範はその時々の政治的事情を反映して、様々な矛盾を抱え込み、戦後も長きにわたり見直されることなく、今日に至っている。しかし幸い今世紀に入り、小泉純一郎内閣の下で皇室典範の本格的検討が進められた。
2005年11月24日、小泉首相の私的諮問機関である「皇室典範に関する有識者会議」が提出した報告書には、「男系による継承を貫こうとすることは、最も基本的な伝統としての世襲そのものを危うくする結果をもたらす」とある。
これはもちろん、「皇位は、世襲のもの」とする憲法第二条の規定を尊重しており、世襲(親から子へ、子から孫へと受け継いでいくこと)を守るために、女性・女系天皇を認めたということになろう。男系か女系か、いずれが重要かということではなく、世襲こそが重要なのである。歴史を振り返れば、世襲王権は遠く継体・欽明(いずれも6世紀に在位した天皇)とその子らにより、たゆまぬ血統と婚姻の尊重の積み重ねのうえに成立した。
我々はやはり、2005年の原点に立ち返って議論を再開すべきであろう。
(まえがき、著者略歴は『皇室典範―明治の起草の攻防から現代の皇位継承問題まで』初版刊行時のものです)
