- 2024 12/24
- まえがき公開
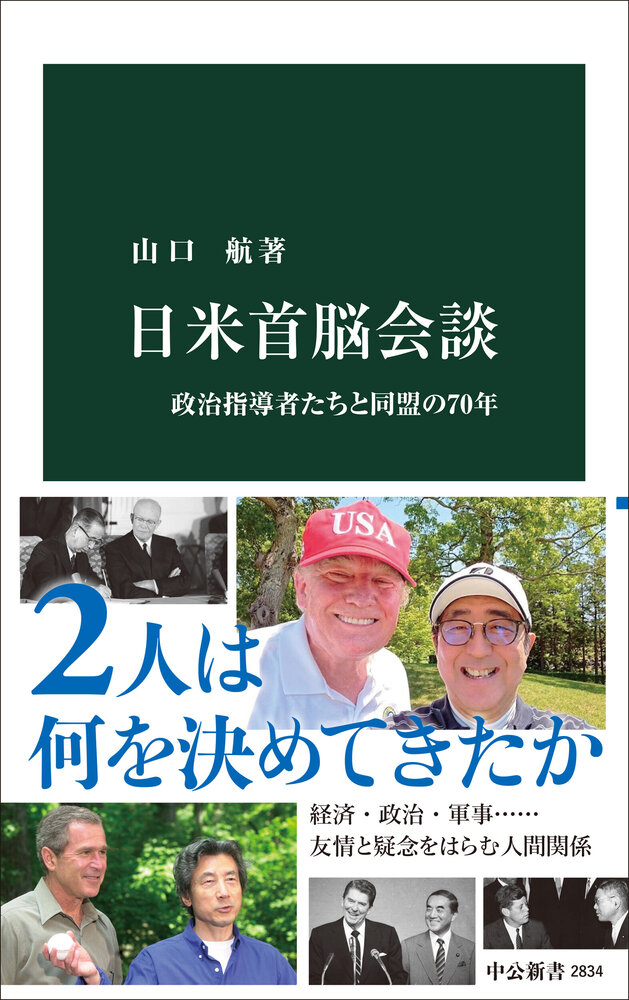
日本の「参勤交代」「物乞い」とまで当初揶揄された日米首脳会談。経済面での日本の台頭、米国の翳りから、貿易摩擦や安全保障問題を抱える関係、2国間を超えた国際社会でのパートナーへと変貌。他国と比しても会談頻度は増している。トップ同士の対話や人間関係は、何を生み、創ってきたか――。本書は、米国14人、日本28人の首脳による約150回に及ぶ会談を追い、70年以上にわたる日米関係を政治指導者を通して描く。
『日米首脳会談 政治指導者たちと同盟の70年』の 「まえがき」を公開します。
近衛文麿首相には秘策があった。日本とアメリカ合衆国との戦争を回避する秘策である。
1941年半ば、両国は破局の瀬戸際にあった。そこで事態を収束させるべく、近衛はフランクリン・ローズヴェルト米大統領と直談判をしようとする。もしこの史上初の日米首脳会談が実現していれば、あるいは、歴史が大きく変わったかもしれない。だが、これは幻に終わり、両国は太平洋戦争へと向かっていく。
直接目を見て話せばわかり合えると考えるのは人間の性だろう。今日の社会でも、メールらちや電話で埒があかなければ、一度会おうという話になる。部下同士でまとまらない話をトップ会談に懸けることもある。
外交でも、官僚レベルで結論が出ない懸案について、首相や大統領といった政治指導者同士の会談がしばしば行われる。
たとえば、1960年代末の沖縄返還交渉で、現地に配備されている核兵器の存在が争点となった。米国は撤去しても有事の際に再び持ち込むことを求めたが、日本は認めず、議論は平行線をたどる。最終的には佐藤栄作首相とリチャード・ニクソン大統領が対面し、核再持ち込みの「密約」を結んで、まがりなりにも決着する。
2017年2月には、安倍晋三首相が、日米同盟への不満を隠さないドナルド・トランプ大統領と会談を行った。最終的に発表された共同声明には、日本の防衛に対する米国のコミットメントや日米安全保障条約の尖閣諸島への適用などが明記され、基本的に日本の意向に沿うものとなった。
だが、トップ会談での決着は諸刃の剣でもある。1994年2月の細川護煕首相とビル・クリントン大統領の会談は交渉が決裂する。日本の市場開放をめぐり米国が数値目標を求めたのに対し、日本政府は拒否したからだ。日本が「ノー」と言えたことに溜飲を下げる向きもあったが、その後、日米政府の高官の接触が一時的に停止するなど両政府の関係は悪化した。
もっとも、首脳会談でこのような丁々発止の交渉が行われることは、むしろ少ない。
日米首脳会談は、1951年に吉田茂首相とハリー・トルーマン大統領がサンフランシスコで顔を合わせたのが最初である。これ以降、鳩山一郎、石橋湛山、羽田孜の3人を除き、すべての首相と大統領が日米首脳会談を経験している。その合計は約150回に及ぶ。たとえば、第2次安倍政権(2012~20年)の対面の2国間会談に限っても、安倍首相はバラク・オバマ、トランプ両大統領と23回の首脳会談を行っていた。これは、習近平中国国家主席との9回、朴槿恵・文在寅両韓国大統領との9回を大きく上回っている。
これだけ多くの前例があれば、型にはまった会談となるのも無理はない。
しばしば「首脳会談に失敗なし」と言われる。政治家が主役に見える首脳会談も、実は外交当局によって双方が満足するシナリオができており、基本的には成功するとの意味だ。無難に話し合いが終わることを期待し、具体的な内容はともかく、関係者は「成功」だったと強調するのがつねである。首脳が直接細かい交渉をすることはほとんどない。
交渉をしないのだとすれば、首脳会談には意味がないとのシニカルな見方があるのも当然だろう。
以上のように、首脳会談に対する見方は大きく二つに割れている。一方には、トップがリーダーシップを発揮し懸案をすべて解決してくれる、と過大な期待が寄せられることがある。他方では、官僚たちが何から何まで決めているのだから首脳会談はセレモニーにすぎない、とシニカルに過小評価する向きもある。
さらに、
だが、それらは実態と懸け離れた幻想である。
本書で明らかにしていくように、両国の政治家と外交官をはじめとする官僚が協同し、時に両国がせめぎ合うのが日米首脳会談なのだ。
本書は約150回を数える首脳会談を描くことで、70年以上にわたる日米同盟の変遷を論じる。日米同盟を論じた書籍は数あるが、意外なことに首脳会談を主題としたものはほとんどない。今日、両国政府ですら首脳会談の通算回数をカウントしていないのが実情である。
だが、外交には過去の経緯に拘束される側面がある。したがって、首脳会談の前例を知ることは、今日の首脳会談を読み解くうえで重要だ。
戦後、日本と米国は被占領国と占領国から、責任分担の問題や経済摩擦を抱える関係へ、そして、グローバルに協力するパートナーへと変化してきた。こうしたなか、日米首脳は、両国の「対等性」を意識しながら、そのときどきの関心事を議論し、信頼を培おうとしてきた。本書では政治指導者の目を通じて、日米関係をめぐる中心的な議論を明らかにしていきたい。
その際には、筆者が収集した日米両政府の機密解除文書などを用いる。一定の期間を経た首脳会談については、公文書の機密指定が解除され、当時報道されなかった実際のやりとりや言葉遣いが明らかにされつつある。
だが、とくに1990年代以降については、機密資料の開示が進んでいないため、当事者の証言やメディアの報道を中心に追っていく。もちろん、証言には記憶違いなどが含まれることもある。それでも、本書が基礎的な資料となることも期待して、近年の日米首脳会談も概観しておきたい。
もとより、本書は会談で扱われた議題を網羅し関係者全員を描くことはできない。そもそも、日米首脳会談のみで日米関係のすべての側面を論じ切ることも不可能だ。山の頂を見るだけでは、山を語ることができないのと同じである。いみじくも首脳会談は、英語で今日「
しかし、両国政府の会談の最高峰である首脳会談抜きに、日米関係は語れない。とくに「日本が米国に従属している」との議論は、多くの場合、そこに人間の顔が見えない。より具体的に言うと、米国の
トップ同士の会談が何を生み、何を創ってきたのか。本書は、顔の見える首相と大統領、その周辺に着目し、日米関係を捉える試みである。
(まえがき、著者略歴は『日米首脳会談 政治指導者たちと同盟の70年』初版刊行時のものです)
