- 2024 11/25
- まえがき公開
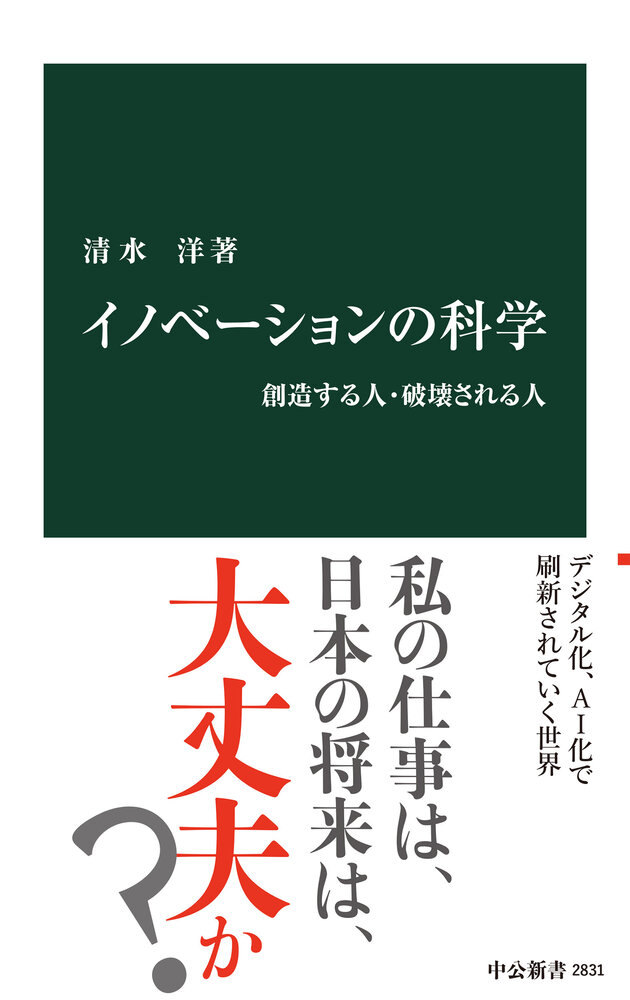
経済成長の起爆剤として期待されるイノベーション。将来への新しい希望であると同時に、「創造的破壊」と言われるように、人々のスキルや生活の基盤を壊す側面もある。本書は「人」の観点から検討し、創造の促進は元より、破壊の打撃を軽減する方策を考察する。創造する人、破壊される人の特徴とは? 抵抗と格差を縮小する教育投資、ミドル・シニア層のリスキリングとは? 希望と幸せのための二つのリスク・シェアとは? 『イノベーションの科学 創造する人・破壊される人』の 「まえがき」を公開します。
イノベーションとは、経済的な価値を生み出す新しいモノゴトを指します。創造的破壊(Creative Destruction)とも言われ、企業の競争力や経済成長の源泉になります。私たちの生活を豊かにしてくれるものでもあります。
創造的破壊と言うわけですから、古いモノゴトを、新しいモノゴトが創造的に破壊します。古いモノゴトがより良い新しいモノゴトへ置き換わるからこそ、生産性が高まるのです。
そしてそこには、創造する人がいると同時に、破壊される人もいます。新しいモノゴトが、古いモノゴトのためにスキルを身につけてきた人たちのスキルを破壊するのです。
*
1816年11月21日、イギリス・ノッティンガムのジェームズ・トウルの葬儀に3000人を超える人が参列しました。関係者以外の人の参列は禁じられていたにもかかわらずです。トウルは、4人の子どもと妻を持つ36歳の編み物職人でした。葬儀への参列が禁じられていたのは、彼が機械の打ち壊し運動のリーダーだったからでした。彼は有罪判決を受け、前日に死刑となっていたのです。当時のイギリスは産業革命が進展し、布の仕上げや綿手織りのプロセスで機械化が進んでいました。機械化によって自分たちの仕事が奪われることを恐れた熟練工たちは、集団で工場の機械を破壊する運動を起こしました。ラッダイト運動と呼ばれるものです。トウルの葬儀に多くの人が参列したのは、自分たちの生活が壊されてしまう不安と、それに立ち向かった彼への強い共感があったからでしょう。
一方で、機械を打ち壊された側の人々もいます。機械を発明していた人には教育水準が高かったり、裕福な家に生まれた人もいましたが、多くは、床屋や大工、あるいは手織り機の見習いとして働く普通の人でした。なぜ、彼・彼女たちは、機械を発明したのでしょう。
当時のイギリスは賃金が国際的にも最も高い水準で、人件費が高騰していました。その要因は需要の拡大に対する労働力不足です。1348年から49年のペストにより多くの人が死亡しました。16世紀中頃から人口は増加し始めましたが、労働需要の伸びに比べると供給は少なく、17世紀や18世紀になっても高賃金は続いていました。
繊維産業では、安価な労働力を武器に輸出を伸ばすインドとの厳しい競争もありました。それゆえ機械の創造は、生産工程を省人化して工場の競争力を向上させる、ひいては自分の暮らしを変える希望だったのです。最終的に打ち壊し運動は政府に鎮圧され、工場の機械化が進みました。この創造的破壊によって、それまでヨーロッパでも辺境の田舎だったイギリスは世界の工場になったのです。イギリスの人口は増え、寿命は延び、生活水準も大きく向上しました。この恩恵は広く社会に広がりました。
*
このエピソードは、本書のテーマをよく表しています。イノベーションには必ず、創造と破壊の二つの側面があります。そして、創造する人と破壊される人は、それぞれ別なのです。
創造する人は、もっと良いやり方があるはずだと考え、どんどん変革しようとします。その人たちにとって創造は希望です。しかし、それは他の誰かのスキルや、生活の基盤を破壊します。つまり、ある人の希望が、他の人の安定的な暮らしを壊してしまう側面があるのです。破壊される人は抵抗します。その抵抗や破壊されるスキルの保護が強いと、創造的破壊は広く導入されません。
もしかしたら、創造的破壊などない方が良いと考える方もいるかもしれません。しかし、それは経済成長の源泉であり、その恩恵は広く社会に行き渡って我々の生活を豊かにしてくれます。何より、創造的破壊は、資本主義のメカニズムとしてそもそも埋め込まれています。
人々を創造的破壊へと駆動するインセンティブが内包されていますから、止めようと思っても止められないのです。
創造する人も、破壊される人も、同じ社会に暮らしています。当然のことながら、創造する人を増やし、破壊されて苦しむ人を少なくし、お互いが包摂された社会をつくることが大切です。そのために、私たちはイノベーションにはどのような特徴があるのか、どのような人が創造しやすいのか、そして、破壊される人はどのような人なのかを考えなければなりません。
これらが分からないと、誰をどのように応援すれば良いのかも分かりません。この理解があるからこそ、どうすれば破壊される側を抵抗勢力にすることなく、創造的破壊を促進できるのか、対策を適切に講じることができるはずです。
これまで、イノベーションの創造の側面は繰り返し強調されてきました。一方で、破壊の側面はきちんと考えられてきたとは言えません。破壊の影響(例えば、産業の衰退や賃金の低下、失業対策)などについては、政府の政策担当者が考えるべきことであり、ビジネスパーソンは創造の側面だけを考えていれば良いと捉えられているのかもしれません。あるいは、イノベーションの大切さを説くには、破壊の側面はやや都合が悪い点もあるからかもしれません。ただ、創造と破壊は共起します。だからこそ、本書ではこれらを一緒に考えていきましょう。
イノベーションにおける創造と破壊を「人」の観点から見ていくことで、より上手く、より効果的にイノベーションと付き合っていけるはずです。創造するにはどうすれば良いのか、破壊されないためには何をすべきなのか、そして、包摂的な社会をつくるには何がカギとなるのかを考えていきましょう。これが本書のテーマです。
せっかちな方、忙しい方、あるいは今、立ち読みしているため時間がない方(できればこのままレジに急いで向かってほしいですが)のために、最初に本書のポイントを三つにまとめておきましょう。
1 創造する人と破壊される人は、それぞれ特徴がある
新しいモノゴトを創造する人は、若く、新参者で、内的動機づけが高いという特徴を持っています。
自分にはこのような特徴がないと落ち込む方がいるかもしれませんが、諦めないでください。このタイプの人が創造するのは、新しい知識や情報のアクセスが重要な役割を担うからです。同じところで同じことをしていては、新しいモノゴトは創造されにくくなりますが、意識的に新しいところ(できれば、自分が好きと思えるところ)に身を置くことで状況を変えることができます。
破壊が起こるのは、特定のスキルを新しいモノゴトに置き換えることがビジネス・チャンスになる領域です。一方、そこでは、在職年数が長い人や高齢の方など、その領域でスキルを蓄積してきた方が破壊されやすくなります。また、時間割引率が高い人(典型的には夏休みの宿題を後回しにしがちな人です)はキャリアを変えたり、次の仕事を見つけたりすることが難しく、破壊から立ち直りにくい傾向があります。
2 創造の恩恵は浸透に長い時間がかかり、破壊のダメージは短期間に局所的に出る
創造的破壊の直接的な利益は、一時的にそれを生み出した企業家に向かいます。しかし、より大きな恩恵は、長い時間をかけて社会全体へと浸透していきます。
一方で、破壊のダメージは短期間に局所的に強く出ます。イノベーションが社会に浸透する過程で、経済的な格差が一時的に大きくなるのもこのせいです。また、イノベーションの恩恵は人々に実感されにくい一方で、破壊のコストは特定の人々に短期的に集中するため深刻な実感を伴います。それゆえ、破壊される人は職を失うかもしれず、大きな声でその変化に反対します。コストが特定の人に集中すればするほど、その人たちの抵抗は強くなります。
そのため、イノベーションが達成される前にはどうしても抵抗運動が現れやすくなります。
3 リスク・シェアの仕組みをアップデートする
創造する人を増やしながら、破壊される人のダメージを少なくしていくためには、リスク・シェアのアップデートが重要です。リスクとは、望ましくないできごとが将来に起こりうる可能性です。イノベーションについては、それを生みだそうとして失敗するリスクと、イノベーションにより破壊されてしまうリスクという二つのリスクがあります。これらのリスクをシェアする仕組みが大切です。
リスクのシェアがなければ、新しいモノゴトを創造しようとする人は少なくなります。新規性の高いものへの挑戦は失敗する可能性が高いからです。同時に、リスクのシェアは破壊される人にとっても大切です。自分の生活を成り立たせている基盤を分散的にしてリスクの共有ができれば、安定性が増すからです。これまでは国や企業がリスク・シェアの中心的な役割を担ってきましたが、その機能が弱まり、個人がそのリスクを負うようになってきています。本書では、このアップデートのあり方を考えていきます。
現在、多くのイノベーションがアメリカから生まれています。スタートアップ企業が次々と生まれ、画期的な製品やサービスを展開しています。日本も低迷する経済を復活させるべく、アメリカと同じような制度を整えようとしています。確かに、ベストプラクティスに学び、取り入れることができる点があれば、模倣すれば良いでしょう。ただし、表面的に制度をなぞったとしても成果は上がらず、政策的に「やった感」を醸し出す以外の効果は期待できません。例えば、アメリカでは世界で最も巨額な国防費が、イノベーションを下支えしています。日本にはこれがありません。歴史的な経緯からもこの方向に舵を切ることはできませんし、するべきではありません。さらに、アメリカの社会をよく見てみれば、イノベーションは起きやすいものの、スキルを破壊された人々の立ち直りが難しく、人々の苦しみが大きくなっています。
目指すべきモデルがどこかに存在していて、それを探し当てるのではなく、どのような社会をつくりたいのかを考えて、社会の制度を発明していくことが大切です。本書はこの一助になればという思いで書かれています。
イノベーションの研究はおよそ100年前から徐々に始まり、1980年代から本格的に進展しています。これまでに積み重ねられた知見と最新の議論に基づき(つまり、巨人の肩の上にのって)創造的破壊の未来を考えていきましょう。どのようにしたら、私たちは創造的破壊ともっと上手くつきあえるのでしょうか。
(まえがき、著者略歴は『イノベーションの科学』初版刊行時のものです)
