- 2024 10/24
- まえがき公開
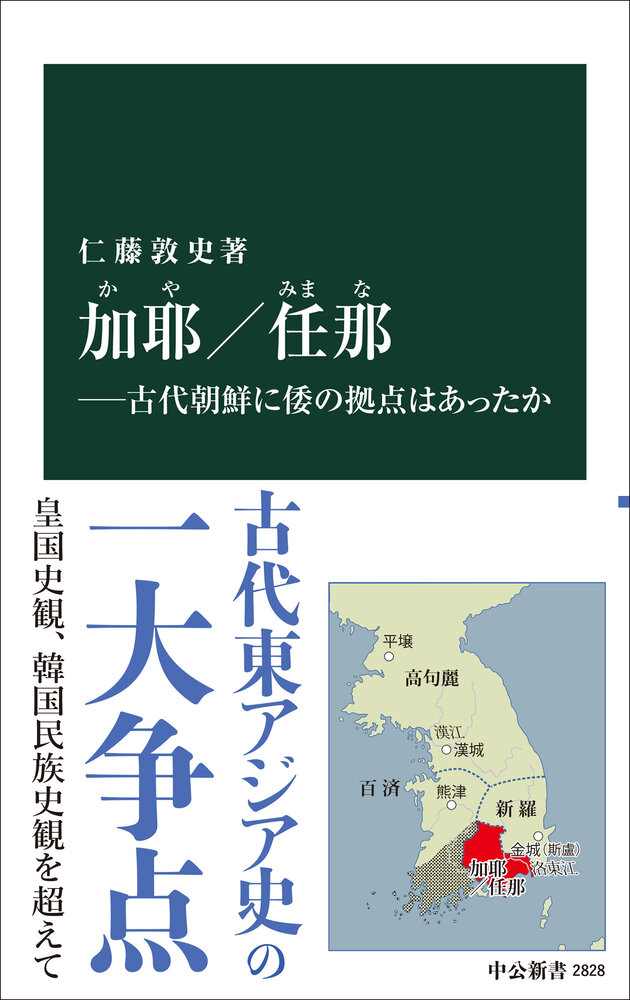
加耶/任那は3~6世紀に存在した朝鮮半島南部の小国群を指す。『日本書紀』は任那と記し、「任那日本府」の記述などから長く倭の拠点と認識されてきた。だが戦後、強く疑義が呈される。歴史教科書の記述は修正が続き、呼称も韓国における加耶へと変わる。他方で近年、半島南部で倭独自の前方後円墳の発掘が相次ぎ、倭人勢力説が台頭する。本書は、古代東アジア史の大きな争点である同地域の実態を実証研究から明らかにする。 『加耶/任那―古代朝鮮に倭の拠点はあったか』の 「まえがき」を公開します。
加耶とは、3世紀から6世紀にかけて、朝鮮半島南部にある洛東江(大邱、釜山を通り朝鮮海峡に流れる)の流域に存在した十数ヵ国の小国群を示す名称である。
しかし、加耶と表記し「カヤ」と読むことは、近年では歴史教科書でそう記されているとはいえ、日本ではなじみが薄い。加耶は6世紀後半に百済と新羅に東西から侵略され滅亡したこともあり、高句麗・百済・新羅という三国と比べて知名度は高くない。むしろ、日本では『日本書紀』の記載から「任那」と呼ばれることが多い。これら小国群が注目されるのは、古代朝鮮史のなかで重要であるだけでなく、倭の政治・経済・文化にも大きな影響を与えたからだ。
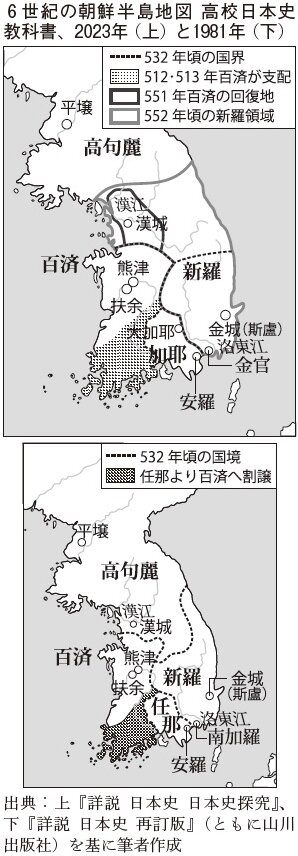
この小国群の歴史を正しく理解するうえでは、解決すべき大きな課題がいくつかある。
第1に、表記や名称が多様なことだ。
中国や朝鮮の古代史料には加耶と表記されるだけでなく、伽耶、狗邪とも記される。また、加耶と同源・同義として加羅、駕洛、迦羅、伽洛(すべて「から」と読む)の表記もあった。特に加羅は、5世紀に高句麗王が作らせた「広開土王碑」にも記される。このように、同一実体を示す用語が多様に存在し、一定せず、現代でも定着していない。
第2に、加耶の範囲である。
金官加耶・大加耶・阿羅加耶・非火加耶など、加耶が付いた小国は最大で7ヵ国に及ぶ。ただし、さまざまな異字や呼称があり、すべての国に加耶が付いたわけではない。時期にも考慮が必要だ。
また、洛東江の流域には多数の小国が存在したが、加耶や加羅はそのすべてを総称する地名ではない。加耶が歴史的にどのようなまとまりだったかを考えることが重要だ。
第3に、日本ではこの地域を任那という名称で呼び、教科書でも長く用いてきたことだ。
8世紀初頭に成立した『日本書紀』には、神功皇后から欽明天皇の間の外交記述に、「百済三書」と総称される3種類の百済系歴史書が直接・間接に多く引用されている。それに由来する表記として任那の記述が豊富に存在する。さらに、任那は個別の国名だけでなく、小国群の総称としても用いられている。
たとえば、『日本書紀』(欽明紀23年条)には、加羅・安羅など10ヵ国の総称として「すべては任那という」とある。『日本書紀』における任那の用例を素直に史実として位置づけてよいかが問題となる。
また、『日本書紀』は思想性を持って、任那諸国を一括し「官家」(朝貢の拠点)と表記し、隷属の対象として位置づける。だが、思想性があるからといって任那の記事を一切否定するのも極端な見解だ。
さらに、『日本書紀』は任那と加羅を並記する。先に触れた「広開土王碑」、中国の史書『宋書』、13世紀半ばに成立した朝鮮の史書『三国史記』にも、「任那加良」という両者を並記した表記が存在する。両者の地域的区別や、総称としての任那について考える余地がある。
他にも課題は多い。たとえば、「任那日本府」と呼ばれた存在だ。『日本書紀』に「百済三書」の引用から伝えられる任那日本府は、古い通説では大和朝廷の出先機関とされた。だが、近年では否定的な見解が多い。私見では、百済がこの地域を併合しようとしたときに、加耶諸国の独立を維持するため、それに抵抗した倭系の移住民(「韓子」や「韓腹」と表現される二世)ら反対勢力を百済側が意図的に呼称したものと考える。
加耶/任那をめぐっては、近年でも多くの問題を孕んでいる。本書では、史料に基づきながら、また、朝鮮半島における近年の前方後円墳や倭系遺物の発見による倭人の一部移住の可能性など考古学的発掘成果を含め、できるだけ客観的に加耶/任那の歴史と、古代の日本との交流関係を平易に述べることを目的としたい。
以下、本章の構成を述べておく。 序章は、入門と位置づけ、加耶/任那の記載がある基本史料の解説と、近世以降の古典的な研究の紹介、さらには研究上の問題点などを論じる。
第1章では、従来、倭による支配の対象としてのみ捉えられてきた加耶/任那の歴史を、朝鮮古代史の正しい文脈に位置づけることを試みる。神話・伝承から歴史への流れのなかでその前史を検討する。
第2章では、4世紀、加耶諸国が台頭し百済や倭と交渉を始めるが、その史実を解明する。
第3章では、5世紀、中国の王朝にも朝貢するようになった加耶諸国の発展と、倭や百済との交渉・抗争の歴史を考える。
第4章では、6世紀、百済と新羅の東西からの侵攻により、中心的な国であった金官・大加耶などが滅亡する歴史を描く。
第5章では、加耶諸国の滅亡後も、7世紀まで倭国は任那の「復興」や「調」の貢納を要求するが、その背景を考える。また、加耶の滅亡後に近隣諸国に与えたさまざまな影響を論じる。
終章では、最新の研究動向と本書の主張を記す。 この本を通読することによって、加耶/任那=加耶諸国に対して、従来のような倭の植民地的な見方をするのではなく、周辺諸国のさまざまな分野に影響を与えるようなきわめて重要な地域だったことを理解していただければ幸甚である。
(まえがき、著者略歴は『加耶/任那―古代朝鮮に倭の拠点はあったか』初版刊行時のものです)
