- 2024 09/20
- まえがき公開
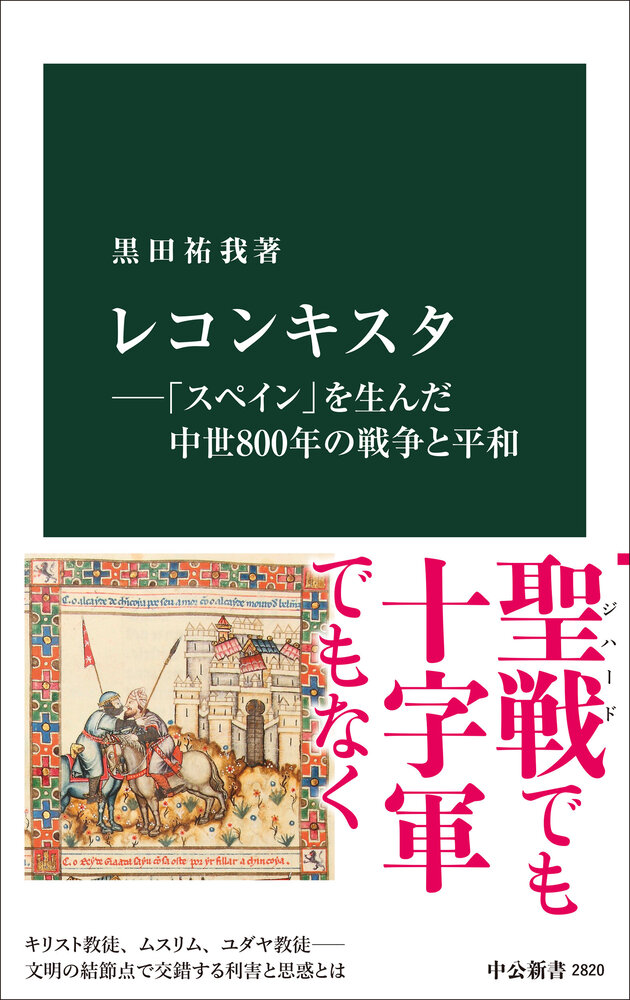
8世紀の初め、ジブラルタル海峡を渡ってイベリア半島、さらにフランスまでを席巻したイスラーム勢力。その後はキリスト教徒側が少しずつ押し戻し、1492年のグラナダ陥落でイスラーム勢力を駆逐した。この800年に及ぶ「聖戦」はレコンキスタの一語でまとめられてきた。だが、どちらの勢力も一枚岩ではなく、戦争と平和、寛容と不寛容、融和と軋轢が交錯していた。レコンキスタの全貌を明かす、初の通史。 『レコンキスタ―「スペイン」を生んだ中世800年の戦争と平和』(黒田祐我著)の「はじめに」を公開します。
スペインは、ヨーロッパにあるが、アフリカでもある。西洋でありながら、東洋(オリエンタル)的な要素も併せ持つ。なぜスペインではこのように他のヨーロッパ諸国とは異なるエキゾチックな文化が育まれたのであろうか。本書は、その答えを求めて、中世の歴史を探訪していく。
ところで、サッカーの試合などで目にする機会も多いスペインの国旗がどのようなものであるか、あなたはご存じだろうか。赤・黄色・赤の三つの配色の旗まではイメージできる人が多いであろう(ヨーロッパの旗には三つに色分けされたものが多いので紛らわしいが)。しかし実際に見てみると、国旗の真ん中あたりに、よく分からない複雑なシンボルが描かれていることに気がつくはずである。
シンボルの上部には、十字架のついた王冠があり、赤帯が巻きついた2本の柱に挟まれた真ん中には、盾の型をした紋章がある。紋章には砦、ライオン、黄色の地に四本の赤の縦線の入った盾、八方に広がる鎖状の盾があり、下の隙間にはザクロの実が小さく描かれている。これらは順にそれぞれ、カスティーリャ、レオン、アラゴン、ナバーラ、そしてグラナダという中世に興った五つの政治単位を象徴する。そして盾の真ん中には青地を背景に、18世紀から続く現在のスペイン王家ブルボン家の紋章(金のアヤメの花)が挿入されている。本書で扱う中世から現在に至るまでの、紆余曲折を経て成立したスペインの成り立ちが一目で把握できる紋章である。
ちなみに2本の柱は古代において「ヘラクラスの柱」と呼ばれた、ジブラルタル海峡を象徴する。赤帯には16世紀のスペイン帝国を率いた、神聖ローマ皇帝カール5世(スペインのカルロス1世)の用いたとされるモットー「プルス・ウルトラ(PLVS VLTRA:より向こう側へ)」が記されている。いわゆる大航海時代、西欧内の勢力図を飛び越え外の世界へと躍進する気概を示す、野心あふれるモットーである。
 スペイン国旗の紋章
スペイン国旗の紋章711年、イベリア半島のほとんどが、ダマスクスを本拠とするイスラーム王朝、ウマイヤ朝の版図に組み込まれる。それまで半島を支配していた西ゴート王国は、滅亡する。しかし半島の北部には、ウマイヤ朝に服従しない人々の社会が形成され、次第にその力を増していった。こうして、現在スペインとポルトガルが位置するイベリア半島では、この中世と呼ばれる時代の8世紀から15世紀末までの約800年の長きにわたって、キリスト教勢力とイスラーム勢力とがせめぎあった。この二つの宗教文明間のせめぎ合いは「レコンキスタ」という用語で総称されてきた。
こうしてイベリア半島の北と南に分かれて、相争った中世レコンキスタの時代、確かに政治的な思惑と宗教的な熱意が複雑に絡み合いながら、激しい対立が繰り返された。これは間違いない。しかし対立と並行して、多岐にわたる政治的、経済的、文化的な接触と交流も繰り返された。一見すると、二つの異なる宗教勢力が同じ半島を二分したように見えるが、そう単純ではない。複数乱立したキリスト教徒とムスリムの諸政権はどちらも入り乱れて一枚岩ではなく、同じ信仰を持つ「同胞」を排除するために異教徒と手を結ぶことは日常茶飯事であった。このような中世スペインのダイナミックな歴史を経て、現在のスペインはヨーロッパのなかで最も奇妙、かつ光と影のコントラストが激しい魅力的な国へと仕立てあげられた。
 アーモンドと砂糖を練り合わせたトレードの伝統菓子マサパン 日本ではマジパンあるいはマルチパンの名称のほうが有名かもしれない。その起源は諸説あるが、東方伝来という点ではほぼ一致している(筆者撮影)
アーモンドと砂糖を練り合わせたトレードの伝統菓子マサパン 日本ではマジパンあるいはマルチパンの名称のほうが有名かもしれない。その起源は諸説あるが、東方伝来という点ではほぼ一致している(筆者撮影)ヴァリエーションのある甘すぎるお菓子、柑橘類を多用するレシピの多さは、本書で扱うイスラーム世界との様々な接触の結果である。スペイン料理として誰もが知るパエリアで、なぜ米が使われるのか考えたことはあるだろうか。またこの料理は、なぜ黄色く色づけされているのだろうか。それは、イスラーム教徒の故地であった中東からアンダルス(イスラーム・スペイン)に持ち込まれた米やサフランという食材が中世に定着した結果なのである。
言葉も同じである。スペイン語は、古代ローマ帝国時代の公用語ラテン語が俗語化したものであり、フランス語やイタリア語とは近しい姉妹関係にある。しかしスペイン語には、おびただしいアラビア語からの借用語が組み込まれており、その数が4000語にのぼるというのが定説となっている。日本でも有名なハリウッド映画『ターミネーター2』のなかで、ターミネーターに扮するアーノルド・シュワルツェネッガーが「アスタ・ラ・ビスタ(Hasta la vista)」というスペイン語(「また会うときまで」の意味)を話すが、この「~まで」を意味する前置詞「アスタ(Hasta)」もアラビア語起源である。この前置詞がないと、私たちはスペイン語で別れの挨拶を交わせなくなってしまうのである。
さあ、いまのスペイン文化を心から堪能するために、中世800年間の歴史をひもとく旅に出よう。
(まえがき、著者略歴は『レコンキスタ―「スペイン」を生んだ中世800年の戦争と平和』初版刊行時のものです)
