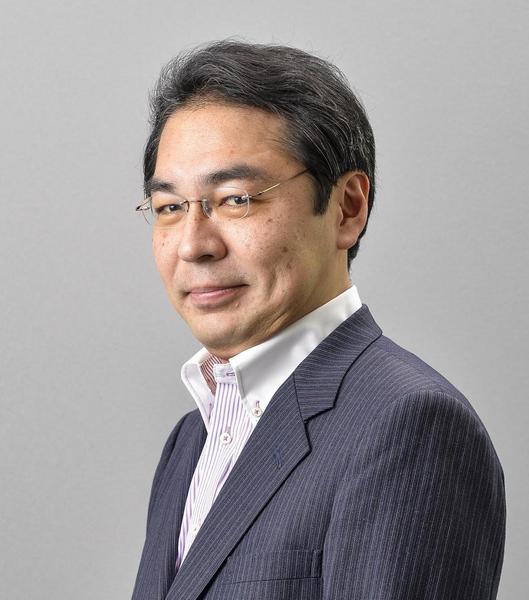- 2019 04/22
- 著者に聞く
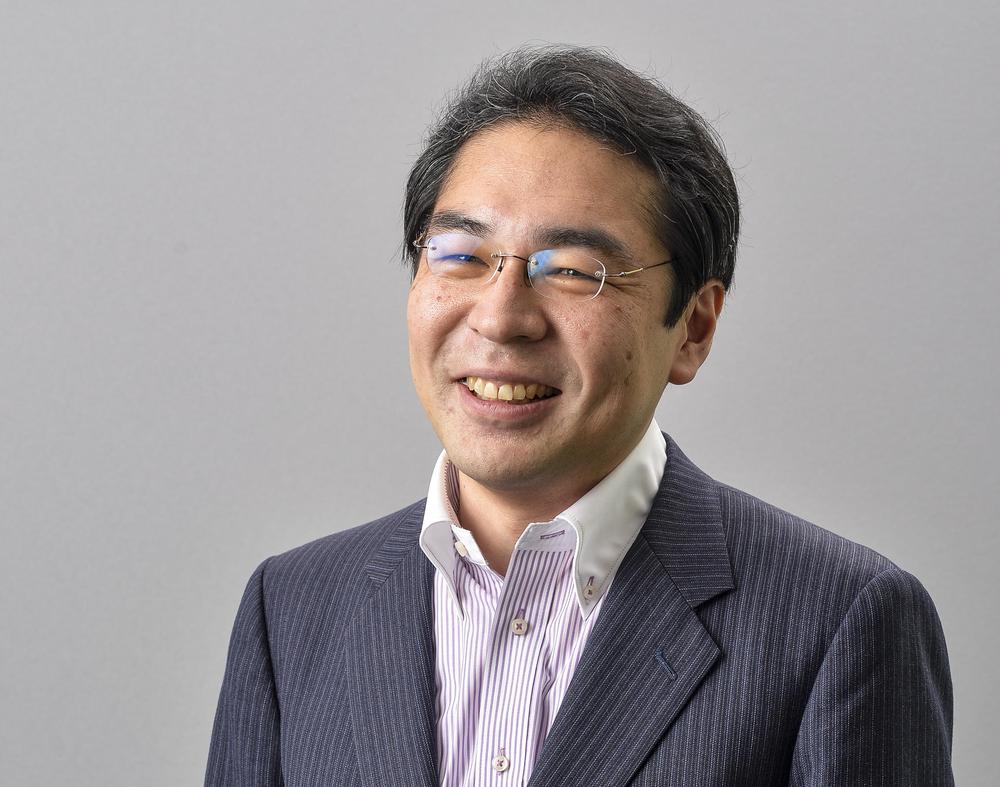
小笠原群島の南方に位置する硫黄島。その知られざる歴史を入植の時期から悲惨な戦争、そして戦後の軍事基地化していくまでを鮮やかに描いた話題作『硫黄島 国策に翻弄された130年』。その著者である石原俊さんに、本書に関して話をうかがった。
――石原先生は、『近代日本と小笠原諸島』(平凡社)や『〈群島〉の歴史社会学』(弘文堂)、そして新刊『硫黄島』と島をめぐる研究で知られています。このテーマを選んだ理由をお教えください。
石原:まず何より、研究の空白領域だったからです。小笠原群島に関しても硫黄列島に関しても、その近現代を包括的に記述する社会史的なあるいは歴史社会学的な研究は、近年までほとんどありませんでした。もちろん、小笠原群島の幕末維新期に関しては、近世史や外交史の専門家が著作を発表していましたが、それらが扱ったのはごく限られた期間でした。硫黄列島に関しては、外交史・日米関係史の立場からの著書はありましたが、そこで生きた人びとの歴史経験に注目した研究はまとめられていませんでした。
最初の単著『近代日本と近代日本と小笠原諸島』(2007年)では、19世紀に入植者、捕鯨船からの脱走者、漂流者、海賊などとして、世界各地から小笠原群島に集まってきた人びととその子孫たちに、照準を当てました。かれら(現在の「欧米系島民」)が、近代日本国家のなかで、また敗戦後の米軍占領下において、どのような歴史経験をたどってきたのか、150年の社会史を記述したこの本は、500頁を超える大部となりました。
いっぽう『〈群島〉の歴史社会学』(2013年)では、前著で正面から扱うことができなかった、小笠原群島の日系島民(現在の「旧島民」)と硫黄列島民の歴史経験にも論及しました。また、これら北西太平洋に浮かぶ小さな島々の社会史を、太平洋世界の200年の近代、さらには大西洋世界を含む海洋世界の500年の「長い近代」のなかに位置づけようとしました。特に小笠原群島は、16世紀から400年におよぶ海洋グローバリゼーションの波が、帆船時代の最終期に到達した地点のひとつにあたり、単なる「日本の辺境」といった視点からは決定的に見落とされてしまう、大きな世界史的背景をもっているからです。
そして、このたびの『硫黄島』は、「地上戦」イメージにすっかり覆い尽くされてきた硫黄列島の歴史を、「地上戦」史観から解放することを目的として書かれました。本書の特徴は第一に、これまで通史がまとめられていなかった硫黄列島の近現代史を、島民の経験を軸とする社会史として描き出したこと、第二に、硫黄列島の歴史経験を、現在の日本の国境内部にとどまらないアジア太平洋世界の近現代史のなかに位置づけようとしたことにあります。
――歴史社会学の観点から本書は書かれています。この学問分野の特徴などは何でしょうか?
石原:時代や国によって歴史社会学の位置づけはやや異なりますが、現在の日本では、歴史社会学は歴史学ではなく社会学の一領域だとされています。
社会学は、近代以後の社会事象・社会問題であれば、何でも対象にできる学問分野です。たとえば、都市社会学、家族社会学、医療社会学、環境社会学といった、さまざまな連字符(ハイフン)社会学があります。それぞれに膨大な調査研究の蓄積がある領域ですが、ただ、これら連字符社会学が歴史的な側面を扱うときに、研究者が生きている同時代の視点から、過去の事象を過度に整理・平板化してしまう場合があります。
これに対して歴史社会学は、ある時空間における歴史経験を、現在の観点から一方的に評価するのではなく、過去を生きた当事者の意識や実践の意味にできるだけ寄り添いながら捉えることを重視しています。私もまた、社会学者の肩書をもつ者ですが、本書は先にふれた2つの著書以上に、「歴史書」に近いスタイルになったと思います。ただ、本書に狭い意味での歴史学者の著作とやや異なる点があるとすれば、オーラルヒストリーとりわけ当事者のライフヒストリー(生活史)を重視していることでしょう。
むろん、歴史的事実の妥当性を高めるための「史料批判」に相当する手続きは、本書でも可能な限りおこなっています。一方で本書は、証言者がたったひとりしか残っていない事象についての語りや、1~2点の文書にしか書かれていない記録などを、「史料」から排除していません。コンテクストに照らして一定の妥当性や迫真性を持つ語りや記録を、積極的に採用しています。そうした意味でも、本書は日本語圏の文脈では、「歴史社会学」の書物だと言えるかもしれませんね。
――本書は副題にもあるように、「国策に翻弄された130年」を描いています。入植・開発の時期から、日米の凄惨な戦場となり、島民が「偽徴用」により大変な被害を受けた様子、そして戦後は米軍、続いて海上自衛隊の管理下に置かれたため住んでいた人々が戻れない現実までが、周到にまとめられています。改めて、この130年を振り返って感じたことなどはございますか?
 米軍が硫黄島占領後、桟橋を作るために沈めた船の残骸
米軍が硫黄島占領後、桟橋を作るために沈めた船の残骸石原:20世紀の世界を大きくつかむキーワードを3つ挙げるとするならば、それは本書のオビにある言葉、「帝国」「戦争」「冷戦」だと思います――もうひとつの重要なキーワード「社会主義」は、「冷戦」に含めることができるでしょう――。そのなかにあって硫黄列島民は、アジア太平洋世界の「帝国」「戦争」「冷戦」の最前線に置かれ続けました。
20世紀の前半、硫黄列島は日本帝国の典型的な「南洋」植民地として発達していきます。硫黄列島に作られたプランテーション社会は、あの広大な南洋群島(ミクロネシア)を含む、日本帝国の「南洋」植民地開発にとって、事実上のモデルとなりました。20世紀半ば、硫黄列島は日米の総力戦の最前線として利用され、島民は強制疎開または地上戦への動員を強いられます。そして敗戦後、硫黄列島は沖縄や小笠原群島とともに、日本の主権回復・復興と引換えに、米軍の排他的な利用に提供されました。
約半世紀前の1968年、小笠原群島とともに硫黄列島の施政権が日本に返還されました。しかし日本政府は、硫黄島を自衛隊に軍事利用させ始め、島民に引き続き帰郷を認めませんでした。硫黄列島は、軍事利用のために75年にわたって島民全体が帰郷できていません。これは、世界でも類例をみない異常事態です。
硫黄列島民のたどった130年は、日本本土にとって一方的に都合のよい歴史像、すなわち「立派に耐えた玉砕の島」といった地上戦イメージや、「焦土から復興へ」というおなじみの戦後イメージに対して、激しい揺さぶりをかけてきます。強制疎開前の硫黄列島民の大多数は、たしかに拓殖会社の搾取に苦しんでいましたが、魚や鶏卵など豊富なタンパク源を常食していました。他方で強制疎開後・敗戦後、島民の多くは生業の基盤のない本土で、最低限の衣食住さえ満たせない辛酸をなめつくしました。これは、農地解放・復興・高度経済成長によって戦前より戦後の生活のほうが楽になったという、日本の一般の庶民感覚と大きく異なる経験・記憶です。
硫黄列島は、大多数の日本人が見ないようにしてきた20世紀の「もうひとつの」姿、「帝国」「戦争」「冷戦」の世紀であった20世紀とはどのような時代であったのかを、その最前線からわたしたちに突きつけてくる場所なのです。
――刊行後の反響などをお教えください。
石原:新聞・雑誌などの紙メディア、ブログやツイートやコメントサイトなどのインターネットメディア、そしてお手紙や口コミ、いずれも大きな反響をいただき、驚いています。毎日新聞に著者インタビューを掲載いただいたほか、読売新聞、日経新聞に書評が掲載され、朝日新聞の「天声人語」でも本書の内容に関連する拙談話が使われるなど、全国紙で紹介を受けました。また多くの地方紙にも、共同通信から配信された短評が掲載されました。週刊誌でも次々と紹介いただいています。
ネット上やお手紙、口頭でいただいた反響の内容としてはまず、戦前の硫黄島に定住者の社会があり、島民が強制疎開させられたり地上戦に巻き込まれたりしたことを知らなかった、東京都下の島に軍事利用のために戦後75年も島民が帰れない島があるのを知らなかった、といった素朴な驚きを示す感想です。強制疎開前の硫黄島が日本帝国下のコカの一大産地だったことも、多くの読者にとってかなり衝撃的な史実だったようです。
次に、本書の視座や着眼点を評価いただくコメントが多かったですね。硫黄島といえば地上戦といった史観から解放された、硫黄島という場所からこれほどの普遍性をもって近現代の世界史を語ることができるのに驚いた、といった反応です。
そして最後に、関連領域にかなり精通した読者や専門家・研究者からの反応ですが、硫黄島のプランテーションのシステムが日本帝国の「南洋」開発の事実上のプロトタイプになったことや、島民が硫黄島産業株式会社の役員らによって「偽徴用」され地上戦に巻き込まれた件、あるいは施政権返還後に日本政府当局が硫黄列島民を帰島・居住させない方針を既成事実化していくプロセスについて、よくぞここまで調べあげて書いてくれたという趣旨のお声をいただきました。
――本書にも登場する新井俊一さんが亡くなったとうかがいました。どうにか「偽徴用」から逃れた方です。島民の現状や想いなどについてお考えをお聞かせください。
石原:読者といえばもう一点、何より島民のことを忘れてはなりません。本書の出版は、島民の同郷団体である「全国硫黄島島民の会」の方がたをはじめ、多くの当事者に喜んでいただきました。私もそれがいちばん嬉しかった。さらに驚いたのは、芥川賞作家の滝口悠生さんから突然、本書を読んで感銘を受けたというメールをいただいたことです。滝口さんの母方のお祖父さまとお祖母さまが、硫黄島から強制疎開させられた島民一世にあたり、新井俊一さんの親戚に当たられるとのことでした。それからしばらくして滝口さんから再びメールがありました。新井さんが亡くなられたという知らせでした。
残念ながらいま、島民一世の方がたは、次々と亡くなったり、体調を崩されたりしています。強制疎開前の生活経験の記憶や地上戦に動員された記憶をもつ、狭い意味での島民一世は、1930年代前半以前に生まれた方がたですが、そうした意味での一世の存命者は、非常に少なくなってしまいました。本書はこの方がたへのインタビュー調査なしには書けませんでしたが、私がおこなった調査は、文字通りギリギリのタイミングだったのかもしれません。
そして日本政府当局は、硫黄列島に島民を帰すことなく、島での生活経験の記憶が消滅する時を待っているかのようです。このかん小笠原村は、硫黄島平和祈念会館を建設し、島民が島内で宿泊できるような環境整備に努めてきました。ところが、年に最大3回実施される島民の墓参のうち1回(自衛隊機による墓参)は日帰りであり、ほか2回の墓参(船による墓参と自衛隊機による墓参が1回ずつ)においても、島民が島内で宿泊できるのは、たった1泊だけなのです。その3回の墓参さえ、さまざまな理由によって中止になることがあります。ここは国会や内閣がイニシアチブをとって、希望する島民が数週間、硫黄島内で過ごすことができるように、防衛省・自衛隊はじめ関係諸方面を説得すべきです。
また、自衛隊や米軍の訓練場として排他的に使用されている硫黄島に島民を帰還させることが難しいのなら、日本政府はせめて、無人島となっている北硫黄島に最低限のインフラを整備し、希望する硫黄列島民が一年のうち数週間から数ヵ月間、生活できる環境を作るべきでしょう。
硫黄列島民は、冷戦体制から大きな利益を得てきた日本の国家と社会が、一方的に矛盾を押しつけられてきた存在です。硫黄列島問題は、国内最大の戦後補償問題のひとつなのです。島民一世にとっては、もう時間がありません。日本政府と本土住民は、硫島民が戦時から戦後にかけて経験してきた苦難に対して、せめてもの償いをする必要があるのではないでしょうか。
――これからのお仕事について、お教えいただけますか。
 摺鉢山からの眺望
摺鉢山からの眺望石原:ひとつは硫黄列島に限らず、日本帝国の南方離島からみた戦争(総力戦)と戦後(冷戦)の比較史研究を展開したいですね。このプロジェクトでもまた、強制疎開/軍務動員、占領、帰還/離散がキーワードになってきます。
本書でもふれましたが、アジア太平洋戦争の末期、米軍はミクロネシア(南洋群島)からフィリピン、硫黄島、続いて沖縄諸島へと侵攻しました。いっぽう日本軍は、米軍のあらゆる侵攻ルートを想定し、小笠原群島、硫黄列島だけでなく、沖縄諸島、先島諸島、大東諸島、奄美諸島、大隅諸島、伊豆諸島などで、女性と高齢男性・少年男子を強制疎開させ、10代後半から50代の男性を軍属として島に残留させました。こうした方針が最初に策定されたのは、南洋群島だったことがわかっています。これら日本帝国の南方離島は、本土決戦に備えるために、かなりシステマティックなかたちで「捨て石」にされていったといえます。
硫黄島の地上戦をめぐって島民がどのような境遇を強いられたのかは、本書で書いたとおりです。また、民間人の疎開が完了する前に地上戦が始まった沖縄島のことも、よく知られています。しかし、その他の南方離島、たとえば先島諸島、大東諸島、奄美諸島、大隅諸島、伊豆諸島とその島民らが強いられた歴史経験は、日本社会ではほとんど知られていません。敗戦後、これらの島々は、早期に施政権が日本に返還された伊豆諸島を例外として、米軍による直接統治が行われたために、島民の帰還や社会の再生は容易ではありませんでした。
それから、本書『硫黄島』と並べられるような、小笠原群島史(父島・母島中心)の新書を、いずれは書いてみたいですね。『近代日本と小笠原諸島』や『〈群島〉の歴史社会学』を下敷きにしつつ、最新の国内外の研究成果を取り入れて。
――読者へのメッセージがあれば、ぜひ。
石原:硫黄島は、日本軍将兵の遺骨が現在も8000体以上埋まっている、「終わらない戦争」の現場です。いっぽう「終わらない戦争」というとき、硫黄列島に半世紀以上も定住社会が存在していたこと、島民の約9割が強制疎開の対象となった事実は、まだまだ知られていません。「偽徴用」も含め103人の硫黄島民が地上戦に動員され、そのうち93人が亡くなった事実は、さらに知られていない。
そして忘れてはならないのは、硫黄列島は「終わらない冷戦」の現場でもあることです。硫黄島のように、第二次世界大戦の戦中から冷戦期を経て現在に至るまで、一つの群島の島民全体が軍事利用のために故郷に帰還できない場所を、私は聞いたことがありません。
本書で描き出したように、硫黄列島民は、単なる歴史の客体だったわけではありません。かれらは日本や米国といった国家の都合によって翻弄されながらも、この130年間をなんとか生き抜いてきたのです。にもかかわらず、日本社会は硫黄列島民に押しつけてきた矛盾や痛みを忘れ続け、さらにはかれらの存在そのものをも忘れ続けてきました。
硫黄島は、近現代日本の姿を、背中から見るような場所です。硫黄列島をめぐる適切な歴史認識の構築は、まだまだ端緒についたばかりです。高校や大学の歴史教育のなかに硫黄列島の歴史経験を位置づける作業は、まったく手がつけられていません。本書を手にとっていただいたみなさまは、政治的・思想的立場を超えて、硫黄列島とその島民の歴史経験を、社会の記憶と記録のなかで正当に処遇していくために、お力を貸していただきたいと思います。