- 2018 10/09
- 日本ノンフィクション史 作品篇

本連載は加筆・修正の上、中公新書『現代日本を読む―ノンフィクションの名作・問題作』として2020年9月に刊行されました。現在、好評発売中です。連載第3回以降の記事は書籍でお楽しみください。
■「心の中で言っていることを文字にすると、ああなるんだもの」
まず意図的な品切れを疑われた『苦海浄土』だが、1972年には講談社から文庫化されている。しかし、巻末に寄せられた渡辺京二の解説が物議を醸した。
《私のたしかめたところでは、石牟礼氏はこの作品を書くために、患者の家にしげしげと通うことなどしていない。これが聞き書だと信じこんでいる人にはおどろくべきことかも知れないが、彼女は一度か二度しかそれぞれの家を訪ねなかったそうである。「そんなに行けるものじゃありません」と彼女はいう。むろん、ノートとかテープコーダーなぞは持って行くわけがない。》
実は渡辺自身にとってもその事実はおどろきだったという。
《瞬間的にひらめいた疑惑は私をほとんど驚愕させた。「じゃあ、あなたは『苦海浄土』でも……」。すると彼女はいたずらを見つけられた女の子みたいな顔になった。しかし、すぐこう言った。「だって、あの人が心の中で言っていることを文字にすると、ああなるんだもの」。》
渡辺は『苦海浄土』と改題される前の「海と空のあいだに」の連載媒体となった同人誌『熊本風土記』の編集者であり、その後も長く石牟礼と二人三脚の活動をしたパートナー的存在だった。この解説も真相を暴露するというよりも、石牟礼のためを思って書かれている。というのも、石牟礼自身が単行本の刊行1年後のノートにこう書いているのだ。《誰も彼も、もうすっかり聞き書リアリズムだと思いこんでいる。/あんまりおもいこまれると、つまり私の方法論にこうもすっかりみんな完全にだまされてしまうと、がっかりする。不本意だが、著者自身が、解説、苦海浄土論を書いて、方法論のヒミツを解きあかさねばならないであろうかと考える》(米本浩二『評伝 石牟礼道子』より)。
「方法論」という言葉を石牟礼は使った。確かに1960年1月に『サークル村』に発表された最も初期の短編作品は「奇病」と題されていた。しかしそこには「水俣湾漁民のルポルタージュ」と銘打たれてもいたのだ。そして『熊本風土記』に連載されたときに「奇病」はタイトルを変えられてその第5話「海と空のあいだに――坂上ゆきのきき書より」となり、『苦海浄土――わが水俣病』に収められたときにさらに「ゆき女きき書」となっている。つまりその作品がルポルタージュであり、聞き書きだと周囲が思った最大の原因は、他でもない、石牟礼自身にある。自分自身がそう書いているのだ。
ただ、それが全面的に石牟礼自身の発案とは言いにくいところもある。戦中には従軍報告が多く書かれたルポルタージュは、戦後一転して民主化運動のなかで多用されるスタイルとなった。民主主義の主体である「民」の声を聞き、姿を描く。『サークル村』もその流れを汲んでおり、「創刊宣言/さらに深く集団の意味を」では文化を個人のものとみなすのではなく、集団的な創造とすることが謳われており、聞き書きを方法として特定集団のあり方の全体像を描き出すルポルタージュが試された。
「ゆき女きき書」はまさにそうした方法の適用だった。
《――うちは、こげん体になってしもうてから、いっそうじいちゃん(夫のこと)がもぞか(いとしい)とばい。見舞にいただくもんなみんな、じいちゃんにやると。うちは口も震ゆるけん、こぼれて食べられんもん。そっでじいちゃんにあげると。じいちゃんに世話になるもね。うちゃ、今のじいちゃんの後入れに嫁に来たとばい、天草から。》
方言をそのまま書くことは集団の声をそのまま伝え、創作を個人のものから集団のものに変えるための方法とみなされていた。『苦海浄土』は『サークル村』文学運動のなかで「聞き書き」による「ルポルタージュ」と名乗る必要があり、石牟礼もそれを選んだ。
しかしその策があまりにも功を奏してしまった。実際には声をテープレコーダーで記録して忠実に再現するような方法までは採用していない。心のなかの声を代弁して語りとして描いた作品だったが、大宅賞の選考委員は選評で、誰一人、この作品が「聞き書き」による事実の記述を踏まえていることを疑っていない。臼井吉見が《魂の記録》、草柳大蔵が《事実を突き破るもの》という表現を使っているが、それらも聞き書きを疑うというよりもジャーナリズムの作品として高く評価するという意味合いだ。
うがった見方だが、石牟礼が大宅賞を辞退した理由のなかには、それがノンフィクションの賞に値するか、著者自身としても自信を持てなかったことがあったのではないか。たとえば翌年に大宅賞を受賞するイザヤ・ベンダサン『日本人とユダヤ人』は作者がユダヤ人という触れ込みであったが、本当の著者は訳者である山本七平だった。にもかかわらず授賞式には代理人と名乗る人物が登場し、平然と大宅壮一ノンフィクション賞を貰っている。もっとも著者が偽ユダヤ人であったことよりも、作品自体がノンフィクションではなかったことのほうが衝撃は大きいかもしれない。石牟礼はそんな結果になることを恐れて、熊日文学賞を辞退したが、その後も聞き書き説が全国区的に独り歩きし、話題の大宅賞まで受賞することになったことをさすがに気にした。だからこそノートに逡巡する気持ちを記したのではなかったか。
渡辺との間で、どこまで「方法論」について腹を割った話があったのかはわからないが、結果としては逡巡する著者に代わって「方法論のヒミツ」を渡辺が公表することになった。案の定、『苦海浄土』が聞き書き作品だと思い込んでいた人は驚くことになるが、渡辺はそれによって作品の価値が消失しないように『苦海浄土』の正しい読み方を提示する。
《実をいえば『苦海浄土』は聞き書なぞではないし、ルポルタージュですらない。ジャンルのことをいっているのではない。作品成立の本質的な内因をいっているのであって、それでは何かといえば、石牟礼道子の私小説である。》
渡辺は「私小説」という言葉に多くの含蓄をもたせている。
《『苦海浄土』はたちまち、公害企業告発とか、環境汚染反対とか、住民運動とかという社会的な流行語と結びつけられ、あれよあれよという間に彼女は水俣病について社会的な発言を行なう名士のひとりに仕立てられてしまった。……
しかし、それは筆者にとってもこの本にとっても不幸なことであった。そういう社会的風潮や運動とたまたま時期的に合致したために、このすぐれた作品は、粗忽な人びとから公害の悲惨を描破したルポルタージュであるとか、患者を代弁して企業を告発した怨念の書であるとか、見当ちがいな賞讃を受けるようになった。》
『苦海浄土』はそうした社会的風潮に迎合する作品ではない。渡辺は《粗雑な観念で要約されることを拒む自律的な文学作品として読まれるべきである》とも評している。そこで注目されるのは、聞き書きを装う方法論の、周囲をだますようなネガティブではない側面についてである。石牟礼は少女のようなあどけなさで《「だって、あの人が心の中で言っていることを文字にすると、ああなるんだもの」。》と述べたという。石牟礼の聞き書きとは心のなかの声ならぬ声を「聞いて」本人に代わって書くことなのだ。
こうした書き方について石牟礼自身が著した自伝『葭の渚』のなかにも記述がある。
《当時、私は患者さんたちと同じ運命共同体の中に幾重にも入っていくような感覚になっていて、世界史の動向を全身全霊ではかっている気持ちだった。
「こやんこつばあんたは体験しよっとよ、忘れちゃならん。患者さんたちが一所懸命語んなはっとば、ちゃんと耳に入れとかんばいかんよ」
執筆にあたって、私はそう自分に言い聞かせていた。患者さんの思いが私の中に入ってきて、その人たちになり代わって書いているような気持ちだった。自然に筆が動き、それはおのずから物語になっていった。》
■内面を描くための「私小説」という方法
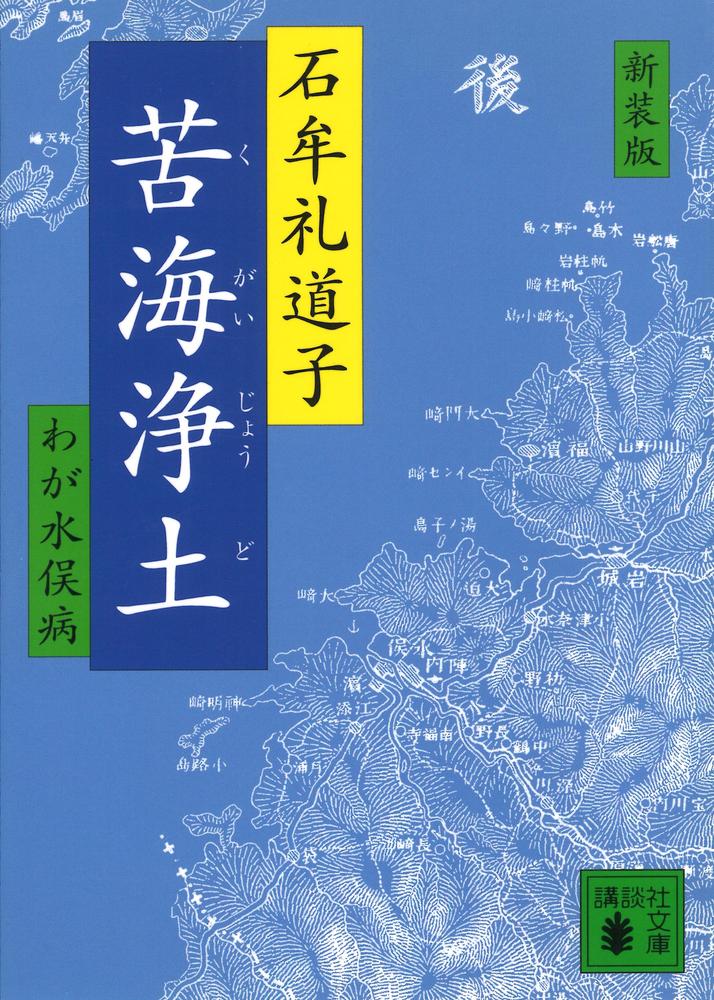 石牟礼道子『苦海浄土――わが水俣病』(講談社、1969年。新装版、講談社文庫、2004年) 工場廃水の水銀が引き起こした水俣病の患者とその家族を描く。本作に続き、第2部「神々の村」、第3部「天の魚(うお)」で完結した。熊日文学賞・大宅壮一ノンフィクション賞受賞決定も辞退、のちマグサイサイ賞受賞。
石牟礼道子『苦海浄土――わが水俣病』(講談社、1969年。新装版、講談社文庫、2004年) 工場廃水の水銀が引き起こした水俣病の患者とその家族を描く。本作に続き、第2部「神々の村」、第3部「天の魚(うお)」で完結した。熊日文学賞・大宅壮一ノンフィクション賞受賞決定も辞退、のちマグサイサイ賞受賞。実は石牟礼が経験したこととよく似たやり取りをジャーナリズムの歴史はたどっている。米国の「ニュージャーナリズム」の最高の書き手と評価されることの多いアメリカのゲイ・タリーズは圧倒的なディテール描写で知られる。そんなタリーズが来日して日本のノンフィクション作家である柳田邦男と対談したことがある(『事実からの発想』に収録)。そこで柳田が尋ねる。
《タリーズさんの作品を読むと、いつもディテール(細部)に非常に感心します。たとえば『汝の父を敬え』の場合、家長のジョゼフ・ボナンノ、長男のビル・ボナンノなどの人物を描く時のディテールが、文学的完璧さを備えていると思います。この本はどこを開いてもそうなんですが、一例をあげますと、「ジョゼフ・ボナンノは半ば目を閉じ、居間の柔らかな椅子の背に寄りかかって、マントバーニの心和(なご)む音楽をステレオで聞いていた。黄褐色の絹のシャツの上にジッパーの付いたグレーのカシミヤのセーターを着ていた。足はゆったりと足台に載せ……」とか、あるわけです。》
それに対してタリーズは答える。
《私はその時、その部屋におりました。》
『汝の父を敬え』の主人公であるボナンノ親子はイタリア移民のマフィアであり、タリーズは彼らと家族ぐるみの付き合いをしていた。一緒にいた時間は少なくなかった。自分がその場にいて見てきたものだから詳細まで描けるというのはそのとおりだろう。
しかし、いつも取材相手と共にいられるわけではない。実際、タリーズが立ち会えなかった場所でも著述の密度は変わらない。普段の暮らしであればタリーズが時間を掛けて見てきたことからの連想や、長く付き合ううちに考え方や感じ方もわかってきてディテールの描写を補完できることもあるかもしれない。しかしビル・ボナンノが収監された監獄のなかでも同じように濃密なディテール描写が貫かれるとなると、これは果たしてどうしたものかと思ってしまう。ニュージャーナリズムは見てきたような嘘を書くと言われたのは、こうしたタリーズの作風も原因のひとつだった。
石牟礼の場合はどうか。渡辺がそれを私小説だと解説した真意は『苦海浄土』の文学性の高さの指摘にあった。患者たちの存在はすべて石牟礼に一度引き受けられてから言葉として書かれる。それはタリーズがボナンノ親子との長い付き合いのなかで彼らの考えや気持ちがわかるようになったことと通じているが、その作風を、渡辺は一人の作者の内面を経由して描かれているという意味で私小説と呼んだ。
だが渡辺は、『苦海浄土』が告発に躍起になるような社会的書物ではないと考えているが、それが現実から遊離した仮構の作品だとまでは言っていない。
《私は何も『苦海浄土』が事実にもとづかず、頭のなかででっちあげられた空想的な作品だなどといっているのではない。それがどのように膨大な事実のデテイルをふまえて書かれた作品であるかは、一読してみれば明らかである。ただ私は、それが一般に考えられているように、患者たちが実際に語ったことをもとにして、それに文飾なりアクセントなりをほどこして文章化するという、いわゆる聞き書の手法で書かれた作品ではないということを、はっきりさせておきたいのにすぎない。……
患者の言い表わしていない思いを言葉として書く資格をもっているというのは、実におそるべき自信である。石牟礼道子巫女説などはこういうところから出て来るのかも知れない。この自信、というより彼らの沈黙へかぎりなく近づきたいという使命感なのかも知れないが、それはどこから生れるのであろう。……
彼女には釜鶴松の苦痛はわからない。彼の末期の眼に世界がどんなふうに映っているかということもわからない。ただ彼女は自分が釜鶴松とおなじ世界の住人であり、この世の森羅万象に対してかつてひらかれていた感覚は、彼のものも自分のものも同質だということを知っている。ここに彼女が彼から乗り移られる根拠がある。》
とはいえ、頭のなかででっちあげられた空想的な作品ではないにしろ、聞いたことを忠実に言葉にしたわけではない作品をノンフィクションと呼んでいいのか。語感の問題、定義の問題とも言えるが、そこにはやや無理を感じる。渡辺にしても、もしも『苦海浄土』がノンフィクションの賞を辞退していなければ、こうした説明は許されなかったのではないか。ビル・ボナンノに憑依したかのように、彼の見たことや内面を描き出したタリーズは、ニュージャーナリズムを名乗ったために「見てきたような嘘を書く」という批判を受けた。石牟礼は賞を受けることで作品がノンフィクションとみなされる道を自ら断ったことと引き換えに、同じ世界に住む者として、同じ世界の住民が見たもの、感じたことを自分の内面を経由してリアルなものとして描く特権を認められた。
■創作以外ならノンフィクションか
 尾川正二『極限のなかの人間――極楽鳥の島』(国際日本研究所、1969年。改題『「死の島」ニューギニア――極限のなかの人間』新装版、光人社NF文庫、2004年) 太平洋戦争末期の東部ニューギニア戦線3年間の体験記。《戦争という極限の状況下における「人間」の素描を試みた、人間レポート》(単行本あとがき)。第1回大宅壮一ノンフィクション賞受賞作。
尾川正二『極限のなかの人間――極楽鳥の島』(国際日本研究所、1969年。改題『「死の島」ニューギニア――極限のなかの人間』新装版、光人社NF文庫、2004年) 太平洋戦争末期の東部ニューギニア戦線3年間の体験記。《戦争という極限の状況下における「人間」の素描を試みた、人間レポート》(単行本あとがき)。第1回大宅壮一ノンフィクション賞受賞作。では尾川の『極限のなかの人間』はどうだったか。丁寧に読むと、こちらにも今の尺度で測ればずいぶんとノンフィクションらしくない部分がある。受賞したのは国際日本研究所版で「極楽鳥の島」という副題が付いている。実際、海岸線で兵士の死骸と対面したときに頭上を極楽鳥が飛んでいるという記述が本文中にある。無残な兵士たちの骸と極彩色の熱帯の鳥との対比が鮮やかだが、コントラストをつけるだけに留まらず、尾川は極楽鳥の描写に相当な熱意を示す。そして極楽鳥への言及がスワルという海岸沿いの村に住む現地人の舞踏の話に続いてゆく。舞踏では、その極楽鳥の美しい飾り羽を身につけるのだ。
《かれらの生活は単調であり、平和である。難しい倫理もなく、徳目もない。本能のままに、しかもおのずから自然法のままに、生存する。自然に対立する自己を主張しようとはせず、自然の一部として、流れる雲のように生きている。踊りは共同体の喜びの表出であり、悲しみの忘却である。》
そして尾川の興味は現地語に向かう。
《かれらの歌うのは現地語であり、その意味を解するのはむずかしい。単に、「ルレ・ルレ・ルレ」を繰り返すのもある。「ルレとは何か」と問えば、「シンシン・ナッティン」と答える。シンシンはsingであり、ナッティンは、nothing である。「意味はない、ただ歌うだけだ」というのである。》
確かにこうした状況描写がなければ作品に厚みはでなかっただろう。しかし、「極限のなかの人間」の観察としては余裕がありすぎはしないか。ここは、なにげない描写だが、原住民が英語話者と親しく交わっていた経緯が以前にあったことを暗示しており(この後にピジン・イングリッシュで書かれた聖書を酋長が読んでいるシーンも登場する)、日本軍が実効支配していたのがほんの束の間であることも示されている。徴用前の尾川は京城帝国大学国文科を卒業しており、復員後にも広島文理科大学大学院で国文学を学ぶ、強い研究者指向の持ち主だ。人類学の素養まであったかはわからないが、従軍中にも現地の習俗をよく観察しており、舞踏、言語、習俗……、僅かの間に多くの知見が得られ、記されている。交戦中にはさすがに現地の習俗や環境を観察する余裕はなくなるが、精度の高い観察眼は友軍の行動や上官の言動の記録に向かう。
尾川は従軍中につけていた陣中日誌を退却時に焼却処分にしている。帰還後、マラリアの熱にうなされながら、陣中日誌に書いたことを、記憶だけを頼りに不用となった包装紙に記し、《昭和二十一年十月、たまたま手にはいった原稿用紙の裏表を使って浄書》したという。石牟礼と異なり、自分の見たこと聞いたことしか書いておらず、これがジャーナリズムなのかと疑われる余地は少ないが、時間も経過しているのにここまでディテールが書き込めるものだろうかという疑念は残る。
それはともかくとして、博学をもって知られていた池島信平は習俗まで描きこむ豊かさを喜んだだろうが、この後に続くノンフィクション作品の多くはここまで迂回的な書き方をしていない。その意味では尾川の『極限のなかの人間』もまた後のノンフィクションの流れとは切り離されて孤立している印象がある。
実はその時点でノンフィクションという概念が確かな内容を持っていたわけではなかった。大宅は「創作以外」という本来のその語の意味に忠実に従うかのように、ルポも書けばエッセーも書き、評論もして、創作以外の多くの作品を残した。池島もそうした広がりでノンフィクションを考えていたのだろう。そんな名を冠した賞の第1回目には、ルポルタージュを自称していながら受賞を辞退し、その後もジャーナリズムの文脈を超えて書き続けられ、愛読されてゆくことになる『苦海浄土』と、戦記ものでありながら、それを超える学術的・文化的な記載をも含む『極限のなかの人間』が選ばれた。
こうした2作品によって日本のノンフィクションは新しい歴史の扉を開くことになり、その後の大宅壮一ノンフィクション賞は創作ではないノンフィクションの広がりのなかで必然のように迷走を余儀なくされて、徐々に焦点を結んでゆくことになる。そのことはまた別の機会に記したい。(以下次回)

