- 2018 09/21
- 日本ノンフィクション史 作品篇

本連載は加筆・修正の上、中公新書『現代日本を読む―ノンフィクションの名作・問題作』として2020年9月に刊行されました。現在、好評発売中です。連載第3回以降の記事は書籍でお楽しみください。
■大宅壮一ノンフィクション賞の誕生
1970年4月8日、大宅壮一ノンフィクション賞の授賞式が新橋の第一ホテルで催された。
受賞者は『極限のなかの人間』を著した尾川正二(おかわ・まさつぐ)。もう一人の受賞者となるはずだった『苦海浄土(くがいじょうど)』の著者・石牟礼道子(いしむれ・みちこ)は受賞を辞退したため欠席。会場に現れた受賞者は尾川一人だけだった。
日本のノンフィクション界を牽引してきた大宅壮一ノンフィクション賞は、このときが第1回だ。賞を創設することが発表されたのは前年の『文藝春秋』誌上であった。
《「事実は小説より奇なり」という言葉があるが、現代は、ある意味では「ノンフィクションの時代」といえるであろう。小説家がつくり出す物語や人物よりも、より意外な、新しい事件や人物が、毎日のように登場しては、われわれのドギモを抜く。まさに、現代は激動の時代だ。》(扇谷正造「ノンフィクションの時代」、『文藝春秋』1969年12月号「大宅壮一ノンフィクション賞応募規定発表」より)
こうしてノンフィクションを対象とする賞の制定自体が初めての試みで大いに注目を集めていたなかで、第1回目から辞退者がでたことはニュースになった。
出版、放送界を横断して活躍し、「烏の鳴かない日はあっても大宅壮一の声を聞かない日はない」と浅沼稲次郎に言われた「マスコミ帝王」の名を冠した賞を作ることで、後に続くノンフィクションの書き手を鼓舞するとともに、マスコミ文化に多大な貢献をした大宅をも労いたい。そんな考えで当時の文藝春秋社長・池島信平が考案したのが大宅壮一ノンフィクション賞だった。
大宅自身は池島の提案に対して《ノンフィクション賞を設けるのはよいことだが、おれの名前をかぶせるのは嫌だな。芥川賞や直木賞を見ればわかるだろ。これら二つの文学賞は本人が亡くなってから制定してるじゃないか。おれが死んでからならかまわないが、生きている間は勘弁してくれよ》と述べて難色を示していたが、夫人まで味方につけて説得にあたった池島に押し切られるかたちになったという。
当時の選考委員は『週刊朝日』の名編集者として知られた扇谷正造、作家の臼井吉見、開高健、そして大宅壮一の弟子で、ジャーナリスト・評論家の草柳大蔵、そこに池島信平が加わる。この面々が選んだ2つの作品から当時の「ノンフィクション」観をうかがい知ることができる。
 尾川正二『極限のなかの人間――極楽鳥の島』(創文社、1969年。改題『「死の島」ニューギニア――極限のなかの人間』新装版、光人社NF文庫、2004年) 太平洋戦争末期の東部ニューギニア戦線3年間の体験記。《戦争という極限の状況下における「人間」の素描を試みた、人間レポート》(単行本あとがき)。第1回大宅壮一ノンフィクション賞受賞作。
尾川正二『極限のなかの人間――極楽鳥の島』(創文社、1969年。改題『「死の島」ニューギニア――極限のなかの人間』新装版、光人社NF文庫、2004年) 太平洋戦争末期の東部ニューギニア戦線3年間の体験記。《戦争という極限の状況下における「人間」の素描を試みた、人間レポート》(単行本あとがき)。第1回大宅壮一ノンフィクション賞受賞作。『極限のなかの人間』はニューギニア戦線で敗走を続けるなかで死線をさまよった著者自身の経験を記した戦記だ。描写は強烈だ。
《村落掃蕩の帰路、思いがけぬ敵の大部隊に遭遇した。突破口を開くため、擲弾筒を据え、敵の機銃に照準をつけ、最大分角で撃ちつづけた。身長一メートルそこそこの、水鉄砲の親方のようなものでしかない小型兵器だが、火砲のない歩兵にとっては頼もしいものに思われた。炸裂音も、相手を威圧するに足るものがあり、手榴弾を撃ちこむこともできた。そのとき、K上等兵も七、八十メートル左の凹地に伏せ、ほとんど同じテンポで撃っていた。五、六発目かに、Kの周辺は何か崩れ落ちたような大音響とともに、黒煙に蔽われた。何事? それっきり、Kの擲弾筒は沈黙した。やられたのか、それにしてもいったい何事がおこったのか。両軍のはげしい応酬のなかに、不吉な黒煙はひろがっていった。
戦い終わって、Kのところに駆け寄ってみた。無残にもKは筒を支え持っていた左手を吹きとばされ、顔面から頭にかけてめちゃくちゃに崩れていた。擲弾筒は、筒の部分が花のように砕け散り、明らかに擲弾の筒内炸裂を物語っていた。》
戦記ものは戦後の月刊誌『文藝春秋』が力を入れてきた企画であり、文藝春秋主催の賞で『極限のなかの人間』が受賞するという構図は理解しやすい。《現代日本人の、戦争を中心に約二十年の経験は、昔の人の一世紀、二世紀に相当するほどの波乱の多いものである。普通の人でも強烈な体験をもつ時代である。小説よりも数奇な時代を経験したわけで、すでに小説自体では物足りない。どうしても強烈なノン・フィクションとなる》。池島はそう書いたことがあった。『極限のなかの人間』がそんな池島のお眼鏡にかなったことは疑うまでもない。
それに対して『苦海浄土』の受賞はどうか。この作品は谷川雁が主宰していた九州の同人誌『サークル村』に「奇病」と題されて一部がまず発表され、その後、『熊本風土記』に連載された「海と空のあいだに」が単行本としてまとめられ、講談社から刊行された。
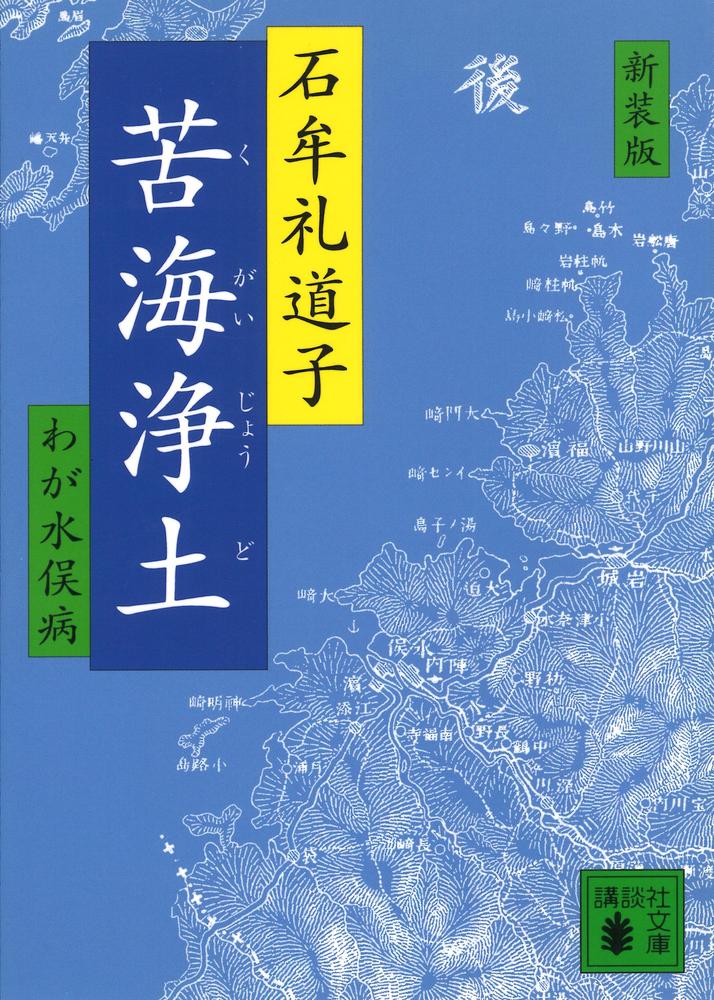 石牟礼道子『苦海浄土――わが水俣病』(講談社、1969年。新装版、講談社文庫、2004年) 工場廃水の水銀が引き起こした水俣病の患者とその家族を描く。本作に続き、第2部「神々の村」、第3部「天の魚(うお)」で完結した。熊日文学賞・大宅壮一ノンフィクション賞授賞決定も辞退、のちマグサイサイ賞受賞。
石牟礼道子『苦海浄土――わが水俣病』(講談社、1969年。新装版、講談社文庫、2004年) 工場廃水の水銀が引き起こした水俣病の患者とその家族を描く。本作に続き、第2部「神々の村」、第3部「天の魚(うお)」で完結した。熊日文学賞・大宅壮一ノンフィクション賞授賞決定も辞退、のちマグサイサイ賞受賞。《年に一度か二度、台風でもやって来ぬかぎり、波立つこともない小さな入江を囲んで、湯堂部落がある。
湯堂湾は、こそばゆいまぶたのようなさざ波の上に、小さな舟や鰯籠などを浮かべていた。子どもたちは真っ裸で、舟から舟へ飛び移ったり、海の中にどぼんと落ち込んでみたりして、遊ぶのだった。》
不知火海に面する水俣の美しい自然が描かれる。豊かな海の恵みを人びとに与えてきた海は、しかし、新日本窒素肥料(1965年にチッソに改称)の工場が排出した有機水銀に汚染されていた。漁獲が多く、米よりも魚を多く食べてきた漁民たちが次々に奇病に倒れてゆく。豊穣な自然と文明の病とのコントラストを鮮やかに描き出した『苦海浄土――わが水俣病』は大きな話題を集めた。
しかし公害病である水俣病を扱うので、当然、加害者であるチッソや、経済成長のなかで大企業優遇政策をとって来た日本政府への告発の色彩を帯びざるをえない。著者の石牟礼も患者団体に寄り添って抗議デモに参加している。
あっという間に店頭から消えて補充されず入手困難になっていた『苦海浄土』は、大企業の顔色をうかがって単行本版元の講談社が販売を自粛しているのではないかという噂すらあったくらいなのだ。2年前に設立され、「右翼的団体」と言われた日本文化会議の機関紙刊行を文春が担う計画が、社内の労働組合員から激しい反対を受けて頓挫し、それに代わるかたちで論壇誌『諸君!』が創刊されるなど、右旋回を指摘されることが多かった当時の文藝春秋には似合わない感もある。
そんな作品を文藝春秋が「意外にも」選んでしまったので、逆に書き手の石牟礼の方が受けられなくなった。そう推測することもできたかもしれない。本人の受賞辞退の弁には政治的なトーンは含まれず、『文藝春秋』誌に載った「選考経過」によれば、《ご好意は大変ありがたいが、まだ続篇を執筆中の現在受賞するのは、気も晴れない心境なので辞退したい》との理由だったとされている。『マスコミ帝王 裸の大宅壮一』はもう少し踏み込んで《わたし一人が頂く賞ではありません。水俣病で死んでいった人々や今なお苦しんでいる患者がいたからこそ書くことができたのです。わたしには晴れがましいことなど似合いませんのでお断りします》と石牟礼が述べたことを伝えている。ちなみに石牟礼は大宅賞に先立って熊本日日新聞の熊日文学賞も辞退している。授賞式で挨拶した大宅も《授賞辞退などというハプニングがあったが、私の中のヤジウマ的なものが現われていて、それもおもしろい》と大人らしいユーモラスな表現に留めている。
こうして第1回の大宅壮一ノンフィクション賞は波乱含みで授賞式を終えたが、そこで賞に選ばれた2つの作品は「ノンフィクション」という文学的ジャンルについて考えさせられるものになった。(以下次回)

