- 2018 05/16
- 知の現場から

『ふしぎの植物学』『雑草のはなし』『植物はすごい』など、植物についてわかりやすい入門書を多数刊行する田中修さん。2年前に定年になった後も、甲南大学特別客員教授として研究を続けています。ふだんはどんな研究をしているのでしょうか。神戸市にあるキャンパスにお邪魔しました。(以下、本当は柔らかな京都ことばでお話しですが、再現不可能なのでほとんど共通語に置き換えました)
 研究室の入口
研究室の入口私が植物学を志した背景には、子どもの頃から両親が庭に草花を育てていて、植物を身近に感じていたというのがありました。
植物の仕組みについての関心のはじまりは、印象に残っています。小学生のとき、春にいっぱい芽が出ているのを指して、先生が「これは暖かくなったからだけで出てきたわけではない」といわれたのです。今から思えば、先生は、「タネが発芽するためには、発芽の3条件以外に、冬の寒さに出会うことが大切なのだ」といわれたのでしょうが、そのときは、「植物は、何か不思議な仕組みをもっている」というように感じました。
植物のすごい力を実感し感激したのも、小学生のときでした。友だちにエンドウの苗を10本ほどもらって栽培してみると、わずか10センチほどだった苗が2ヵ月ほどで自分の背丈と同じくらいに成長して、やがてたくさんの花が咲き、食べきれないほどの実が成ったのです。
このような植物の仕組みの不思議さとすごさを感じた経験が底辺にあったのでしょう。中学、高校で、植物について勉強するにつれて、植物の生き方の「仕組み」について詳しく知りたいと思うようになりました。
 研究室のパソコン前で、論文などをチェック。原稿の執筆は、早朝に自宅で、推敲は往復の通勤電車で行う
研究室のパソコン前で、論文などをチェック。原稿の執筆は、早朝に自宅で、推敲は往復の通勤電車で行う大学に入って「植物生理学」を専攻するようになったとき、動物は生まれたときから(使うか使わないかは別にして)生殖器をもっているのに対して、植物は生まれたときに生殖器であるツボミと花をもっていないことに関心を抱きました。そこで、「植物のツボミがどうしてできるのか、その仕組みを解き明かそう」と思って研究をはじめました。
まず水草の一種であるアオウキクサをいろいろな条件で育てて、その条件の違いでツボミが形成されるかどうかを調べました。
すると、水に青酸カリを混ぜるとツボミが形成されました。青酸カリの成分であるシアンは、植物の硝酸還元酵素(外から窒素を取り込んで体の中の有機物に変えていくプロセスの最初の酵素)を阻害することがわかりました。つまり、植物の体から窒素が足りなくなると、ツボミが形成されることになります。
植物の三大肥料が「窒素、リン酸、カリウム」であることからわかるように、植物が自分の体をつくって維持していく上で、窒素は絶対に必要なものです。この植物は自分の命が危うくなると、子孫を残そうとします。それがツボミをつくることなのです。
窒素が欠乏すると、体の中でどのような変化がおこり、ツボミが形成されるかを明らかにし、また、ツボミの形成を促す物質もいくつか見つけることもできました。その後、シソやアサガオ、トレニアなどでも、窒素が不足するとツボミをつくることがわかってきました。
これらの研究を通して見出された、「窒素欠乏で命が危なくなると、ツボミをつくり、花を咲かせて次の世代へ命をつなぐためのタネをつくる」という性質は、生き物として大切であり、多くの生き物に普遍性があると考えられます。イネやバラ、ウメやモモ、サクラなどでも、この性質で花を咲かせる仕組みがあるはずです。
しかし、実際に栽培されている植物で窒素を抜くのは大変に困難です。たとえば、イネが栽培されている田んぼや、サクラの木の根元にある土壌から窒素を抜くことはできません。
そこで、実験が可能なキノコの子実体形成に、この性質が共通であるかを調べました。子実体とはわたしたちが普通に食べているキノコのことで、そこで胞子がつくられます。植物がツボミをつくることとキノコが子実体をつくることは、その生涯において子孫を残すという同じ過程なので共通性があるのではないかと思ったのです。
 電子レンジ。培養液に含まれる寒天を溶かすために使用
電子レンジ。培養液に含まれる寒天を溶かすために使用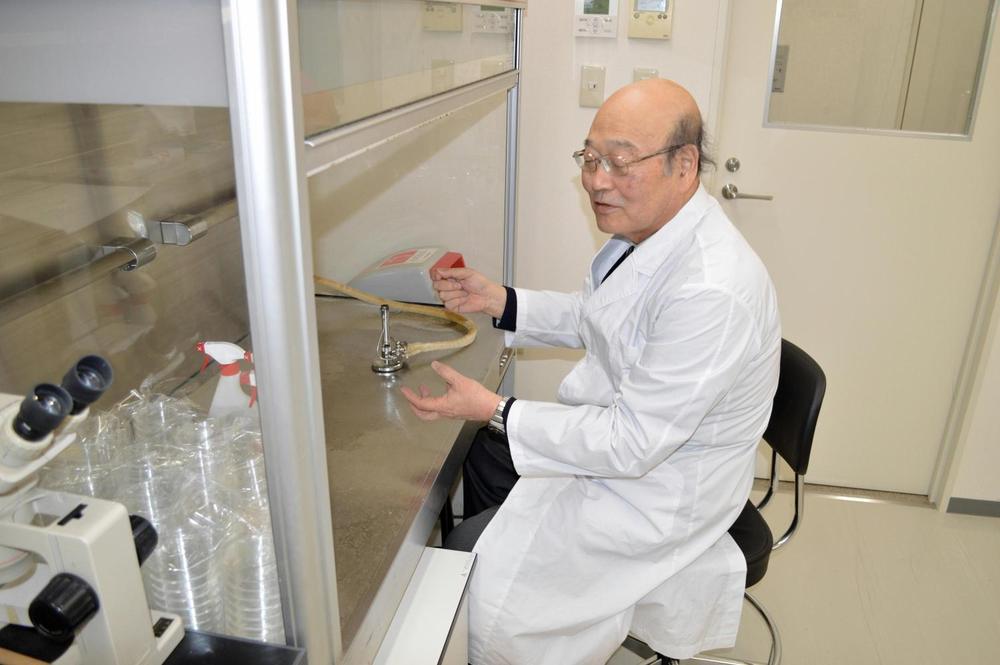 無菌操作は、クリーンベンチで行う
無菌操作は、クリーンベンチで行うキノコでは、アミスギタケやウシクソヒトヨタケなどで、たしかに窒素が欠乏すると子実体がつくられることがわかりました。そうなると「この性質を利用して、マツタケの人工栽培はできるのか」という期待が高まります。
マツタケ栽培の一番の問題は菌糸の増殖の遅さです。シイタケの20分の1という遅さなのです。仮にシイタケが1年で収穫できるとすると、マツタケは20年かかることになります。そのため、菌糸の増殖スピードを速めなければなりません。コメ、ムギ、ダイズ、トウモロコシの他に、ドッグフードやキャットフードなどの栄養になりそうなものをいろいろ菌糸に与えて調べると、ヤマイモを与えるとスピードが速くなることがわかりました。
しかし残念ながら、現在まで、これらの菌糸から、子実体を形成することはできていません。栄養たっぷりのヤマイモで育った菌糸には、「自分の命が危うくなり、子孫(胞子)を残そうとして、子実体をつくる」という気持ちはおきないのでしょう。
 時間の管理は、タイマーで。「バス停まで3分かかるので、バスに間に合うには、研究室を5分前に出なあかん」
時間の管理は、タイマーで。「バス停まで3分かかるので、バスに間に合うには、研究室を5分前に出なあかん」キノコを使っての研究を進めているうちに、キノコ栽培の問題点がわかってきました。
キノコの生産は原木栽培と菌床栽培の2つに大きく分けられます。原木栽培は「ほだ木」と呼ばれる丸太に菌糸を打ち込んで成長させる方法です。一方、菌床栽培はおがくずに米ぬかと水をまぜて培養瓶に入れ、そこに菌糸を植えて育てる方法です。現在、多くのキノコ栽培には、後者の菌床栽培の方法が使われています。
菌床栽培では、おがくずは一回使ったら使い捨てです。近年、ヘルシー志向の高まりに伴ってキノコの消費量は増えており、おがくずの入手や栽培後の廃棄処理の問題が無視できなくなっています。
おがくずの代わりに何か再利用できるものを探そうと考えました。最初は、段ボールをシュレッダーで細かく切って、そこに米ぬかをまぜて培養瓶に入れて育ててみました。段ボールを使った場合にも、ヒラタケ、ブナシメジ、エノキタケ、タモギタケ、ナメコなど、どのキノコもおがくずの場合と同じように育ちました。
これがメディアで報道されると、段ボール業者から、「そのような使い方が広まると、段ボールを回収する価格が高くなるので困る」という声が聞こえてきました。私は知らなかったのですが、その当時、段ボールは回収してリサイクルするというシステムがすでに確立されていたのです。
そこで、段ボールの代わりに、ガラスビーズを使うことにしました。これも栽培自体は、何の問題もなくうまくいきました。しかし、「ガラスビーズは重い」、「使い捨てにすることなく何度でも使えるが、使用後のガラスビーズを洗浄する装置がない」に加えて、「ガラスは割れるかも知れない」と安全を懸念する声があって実用化には至りませんでした。
その後、セラミックボール、数珠玉などでもキノコが栽培できることは確認できましたが、洗浄するための装置を新たに開発しなければならないという問題は解決しませんでした。
植物工場では、野菜は土を使わない水耕栽培で育てられています。そこで、キノコでも、「水耕栽培」のような方法でできないかと考えました。これだと、植物のツボミの形成を促すことがわかっている物質を培養液に加えて、それらのキノコ形成に対する効果を調べやすいとの思いもありました。
培養液を吸収しやすいおしぼりやタオルなどの繊維素材を使うと、水耕栽培に近い栽培法になります。おしぼりに米ぬかを破砕抽出した液を染み込ませて栽培したところ、立派なキノコができました。おしぼりやタオルの洗浄は洗濯機でできます。また、洗浄後のおしぼりやタオルは再利用できるので、廃棄物にはなりません。そのため、現在の菌床栽培の問題点は解消されています。

 おしぼりやタオルを用いたヒラタケ(上)とシイタケ(下)の栽培
おしぼりやタオルを用いたヒラタケ(上)とシイタケ(下)の栽培この栽培方法は、思わぬ方向に発展しました。この栽培がメディアを介して世間に知られると、民間企業から問い合わせが来るようになりました。そして、繊維素材を意味する「ファブリック」という語を使い「ファブリック・キノコ栽培法」と名づけられ、大学が特許を取得しました。
そんなとき、「日本で一番小さい町」として知られる、大阪府の忠岡町から「この栽培方法を使ったキノコを特産品として売り出したい」との申し出がありました。忠岡町は「泉州タオル」で名高い地域にあり、ファブリック・キノコ栽培にふさわしい「繊維の町」ということが、背景にはありました。
幸いにも、この企画は、国の地方創生推進事業の採択を受けて、2016年から大学と忠岡町との連携プロジェクトとしてスタートしています。近いうち、ファブリック・キノコが市場に出まわる日を楽しみにしています。
ツボミの形成とキノコの栽培をお話ししてきましたが、著書でおわかりのように、私の興味は「植物の生き方」です。植物の生き方は、多くの人々の関心からすると、マイナーなものかも知れません。「植物にも生き方って、あるのですか」と聞かれることさえあります。
私たちと植物たちの生き方は、深くつながっています。植物たちは、私たちの食料をすべて賄っており、健康や自然環境、エネルギー、衣類や住居、さらには生け花などの文化もすべて植物が支えてくれているのです。植物を見て励まされたり、癒されたりしていることもあるでしょう。
すでに役に立っている植物だけでなく、現在役に立たない植物も時代が変わると役に立つことがあるかも知れません。たとえば、2015年にノーベル賞を受賞した、中国のトウ・ヨウヨウがマラリアの特効薬として利用したのは、雑草として扱われてきたクソニンジンです。
このような、私たち人間と植物たちとの親密な関係を思うとき、「21世紀は、私たち人間と植物たちとの共存・共生の時代」といわれるのですから、それにふさわしく、私は多くの人に植物たちの生き方に目を向けてほしいと思います。

