ホーム > 検索結果
発行された時期:1973年1月からを含む書籍一覧
全10812件中 6270~6285件表示
-
単行本
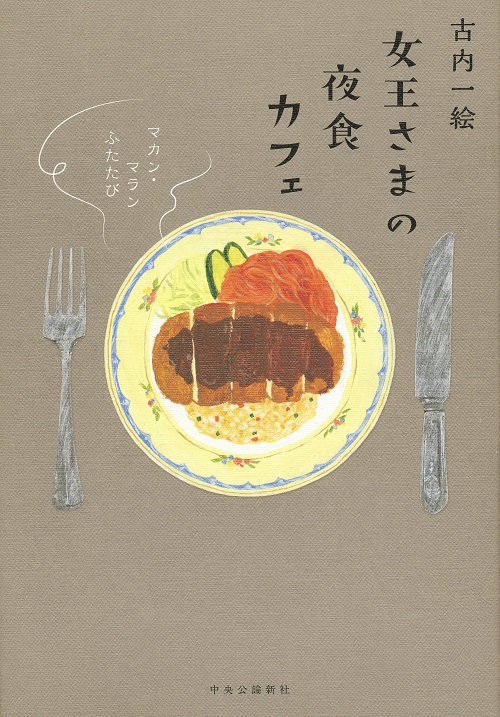
女王さまの夜食カフェ
マカン・マラン ふたたび
古内一絵 著
病に倒れていたドラァグクイーンのシャールが復活。しかし、「マカン・マラン」には導かれたかのように悩みをもつ人たちが集ってきて――?
2016/11/17 刊行
-
中公新書
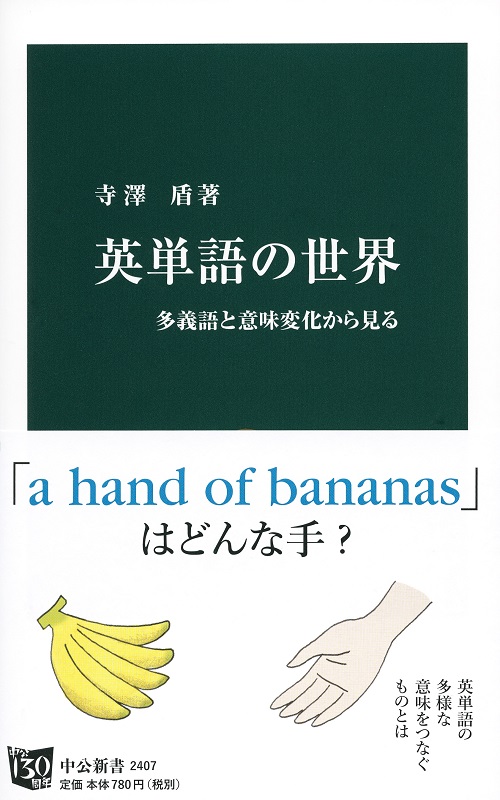
英単語の世界
多義語と意味変化から見る
寺澤盾 著
英語は世界中の言語から多くの語彙を吸収し、既存の英単語も新しい意味を獲得してきた。boot(長靴)に「コンピュータの起動」の意味が生じ、固定して動かない状態を指したfastが「速い」を意味するようになるなど、一見理解しがたい変化もある。しかし、こうした変化は、ランダムにおこったのではなく、何らかの連想関係が存在するのだ。英単語の多様な意味をつなぐものとは何か。その秘密に迫る。
2016/11/17 刊行
-
中公新書
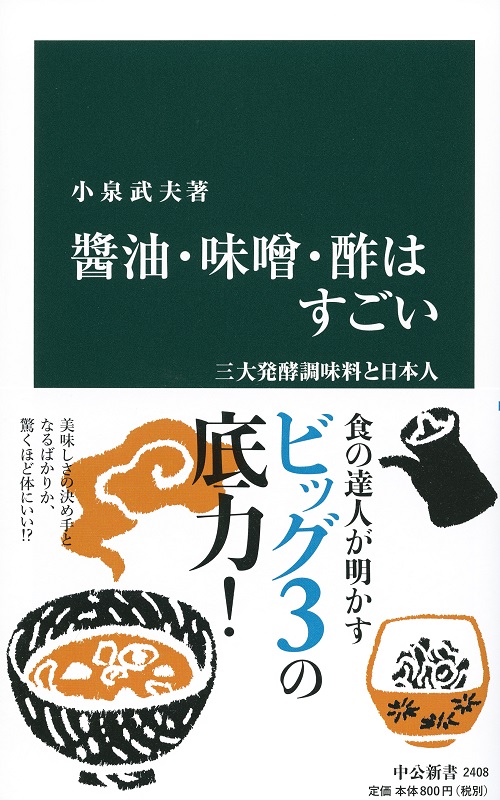
醤油・味噌・酢はすごい
三大発酵調味料と日本人
小泉武夫 著
料理の素材を引き立て、味付けの決め手となる調味料。古くから用いられてきた発酵調味料の醤油・味噌・酢は、日本の食卓に欠かせないばかりか、海外での需要も年々高まっている。本書は、発酵学の第一人者がこれら三大調味料の製造工程や成分をわかりやすく解説。我が国の食文化に根ざした歴史や魅力を述べる。さらには、近年の科学的知見をふまえ、血圧上昇や肥満の抑制、発ガン予防などの驚くべき効能も紹介する。
2016/11/17 刊行
-
中公新書
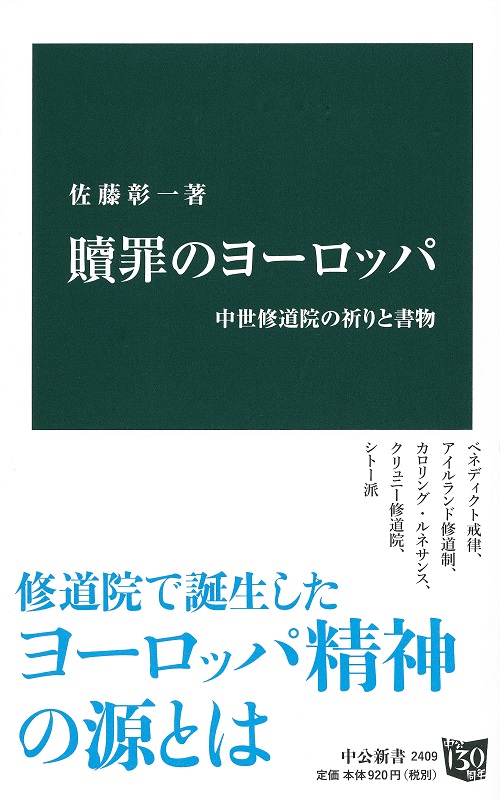
贖罪のヨーロッパ
中世修道院の祈りと書物
佐藤彰一 著
中世初期、アイルランドの聖コルンバヌスによって、自らの心の内に罪を自覚し、意識的にえぐり出す思想が誕生する。この「贖罪」思想は社会に大きな影響を与え、修道院の生活を厳しく規定していく。その絶え間ない祈りと労働からは、華麗な写本も生み出された。本書は、ベネディクト戒律からカロリング・ルネサンスを経てシトー派の誕生に至るまで、修道制、修道院と王侯貴族との関係、経済、芸術等から読み解く通史である。
2016/11/17 刊行
-
電子書籍

外国語を学ぶための
言語学の考え方
黒田龍之助 著
誰もが近道や楽な方法を探そうとするが、結局は地道な努力しかないと思い知らされる外国語学習。だが、それでもコツは存在する。本書は、そのヒントとなる言語学の基礎知識を紹介。「語学には才能が必要」「現地に留学しなければ上達しない」「検定試験の点数が大事」「日本人は巻き舌が下手」といった間違った「語学の常識」に振りまわされず、楽しく勉強を続けるには。外国語学習法としての言語学入門。
2016/11/11 刊行
-
電子書籍

竹島―もうひとつの日韓関係史
池内敏 著
日本と韓国などが領有権をめぐって対立する竹島。日韓それぞれが正当性を主張するものの議論は噛み合わず、韓国による占拠が続いている。本書は一六世紀から説き起こし、幕府の領有権放棄、一九〇五年の日本領編入、サンフランシスコ平和条約での領土画定、李承晩ラインの設定を経て現在までの竹島をめぐる歴史をたどり、両国の主張を逐一検証。誰が分析しても同一の結論に至らざるをえない、歴史学の到達点を示す。
2016/11/11 刊行
-
電子書籍

世界を切り拓くビジネス・ローヤー
西村あさひ法律事務所の挑戦
中村宏之 著
膨大な資料を読み込み、流暢な英語で論理鋭く相手に迫る。ビジネス・ローヤー(企業弁護士)というと、そんな華麗なイメージが浮かぶ。しかし、彼らの仕事の本当の姿はなかなか見えにくい。本書は日本最大のローファーム、西村あさひ法律事務所の実力弁護士11人をインタビュー。そこで明かされる驚異の論理思考、タフな交渉術--。それは法曹をめざす学生はもちろん、国際社会で戦うビジネスマンにとっても役立つ、「勝利の方程式」だ!
2016/11/11 刊行
-
電子書籍
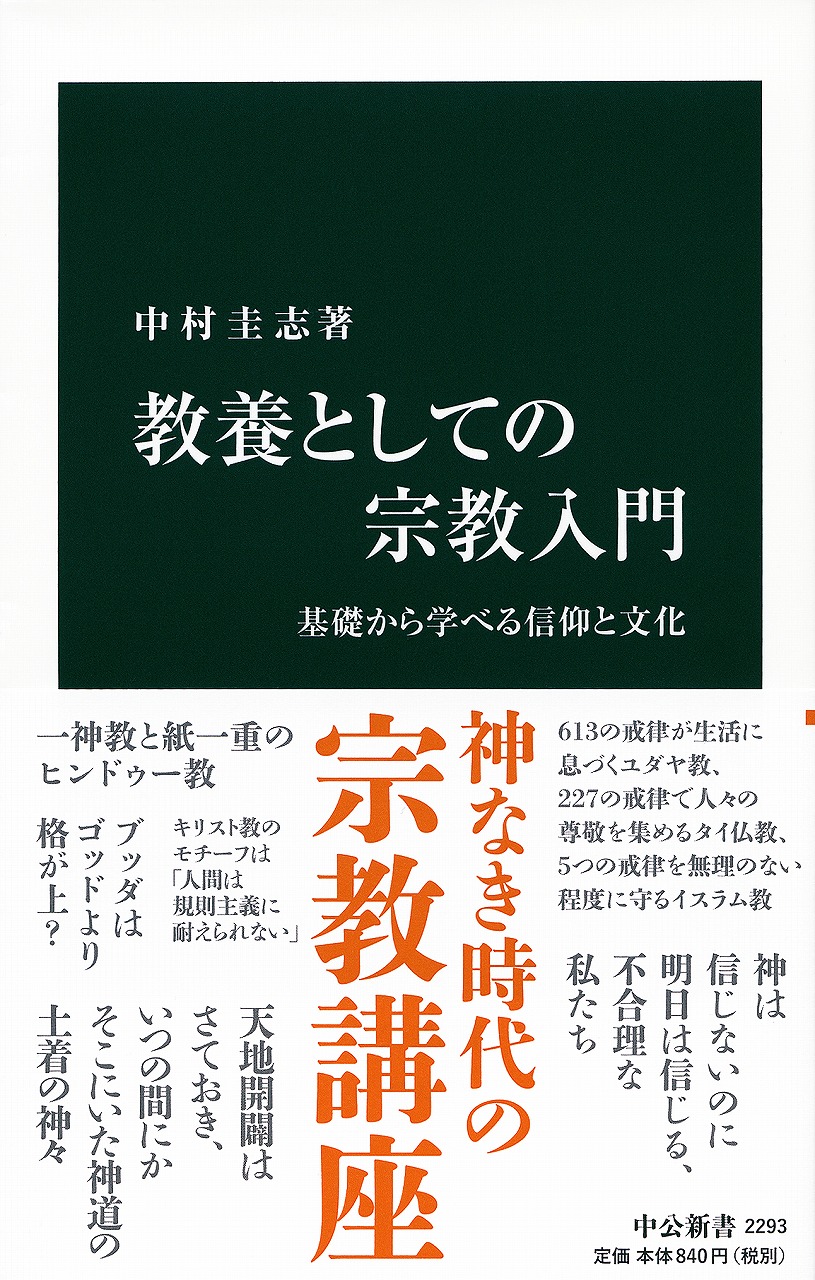
教養としての宗教入門
基礎から学べる信仰と文化
中村圭志 著
宗教とは何か――。信仰、戒律、儀礼に基づく生き方は、私たち日本人にはなじみが薄い。しかし、食事の前後に手を合わせ、知人と会えばお辞儀する仕草は、外国人の目には宗教的なふるまいに見える。宗教的儀式と文化的慣習の違いは、線引き次第なのである。ユダヤ教、キリスト教、イスラム教から、仏教、ヒンドゥー教、そして儒教、道教、神道まで。世界の八つの宗教をテーマで切り分ける、新しい宗教ガイド。
2016/11/11 刊行
-
電子書籍
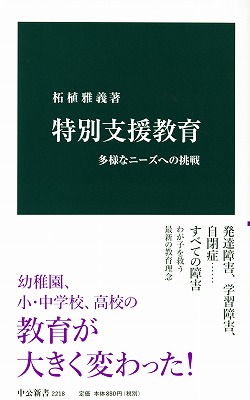
特別支援教育
多様なニーズへの挑戦
柘植雅義 著
小中学校の通常学級で六%、全国で六〇万人を超えると思われる「知的障害のない発達障害児」。彼らを含む、すべての障害のある幼児・児童・生徒の自立や社会参加に向けた取り組みが、教育の場で始まっている。一人ひとりの教育上のニーズを把握し、学習面や生活面の問題を解決するための指導と支援を行う。これが特別支援教育だ。すべての親や教師、そして子どもたち自身が知っておくべきことを収めた現代の新基準の書。
2016/11/11 刊行
-
単行本
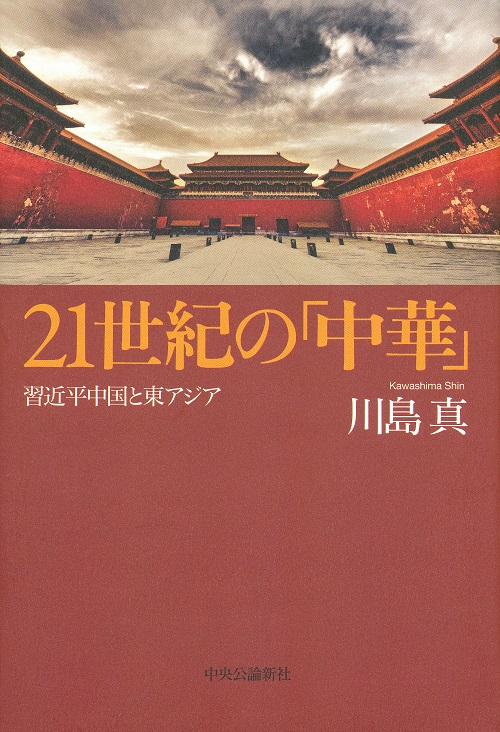
21世紀の「中華」
習近平中国と東アジア
川島真 著
習近平政権が発足して3年。日本にとって中国はなぜ脅威なのか。そして、日本は中国とどう対峙すべきなのか。尖閣諸島「国有化」、戦後70年と歴史認識問題、AIIB発足、緊迫する南シナ海情勢など、具体的事例をもとに、「問題としての中国」をつかむための手がかりを中国外交史の第一人者が冷静に示す。
2016/11/09 刊行
-
全集
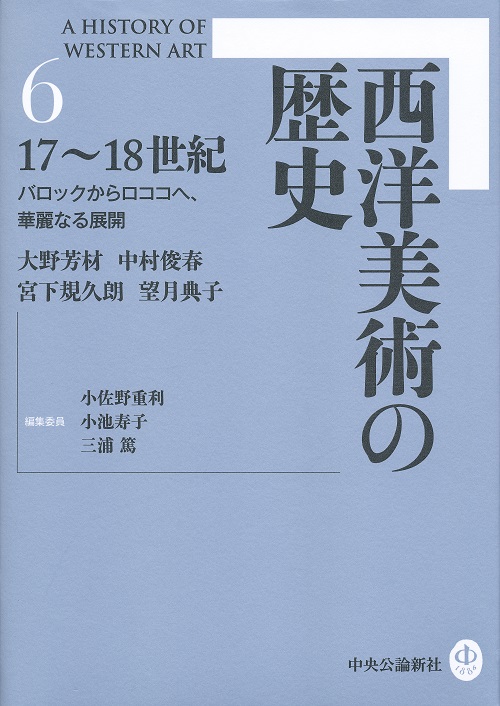
西洋美術の歴史6 17~18世紀
バロックからロココへ、華麗なる展開
大野芳材/中村俊春/宮下規久朗/望月典子 著
17世紀から18世紀にかけて各国で展開した、バロック、古典主義、ロココ美術。西洋美術史上、最も壮麗で豪華絢爛な時代が幕をあける。
2016/11/09 刊行
-
全集
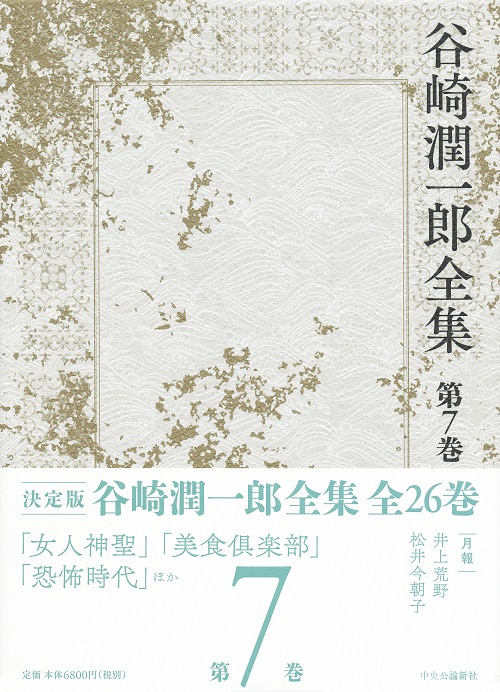
谷崎潤一郎全集
第七巻
谷崎潤一郎 著
美貌の兄妹が思春期を境に世俗にまみれてゆく「女人神聖」、美食を極めた男達がたどり着いた悪夢「美食倶楽部」、グランギニョール風時代劇「恐怖時代」など、大正期の作品群を収載。
2016/11/09 刊行
-
電子書籍
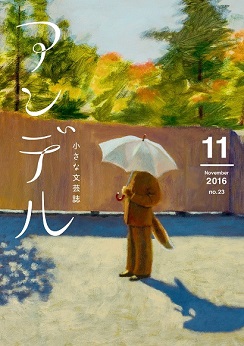
アンデル11月号
前田司郎/柴崎友香/青山七恵/畑野智美 著
<連載長編小説>■畑野智美「大人になったら、」(第2回)■柴崎友香「千の扉」(第10回)■前田司郎「異常探偵 宇宙船」(第11回)<連作短編小説>■青山七恵「あなたの人格」(第7話)
2016/11/01 刊行
-
電子書籍
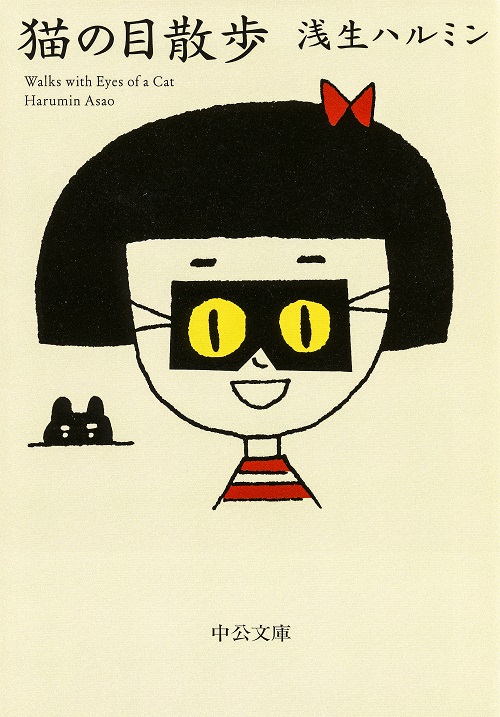
猫の目散歩
浅生ハルミン 著
吉原・谷中・根津・雑司ヶ谷……。「私の中の猫」に導かれ、猫のいる町、路地を行く。猫目線で歩くと、いつもの散歩道も違った景色に見えてくる。猫のパトロールのように、抜き足差し足、ぐるっと回って見聞を綴る、町歩きエッセイ。著者の自筆イラスト多数収録。書き下ろしと単行本未収録のエッセイを増補した。
2016/10/31 刊行
-
電子書籍
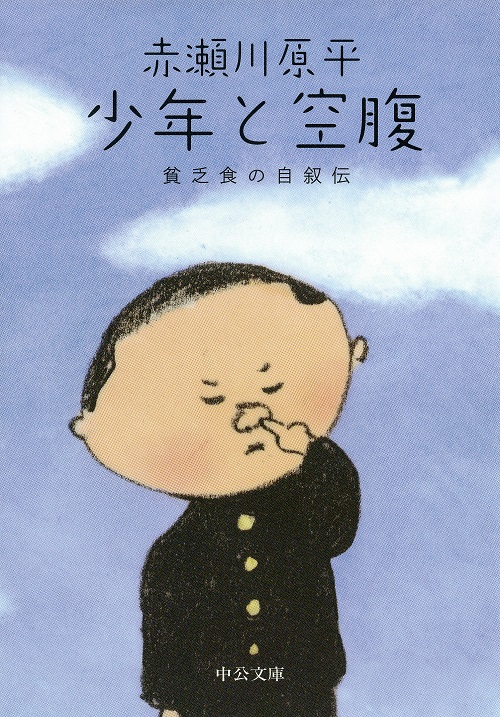
少年と空腹
貧乏食の自叙伝
赤瀬川原平 著
日本中が貧乏だった著者の少年時代、空腹を抱えてさまざまな工夫を凝らし、何でもかんでも「食べ物」にした日々。おかしくせつなく懐かしい、美食の対極をゆく食味随筆の奇書。飽食の時代にこそ噛み締めたい、逆説に満ちた、食事風景の昭和史。『少年とグルメ』改題。
2016/10/31 刊行







