ホーム > 検索結果
発行された時期:1973年1月からを含む書籍一覧
全10812件中 5280~5295件表示
-
電子書籍
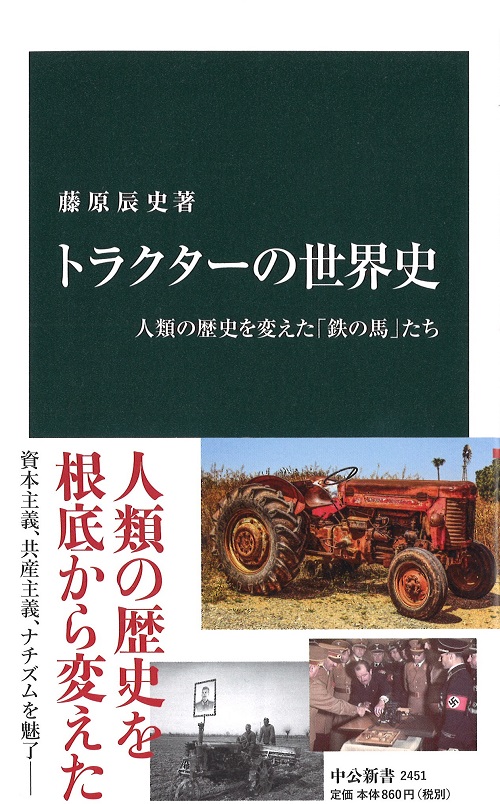
トラクターの世界史
人類の歴史を変えた「鉄の馬」たち
藤原辰史 著
1892年にアメリカで発明されたトラクターは、直接土を耕す苦役から人類を解放し、穀物の大量生産を可能にした。文明のシンボルともなったトラクターは、アメリカでは量産によって、ソ連・ナチ・ドイツ、中国では国策によって広まり、世界中に普及する。だが、化学肥料の使用、土地の圧縮、多額のローンなど新たな問題を生み出す。本書は、一つの農業用の'機械'が、人類に何をもたらしたのか、日本での特異な発展にも触れながら、農民、国家、社会を通して描く。●目次まえがき第1章 誕 生――二〇世紀初頭、革新主義時代のなかで 1 トラクターとは何か 2 蒸気機関の限界、内燃機関の画期 3 夜明け――J・フローリッチの発明第2章 トラクター王国アメリカ――量産体制の確立 1 巨人フォードの進出――シェア77%の獲得 2 専業メーカーの逆襲――機能性と安定性の進化 3 農民たちの憧れと憎悪――馬への未練第3章 革命と戦争の牽引――ソ独英での展開 1 レーニンの空想、スターリンの実行 2 「鉄の馬」の革命――ソ連の農民たちの敵意 3 フォルクストラクター――ナチ・ドイツの構想 4 二つの世界大戦下のトラクター第4章 冷戦時代の飛躍と限界――各国の諸相 1 市場の飽和と巨大化――斜陽のアメリカ 2 東側諸国での浸透――ソ連、ポーランド、東独、ヴェトナム 3 「鉄牛」の革命――新中国での展開 4 開発のなかのトラクター――イタリア、ガーナ、イラン第5章 日本のトラクター――後進国から先進国へ 1 黎 明――私営農場での導入、国産化の要請 2 満洲国の「春の夢」 3 歩行型開発の悪戦苦闘――藤井康弘と米原清男 4 機械化・反機械化論争 5 日本企業の席巻――クボタ、ヤンマー、イセキ、三菱農機終 章 機械が変えた歴史の土壌
2019/01/11 刊行
-
電子書籍
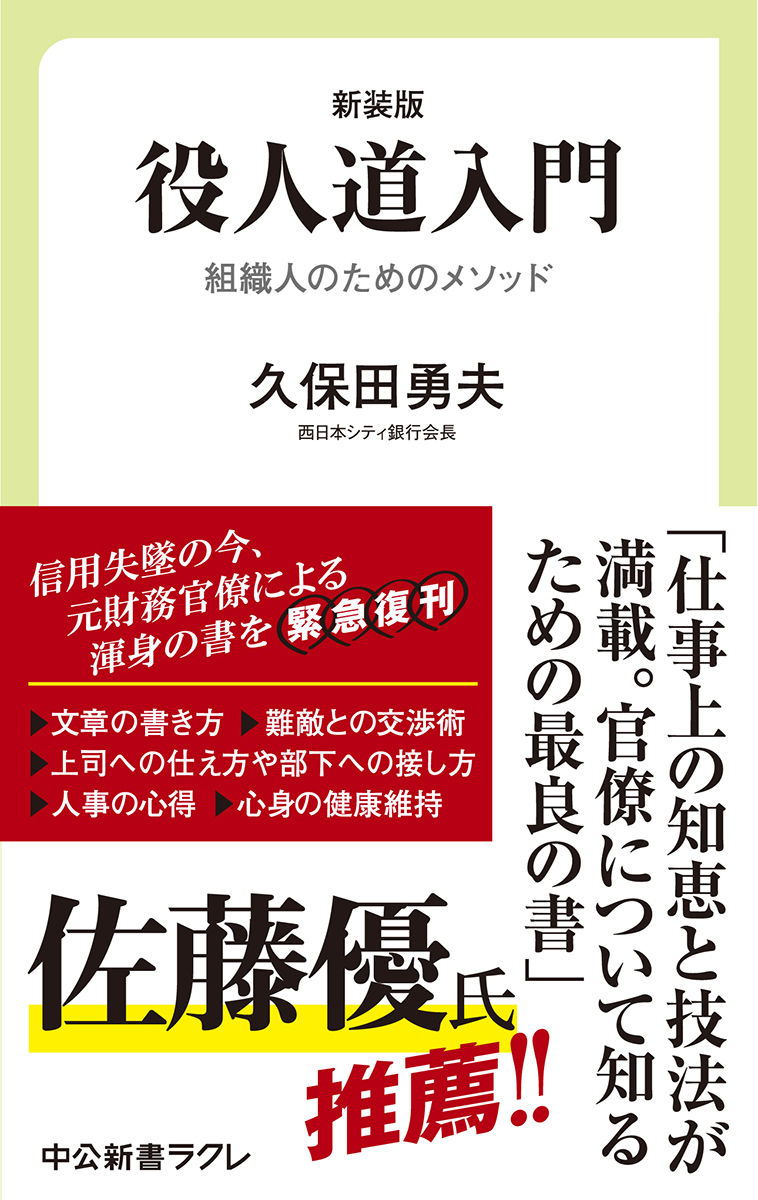
新装版
役人道入門
組織人のためのメソッド
久保田勇夫 著
中央官庁で不祥事が相次ぎ、「官」への信用が失墜している。あるべき役人の姿、成熟した政と官のあり方、役人とは何か? 答えはすべてここにある。「官僚組織のリーダーが判断を誤ればその影響は広く国民に及ぶ」。34年間奉職した財務官僚による渾身の書を緊急復刊! 著者の経験がふんだんに盛り込まれた具体的なノウハウは、指導者の地位にある人やリーダーとなるべく努力をしている若手など、組織に身を置くあらゆる人に有効な方策となる。
2019/01/11 刊行
-
電子書籍
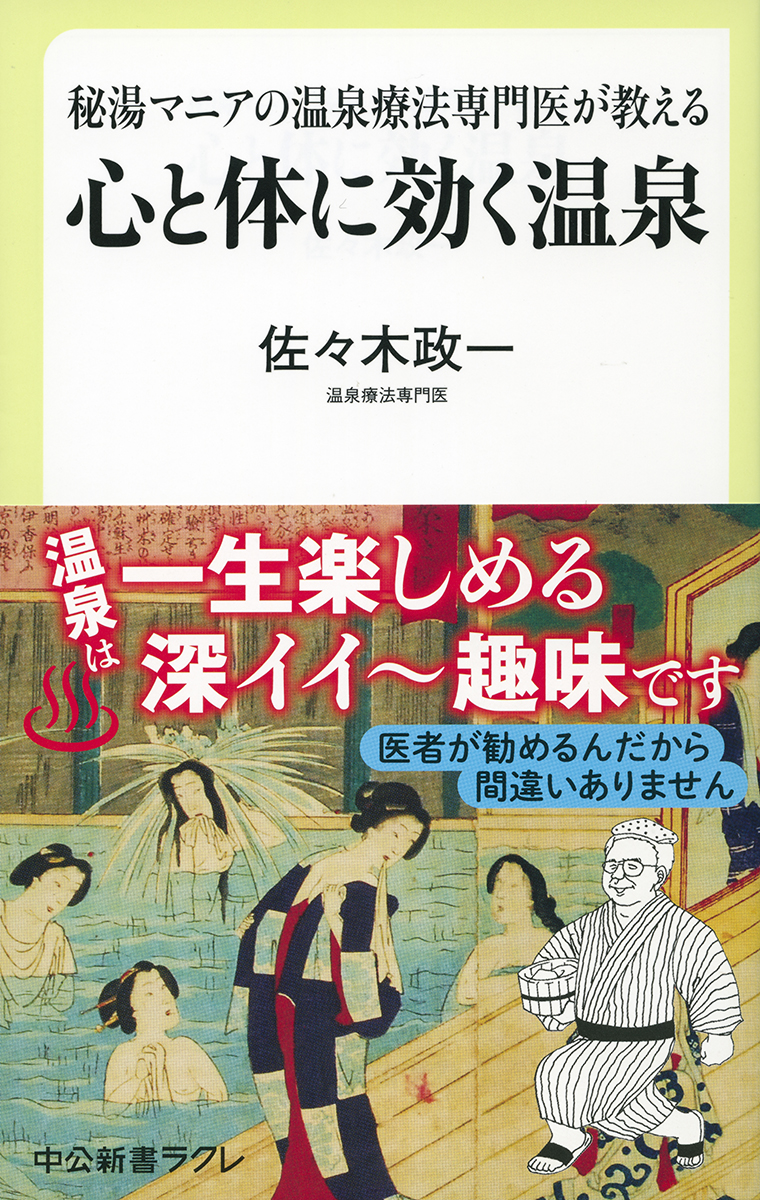
秘湯マニアの温泉療法専門医が教える
心と体に効く温泉
佐々木政一 著
温泉は一生楽しめる深イイ~趣味です。現役医師が自ら215箇所を巡って選んだ秘湯・名湯の数々。温泉の効能から、最新情報、心と体が健康になるための賢い温泉利用法を解説。また、温泉にまつわる言い伝えや歴史、温泉文化についても幅広く言及。知れば知るほど面白い、心も体もイキイキしてくる温泉の世界へ誘います。
2019/01/11 刊行
-
電子書籍
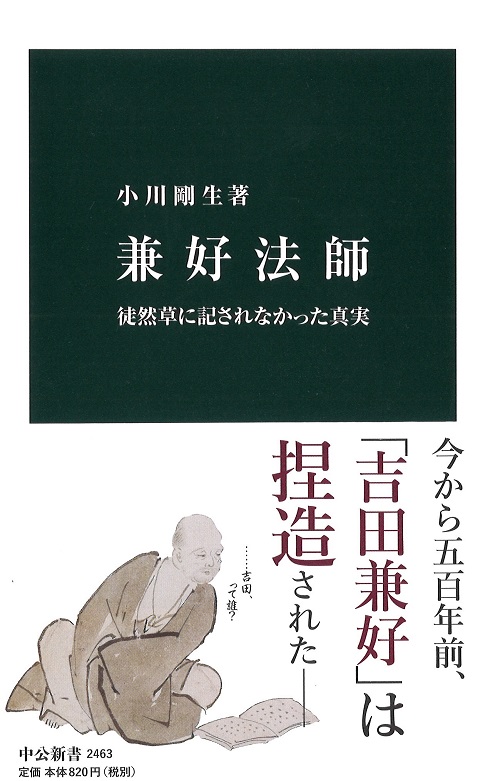
兼好法師
徒然草に記されなかった真実
小川剛生 著
兼好は鎌倉時代後期に京都・吉田神社の神職である卜部家に生まれた。六位蔵人・左兵衛佐となり朝廷に仕えた後、出家して「徒然草」を著す――。この、現在広く知られる彼の出自や経歴は、兼好没後に捏造されたものである。著者は同時代史料をつぶさに調べ、鎌倉、京都、伊勢に残る足跡を辿りながら、「徒然草」の再解釈を試みる。無位無官のまま、自らの才知で中世社会を渡り歩いた「都市の隠者」の正体を明らかにする。
2019/01/11 刊行
-
電子書籍
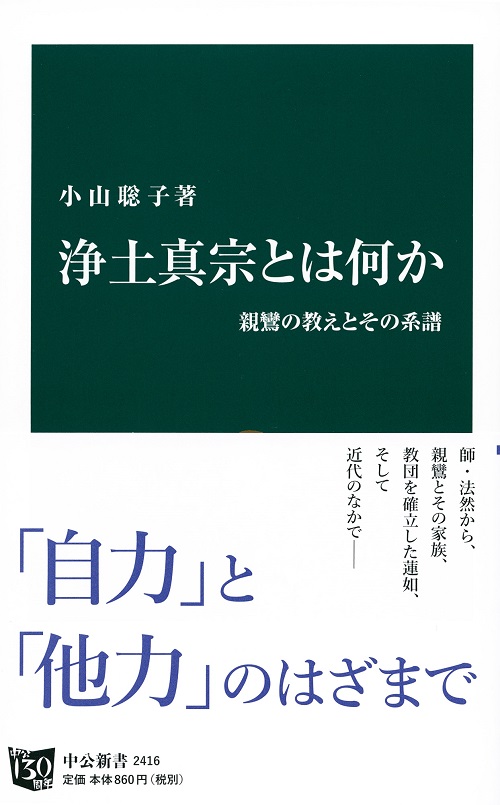
浄土真宗とは何か
親鸞の教えとその系譜
小山聡子 著
日本最大の仏教宗派、浄土真宗。開祖・親鸞は、絶対他力の教え、悪人正機説など、思想の革新性で知られている。本書では、さらに平安時代の浄土信仰や、密教呪術とのつながりにも目を向け、親鸞の教えと、それがどのように広まったのかを、豊富な史料とエピソードに基づき描きだす。師・法然から、親鸞、その子孫、室町時代に教団を確立した蓮如、そして東西分裂後まで、浄土真宗の思想と歴史を一望する。
2019/01/11 刊行
-
電子書籍
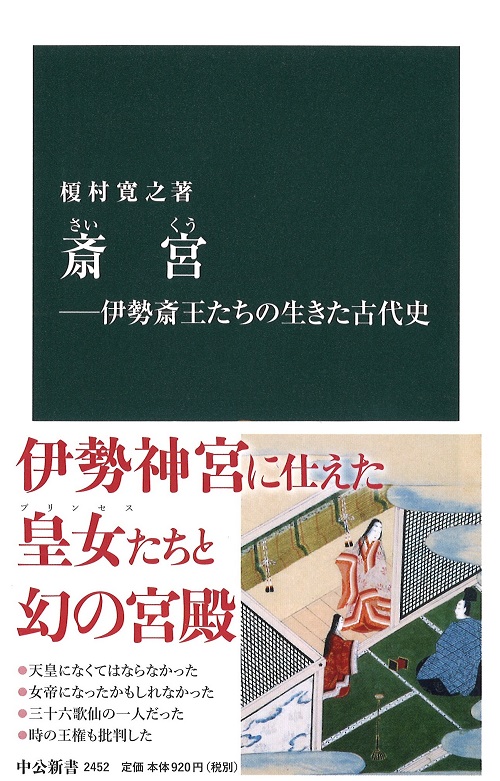
斎宮―伊勢斎王たちの生きた古代史
榎村寛之 著
天皇の代替わりごとに占いで選ばれ、伊勢神宮に仕える未婚の皇女――それが斎王であり、その住まいが斎宮である。飛鳥時代から鎌倉時代まで六六〇年にわたって続いた斎宮を、あらゆる角度から紹介し、斎王一人一人の素顔に迫る。『伊勢物語』のモデルとなった斎王、皇后となり怨霊となった斎王、悲恋に泣いた斎王……彼女たちは都を離れた伊勢で何を祈り、何を思って人生を送ったのか。古代史の新たな姿が浮かびあがる。
2019/01/11 刊行
-
単行本
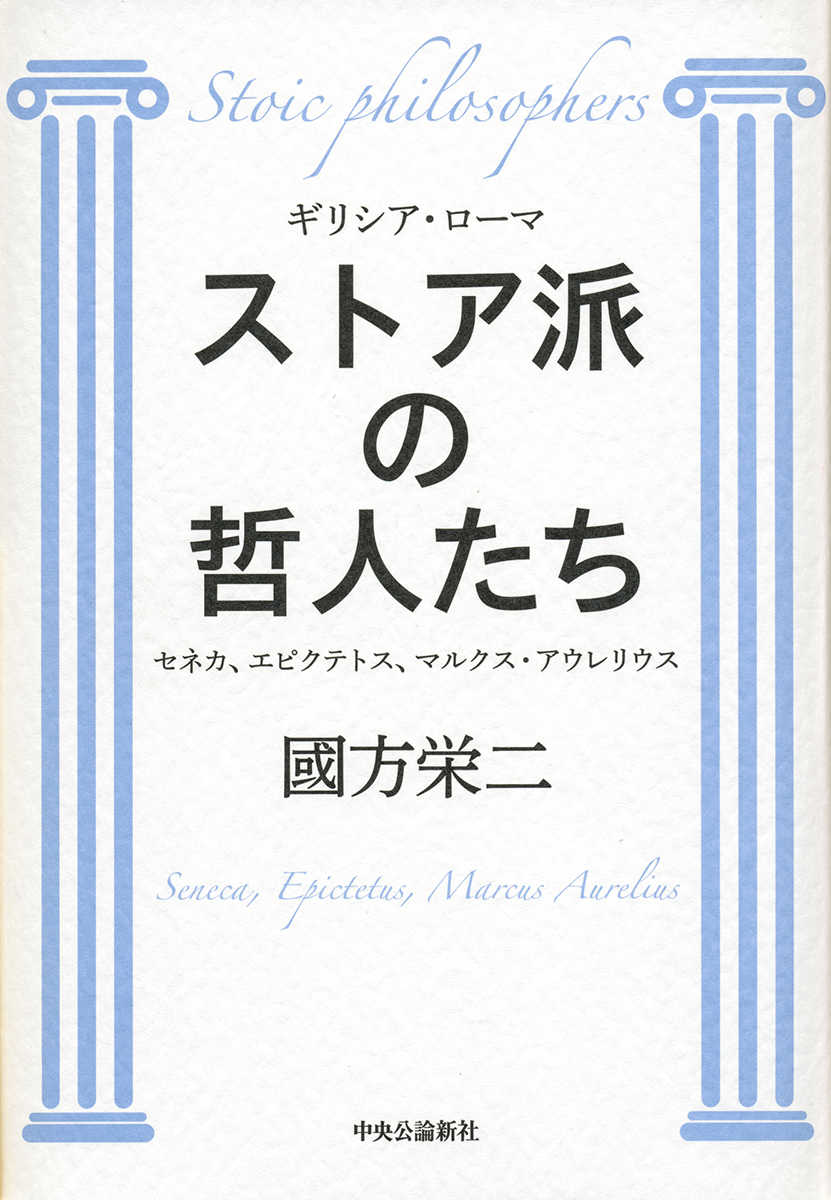
ギリシア・ローマ
ストア派の哲人たち
セネカ、エピクテトス、マルクス・アウレリウス
國方 栄二 著
「ストイックに生きる」ことは、自分に厳しいだけの生き方なのか?キュニコス派ディオゲネスから、ゼノンら初期、パナイティオスら中期、セネカらローマ時代の後期の思想を比較・紹介
2019/01/10 刊行
-
電子書籍
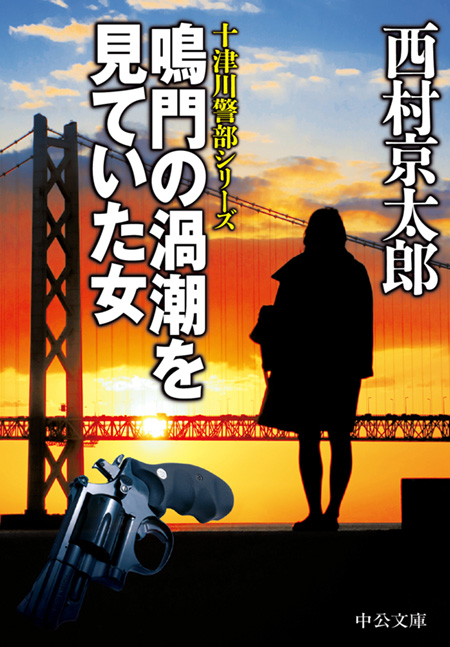
鳴門の渦潮を見ていた女
西村京太郎 著
警視庁捜査一課の警部・佐々木は、一人娘さくらが病気で余命半年と宣告されたため、警視庁を退職し二人で旅行に出た。三年前に妻が病死した時は何もしてやれなかったのだ。しかし、鳴門の「渦の道」でさくらは何者かに誘拐されてしまう。そして解放の条件として、射撃大会で優勝したこともあるその腕で、二日以内に警視総監を射殺せよと命じられる。どうやら事件の背後には、穏健派の現総監に反旗を翻す「強い国家・強い警察」を望む者たちの存在があるようだ。刻々と迫るリミット。果たして佐々木の選択は!? 警視庁内に存在する深い闇に十津川が切り込む。
2018/12/28 刊行
-
電子書籍
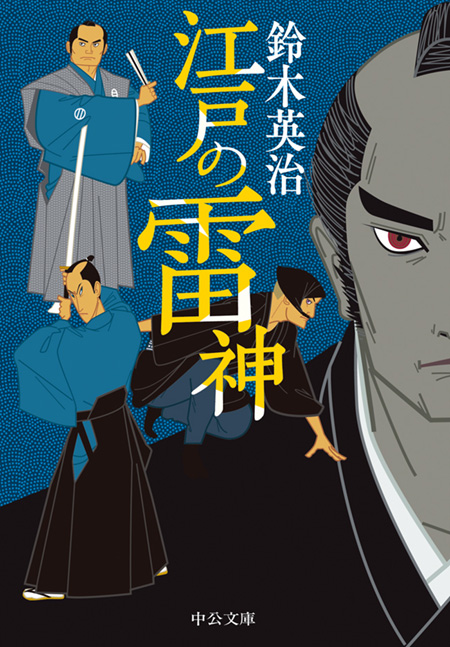
江戸の雷神
鈴木英治 著
火付盗賊改役の伊香雷蔵は、常に捕物の先頭に立ち、町人に人気がある。その勇猛さで「江戸の雷神」と呼ばれる一方、斬り捨て御免の火盗改ながら、できるだけ賊を生け捕るのが信条という快男児だ。府内を騒がす辻斬り、押し込みに加え、その鮮やかな手並みで「匠小僧」と呼ばれる盗賊を追う雷蔵だったが――。痛快時代小説シリーズ、開幕!
2018/12/28 刊行
-
電子書籍
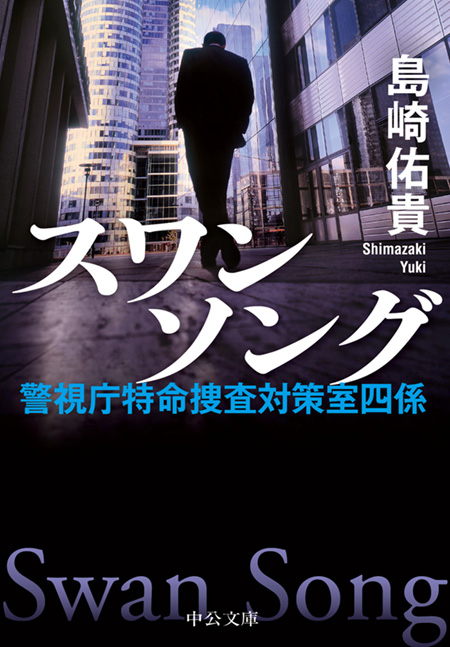
スワンソング
警視庁特命捜査対策室四係
島崎佑貴 著
警視庁一の嫌われ者・小々森八郎巡査部長の命が三度も狙われた。特命捜査対策室四係の面々は、小々森を囮に犯人を誘き寄せる作戦を開始。並行して捜査するうちに、彼の元同僚たちが相次いで死亡していることに気づいた――。暗殺者の正体、小々森を狙う目的とは? それは公安警察をも巻き込む、巨大な闇へと繋がっていた
2018/12/28 刊行
-
電子書籍
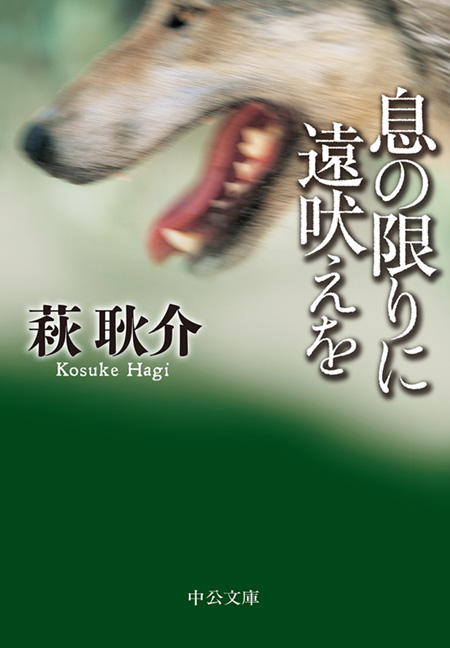
息の限りに遠吠えを
萩耿介 著
ベストセラー『イモータル』の著者が、圧倒的弱者の目線から描き出す「人間の本質」とは?時は一九世紀。一匹の犬が愛玩犬として日本からアメリカへ送られる。道中で出会うのは、性格も肌の色も違う様々な人間たち。優しい人間、その人間を迫害する人間、他の動物を絶滅させようとする人間。抗うことのできない歴史の奔流の中で、彼の命を懸けた反抗が、やがてこの世界に小さな希望を灯す――。『イモータル』の著者が、圧倒的な弱者の目線から「人間の本質」を描き出す意欲作。文庫書き下ろし
2018/12/28 刊行
-
電子書籍

覇権交代2
孤立する日米
大石英司 著
韓国の離反がアメリカの威信を傷つけ、彼らを激怒させた。更に韓国軍の玄武ミサイルが九州に襲来し、百人を超える民間人の犠牲者が出た日本でもヘイト犯罪が相次ぐ。一瞬だけ高まった和平の機運は砕け散り、中韓と日米は再びぶつかりあうことに。そして両者が激しい戦闘を行うのは、かつて旧日本軍が占領した因縁の場所・海南島。特殊部隊〈サイレント・コア〉を率いる土門一佐も、各小隊とともに最前線での戦いに身を投じるが、十倍以上の数で押してくる敵に苦戦続きの展開となってしまう。またそこへ、韓国軍の戦車部隊も登場してきて……!?
2018/12/28 刊行
-
電子書籍
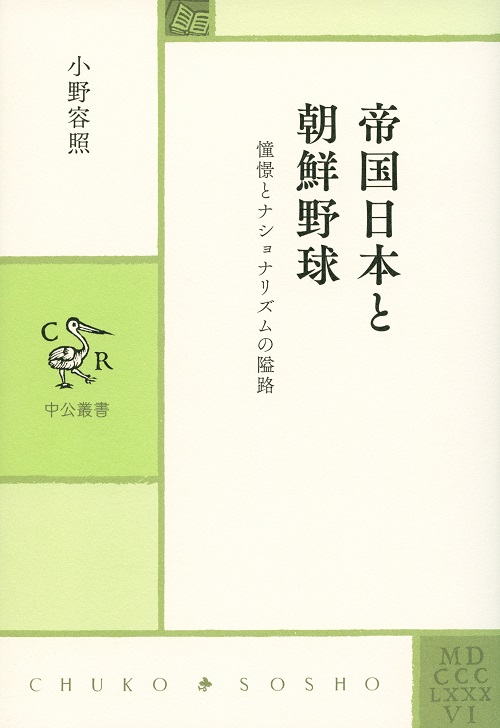
帝国日本と朝鮮野球
憧憬とナショナリズムの隘路
小野容照 著
" 五輪の優勝、WBCの準優勝により、韓国の野球は国民的スポーツとなった。いまその起源や日本経由の用語見直しなど、歴史の解明が喧しい。日本は朝鮮野球にどれだけ関与したのか――。 植民地時代の朝鮮野球は、朝鮮人と支配者日本人双方から重視されていた。日本人との試合は大いに盛り上がり、朝鮮ナショナリズムに火をつける。他方で当局は、中等学校の甲子園出場に道を開き、都市対抗野球を後押しし優勝に導くなど、融和政策 に“活用""する。 本書は19世紀末から「解放」される1945年まで、複雑な道程を辿った朝鮮野球について、2つの""民族""を通して描くものである。 序章 変化する野球用語第1章 ベースボールの伝来と野球の普及―韓国併合前第2章 暗黒時代―武断政治下の野球界第3章 「民族の発展は壮健な身体から」―文化政治期の朝鮮野球界1第4章 帝国日本の野球イベント―文化政治期の朝鮮野球界2第5章 戦時期朝鮮の野球界終章 植民地朝鮮の野球とは何だったのか"
2018/12/28 刊行
-
電子書籍
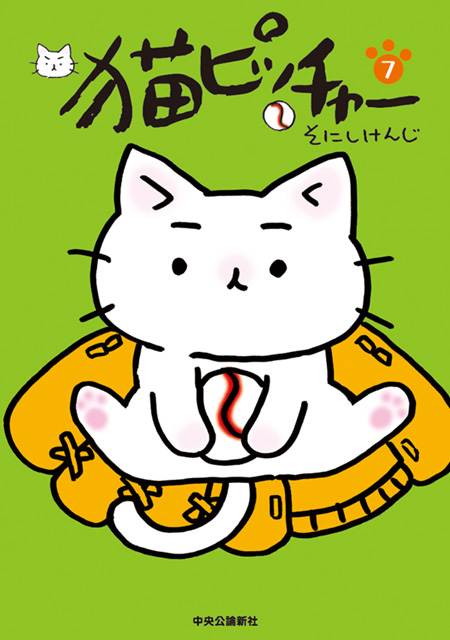
猫ピッチャー 7
そにしけんじ 著
2シーズン目に突入したミー太郎が“先輩”として新人選手にニャイアンツルールを教えたり、研究をし尽くした敵チームは新作戦を繰り出してきたり――より高度で愉快なリーグ戦が展開!「ねこねこ日本史」、「猫ラーメン」「ねこ戦」など“猫マンガの巨匠”そにし先生による代表作。
2018/12/28 刊行
-
電子書籍
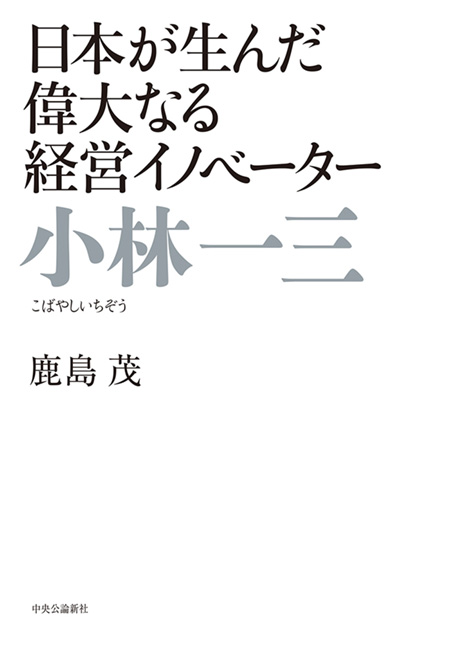
日本が生んだ偉大なる経営イノベーター
小林一三
鹿島茂 著
Amazonでも、googleでもない。2020年、東京オリンピック後の日本社会を構想するヒント阪急電車、宝塚歌劇団、東宝株式会社など、明治から昭和にかけて手がけた事業は数知れず。大衆の生活をなにより重んじ、日本に真の「近代的市民」を創出することに命を捧げた天才実業家の偉大なる事業と戦略とは?【小林一三(こばやしいちぞう)の手がけた事業】阪急、宝塚、東宝、阪急百貨店、第一ホテル(後の第一ホテル東京)、阪急ブレーブス(後のオリックス・バファローズ)、昭和肥料(後の昭和電工)、日本軽金属、東京楽天地など。
2018/12/28 刊行







