ホーム > 検索結果
発行された時期:1973年1月からを含む書籍一覧
全10813件中 2415~2430件表示
-
中公選書
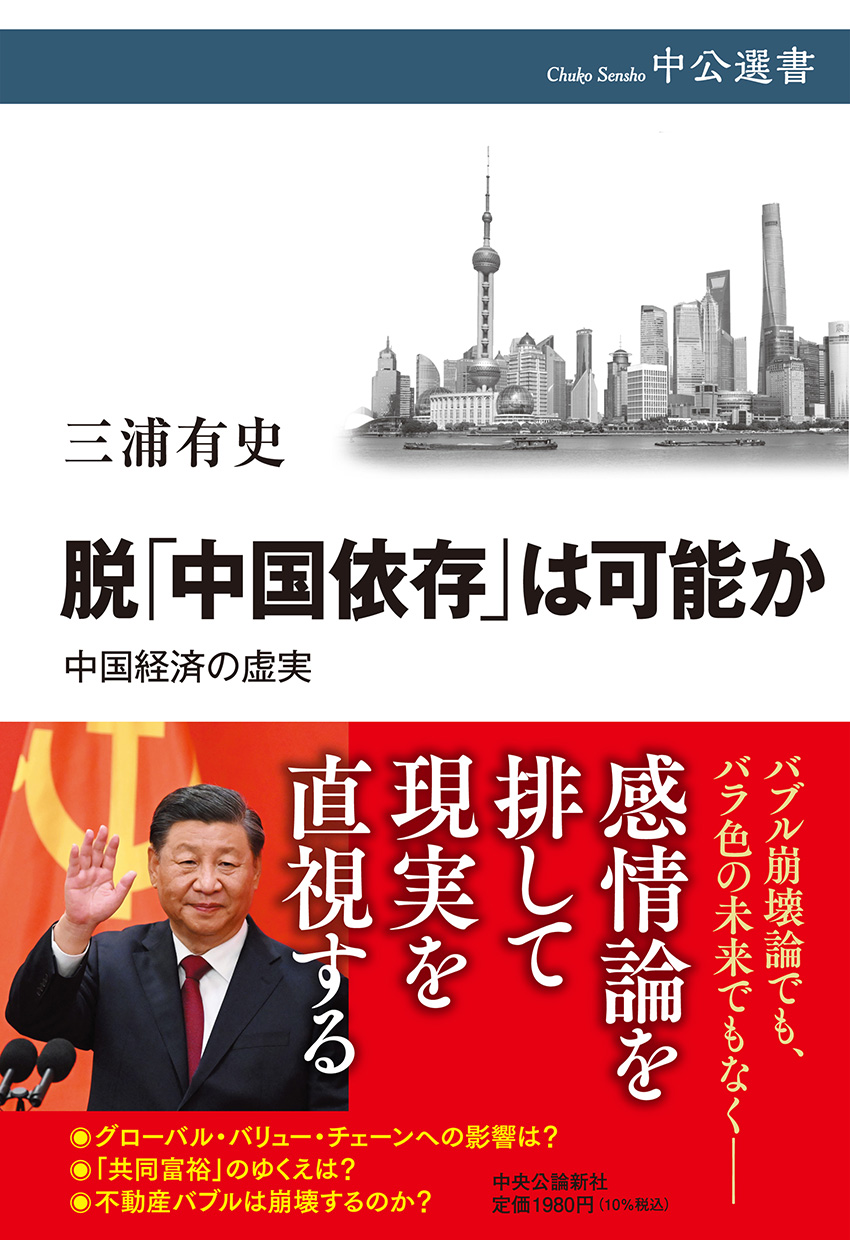
脱「中国依存」は可能か
中国経済の虚実
三浦有史 著
中国は経済成長率が目標を下回るなど減速が著しいが、世界における重みは着実に増し、日本の最大の貿易相手国でもある。だが、深まる一方の「中国依存」に対する不安も急速に高まっている。脱「中国依存」は可能なのか。本書は各種の統計データに基づき、中国経済の正しい見方を提示する。あわせて「共同富裕」や不動産バブルなど習近平政権下の経済政策・経済問題を検討し、今後を展望するとともに、日本の取るべき指針を示す。
2023/01/10 刊行
-
電子書籍
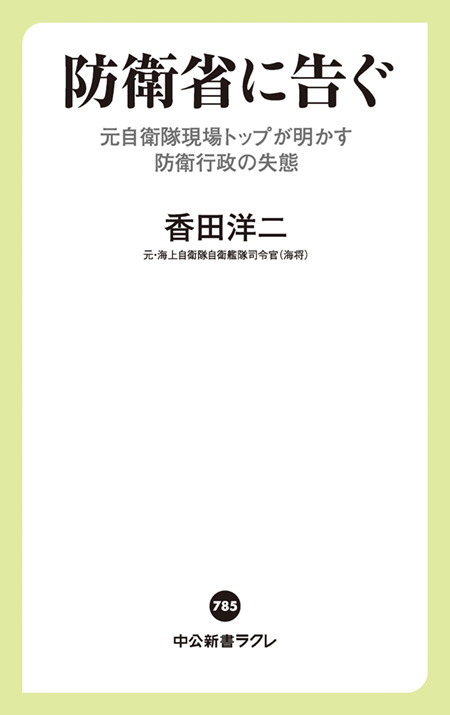
防衛省に告ぐ
元自衛隊現場トップが明かす防衛行政の失態
香田洋二 著
2020 年、イージスアショアをめぐる一連の騒ぎで、防衛省が抱える構造的な欠陥が露呈した。行き当たりばったりの説明。現場を預かる自衛隊との連携の薄さ。危機感と責任感の不足。中国、ロシア、北朝鮮……。日本は今、未曽有の危機の中にある。ついに国防費は GDP比2%に拡充されるが、肝心の防衛行政がこれだけユルいんじゃ、この国は守れない。元・海上自衛隊自衛艦隊司令官(海将)が使命感と危機感で立ち上がった。
2023/01/10 刊行
-
電子書籍
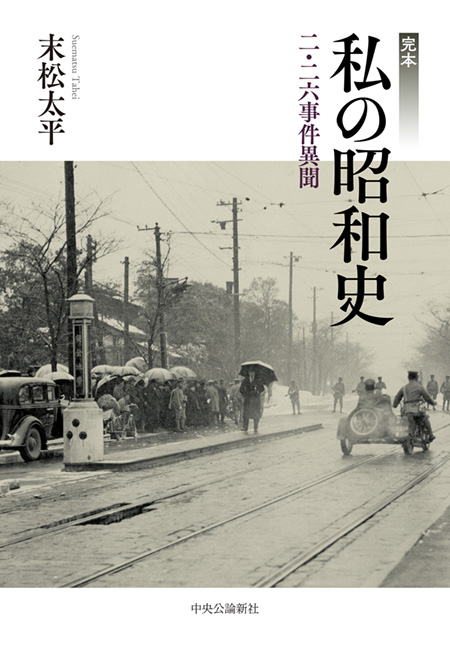
完本
私の昭和史
二・二六事件異聞
末松太平 著
二・二六事件を頂点とする「昭和維新運動」の推進力であった「青年将校グループ」とは、どのような人たちだったのか。彼らはなぜ二・二六事件を起こさねばならなかったのか――。グループの中心人物であった著者が、自身の体験したことを客観的に綴る本書は、貴重な昭和史第一級史料であるとともに、三島由紀夫に「見事な洗煉された文章」として激賞されたことでも知られる。長年読み継がれてきた名著に、拾遺八篇と同時代書評を増補した決定版。〈解説〉筒井清忠「私の人生の本」といえば、この本をあげなければなるまい――三島由紀夫昭和維新運動の全体像を構築するためにも、私に非常に多くのことを教えてくれる――橋川文三【目 次】まえがき Ⅰ残 生/大岸頼好との出合い Ⅱ天剣党以来/十月事件の体験/出征から凱旋まで/十一月二十日事件(その一)/十一月二十日事件(その二)/十一月二十日事件(その三)/相沢事件の前後(その一)/相沢事件の前後(その二)/相沢事件の前後(その三)/相沢事件の前後(その四)/蹶起の前後(その一)/蹶起の前後(その二)/青雲の涯 Ⅲ大岸頼好の死 拾 遺赤化将校事件/青森連隊の呼応計画/刑場の写真/夏草の蒸すころ/続・夏草の蒸すころ/素描・竹橋事件/有馬頼義の『二・二六暗殺の目撃者』について/映画「脱出」について 付録……同時代書評(*は電子には未収録)利用とあこがれ……三島由紀夫(*)人生の本―末松太平著「私の昭和史」……三島由紀夫(*)末松太平著『私の昭和史』について……橋川文三〈解説〉筒井清忠索 引
2023/01/10 刊行
-
電子書籍
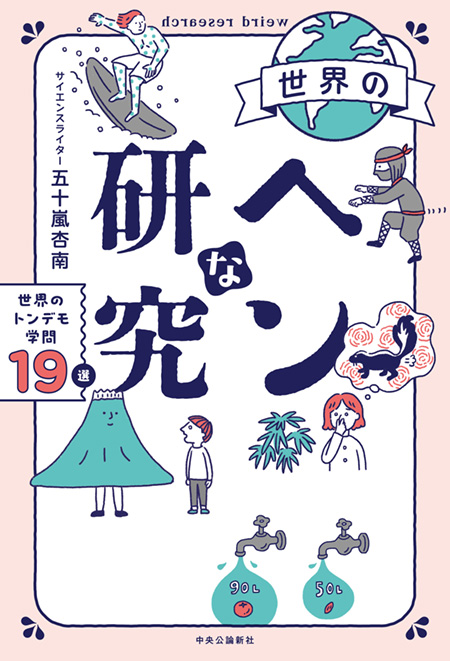
世界のヘンな研究
世界のトンデモ学問19選
五十嵐杏南 著
テーマパークやカジノ、大麻など、日本に住んでいると不思議に思うユニークな授業が、世界にはたくさんある。本書は、サイエンスライターとして世界各国の科学関連のニュースに触れる著者による、「所変われば学びも変わる」異文化事情を伝える1冊。「所変われば品変わる」は研究の世界でも言えることで、世界は風変わりな学びにあふれている。当事者にとっては生活の当たり前の一部なのに、地域性があまりに強いが故に、外からしてみたらちょっとヘンなものがたくさんある。本書では、世界の各地域で、その地域だからこそ行われている学びの場について紹介する。学びの中でも、地域ならではの娯楽や生活の中の楽しみに関わるものがある一方で、地域特有の課題を対処し、生き抜いていくために重要なものもある。さらに、その知識を受け継いでいくために、独特な授業で教えることもある。そんな一面にももれなく着目していきたい。世界は狭いようで広い――本書で登場するのは、世界のヘンなお勉強のほんの一握りのはず。軽くかじるくらいのゆるい気持ちで、お楽しみください。
2023/01/10 刊行
-
電子書籍
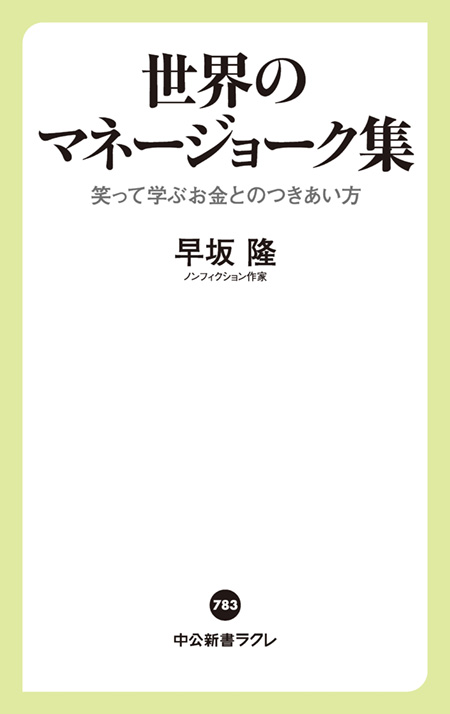
世界のマネージョーク集
笑って学ぶお金とのつきあい方
早坂隆 著
累計100万部突破の人気シリーズが、「マネー」をテーマに新登場。風刺・ユーモアを通して、お金についての知識や教養を深めることができる「本邦初?」の異色の一冊。そもそもお金とは、人間にとっていったい何? 欲望やいやらしさ、それでも憎めないところなど、お金があぶり出すものは、まさに人間の本質か。お金をめぐるニュースも絶えない現代。日本経済の混迷や「働き方」、格差問題、そして消えない将来不安……。ジョークの力で笑い飛ばそう!【目次】序章 お金とは何か?第1章 「働き方」を笑い飛ばそう第2章 経済をユーモアで第3章 貧しい人も富める人も第4章 ギャンブルは是か非か第5章 お金を巡る罪と罰第6章 お金を巡る人間模様最終章 欲と知恵 ――あとがきに代えて
2023/01/10 刊行
-
電子書籍
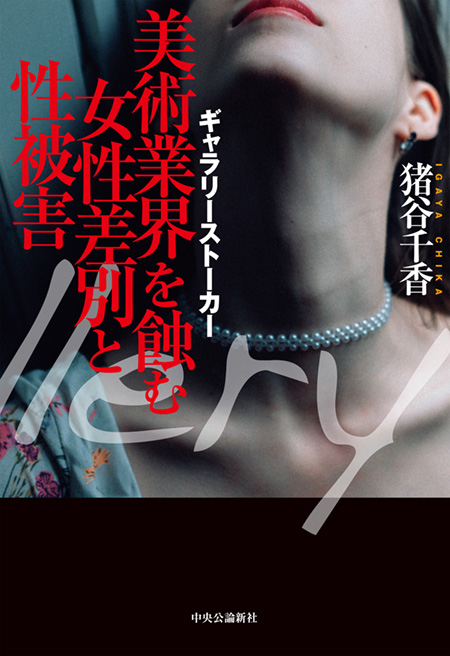
美術業界を蝕む女性差別と性被害
ギャラリーストーカー
猪谷千香 著
美大卒業後、作家として自らを売り出したいと願い、一人ギャラリーに立つ若い女性作家につきまとうギャラリーストーカー。美術業界の特殊なマーケットゆえに、被害から免れることが極めて難しいという異様な実態がある。孤軍奮闘する若い女性作家につきまとうのは、コレクターだけではない。作家の将来を左右する著名なキュレーター、批評家、美術家など、業界内部の権力者によるハラスメント、性被害も後を絶たない。煌びやかな美術業界。その舞台裏には、ハラスメントの温床となる異常な構造と体質、伝統があった! 弁護士ドットコムニュース編集部が総力を挙げて取材した実態と対策のすべて。
2023/01/10 刊行
-
電子書籍
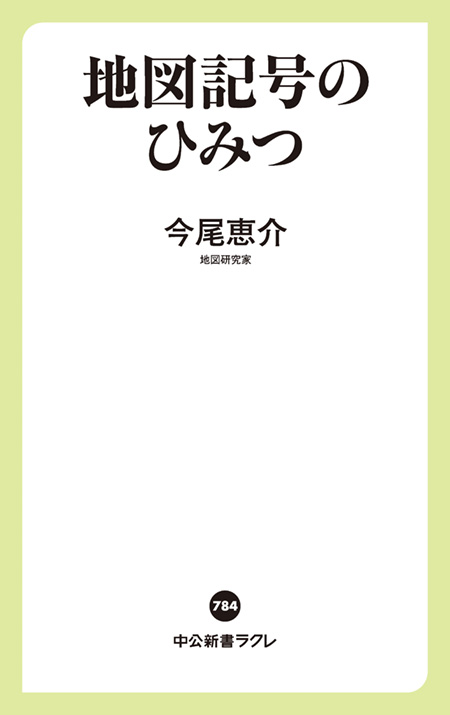
地図記号のひみつ
今尾恵介 著
学校で習って、誰もが親しんでいる地図記号。だが、実はまだまだ知られていないことも多い。日本で初めての地図記号「温泉」、ナチス・ドイツを連想させるとして「卍」からの変更が検討された「寺院」、高齢化を反映して小中学生から公募した「老人ホーム」……。地図記号からは、明治から令和に至る日本社会の変貌が読み取れるのだ。中学生の頃から地形図に親しんできた地図研究家が、地図記号の奥深い世界を紹介する。
2023/01/10 刊行
-
電子書籍
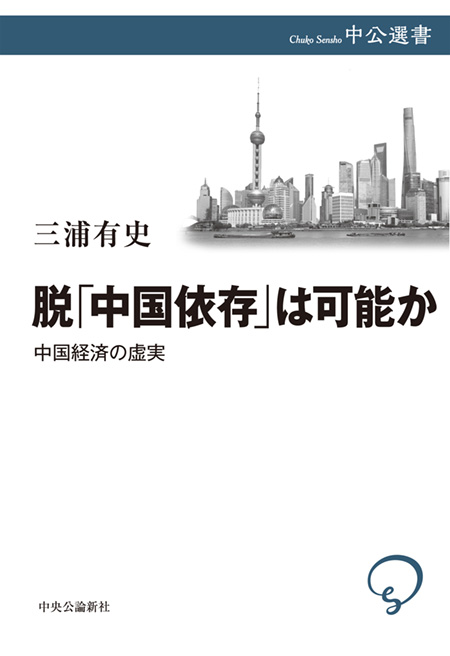
脱「中国依存」は可能か
中国経済の虚実
三浦有史 著
中国は経済成長率が目標を下回るなど減速が著しいが、世界における重みは着実に増し、日本の最大の貿易相手国でもある。だが、深まる一方の「中国依存」に対する不安も急速に高まっている。脱「中国依存」は可能なのか。本書は各種の統計データに基づき、中国経済の正しい見方を提示する。あわせて「共同富裕」や不動産バブルなど習近平政権下の経済政策・経済問題を検討し、今後を展望するとともに、日本の取るべき指針を示す。
2023/01/10 刊行
-
電子書籍
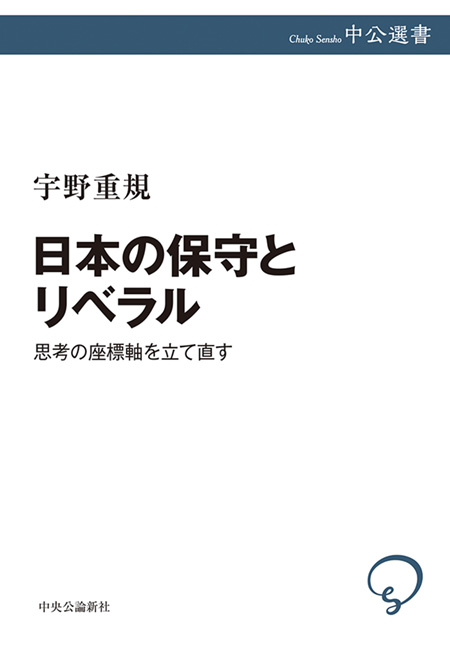
日本の保守とリベラル
思考の座標軸を立て直す
宇野重規 著
近年、日本政治においても、「右」と「左」ではなく、「保守」と「リベラル」という対立図式が語られることが多くなった。しかし、混乱した言論状況のなか、保守とは何か、あるいはリベラルとは何か、という共通理解があるとは言えない。本書は、欧米の政治思想史を参照しつつ、近現代の日本に保守とリベラル、それぞれの系譜を辿り、読み解く試みである。福沢諭吉、伊藤博文以来の知的営為を未来につなげ、真の「自由」を考える。
2023/01/10 刊行
-
電子書籍
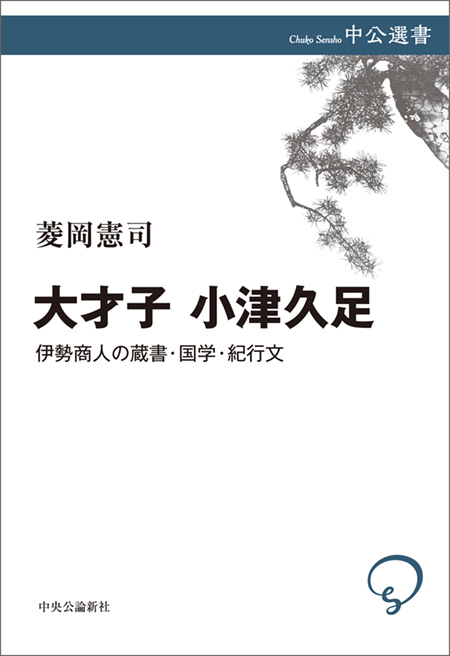
大才子 小津久足
伊勢商人の蔵書・国学・紀行文
菱岡憲司 著
映画監督・小津安二郎は異母弟の孫、伊勢松阪の富商、当世随一の人気作家・曲亭馬琴の友人、本居宣長の孫弟子にして、大蔵書家、そして江戸時代最大の紀行文作家・小津久足。湯浅屋与右衛門、小津桂窓、久足、雑学庵という四つの名前を使い分けて生きた男のそれぞれの営みを通して、近代とは似て非なる、あるがままの江戸社会を探る。文学、歴史、文化、経済を横断すると、あり得たかもしれない、もう一つの日本というパラレルワールドが見えてくる。
2023/01/10 刊行
-
電子書籍

洒落本大成全30巻セット
洒落本は江戸時代中期以降、遊里に取材した文学としてあらわれ、時代の人々の心とことば、風俗と生活を、あるがままに描き出した貴重な文化史料である。また日本語の表現力を極限にまで発揮した、世界にも珍しく高級な遊戯文学でもある。本大成は、天災人災を経て残存した、洒落本と見られるものを網羅することを志し、未翻刻のもの多数をふくむ六百余点の作品を採りあげた。それまでほとんど知られずに埋もれていた写本、稿本類、ことに先学の苦心の収集である、いわゆる地方郷土本のたぐいも多い。また、同一作品においても、各地の公私図書館、文庫、あるいは個人所蔵の現存する諸本をできるだけ広く捜査して対照検討し、初版、後版の別や、改題、改刻のあとなどを明らかにして、本文、挿絵はもとより、外形体裁からも、真に底本となし得る善本の選定にとくに意を用いた。著しい異本の存する場合は、重複をいとわずに採りあげている。活字翻刻にあたっては、原本に忠実を第一とし、技術上活字化の困難なもの、誤りの生ずるおそれのあるものは、写真版によって掲載した。また解題も、文学的鑑賞や注解は第二として、底本の書誌的事項や異版の記述などを主とした。これらの方針は、もっぱら研究の基礎として信憑し得るものを提供しようと期したからにほかならない。江戸時代後半の、いわゆる戯作文学の特色を典型的に示し、また物言う浮世絵として当代の風俗世風を微妙にまで示す、この洒落本の全面的享受と広範囲の研究的活用が、これでほぼ期待できるのではないかと思考する。※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。※
2023/01/01 刊行
-
電子書籍

源氏物語大成全13巻セット
再録された諸本4万、一般語彙カード50万枚、助詞・助動詞カード60万枚をもとに精博な校勘を加え、30余年の心血を注いで成った源氏研究資料の集大成。第一冊~第六冊 校異篇『校異源氏物語』(昭和17年刊行)の訂正増補版第七冊~第十一冊 索引篇校異篇の本文に拠り、一般語彙の部と助詞・助動詞の部および項目一覧の部にわかち、詳細な凡例を付した第十二冊 研究篇著者30年にわたるあらゆる基礎的研究を圧縮第十三冊 資料篇平安・鎌倉期の古註釈その他各種形態の貴重資料を忠実に翻刻※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
2023/01/01 刊行
-
電子書籍

三田村鳶魚全集全28巻セット
三田村鳶魚 著
江戸研究の第一人者にして、江戸学の祖。明治末年には江戸研究を確立、その視線は政治経済から市井の出来事まで広範にわたり、独自の文章で読み物としての面白さを併せ持つ。それは文献の渉猟のみならず、旧幕時代の生き証人への聞き書きなど、非常な熱意をもってなされた努力の賜物であった。文字どおり「生きる江戸百科事典」と称された鳶魚の業績の集大成として、本全集は「事典」的価値を有するものとなった。まさに「江戸」のすべてがここにある。※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
2023/01/01 刊行
-
電子書籍

定本西鶴全集全15巻セット
日本文学史において、芭蕉、近松と並び近世の重要な作家とされる西鶴。その全作品を初版本から忠実に翻刻した「底本」となる全集。元禄時代通行の略字・異体字はもとより、誤字・脱字、仮名遣いの誤りまですべて原文のまま翻刻する。西鶴は長い間その真価を認められず、明治中期以降、紅葉露伴等の文学に影響を与え、諸家によって研究が行われてからも、なおその研究は苦難の道をたどってきた。明治以来、発禁の憂き目をみた西鶴本の出版は、戦後解禁になり、はじめて本書に全集として納められた。その意義は絶大である。西鶴研究に緻密な業績をあげた三氏が編集委員となって全力を尽くし、本文の校訂のみならず、種々の点に完璧を期す。一段組・頭註付挿絵口絵多数※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。※
2023/01/01 刊行
-
電子書籍

未刊随筆百種全12巻セット
三田村鳶魚 編
江戸学の祖・三田村円魚の源泉となった、未刊行の近世随筆を精選。江戸の社会全般を知るための基本文献。第1巻岡場遊郭考/操曲入門口伝之巻/新役竜の庖丁/江戸拾葉/吉原春秋二度の景物/文政年間漫録/慶応雑談/博打仕方風聞書第2巻享和雑記/俗事百工起源/浅草志/勝扇子/青楼年暦考/天明紀聞寛政紀聞/済生堂五部雑録第3巻尾陽戯場事始/迂鈍/吉原失墜/村摂記/事々録/文政外記天保改革雑談第4巻業要集/傾城百人一首/古今東名所/かくやいかにの記/戯言養気集/文化秘筆第5巻七種宝納記/及瓜漫筆/天保風説見聞秘録/東都一流江戸節根元集/芸界きくまヽの記/秘登利古刀/寛延雑秘録第6巻宝丙密秘登津/世のすがた/きヽまにまに/豊島郡浅草地名考/白石先生宝貨事略追加/俗語問屋場始末/宝夢録/関東潔競伝/江戸図書目提要/家守杖第7巻洛水一滴抄/鄙雑俎/江戸愚俗徒然噺/素謡世々之蹟/崎陽賊船考/高田雲雀/露草雙紙/楓林腐草/柔話第8巻文廟外記/一得物語/江戸自慢/柳営譜略/公鑑/水戸前中納言殿御系記/三十三ヶ条案文/御町中御法度穿鑿遊女諸事出入書留/踊之著慕駒連/真佐喜のかつら/雑交苦口記/角力め組鳶人足一条第9巻愚痴拾遺物語/頃日全書/使奏心得之事/公侯凞績/享保通鑑/狩野五家譜/獄秘書/裏見寒話第10巻小うた打聞/柳亭浄瑠璃本目録/新徴組目録/六国列香之弁/六国四季之火合/在京在阪中日記/貴賤上下考/文政雑説集/天狗騒動実録/縁山砂子/十寸見編年集/雪の降道/花柳古鑑第11巻大江戸春秋/東台見聞誌/寛政秘策/江戸芝居年代記/天保新政録第12巻川越松山之記/峡陽来書/身延攻/近世珍談集/難廼為可話/門前地改更之実録/桐竹紋十郎手記/玉川参登鯉伝/一本草※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
2023/01/01 刊行







