ホーム > 検索結果
発行された時期:1973年1月からを含む書籍一覧
全10808件中 1170~1185件表示
-
電子書籍
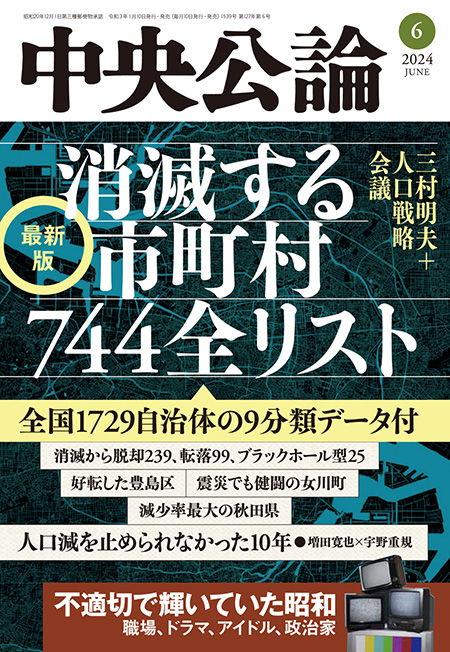
中央公論2024年6月号
中央公論編集部 編
== 特集 ==最新版 消滅する市町村 744全リスト◆『地方自治体「持続可能性」 分析レポート』――地域特性に応じた人口減少対策が必要▼三村明夫+人口戦略会議◆データ解説新たな「消滅」、半数が北海道・東北▼本誌編集部◆全国1729自治体の9分類データ◆〔対談〕人口減を止められなかった10年――外国人・寄合・デジタルは救いとなるか▼増田寛也×宇野重規◆10年前のショックを糧に消滅可能性都市から脱却した豊島区がいま目指すもの▼高際みゆき◆人口増加は結果、目的ではない東日本大震災があっても健闘の女川町▼須田善明◆人口減少率最大の秋田県、「資源県」の強みを活かす▼佐竹敬久◆多国籍タウン・大久保と向き合って図書館は移民のシェルターになれる▼米田雅朗◆〔座談会〕結婚に恋愛は必要か――少子化対策への手がかりを探る▼牛窪 恵×山田昌弘×干場弓子=======【時評2024】●故意の「付随的被害」? ガザが示すAI軍事利用の危険▼三牧聖子●『複合不況』から32年、新たなバブルは発生するか▼牧野邦昭●国立追悼施設の建設を再び考えるとき▼辻田真佐憲◆プリキュア「女の子だって暴れたい」から20年21世紀型アニメヒロインが大人をもひきつけるわけ▼鷲尾 天 聞き手:鈴木美潮== 特集 ==不適切で輝いていた昭和◆〔対談〕ハラスメントは減ったかもしれないが……職場の環境はよくなったのか?▼河合 薫×常見陽平◆令和の若者にウケるわけ昭和レトロはどこに向かう▼高野光平◆田中角栄、山口百恵はもう現れないカリスマなき時代政治も歌もチームで勝負▼枝野幸男◆〔対談〕暴言もあれば共感もあった令和の政治家は言葉の力を取り戻せるか▼御厨 貴×東 照二=======◆科学の通説はなぜ否定されるのか生き残る地球平面説▼松村一志◆伝統宗教が地方で腐る――自浄作用なき「聖域」で起きていること▼広野真嗣《好評連載》●学問と政治~新しい開国進取【第19回】学問の自由のありがたさ 日中歴史共同研究で痛感▼北岡伸一●皇室のお宝拝見【第3回】藤原定家筆《更級日記》▼本郷和人●文品 藤沢周平への旅【第14回】権力への階段――『風の果て』▼後藤正治●炎上するまくら【第90回】「笑点」新メンバー決定!▼立川吉笑《連載小説》●地上の楽園 【第3回】▼月村了衛●美土里?楽部【第13回】▼村田喜代子
2024/05/10 刊行
-
単行本
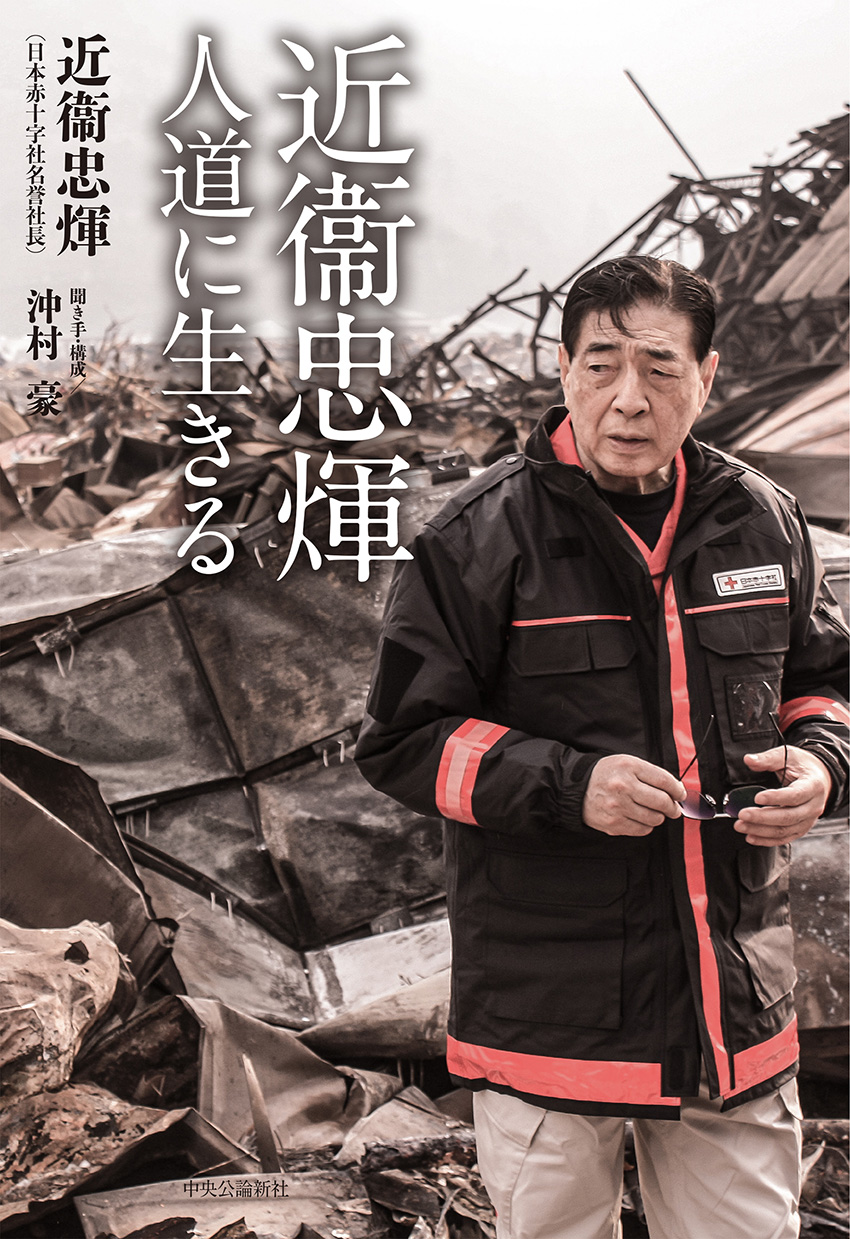
近衞忠煇 人道に生きる
近衞忠煇 著/沖村豪 聞き手・構成
旧華族の細川家に生まれ、母方の近衞家の養子に。学習院大学卒業後、2年間の英国留学を経て、日本赤十字社入社。日本赤十字社社長、また、アジア人として初めて国際赤十字・赤新月社連盟会長も務めた。本書では、幼い頃の記憶、青年期に受けた薫陶を胸に、武力紛争や自然災害などの危機の現場に半世紀あまり立ち続け、ぶれない人道主義を貫いた「赤十字人」の歩みを語る。
2024/05/09 刊行
-
単行本
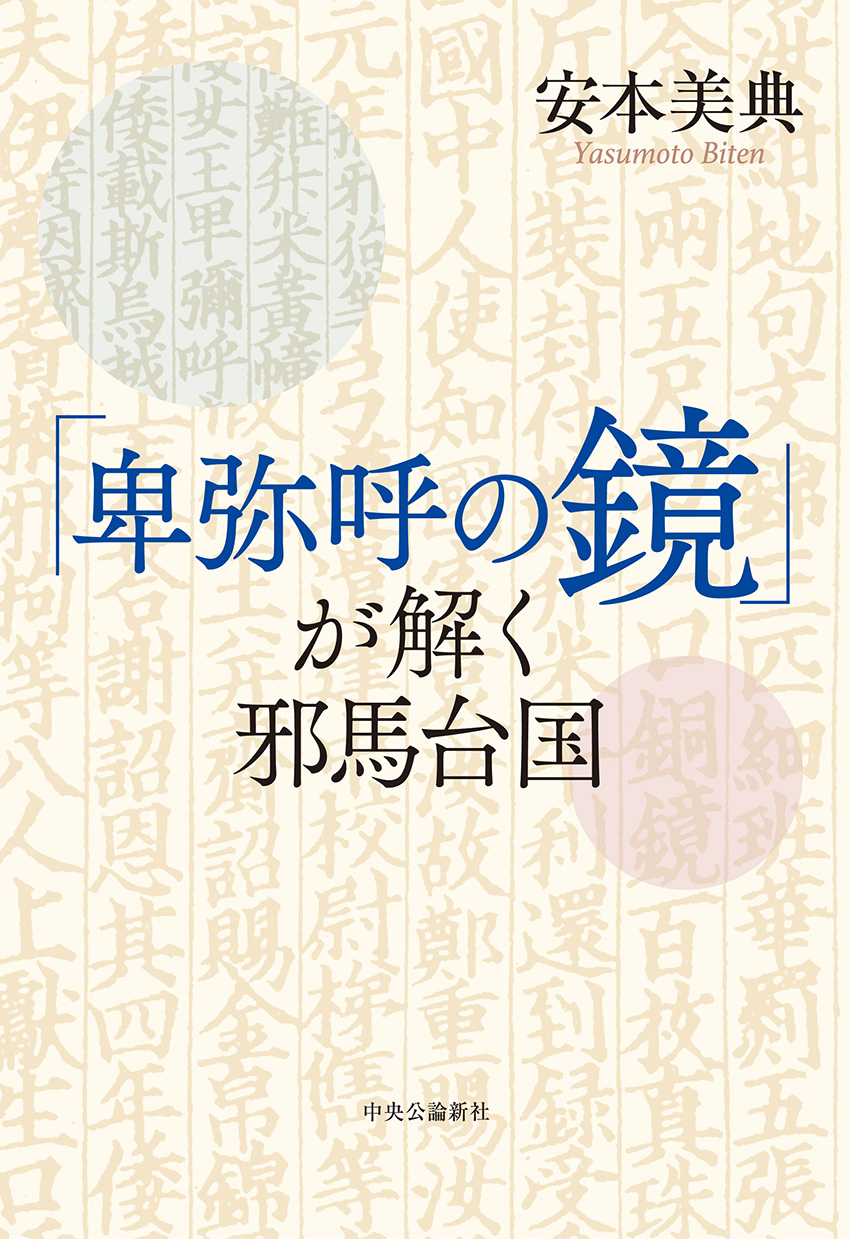
「卑弥呼の鏡」が解く邪馬台国
安本美典 著
京都府の元伊勢籠神社宮司家に伝来する二面の鏡こそ、魏の皇帝が卑弥呼に与えた百面の鏡の一部である! 最新のデータサイエンスが照らし出す邪馬台国の真実とは?
2024/05/09 刊行
-
中公新書ラクレ
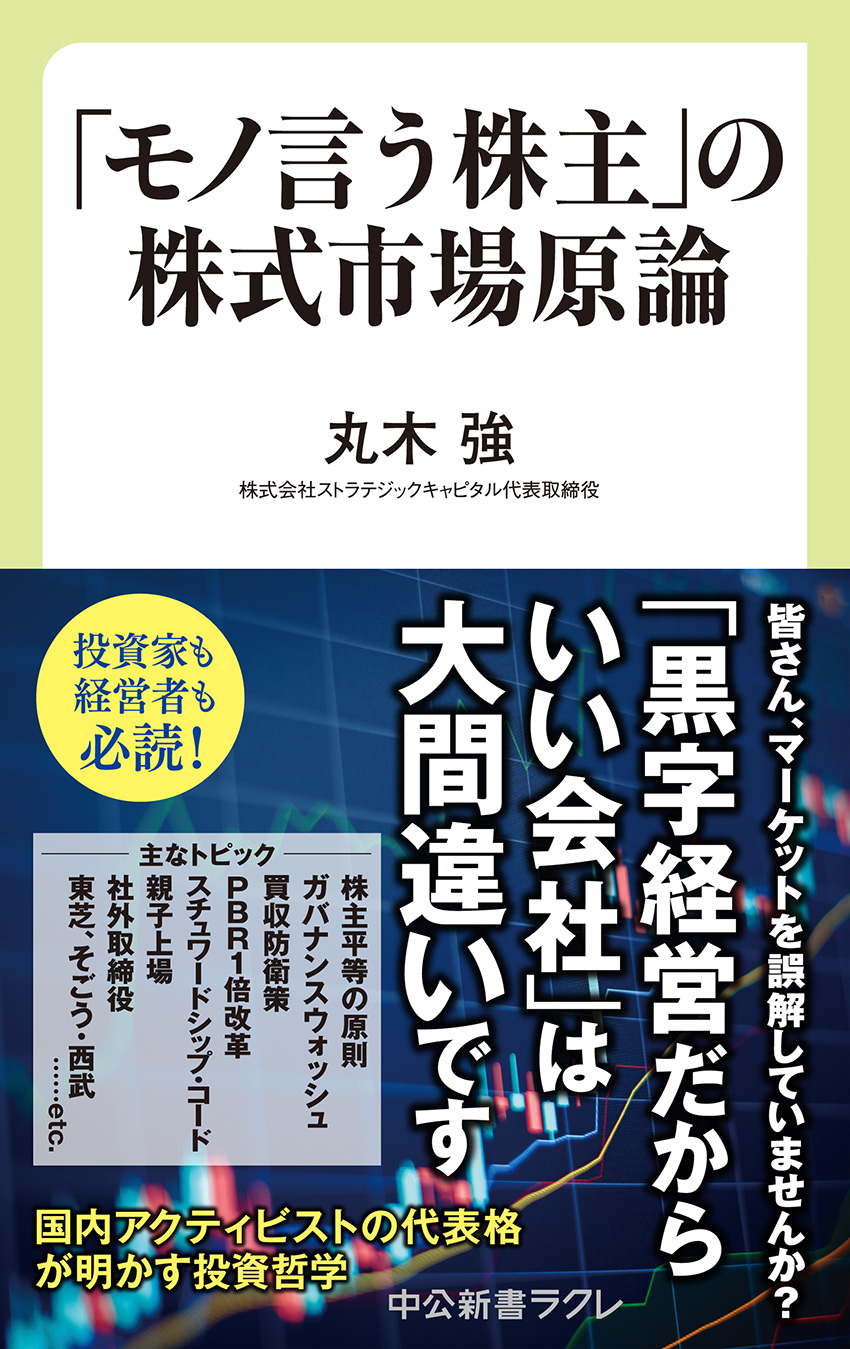
「モノ言う株主」の株式市場原論
丸木強 著
バブル期の最高値を更新した株価。だが30年で世界との差は広がり、日本は「ふつうの資本主義」を取り戻せるか否かの岐路にある。今なお研究開発投資への消極姿勢や、天下り人事等のガバナンス問題がはびこるが、著者は「社長はおやめになったほうがいい」と直言する国内アクティビスト(モノ言う株主)の代表格。市場と経営の本質を喝破するとともに、ピカピカの会社ではなく、あえて改善点が多い会社に投資する自らの哲学を明かす。
2024/05/09 刊行
-
中公選書
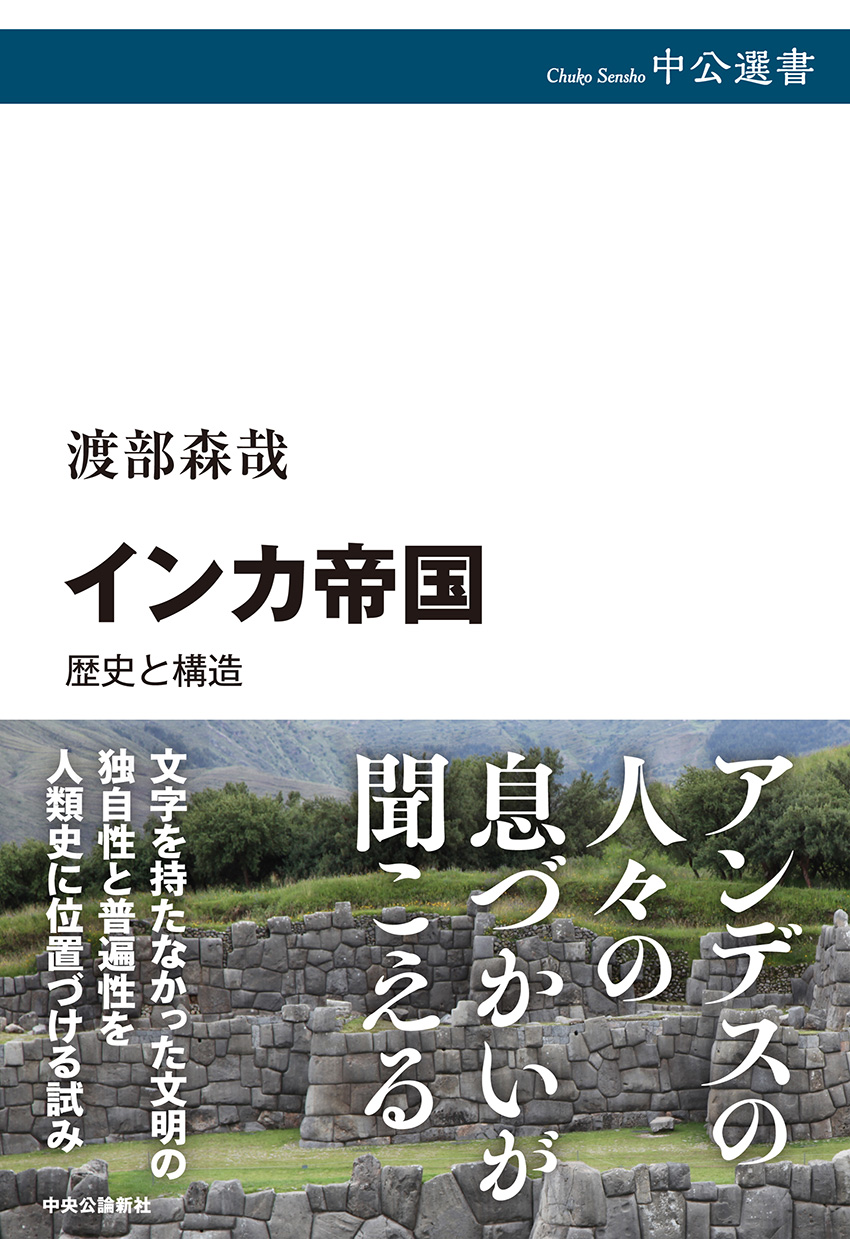
インカ帝国
歴史と構造
渡部森哉 著
古代アンデス文明の最終期、一五世紀に台頭した巨大な政治組織を、現在われわれはインカ帝国と呼んでいる。その領域は南北四〇〇〇キロに及び、およそ八〇もの民族集団を統治した。本書では当時の人々が使用した言葉と具体的なモノに着目し、個別的な分析を積み重ねながらインカ帝国の全体像を生き生きと再現する。ひいては、文字を持たなかったアンデス文明を普遍的な人類史的視野のもとに位置づけることを目指す野心的な試みである。
2024/05/09 刊行
-
中公選書
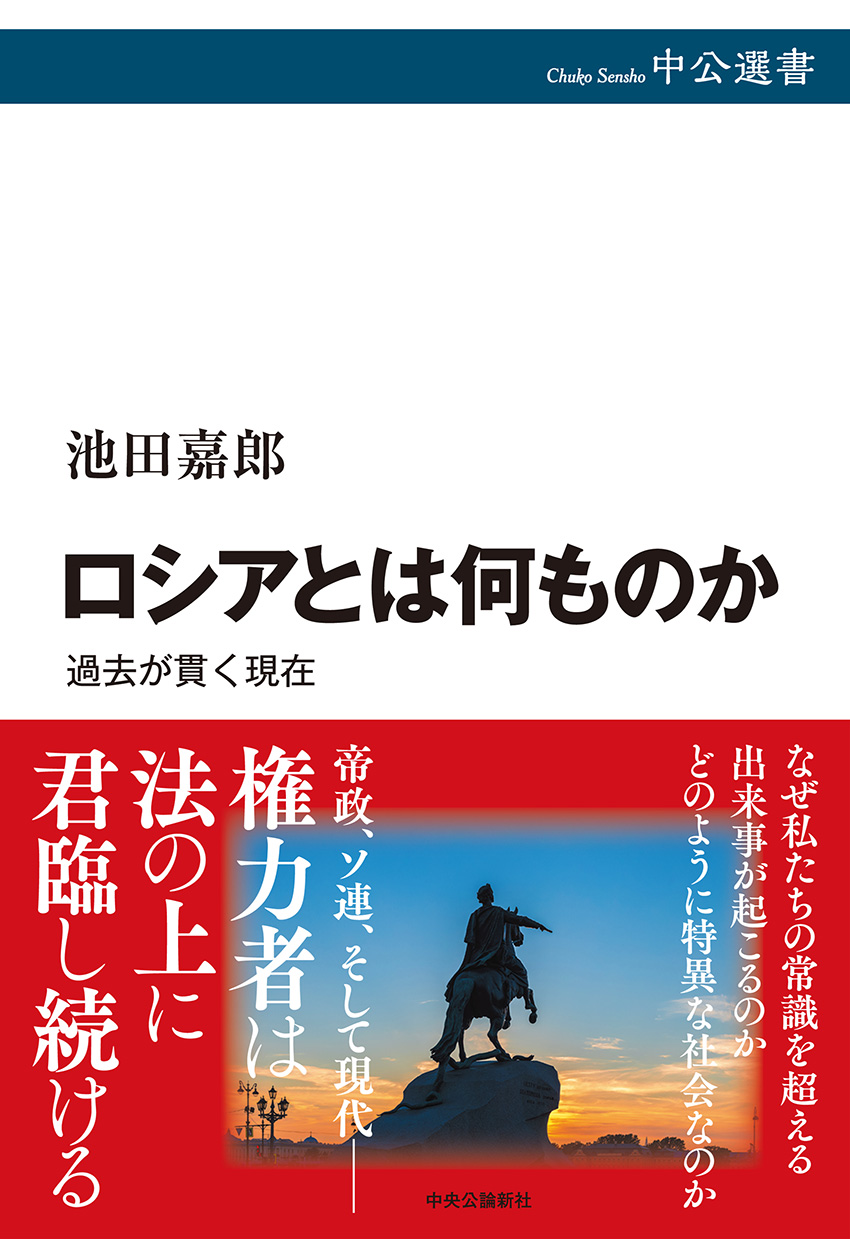
ロシアとは何ものか
過去が貫く現在
池田嘉郎 著
ロシアは過去一〇〇年ほどのあいだに、帝政から共産党独裁へ、そして大統領制国家へと変転を遂げた。だが、ロシア史を貫く基本構造は同じである――。ロシア史を大づかみにとらえた上で、ロシア革命期の自由主義政党カデットや社会主義者最左派のボリシェビキの活動の実態から、プーチン政権の権力のあり方までを考察。そこに生きた人間の運命を通して、世界史の今後にとって大きな意味をもつ「ロシアとは何ものか」を見極める。
2024/05/09 刊行
-
中公選書
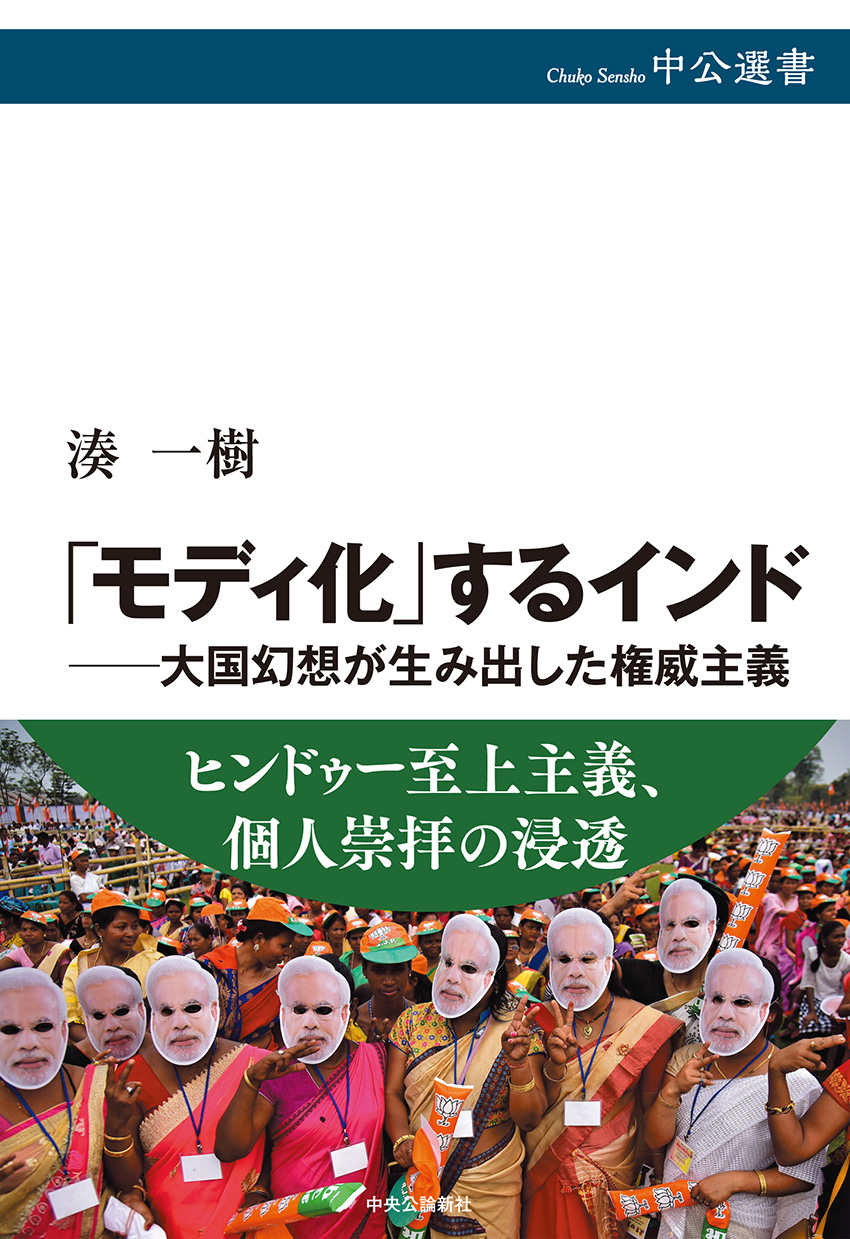
「モディ化」するインド―大国幻想が生み出した権威主義
湊一樹 著
世界一の人口、急成長する経済、世界最大の民主主義、グローバルサウスの盟主……国際舞台で存在感を増す「大国インド」。だが、足元では権威主義化が急速に進む。2014年にナレンドラ・モディが首相に就任して以降、権力維持・拡大のために、実態と離れた「大国幻想」を振りまき、一強体制を推進しているからだ。本書は、政治・経済・社会・外交に至るまで「モディ化」が進行するインドの実像と問題を冷徹な視点から描き出す。
2024/05/09 刊行
-
電子書籍
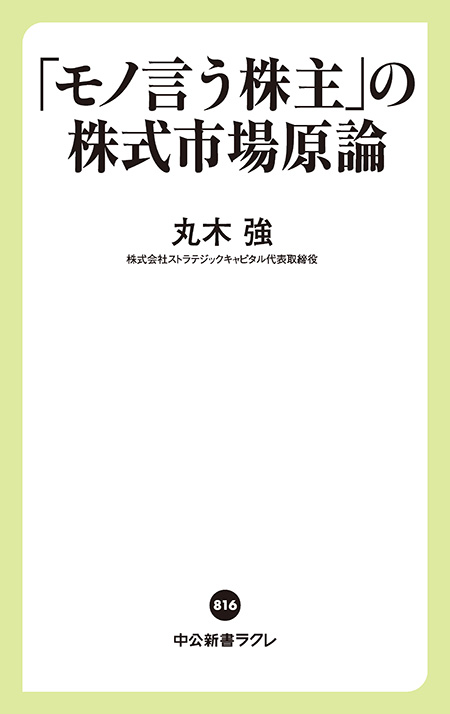
「モノ言う株主」の株式市場原論
丸木強 著
新NISAで投資への関心が高まったこともあり、株価はバブル期の最高値を超えた。だが「失われた30年」で開いた海外との差はまだまだ大きい。逆にいえば、やり方しだいで成長に転じる潜在力が日本企業にはあるとも言えよう。それでは、どこをどう変えればいいのか? まずは「ふつうの資本主義」を取り戻すことから始めなければならない。しかるに、日本企業は内部留保を抱え、研究開発や新規事業への投資に消極的であり、親方日の丸からの天下りなどガバナンスにも問題が大きい。著者は、そんな諸課題を抱える企業を相手に「社長はおやめになったほうがいい」と直言してきた国内アクティビスト(モノ言う株主)の代表格・株式市場と企業経営の本質を喝破するとともに、ピカピカの会社ではなく、あえて改善点が多い会社に投資してきた自らの哲学を明かす。
2024/05/09 刊行
-
電子書籍
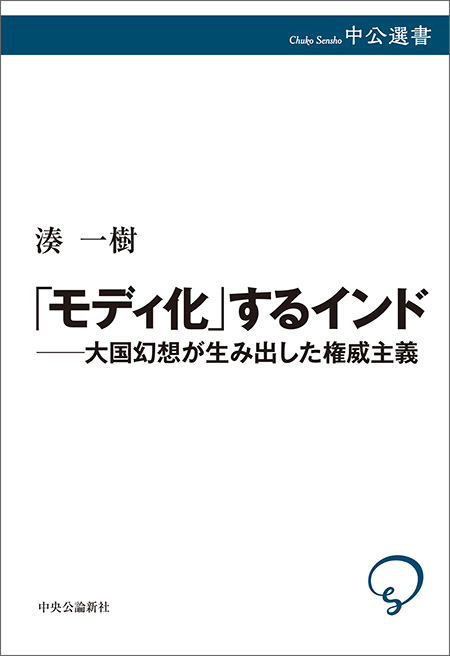
「モディ化」するインド―大国幻想が生み出した権威主義
湊一樹 著
世界一の人口、急成長する経済、世界最大の民主主義、グローバルサウスの盟主……国際舞台で存在感を増す「大国インド」。だが、足元では権威主義化が急速に進む。2014年にナレンドラ・モディが首相に就任して以降、権力維持・拡大のために、実態と離れた「大国幻想」を振りまき、一強体制を推進しているからだ。本書は、政治・経済・社会・外交に至るまで「モディ化」が進行するインドの実像と問題を冷徹な視点から描き出す。
2024/05/09 刊行
-
電子書籍
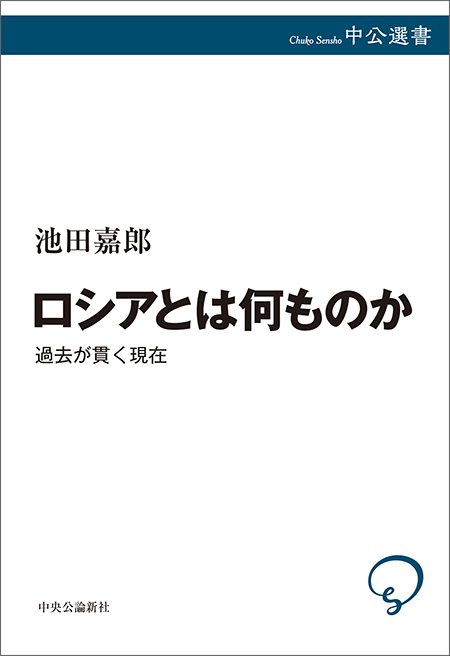
ロシアとは何ものか
過去が貫く現在
池田嘉郎 著
ロシアは過去一〇〇年ほどのあいだに、帝政から共産党独裁へ、そして大統領制国家へと変転を遂げた。だが、ロシア史を貫く基本構造は同じである――。ロシア史を大づかみにとらえた上で、ロシア革命期の自由主義政党カデットや社会主義者最左派のボリシェビキの活動の実態から、プーチン政権の権力のあり方までを考察。そこに生きた人間の運命を通して、世界史の今後にとって大きな意味をもつ「ロシアとは何ものか」を見極める。
2024/05/09 刊行
-
電子書籍
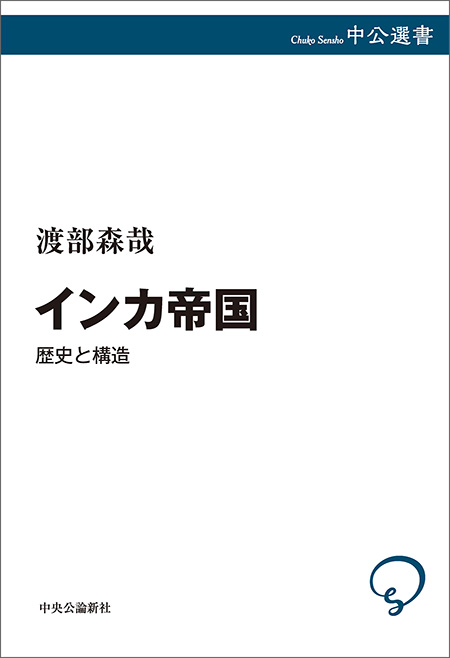
インカ帝国
歴史と構造
渡部森哉 著
古代アンデス文明の最終期、一五世紀に台頭した巨大な政治組織を、現在われわれはインカ帝国と呼んでいる。その領域は南北四〇〇〇キロに及び、およそ八〇もの民族集団を統治した。本書では当時の人々が使用した言葉と具体的なモノに着目し、個別的な分析を積み重ねながらインカ帝国の全体像を生き生きと再現する。ひいては、文字を持たなかったアンデス文明を普遍的な人類史的視野のもとに位置づけることを目指す野心的な試みである。
2024/05/09 刊行
-
電子書籍
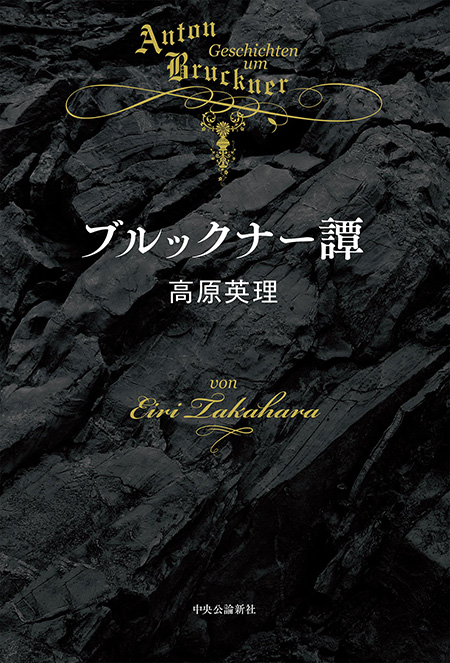
ブルックナー譚
高原英理 著
泥臭い野心と権威への追従――。残念に生きたその人は、いかにして巨大かつ精緻な交響曲を生んだのか? 21世紀の今、多くの聴衆に支持され、時代と響き合うに至った作曲家の実像。その生涯から場面(エピソード)を小説化、事実記録(伝記)と組み合わせたハイブリッド評伝。【ブルックナー生誕200年記念企画】*目次より序第一章 出生から教師時代まで(1824-1855)第二章 リンツでの修業時代(1856-1868)第三章 ヴィーンでの苦難の日々(1868-1878)第四章 遅れに遅れた名声(1879-1889)第五章 晩年(1890-1896)エピローグ 死後の名声後記
2024/04/30 刊行
-
電子書籍
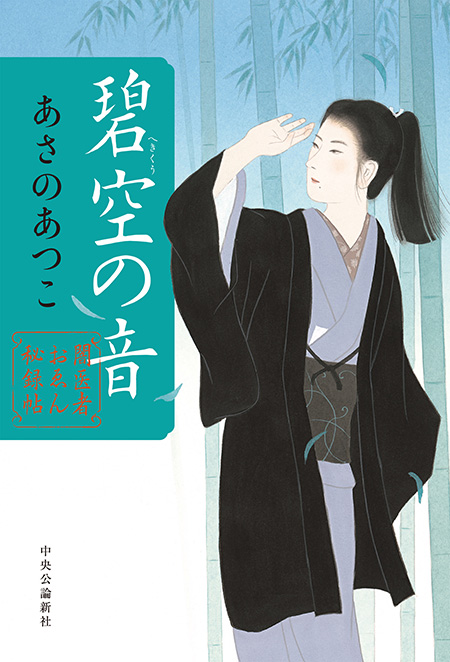
闇医者おゑん秘録帖
碧空の音
あさのあつこ 著
わけありの女たちを診療するおゑんの許へ、何かを極度に怖れている妊婦が訪ねてきた。彼女は目を血走らせ、十両を差し出しながら言った。「お願いします。この子を産ませてください」と――。後日、吉原惣名主に依頼され診ることになった女郎も、奇矯な妊婦だった。大店の主人に身請けされることが決まっていて、その子を身籠っていながら、「産みたくない」と叫びながら自死しようとしたのだ。彼女たちは何者で、何故、一人は出産を望み、もう一人は出産を拒否するのか? 疑念がきざしたおゑんは、遊女連続死を調べる過程で親しくなった吉原の用心棒・甲三郎や薬草に詳しい末音らの力を借り、その謎に迫ろうとするが……。「読売新聞オンライン」人気連載、待望の書籍化。
2024/04/30 刊行
-
電子書籍
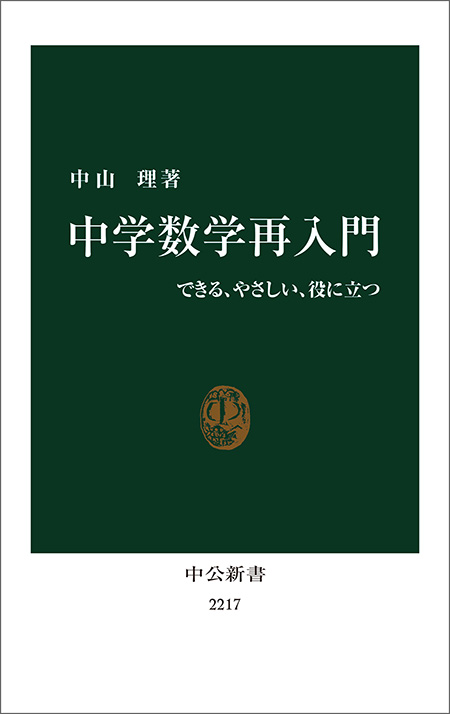
中学数学再入門
できる、やさしい、役に立つ
中山理 著
算数は好きだったのに、中学の数学になると、とたんに苦手になる人は多いでしょう。マイナスの数や、文字式の移項といった箇所でつまずきがちです。「負の数に負の数をかけるとなぜ正の数になるのか」「因数分解の公式はなぜ成り立つのか」「証明が苦手だが、どうすればできるようになるか」など、丸暗記でなく、「なぜそうなるか」をていねいに説明し、間違えやすいポイントを解説します。「苦手」が「好き」に変わる21章。
2024/04/30 刊行
-
電子書籍
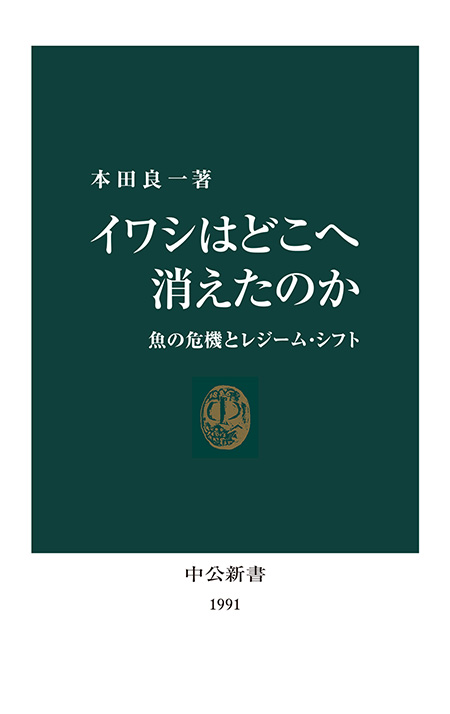
イワシはどこへ消えたのか
魚の危機とレジーム・シフト
本田良一 著
イワシが獲れなくなった。全国水揚げ量はピーク時の一六〇分の一となり、すでに私たちにとって身近な魚とは言えなくなりつつある。一方で、サンマは豊漁が続いている。なぜこのようなことが起こるのか。本書は、九〇年代以降、定説となった「レジーム・シフト」による魚種交替という考え方をわかりやすく説明し、水産行政や地元産業への影響を通して、人類の共有財産である水産資源をどう守っていくかを考える。
2024/04/30 刊行







