- 2025 12/23
- まえがき公開
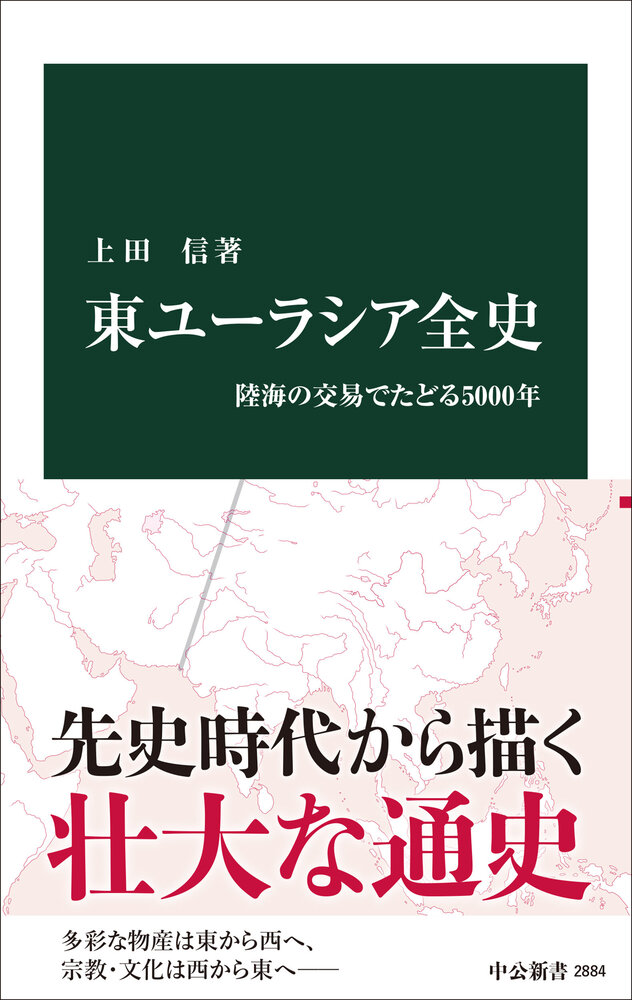
広大なユーラシア大陸は中央の乾燥地帯を境に生態環境が二分される。日本列島を含む東側では古来、遊牧・農耕・海洋の諸文明が興亡。シルクロードほか陸海の路を介して多彩な物産、また宗教・文化が東西を往来した。ソグド商人やペルシア・アラビア商人の活躍、モンゴル帝国の隆盛と解体、明の鄭和の南海遠征、大航海時代の展開から、欧米列強の極東進出、アジア・太平洋戦争まで――。交易をキーワードに壮大な歴史をたどる。 『東ユーラシア全史 陸海の交易でたどる5000年』の「おわりに」を公開します。
東・西ユーラシアと交易
先史時代に始まり1945年に及ぶ本書の要点は、次のようになる。
夏と冬の降水量が反転する生態環境上の境界線が、歴史に深く関わっている。世界史地図を開いてみると、中国史で統一王朝と呼ばれる漢・唐・清の版図は、この線を越えて西に広がることはなく、ペルシア帝国やアレクサンドロス大王の東方遠征も、この線を越えて東に進むことはなかった。アッバース朝と唐が戦ったタラス河畔は、この線上にある。この境界線を本書では「東・西ユーラシア境界線」とし、その東側の歴史を扱った。
東ユーラシアには多様な生態環境が広がり、歴史はその影響を受ける。気候を左右する風に着目して、偏西風アジア、モンスーン陸域アジア、モンスーン海域アジアという地理的な区分を立てた。その北限は北緯60度あたり、それよりも北は極東風に支配されるシベリア高原である。南限は南緯10度あたりで、その南では貿易風が吹く。16世紀に世界一周を成し遂げたスペイン船は、モンスーン海域がポルトガルの勢力圏であったため、寄港せずに貿易風帯を航行している。
生態環境の違いは、各地の物産の違いとなり、その差異に基づいて現生人類は交易を展開してきた。ステップロード(草原の路)、シルクロード(絹の路)、セラミックロード(陶磁器の路)、ムスクロード(麝香の路)、セーブルロード(クロテンの毛皮の路)などの交易路を介して、東西の交易が行われた。また、カウリーロード(タカラガイの路)は、南北に連なっている。低地から高地へと茶が運ばれ、「茶馬古道」として知られる交易路が雲南や四川とチベット高原とを結んでいた。
一般に「交易」というと物産の往来がイメージされるが、本書では知財・人財の空間的な移動も含めて考察した。物産の交易は、大局的にみると生態環境の多様性が高い東から西へと取引されてきた。知財に含まれる宗教や理論、技術などは、西から東へと移動する傾向が見られる。バラモンや仏教の教えはインドから東南アジアやチベット、中国へと伝わり、時代が下るとイスラームやキリスト教も西ユーラシアから東へと伝わった。
東と西のユーラシアにまたがる交易の中核となった地域が、西ユーラシアの東縁に位置し境界線に隣接するバクトリアとソグディアナである。仏教はインドからバクトリアを経由して東へと伝わり、僧の玄奘などもこの地を経由してインドに向かった。ソグディアナは、商人や武人など数多くの人財を東ユーラシアに供給した。
東ユーラシア交易史概観
交易の観点から歴史をたどると、先史時代には草原の路を通じてアワやキビ、ムギなどの作物が伝播し、青銅器などを作る技術は西から東へと伝わった。イネは漢地の華東で栽培が始まり、モンスーン陸域アジアから海域アジアへと伝播し、インド亜大陸まで広がった。青銅器文化も同じ経路で伝わり、各地で独自に発展したと考えられる。偏西風アジアとモンスーンアジアとは、タカラガイの交易などを通じて、紀元前11世紀頃にはすでに往来が始まっていた。
紀元1世紀半ば頃、気候変動のために草原の路を安全に行き交うことができなくなると、タリム盆地、タクラマカン沙漠周辺のオアシスを結ぶ路の重要性が増す。ほぼ同じ時期に漢帝国からモンスーン陸域アジアへと交易ルートが伸び、さらに海域アジアのインドシナ半島の港市との交易が始まる。
5世紀から8世紀にかけて、偏西風アジアの草原から勃興した遊牧騎馬民の鮮卑拓跋部とその系譜を引く隋・唐帝国、テュルク系の突厥などの勢力が、東ユーラシアの北に広大な交易圏を形成する。一方、モンスーンアジアでも、交易圏が形成される。港市国家の間に安定したネットワークが形成され、シュリーヴィジャヤと呼ばれる連合体が形成された。
9世紀に気候の寒冷化・乾燥化のために、遊牧騎馬勢力は分裂・衰退し、代わってマンチュリア(満洲)からキタイ・金という勢力が勃興してくる。他方、モンスーン海域アジアでは後背地を有する港市国家が形成されるとともに、ペルシア・アラビア商人が活躍するようになる。この二つの交易圏は、モンスーン陸域アジアを領域とする宋(ならびに南宋)が接合する。12世紀には、新たに日本が東ユーラシアの通商に加わり、銅銭などを輸入した。
東ユーラシアで一体化し始めた南北交易圏に、さらにモンゴル高原やオアシス都市国家群を加えてユーラシア全域を覆う通商圏を形成したのがモンゴル帝国である。マルコ・ポーロの旅は、この通商圏を巡るものであった。
モンゴル帝国が14世紀半ばに分裂すると、陸の交易路は寸断され、通商はもっぱら海域で展開されるようになる。倭寇と呼ばれる密貿易商人、ポルトガル出身の商人や宣教師などが、この海域アジアを往来した。17世紀になると、清朝や江戸武家政権、オランダ東インド会社などの陸上の勢力が、海域アジアの通商を管理するようになる。そうして19世紀半ば、ロシアとイギリスなどのヨーロッパの勢力が東・西ユーラシア境界線を越えて進出し、太平洋を渡ってアメリカも参入する。こうして東ユーラシアは環球に包摂されるようになった。
グローブか「環球」か
1860年代に東ユーラシアは、地球規模のシステムに包摂される。
「地球」という日本語に対応する英語には、アース(earth)とグローブ(globe)の二つがある。後者はグローバルやグローバリゼーションといったカタカナ語に含まれている言葉である。アースとグローブの違いはどこにあるか、解答を導き出す問いは「アースの中心はどこか、グローブの中心はどこか」となる。
アースの中心は天体としての地球の中心ということになり、地中深くマントルを突き抜けたコアの中心、ということになる。一方、グローブの中心は球体としての地表の中心ということ。大学の授業で学生に問うと、「アメリカ合衆国の連邦政府が置かれるワシントン」という回答も聞かれるが、正答は「地表のどこでも中心になりうる」となる。自分がいまいるところを中心に同心円を描き、その半径を地表に沿って伸ばしていくと、地球の円周を4万キロとした場合、その4分の1の半径1万キロまで広げたところから、地表の反対側に回り込み、最終的に自分の立地点から見て地球の裏側の一点に収斂する。
こうしたイメージを表現するグローブの訳語として、筆者が「環球」を造った。「環」とは円を描くように囲む、めぐる輪であり、「球」とは球体を意味する文字となる。したがって、「環球」は直訳すると「球体を巡る」「球体を取り巻く」というような意味になる。
現代中国語でグローブの訳語として、一般には「全球」が充てられるが、「環球」が用いられる場合がある。たとえば国際ニュースを扱う新聞「環球時報」はGlobal Times、ユニバーサル・スタジオは「環球影城」と表記される。もともとグローブやユニバースといった英語には、「寰球」という訳語が用いられていた。「寰」には天下や世界という意味があり、「寰宇」となると「全世界」と対応する。「寰球」と音通であることから「●球」(環球)が広く用いられるようになった。筆者の造語に由来する「環球」とは来歴が異なる。
※●は王へんに「不」
21世紀になってから、歴史学界ではグローバルヒストリーという潮流がもてはやされている。国家や地域という枠にとらわれず、地球規模でヒトやモノ、イミの伝播などを研究する歴史学の一分野であるが、筆者が構想する「環球史」は既存のグローバルヒストリーとは一線を画したいと考えている。
環球史の基本は「私が立つここは環球の真ん中、そしてあなたがいるそこも環球の真ん中」となる。地域を越えた移動や伝播だけを対象とするのではなく、起点を定めて、そこを中心にして歴史的な事象を再構成する。本書から事例を拾うならば、明朝の皇帝として南京または北京にいる永楽帝と、メッカ巡礼者を父に持つ鄭和とでは、それぞれが生きた世界がどのように異なっているかを考察するのである。一般的なグローバルヒストリーでは捨象されがちな、個々人の生きざまが、環球史では重要な研究課題となる。
東ユーラシアの中の日本
1945年以降になっても、東ユーラシアで先頭に立つのは日本、という意識が残る。
アジア・太平洋戦争の戦禍による社会経済的荒廃からの復興と、国際秩序への再統合が急務とされた。1951年のサンフランシスコ講和条約および同時に締結された日米安全保障条約は、日本が主権を回復する一方で、自衛権の行使および軍備の保持に関する制約と、米国による安全保障の肩代わりを制度化するものであった。この体制は、日本が再武装を回避しつつ、経済的再建に国力を集中する条件を形成した点で、冷戦下における特異な国家戦略の基盤となった。
1950年に始まる朝鮮戦争の特需により復興の糸口をつかむ。冷戦構造の下、日本は戦争賠償を通じて東南アジア諸国との関係修復を進めた。対フィリピン・ビルマ・インドネシアなどに対して供与された賠償資金・役務は、道路、港湾、発電所といった基礎インフラ整備に利用され、受給国にとっては戦後復興と工業化の初期投資としての意味を有した。日本はこうしたアジア諸国との関係を軸に、高度経済成長へと向かう。
この時期に発表されたのが梅棹忠夫の「文明の生態史観」である。
1960年代以降、賠償は経済協力へと制度的に移行し、日本のODA(政府開発援助)はアジア諸国の開発計画と連動する形で拡充された。戦後賠償に代わるものとしてとりわけ円借款は、資金供与国である日本の建設業や重機メーカーの対アジア進出を可能にし、供与国と受給国の経済的連関を強化した。
1970年代から80年代にかけて、韓国・台湾・香港・シンガポールなどのいわゆる「新興工業経済地域(NIES)」が急成長を遂げ、東アジアにおける輸出主導型工業化の先行事例として国際的に注目を集めた。これらの経済は、米国市場を主たる輸出先としつつも、域内における生産分業体制の構築を進めた。日本企業がアジア諸国に進出する過程で、資本・技術・部品が南方に移転した。その結果、韓国・台湾が中間財の供給者として位置づけられ、ASEAN諸国が労働集約的組立工程を担うという「雁行型経済発展」モデルが形成された。
この雁行型モデルは、先進国が新技術・新産業を先行導入し、それが追随国に順次移転するという構造を想定していた。日本を先頭に、韓国・台湾、さらに東南アジア諸国、中国へと、技術・資本・労働力の再配置が行われ、アジア域内の貿易と投資の相互依存性が飛躍的に高まった。1990年代以降、中国の改革開放政策の本格化により、中国は「世界の工場」としてこの雁行の最後尾に加わる。さらに繊維生産の受注地としてバングラデシュが加わり、東ユーラシアの中にサプライチェーンが張り巡らされることになった。
この時期に発表されたのが、川勝平太の『文明の海洋史観』であった。
しかし2000年代後半以降、この雁行型発展モデルは徐々に機能不全を示し始める。その要因の一つは、莫大な市場を有する中国一国の中に、先端の産業から労働集約的な産業までが一つのセットとして成立したことが挙げられる。日本はバブル経済の崩壊後、韓国に追い上げられ、東ユーラシアの中で劣後していく。
日本がこれから採るべき方策は、モノの交易からイミの交易への転換であろう。日本は東ユーラシアを介して、さまざまな文化を受け入れ、熟成させてきた。こうした文化の多様性を活かして、製品の輸出から、知財の輸出へと転換する必要がある。
(まえがき、著者略歴は『東ユーラシア全史』初版刊行時のものです)
