- 2025 10/21
- まえがき公開
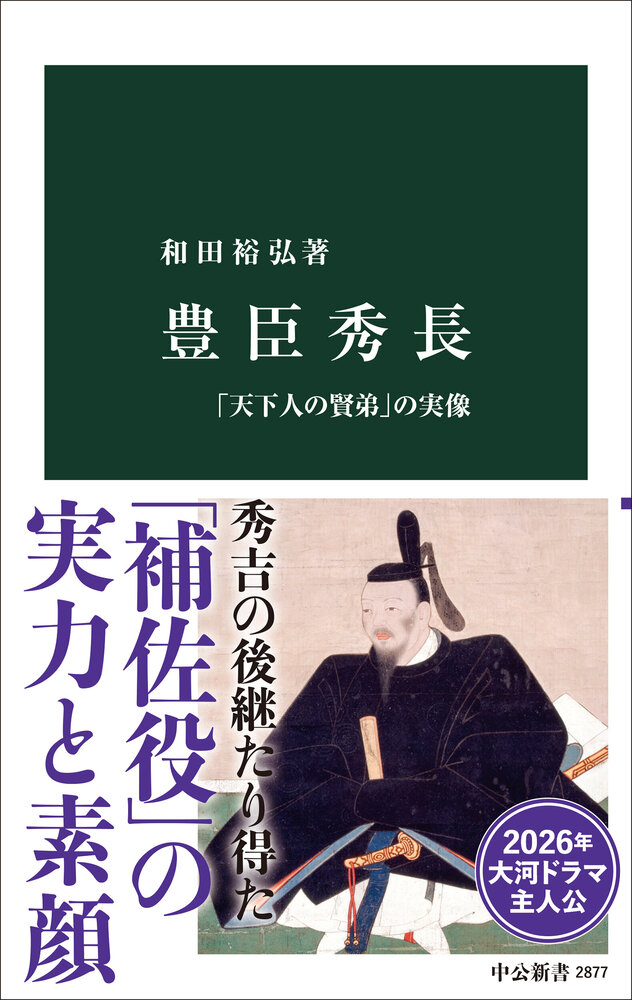
兄秀吉を天下人に押し上げた功労者、豊臣秀長。本能寺の変後、山崎・賤ヶ岳の両合戦に従軍して覇権確立に貢献し、四国・九州平定戦で大軍勢を指揮する。大功により紀伊・和泉・大和を拝領。郡山城を居城とし、大和大納言と呼ばれた。忠実無比の補佐役というイメージだが、それにとどまらぬ秀吉の「名代」であり、後継たり得る実力者でもあった。諸大名の信望厚く、豊臣政権を支えながらも志半ばで病没した五十余年の生涯。 『豊臣秀長 「天下人の賢弟」の実像』の 「はじめに」を公開します。
豊臣秀長は、近年では比較的知られるようになった歴史上の人物の一人だろう。兄秀吉を天下人たらしめた功労者である。一般的には、小説やテレビドラマなどの影響で豊臣政権ナンバー2の補佐役として、秀吉を陰で支えた有能な実弟という印象であろう。その性格も温厚で調整能力に長け、秀吉と有力大名との折衝役として秀吉の高圧的な態度を陰で支えていたともいわれる。また、秀吉は人たらし、として知られるが、初期の秀吉家臣などは、じつは秀長を慕って秀吉の配下になった者もいたという。
この一方、少し歴史に詳しい人になると、蓄財家という側面を見出している。守銭奴と評する見方すらある。秀吉の九州攻めの時、秀長はようやく届いた兵粮米を全軍に配るどころか、味方に高値で売りつけたという逸話がある。さらに、家臣が材木の販売で不正を働いたことや、死去した際に莫大な遺産を蓄えていたことなどから金の亡者という評価が下されている。兵粮米を高値で売りつけたというのは、信憑性の低い記録であり、また材木での不正についても詳細に検討する必要がある。莫大な遺産を蓄えていたというのは、権力者としては当然であり、秀長の実績を否定する材料にはならないだろう。
武将としての能力についても両様の見方がある。秀吉の右腕として各地の平定作戦などを着実に実行していたという肯定的な見方もあれば、九州平定戦においては、島津軍の夜襲に油断したことを秀吉から叱責されたともいう。また、柴田勝家と対決した賤ヶ岳の戦いに際しては、秀吉と親密だった中川清秀の危急に援軍を出さずに清秀を見殺しにしたと評価され、のちに秀吉から満座の中で、「種違い」と揶揄されたという逸話もある。もちろん、信用できない。むしろ秀吉の命令を忠実に守っていた印象である。このように秀長に対する見方は、相反する評価が混在している。これは取りも直さず、秀長に対する研究の遅れでもある。
秀吉の前半生も謎だらけだが、秀長になるとさらに不明である。秀吉の弟であるのは間違いない。定説では異父弟だが、同父弟という見方もある。ただし、両説ともに信頼できる史料では確認できない。詳しくは本文で触れるが、おそらく同父弟であろう。
秀長の史上への登場も秀吉以上に伝説的である。一般的には、徒手空拳で武士に取り立てられた秀吉が、譜代の家臣を持たないため、「百姓」をしていた秀長を家来として誘ったといわれる。可能性はまったくないとはいえないが、こうした「伝説」に引きずられることを排除すれば別の見方もできよう。その一つが「秀長」の前に名乗っていた「長秀」という諱を読み解くことである。
秀長を語る時に、しばしば引用される有名な一節がある。九州の名門大名である大友宗麟が薩摩の島津氏の圧迫に耐えかねて、秀吉を頼って大坂城に参礼したあと、秀長が宗麟の手を取り、「内々の儀は宗易(千利休の法名)、公儀の事は宰相(秀長)存候」と助言したという。私的なことは千利休、公的なことは秀長が対応する、と理解されており、豊臣政権における秀長の立ち位置が象徴される言葉でもある。秀長と利休が両輪となって豊臣政権を支えていたという認識である。実際、秀長の病死後すぐに利休は失脚し、切腹に追い込まれている。
秀長が病没したのは天正十九年(1591年)正月。前年には関東の雄北条氏を降し、東北も平定するなど秀吉の天下は盤石に見えたが、秀長の死の前後から豊臣一門の不幸が始まり、結果的には豊臣政権の凋落が始まることになった。ただし、秀長が長生きしていれば、大陸侵攻(唐入り)を止められたかどうかは別問題である。それでも、秀吉より長生きしていれば、徳川家康の台頭はなかったであろう。徳川幕府というのも誕生していたかどうか分からない。
さて、本書の主人公である秀長の兄の秀吉については説明不要かもしれないが、織田信長のもとで立身出世し、のちには関白・太政大臣となるなど位人臣を極めたことで、その一代記『太閤記』が次々に生み出され、日本一の出世男としても知られるが、虚像が独り歩きし、その実像は掴みにくくなっている側面がある。近年、豊臣秀吉が発給した文書集が完結し、秀吉をめぐる研究環境は格段に向上している。これまで軍記物などで知られていた秀吉の人となりが見直されつつあるが、同文書集の刊行でさらなる修正が迫られることになろう。刊行後も新出の秀吉文書が発見されており、ますます研究が進展するものと期待される。その秀吉文書には、直接秀長に宛てた書状はもちろん、他者宛の中にも秀長に言及している文書もあり、秀長研究にも益すること大である。
秀長の知名度はその実績に比して低かったが、1985年に堺屋太一氏の小説『豊臣秀長 ある補佐役の生涯』がベストセラーになるに及んで歴史ファンには馴染みの武将の一人になった感がある。一般の歴史ファンの秀長に対する認識は高まったものの、秀吉に比して残存史料が少なく、秀吉のような派手なエピソードがないこともあり、爆発的な人気にはなっていない。小説やドラマなどの影響によるものか、黒子のように、秀長は秀吉の補佐役に徹していたような印象が前面に出ているようである。補佐役には違いないが、万年ナンバー2というポジションではない。秀吉の名代を務め、最有力の後継者でもあった。四国攻めでは秀吉の出陣を思いとどまらせて自らの武勲を立てようとするなど、単に陰で支える補佐役とはとても思えない。ただし、他の戦国大名の兄弟にありがちな兄弟同士で争うような関係ではなかった。彼ら兄弟の出自も影響していよう。そもそも家督争いするような「家」もなければ、秀長が秀吉に謀叛することなどは想像すらできない。
秀長は秀吉の補佐役には違いないが、単なる補佐役ではなく、秀吉の後継者と目されていた。このあたりも含めて秀長の実像に迫っていきたい。
なお、書名については、本来であれば『羽柴秀長』とすべきとの考え方もあるが、一般に知られる『豊臣秀長』にしたことをお断りしておく。また、史料の引用などについては、原則的に分かりやすさを考慮し、読み下しや仮名変換など手を加えている。
(まえがき、著者略歴は『豊臣秀長』初版刊行時のものです)
