- 2025 09/19
- まえがき公開
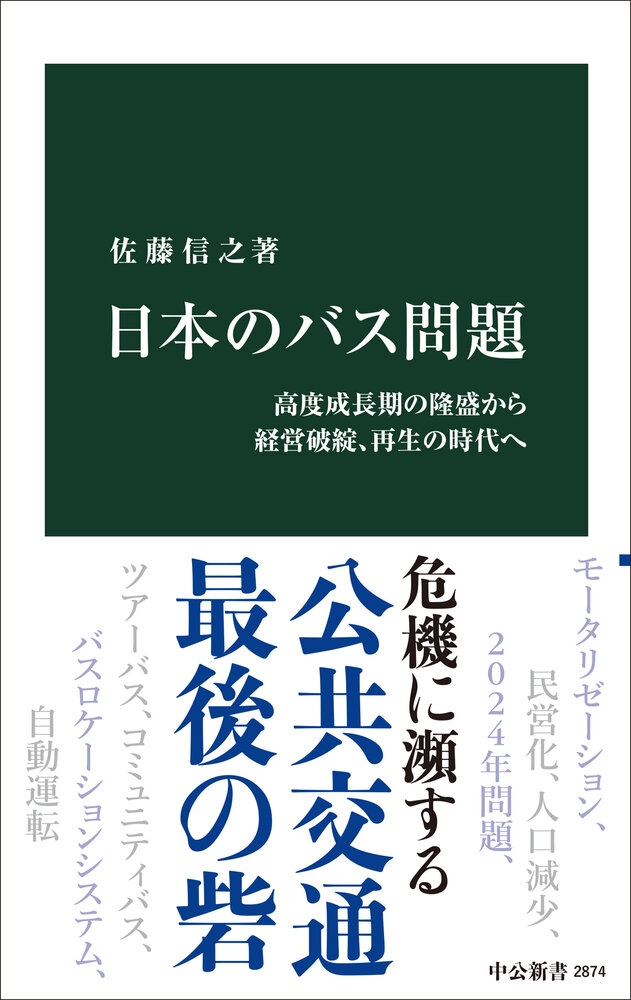
公共交通の最後の砦・バス。しかし現在、各地で減便や路線廃止、さらには会社の清算が相次いでいる。なぜ、このような事態になってしまったのか。本書は戦前日本におけるバスの誕生から、戦後のモータリゼーションによる乗客減とサービス向上のための様々な施策を解説。さらに既存事業者の保護から規制緩和へという潮流と、それを受けて新たに生まれた独創的な企業も紹介。揺れ動くバス事業の課題と将来を展望する。
『日本のバス問題 高度成長期の隆盛から経営破綻、再生の時代へ』の「はじめに」を公開します。
□ ■ □ ■ □ ■ □
はじめに
バス事業は、人々の生活に密着していて社会的に重要である。にもかかわらず、経営の近代化が遅れているケースが散見される。
近年、多くのバス会社で運行本数削減や路線の廃止が相次いでいる。
なかでも大阪府富田林市周辺を営業エリアとする金剛バスは、2023年(令和5年)12月下旬に路線バスの全てを廃止してしまったという点で衝撃的であった。同社はかねてから労使関係が劣悪でストライキが頻発していたが、2001年(平成13年)、会社側は突如祝日手当と公休出勤を廃止してしまった。組合は大阪府労働委員会に仲裁を申し入れ、組合の言い分が受け入れられて会社に命令書が交付されたが、会社は組合員すべてを解雇して、契約社員に切り替え、組合は事実上解散させられた。
その後、2021年以降は赤字が続き、人員も不足したため、事業の継続が困難だとして2023年9月に廃止を発表したのである。
昔ながらのバス会社は、経営が悪化するとサービスを縮小して人員を削減し、手当の支給を減らして人件費を削減した。その結果、従業員の収入が減って、若者にとって魅力のない業界となってしまった。もともと人員が不足する傾向があるのに加えて、働き方改革による2024年問題が起こると、サービスを維持することができなくなってしまった。金剛バスはその典型であるといえよう。
本書では、近年多くの問題を抱えている日本のバス事業について、まず、事業と制度の成り立ちを解説し、そのうえで今日の多くの課題の起源を考え、今後のバス業界の進む方向を展望しようと思う。
交通という複雑な社会的構造の中で、バス事業という一つの交通モードだけにテーマを絞ることには、それなりの危険性がある。しかし現実のバス事業に対する社会の関心度が低いことが、全国レベルから地域レベルまでの多面的な交通問題を考えるうえで、ただしい判断をすることの障害になっているような気がする。
一例をあげると、地方のローカル鉄道の維持が問題となる場合、鉄道の存続を訴える一方で、代替交通機関とみなされるバスの欠点を強調する論調が多い。
実際、バスに転換することで、所要時間が延び、たいていの場合はコマ切れの運行となり、乗客の運賃負担も増加する。目下の問題としては、バスの運転士不足のために、鉄道の需要を代替するだけの輸送力を確保できないことなども問題となっている。論者はたいてい鉄道には詳しく、バス事業についての理解は低いことが多いような気がする。
だが、本来第一に議論すべきは、「鉄道とかバスといった交通モードをどうするか」ということではなく、「地域の住民や来訪者にとってのモビリティ(移動可能性)を確保するためにはどうすればよいか」ということである。その地域の住民や来訪者にとって、いかに交通モードを選択して組み合わせれば効果があがるのかという視点に基づいて議論する必要がある。
鉄道が優位なのは、生活交通を基本としつつも、観光交通や物流といった多様な需要に対応できることにある。路線を維持するために大きな金額が必要であるものの、利用法も多岐にわたるので、組み合わせ次第では、維持が可能となる場合も多いだろう。
それに対して、バスは、自宅近くの停留所で乗れ、市街地や学校に直行できるという点で有利である。この点、鉄道では駅から徒歩や二次交通の利用が必須である。そのため、家から用務先までの一連の一般化費用(本来経済価値で計れないようなものも金額で推定することによる費用の総額)では、たとえ所要時間が延び、運賃が高くなったとしてもバスが有利な場合がある。
バス事業と鉄道や自家用車との交通モードの選択の問題ではなく、まずはバス事業とはどういう業種であり、現在どういう問題を持っているのかということの理解が必要であると考える。そうすることで、鉄道かバスかの二択ではなく、場合によっては鉄道とバスを組み合わせることで、いままでは予想もできなかった付加価値が生み出せる可能性がある。
どちらが正しく、どちらが間違っているのかということではなく、どう組み合わせれば国民や地域住民にとって最適解となるのかを考えることが、いま求められている。
さらに、過度に社会の自家用車依存が高まってしまった結果、さまざまな問題が起きている。
地球温暖化対策といった大きな問題から高齢者の運転免許証の返納といった身近な問題まで多様である。市役所や病院などの公共施設が、自家用車に便利な広大な駐車場が設置できる郊外に移転してしまった例は多い。免許を返納した高齢者だけでなく、免許を持たない人たちのためにも公共施設までの交通手段が必要であるが、利用者数が少ないので、デマンドタクシーなどのように、自治体が一人当たりのコストとしては大きな負担をしなければならなくなっている。このコストは、もともと鉄軌道系の駅の近くに公共施設を建設すれば不要となったものであるかもしれない。鉄軌道がない場合には、路線バスがその役割を担うことになる。
自家用車に便利な町は、地域全体として本当に幸せなのかということも考える必要があるだろう。
(はじめに、著者略歴は『日本のバス問題――高度成長期の隆盛から経営破綻、再生の時代へ』初版刊行時のものです)
