- 2025 07/23
- まえがき公開
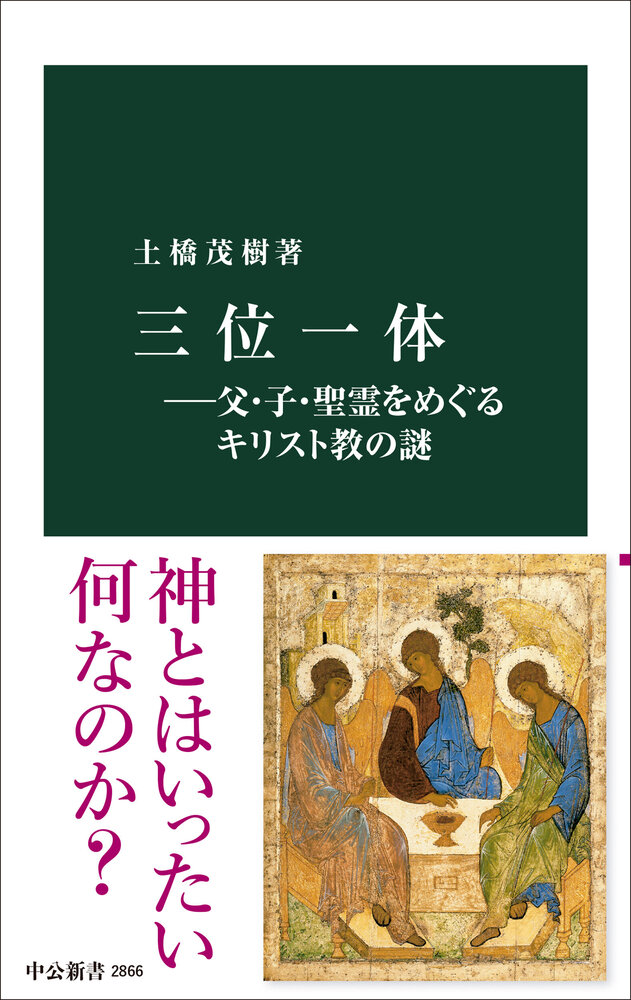
キリスト教の三位一体とは、父なる神、子なるイエス、聖霊の三者は本質的に同一だとする説である。ユダヤ教から分派したキリスト教が世界宗教へと発展を遂げる過程で、教会は神とイエスの関係の解釈に苦慮した。教会内の様々な派閥がしのぎを削った異端論争を経て、4世紀後半に三位一体の教義は確立を見る。初学者が誰しも躓く、この謎の多い教えについて、専門家が丹念に解説。キリスト教の根本思想に迫る。 『三位一体―父・子・聖霊をめぐるキリスト教の謎』の 「はじめに」を公開します。
今から2000年以上昔、中東のナザレという町に一人の男がいた。その男の特異な生と死、行動と言葉は、周囲の者たちに大きな衝撃と多様な影響を与え、人々の口から口へと語り継がれた。多くの不幸に見舞われ生の苛酷さに耐えかねていたユダヤの人々にとって、イエスという名のその男は、まさに自分たちが待ち望んでいた救い主キリストと信じられた。それどころか、やがてその男は、イエス・キリストという宗教的カリスマとして世界中の人々に知られるところとなった。こうしてナザレのイエスという男の一生は、受肉から十字架の死を経て復活に至るまでの〈神の子〉イエス・キリストのストーリーとして人々に語り継がれ、ヘブライの民の掟の書(いわゆる旧約聖書)に呼応する形で、私たちの知る四つの福音書(さらには新約聖書)へと言説化されていったのである。しかし、そこからさらに、〈父〉と〈子〉と〈聖霊〉が「一なる神」であるといういわゆる「三位一体」の教えが人々の知るところとなるには、4世紀を過ぎる頃までしばらく俟たねばならなかった。
キリスト教に関するこのような教科書的説明は、キリスト教系諸宗派を合わせても信者数が全人口の1パーセント前後に過ぎない我が国にあって、比較的よく知られているのではないかと思われる。キリスト教にあまり馴染みのない人でも、十字架に磔にされたあの印象的なイエスの姿はどこかで見たことがあるだろう。確かにイエス・キリストが世界史上の極めつきのビッグネームであることは間違いない。ナザレから出た一青年が起こしたイエス派のユダヤ教改革運動は、キリスト教の成立史に不可欠な紛れもない歴史的事実なのだ。
しかし、聖母マリアから生まれた彼は、同時に「神の子」でもあると言われる。初めて新約聖書を読んだ人は、読み進むうちに、イエスが何者なのか、人間なのか神なのか、だんだんわからなくなってきたのではないだろうか。聖書を読んだことのない人も、ヨハネ福音書冒頭の「始めに言葉があった」というフレーズなら、きっとどこかで耳にしたはずだ。けれども、そこで言われる「言葉」こそが実は神の子である御言葉・キリストを指すのだと説明されたならば、やはり何が何だか見当もつかないだろう。それに、もし「始め」が世界創造の時だとすれば、神の〈子〉は世界創造の前に〈父〉なる神から生まれたことになる。では、母マリアから生まれたイエスはもはや「神の子」ではないのか。そもそも〈父〉も神であり〈子〉も神であるなら、それは一神教とは呼べないのではないか。キリスト教のことを知りたいと思って聖書や解説書を読み始めた多くの読者は、史実と神話、神話と神学の振れ幅のあまりの大きさに翻弄され、すっかり面食らってしまうことだろう。
しかし、イエス・キリストの存在をどのように理解すべきか、その扱いに苦労したのは、なにもキリスト教に馴染みの薄い、現代日本の私たちだけに限った話ではない。創設当時のキリスト教教会も事情は同じであった。
唯一の神を奉じるユダヤ教やイスラーム教は、神の言葉を人間に媒介するために預言者を必要とした。それに対し、同じ一神教でありながら神と人間を媒介する存在として、預言者ではなく「神の子」イエス・キリストを擁立した点に、キリスト教のキリスト教である所以がある。実際、ユダヤ教徒から見れば、イエスはよくてラビ(宗教的指導者)、へたをすれば詐欺師呼ばわりされかねないし、7世紀にムハンマドが創始したイスラーム教においても、イエスはあくまで預言者として扱われるに過ぎない。
しかも、キリスト教が地中海世界へと宣教され始めた時期には、ユダヤ教はもちろんのこと、古代ギリシアや古代エジプトの多神教など先行する諸宗教に対して、キリスト教は自らのアイデンティティを明確に示さねばならなかった。そのために、ユダヤ教徒たちに対しては父なる神とは異なる「子なる神」の実在性を擁護し、他方で、ギリシア人やエジプト人などの多神教教徒、つまり異教徒らに対しては「一なる神」を主張する必要があった。やむなく二正面作戦をとらざるを得ないという厄介な事情が彼らにはあったわけである。
こうした無理難題に取り組んだのが、キリスト教の土台を築き上げた古代のギリシア教父(東方キリスト教教父)たちである。彼らは古代ギリシアの文化的教養を高度に身につけており、ごく自然にギリシア哲学のものの見方、考え方に即してキリスト教の教えをまとめあげていったものと考えられる。実際、ローカルな民族宗教であったユダヤ教からグローバルな世界宗教としてのキリスト教へと展開していくためには、根本教義の確立が不可欠であった。その極めつきが、キリスト教におけるイエス・キリストの位置づけの理解をさらに深め展開した教え、すなわち〈父〉と〈子〉と〈聖霊〉が「一なる神」であるという三位一体論である。しかし同時に、キリスト教を理解しようとする人なら、誰もが一度は躓き、理解を諦めたに違いないのが、この三位一体論という謎めいた教えなのである。
本書は、キリスト教をキリスト教たらしめる根本教義であり、最大の謎でもあるこの三位一体の教えを、古代キリスト教における護教家たちや教父たちの議論を研究する教父学の観点から解明する試みである。なにより、旧約・新約聖書から縦横無尽に引用された聖句に、プラトン主義やストア派などのギリシア哲学の思考枠が適用された彼らの解釈は、聖書解釈と哲学史の双方にとってとても興味深いものである。さらに、教会内の様々な派閥が三位一体論の形成過程でしのぎを削る異端論争は、教会政治の泥臭い実態を窺い知るよすがとなることだろう。実際、そうやって確立された三位一体論は、決して過去の遺物として忘れ去られることなどなく、キリスト教全盛の西欧中世世界はもちろんのこと、キリスト教が歴史の背景に退いた近現代社会においてさえ、その都度の独自の役割を担い続けていくことになるのだ。
ともあれ、本書で三位一体論をめぐる様々な議論を読み進めることが、読者にとって、キリスト教理解の最良の、しかもことのほか面白い道行きとなることを願ってやまない。
(まえがき、著者略歴は『三位一体―父・子・聖霊をめぐるキリスト教の謎』初版刊行時のものです)
