- 2025 04/30
- まえがき公開
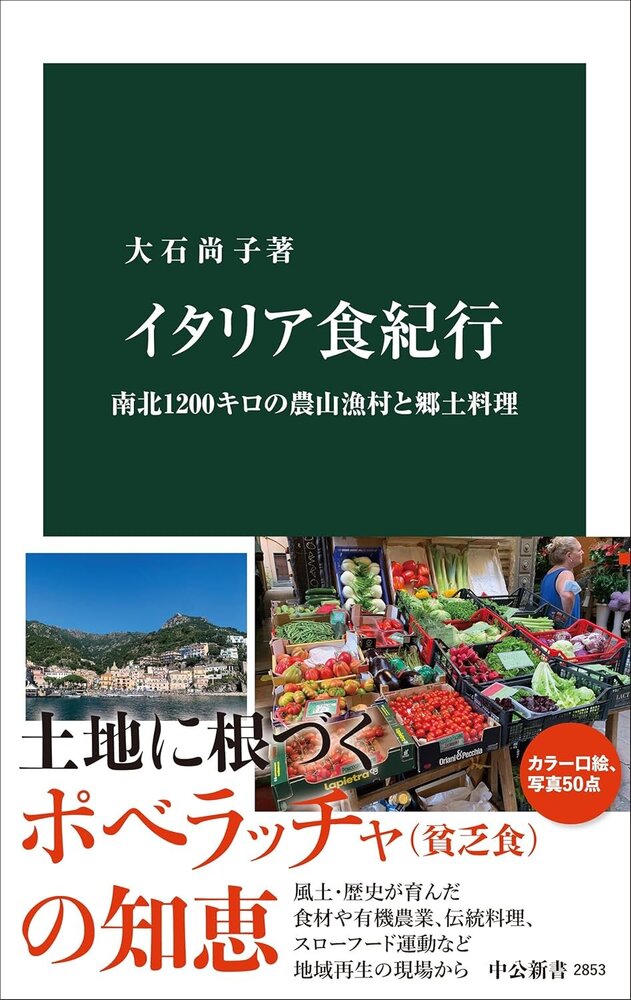
米中の覇権争い、あいつぐ戦争。試練の時代に日本外交はどこへ、どう向かうべきか。本書が探るのは戦争をせず平和的に問題を解決するための要諦である。現実主義と理想主義、地政学と戦略論などの理論、E・H・カーやキッシンジャーらの分析に学ぶ。また陸奥宗光、小村寿太郎、幣原喜重郎、吉田茂、そして安倍晋三らの歩みから教訓を導く。元外交官の実践的な視点から、外交センスのある国に向けた指針を示す。
『イタリア食紀行 南北1200キロの農山漁村と郷土料理』の 「まえがき」を公開します。
はじめに――食と社会の未来を求めて
隣町に行けば言葉もパスタも変わる――。イタリア料理は味わいのみならず、多様性が魅力。地域の風土・歴史に根ざした食材や伝統料理法が受け継がれているのだ。著者は南・北・中央・島々をめぐり、ポベラッチャ(貧乏食)の知恵を足と舌で探る。またアグリツーリズムや有機農業、スローフード運動など、地域再生のソーシャル・イノベーションにも注目。人口減少が進む日本の地方にとって、有益なヒントが満載。写真多数。
世界初・食をテーマにしたミラノ万博
二〇一五年、イタリア経済の中心都市ミラノで万国博覧会が開催された。テーマは「食」。万博のテーマに「食」が取り上げられたのは世界初だった。しかし、世界各国の食材やグルメが一堂に勢ぞろいする、というわけではない。コンセプトは、「Feeding the Planet, Energy for Life(地球に食料を、生命にエネルギーを)」。飢餓や食料安全保障、生物多様性といった人類の存続に関わる重要な課題を人々に問いかけるものだった。あらゆる人々に最も身近な「食」をテーマに掲げて、社会のあらゆる問題にアプローチする、というわけである。
テーマが発表されたのは二〇〇八年。二〇一五年に国連がSDGs(持続可能な開発目標)を宣言することを予測していたかのようである。食の問題は、社会の持続可能性を左右する最も重要な政策テーマでもあり、SDGsの一七の目標すべてに関連付けられる。そのため、国連や欧州連合(EU)などの国際組織も、ミラノ万博を食料や農業政策について各国間で議論する場と位置付け、参加活動に力を入れていた。
イタリアの食と持続可能性にピンとくる人は、あまりいないかもしれない。同国の食文化の特徴は、土地との結びつきと多様性にある。それぞれの地域の気候・風土・歴史が、その土壌に合った食材を育み、その特性に合った料理法、保存法をあみだし、多様で魅力的な食文化を創ってきた。そこには必ず、大地の美しい風景がなくてはならない。地域のベッレッツァ(Bellezza=美しさ)を、人々の叡智で存続させてきた。イタリアは、食と持続可能性を語るに最もふさわしい国の一つである。
本書の目的はイタリアそれぞれの地域に根ざした食の多様性を描くことにある。したがって、本書で取り上げるのは高級な食材を贅沢に使った都会的な料理よりも、農民たちの土地で採れた食材を使った素朴な料理だ。
日本とイタリアの類似性
イタリアが統一されたのは、一八六一年である。明治維新と同じ頃。それまでは、地方が一つの国として存在する地方都市国家の寄せ集めだった。この歴史が、地域に根ざした強いアイデンティティを育むことにつながった。日本でも、江戸時代には幕府が全国を統治したが、住民は藩の統治を強く意識し、藩に対するアイデンティティがより強かった。食の習慣も同様で、各地に郷土料理がある。
しかし、日本では、一九七〇年代の高度成長期に、食生活が欧米化した。その代償として、地域食が失われた。核家族、共働き家庭が増え、ファストフードやファミリーレストランが普及した。外国産農産物が大量に輸入され、食のグローバル化が進展した。時間をかけて料理をしなくとも、コンビニ食で簡単に食事をまかなえるようになった。親から子へと引き継がれてきた郷土料理も、こうしたライフスタイルの変化から影響を受けている。地方から都市への移住が加速し、都市型生活の中で郷土料理を振る舞い、振る舞われる機会が減った。地域の食文化が子から孫世代に伝わらず、消滅しかかっている。
イタリアも、日本と同じく一九七〇年代の高度成長を経験し、人口減少により農村は衰退している。北イタリアのミラノ、トリノ、ボローニャの三都市を中心に、自動車産業や機械・繊維産業が発達し、労働力が求められた。その労働力の供給源となったのが、都市部から離れた北東部の中山間部や南イタリアなど条件が不利な地域にある農村である。中世からの大地主制度(ラティフォンド)に由来する農村システムが残ったまま、戦後の復興期も産業が発達せず、粗放的農業を脱却することなく、収益の挙がる農業に転換できなかった。そのため、南部、シチリア島とサルデーニャ島、あるいは中部・北部の農村地域からは、大量の若者が北部の都市に流出した。
しかし、農村が衰退の一途をたどって東京一極集中が進む日本と違って、イタリアでは、地方都市の再興が見られる。例えば、一九七〇年代終わりから八〇年代にかけて発達した独自の農村観光アグリツーリズム(農体験ができる農家民泊。アグリツーリズム法で自家製食材や地元産食材を一定割合以上使うことが義務付けられている)に注目したい。トスカーナ州の一貴族が、農村からフィレンツェなどの大都市に人口が流出していくことに抗し、「田舎には田舎ならではの美しさ、豊かさがある」と唱導し、美しい自然とその土地の食を満喫する滞在型観光を提案した。アグリツーリズムの始源である。これを正式に国として推進していくべく、戦略的に地元農家や地主などいろいろな人を巻き込むネットワークが立ち上げられ、ついには一九八五年、アグリツーリズム法まで制定された。
また、同時期に生まれたスローフード運動は、当時、ローマの中心地に進出してきたファストフードに対峙し、地域に根ざした食や伝統料理法を守り、継承しようと、田舎町の小さなサークルが始めた運動である。今や世界一六〇ヵ国以上にまたがる国際NPO団体に成長し、生物多様性の保護や食の主権の回復をミッションとして、EUや国連へのアドボカシー活動(意見や意思の表明や、権利の行使を支援すること)を展開している。EUの二〇五〇年までの食料システム総合戦略「Farm to Fork(農場から食卓まで)」の策定にも関わり、有機農業やアグロエコロジーのコンセプトの導入に貢献した。
このように、一市民、一ローカルグループが、新しい価値を創造して、国家・国際レベルの運動に盛り上げ、農村全体の価値を高めるようなダイナミズムは、日本では見ることができない。
農村が未来を切り拓く
二一世紀に入り、さらにグローバル化が進む。環境破壊や自然災害が頻発し、被害が甚大化している。経済破綻や格差が顕在化し、社会不安が増大している。パンデミックやウクライナ問題は、原材料の多くを輸入に頼る日本の暮らしを揺るがせる。
食料安全保障は喫緊の課題である。日本の二〇二二年の食料自給率はカロリーベースで三八%。材木も、ありあまる森林が存在しながら六〇%を輸入に頼る。暮らしの根本要素である衣食住を、海外に頼らざるを得ない状況である。近い将来、世界では人口爆発による食料危機が心配される。現在、輸入している食料も他国へ流れ、日本に回ってこない可能性がある。実際、すでに小麦粉や飼料などは、巨大なマーケットを持つ大国に買い負けし、日本では品薄状況が続く。日本の農村は衰退の一途だ。農業者は、毎年平均六万人近く減り、一五年前に比べ半分になっている。農業者の平均年齢は六八歳。この状況を打破しなければ、日本の農村、および農業は崩壊する。その時、食料をどこから調達するのか。
日本の国土は、イタリアと同様に森林が多くを占める。国土全体の七〇%が中山間地域で農地全体の四〇%がこの中山間地域にある。起伏が多く、したがって一区画の農地面積が狭い。大規模に工業的な農業をする上で不利な地域である。そのために生産量が確保できず、新市場の開拓も難しい。農業者は十分に稼ぐことができず、離農して都市部へ移住する。親も、子どもに農業を継がせようとは言わなくなった。「農業は儲からず、しんどいだけ」というイメージを子どもに植え付けたのは、戦後の高度成長期当時に生産年齢世代であった大人たちである。特に、大規模化できなかった中山間地域で過疎化が進む。
イタリアも国土の七〇%を条件不利地域が占める。農業者の減少、耕作放棄地の増加といった課題を抱える。しかし、その中で、農業・農村は元気である。若者世代が田園回帰し、オーガニック栽培や伝統農法を復活させて、環境保全・循環型農業を始めている。それが豊かな食文化とつながり、イタリア農業の強みになっている。
ただ、伝統をそのまま継承しても、地域は再生しない。根本的な経済社会の課題解決には、新たな手法や新しい生産物、これまでなかった価値観、創造的な活動を生み出し、社会システムそのものを変革するソーシャル・イノベーション(社会変革)が必要である。伝統をまるごと踏襲するのではなく、伝統の中にある知恵や技を、現代の新たなアイデアやテクノロジーと融合させ、社会、環境、経済の持続可能性を実現する革新を生むことが求められる。 イタリアの食農をめぐる現在に至る活動にはそうした革新性がある。その食文化が魅力的に継承されているのは、それぞれの時代に起きた危機を、その都度、新しい考え方や価値の創造によって乗り越えてきたからである。本書では、そうしたイタリアの食や農のソーシャル・イノベーションを具現する事例を取り上げる。
日本にも、「里山の暮らし」という自然と人が共生する時空があった。自然の循環を活かしながら農業を営む―そのために私たちの祖先は、いろいろな知恵を出し合い、持続可能な暮らしを創り出してきたのである。もし読者が、イタリアの生き生きとした農村の姿を通して、日本の美しい農村、そこにあった暮らしの叡智に再び気づくことができれば、本書の目的が幾分か達成される。
(まえがき、著者略歴は『イタリア食紀行』初版刊行時のものです)
