- 2025 03/28
- まえがき公開
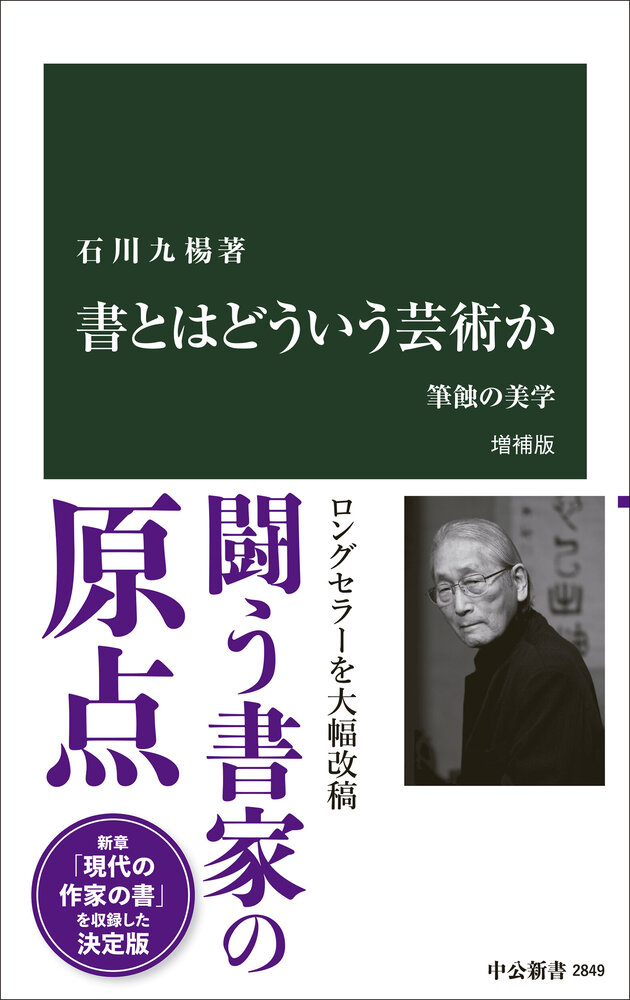
書は紙と筆と墨の芸術である。墨跡には深度・速度・角度と力が秘められている。書の美は草書体に萌芽し、楷書体とその基本運筆「三折法」の成立により完成したが、そこには石と紙の争闘史があった。筆と紙の接点に生じる力(筆蝕)こそ書の美の核心で、文字でなく言葉を書くところに書の価値はある。甲骨文から前衛書道までを読み解き、書の表現を歴史的、構造的に解明したロングセラーに、新章「現代の作家の書」を収録。 『書とはどういう芸術か 増補版 筆蝕の美学』の 「増補版発刊にあたって」と「はじめに」を公開します。
増補版発刊にあたって
1990年、わたしの5冊目の著書『書の終焉―近代書史論』が思いがけなくもサントリ―学芸賞を受賞した。表彰式後の懇親会で当時の中公新書の編集長の紹介を受け、書とは何かについての初の新書執筆が決まった。そして4年後に、『書とはどういう芸術か―筆蝕の美学』の題名で上梓された。
旧版のあとがきに、いささか昂揚した気分とともに
「書とは何か」についての初めての新書が生まれた。
*
百十数年を経て、「書は美術ならず」論争に終止符は打たれた。
と記したが、本書以前に、先人たちの「書論」にはいっこうに書という表現をとらえたと思える腑におちる論は存在せず、自らの手でそれを解明する以外にないと取り組んだ。
旧版では、従来の原理論的諸説を整理、点検し、中国と日本の書史を考慮に入れ、それらを実際の書の制作現場での経験でたしかめながら、「ああでもない、こうでもない」と思考しつつ書き進めていった「〈往路〉の思考」が深く刻印されている。それゆえ、発見にいたった事象については、少々くどいまでに微に入り細を穿ち、また誇らしげに反復的に記述する箇所があり、またあまりにも従来の説からかけ離れた結論に達したがゆえに、断言をさけて「○○と思われる」と少々遠慮がちに記した箇所も多く存在した。
上梓以来30年を経て、さいわい版数も13版を数え、多くの読者に恵まれることになった。その後「書とは何か」について、本書が明らかにした「筆蝕の美学」なる書論はさまざまな反論に耐えてさらにいっそう鍛えられ、その厚みと深みと広がりを強めて、すっきりと整理された体系からなる〈復路〉をたどってきた。
旧版が明らかにしたのは、大まかには、
第一に、書とは、「筆蝕」という名の「書く」場に生まれる表現であり美学である。ほ
第二に、その美学は、石を鑿で刻ることと紙に筆で書くことの「あや」に生まれた。
第三に、その美学の根底には、草書体→行書体→楷書体と展開した書体が、一般には、楷書体をくずした行書体、行書体をくずした草書体と理解されるにいたる、西暦350年ころから1100年ころの中国書史の歴史過程が横たわっている。
この結論と構成はもとより、貴重な苦吟の痕跡も残しつつ、新しく一章、またいくつかの新項目を加筆し、ほぼ全ペ―ジにわたって整理と削除を施すことによって、『書とはどういう芸術か―筆蝕の美学』という題名を残しつつも、新たな一書「増補版」として上梓することになった。〈復路〉の思考によって表記を変更したのは次の2点である。
東アジア漢字文化圏 → 東アジア漢字文明圏
漢字語は文化にとどまらず、文明に深くかかわることが明らかになったからである。
筆蝕 → 筆触、筆蝕
楷書体成立以前の筆で紙に書く筆触と、筆で紙に書くことが鑿で石に刻ることと合流することによって生まれた楷書体以降の「書きぶり」である筆蝕を仕分けするためである。
本書が従来に加えてさらに多くの新たな読者に出会うことを心から願っている。
はじめに
「書」というと一般の人は何を思い浮かべるのだろう。子供が習字塾に通う姿や、子育てのめどのついた主婦の稽古事など、「習字」を思い浮かべる人がやはりいちばん多いのではないだろうか。少し古風な趣味を持つ人なら、田舎の家や料理屋の床の間の掛軸や欄間の扁額、僧侶や政治家が揮毫した掛軸を思い浮かべるかもしれない。
何となく筆と墨に魅かれ、暇ができたら書でもやってみたいと考えている人が最近はとても多い。
近代、とりわけ、アメリカ軍の進駐した戦後には、剣道、柔道、茶道、華道とともにいったんは見捨てられた感のある書が、最近になってしぶとく、われわれ日本人の意識の中に甦ってきたように思われる。何かの折に、身近で書を見かける機会も多くなった。見かけることは多くなったけれども、書を見てどことなく、「上手い」「下手」「勢いがある」「弱々しい」とは感じても、ほんとうに「良い」のか「悪い」のか自信をもって判断できる人は少ないのではないだろうか。
ご多分にもれず、美術記者も「書は難しい」と言って見て見ぬふりをして過ごし、知識人は、書の良し悪しなんてさっぱり解らないと言って、すましている。
しかし、実際には、いつまでながめていても飽きない書があり、逆に、しばらく掛けて見ていると、すぐ嫌になってしまう書がある。心が落ち着く書があり、勇気づけられる書がある。
もしも、書が人の心を落ち着けたり、人を勇気づけたりすることがあるとすれば、書の美というものは確実に存在する。その力はどこから来るか、それを解き明かすことが、書の美を解き明かすことになる。
書というとまっさきに思い浮かべる習字も、またその発表会に並ぶ書道作品も、確かに書の一種であることにはちがいない。しかし、少し考えてみると、おかしなことに気づく。たとえば、書道史に登場する王羲之、唐の太宗皇帝、顔真卿、蘇軾(東坡)、黄庭堅(山谷)らは、中国一級の政治家であった。日本の空海、嵯峨天皇、小野道風、藤原行成、藤原俊成、藤原定家、良寛らも、またそれぞれに時代を背負った人たちであった。「大衆の時代」とはいえ、現在習字に熱を上げる子供や主婦の習字、あるいはその先生方の書と、これら書の歴史上の担い手の書との表現上の大きなギャップを見過ごすわけにはいかない。現在の書や書道界を皮肉って、「一休や良寛が現在の書道展に出品したら、きっと落選するだろう」というブラックユーモアさえあるほどだ。
近代以前の書がとらえにくくなった原因を時代のせいにするのはやさしい。時代のせいにはちがいないからだ。しかし、近代以降、とりわけ戦後の書のとらえ方や見方は、時代的限界に色濃く縁取られた大きな歪みを持っている。その歪みが、近代以前の書を見えにくくし、自ら書く書についても、自信と確信とを失わせている。近代以降流布された数々の書論、それらを再検討し、採用すべきところは採用し、捨てるべきところはきっぱりと捨て去り、歴史的かつ現在的視点を獲得すれば、書は驚くほどみずみずしい姿を現わす。すぐれた書は、くんでもくみつくせないほど豊かな劇を秘めていて、ほんとうにおもしろいものだ。
書は暗く、辛気くさく、古くさいように見える。事実その通りかもしれない。しかし、その読み方が深まると、実にさまざまな姿を魅惑的に見せてくれる。
新聞記事をていねいにチェックしてみると、意外に書に関する記事が多い。ただしその中身となると、大半が、町の公民館や美術館、画廊等での団体展、いわば書道塾の発表会である。書は、華道、茶道と同様の稽古事であり、書道展というのは稽古事の発表会であるという大衆一般の意識が、新聞記事からはっきり見えてくる。
むろん、決して華道や茶道等の稽古事をつまらぬものと頭から否定しているのではない。真意はむしろ逆で、近代以降、公の権力や教育機関、知識人からは見捨てられながら、それらを延命させ、その機構を支えつづけたのは、実に大衆であり、大衆の力がそれらの灯を絶やさなかった必然性を言いたいのだ。華や茶や書に大衆の根強い共感と支持があったからこそ、それらは稽古事に姿を変えながら、生き延びてきた。その生命力は、近代以降日本に入ってきた西洋音楽や西洋絵画の比ではない。
書道は大衆に支持され、生き延びてきた。それゆえ、同じ美術館で開催されることはあっても、美術展と書道展は自ずと異なった態様をとる。
書道展の観客の大半は、出品者とその友人、知人。新聞社主催の大がかりな書道展では、入賞作品が多すぎるため、2段、3段と壁面を埋めつくすように作品を掛けていることもある。受付で見たい人の名を告げると、展示してある部屋までの道順を赤いサインペンで書き込んだ地図を渡してくれる例もある。なにしろ展示作品数が厖大だ。ちなみに、大新聞主催の公募展の出品数は約2万点。入賞率は6割程度。6割を切ると「今年の審査は厳しかった」と業界紙が報じる世界だ。落選した人を探すほうが、入選した人を探すよりよほど難しい。
こういう超特大の稽古発表会を、文化勲章受章者、文化功労賞受賞者、芸術院会員の書道家が頂点で取り仕切る。西洋美術家や西洋音楽家には信じ難い世界だろうが、日本の政治家が、市町村議会議員から都道府県議会議員、国会議員、そして大臣、総理大臣という出世コースを描くように、大衆に基盤を置いた日本の組織は、多かれ少なかれ、地方から中央へという立身出世型、年功序列型の似たような形をとる。書道組織、書壇も例外ではない。
他方、公の考えもまた、この姿の鏡としてある。一部の私学系の美術大学や短大で、書の講座を開こうという動きが多少あるものの、美術大学で本格的な書道科や書道専攻というものはひとつもない。国立大学で書道科をもつものは、東京学芸大学、新潟大学教育学部、奈良教育大学、筑波大学(旧東京教育大学)、福岡教育大学などであった。書道科などと銘打ってはいるものの、実態は、書道教員養成機関。しかも21世紀に入ると書道科の数は減った。他には私立の大東文化大学、二松学舎大学など中国文学の傍らに書道専攻課程があるくらいだ。
大衆、文部科学省ともに、書道とは、教育もしくは中国文学の一種だと考えている。
その証拠に、カルチャーセンターで人気の高いのが書道。大きなカルチャーセンターではほとんど満員で、新規受講生を受け入れることができないほどだという。
このように見てくると、華道や茶道のように、全面的に民間に依存している形態と似てはいるが異なり、また美術のように公の美術大学で教育を授けられる形態とも異なり、また文学のように、大学に研究者、民間に作家と棲み分けている形態とも異なる、特異な書の構造が透けて見えてくる。いずれにも似ながら、いずれとも異なった形態で書は存在している。
柔道や剣道、囲碁や将棋、算盤のように、習字や書道には級段位認定制度もある。しかし、書道のそれは、他のジャンルのように半ば公的なものではなく、まったく私的なものである。級段位の認定制度は、書道団体、結社の数だけ、つまり無数にある。本書の読者のひとりが思いたって、明日から書道団体を名乗り、勝手に級や段位をつけ、師範認定をしてもなんらさしつかえない。ときどき、芸能人やスポーツ選手が「書道○段」と名乗り、マスコミが「達筆、名筆」とはやし立てているのを見かけるが、書道の級段位はいいかげんなものにすぎぬから、これほど滑稽なことはない。
書道や習字は、他の誰でもなく日本の大衆によって支えられてきた生命力のある分野である。しかし、それゆえに、書を書道ないし習字とイコールと考え、書の制作や理解の前段階に位置するにすぎない教育や稽古そのものを書ととらえる大衆的誤解が広く定着してしまった。受験生が「現代国語」の中で、小林秀雄の評論をマークするように、書の名品である王羲之や顔真卿の書は単なる習字手本となり、書を制作し理解することは、もっぱら習字技法の問題にすりかえられている。
書道を教育ととらえるこの大衆の視点からは、「上手い」「下手」という価値判断、評価しか生まれてこない。「上手い」「下手」という評語からは、書はいっさいその姿を現わさないにもかかわらず……。
一方、このような書の状況にいらだった若い一部の書道家は、書を絵画のような美術の一環として位置づけたいと考えている。書を絵画のように売れる商品にすべきだと称して、現代美術まがいの作品をつくって、画廊に並べる。書の研鑽や解明などそっちのけで、安易に現代美術の知識を仕入れるのにやっきになっている。気持は解らぬではないが、やはり、「ちがう」と思う。書はどこまで行っても書だからだ。この手の書道家は、根無し草であるだけに、成長の契機がなく、伝統的な書道家よりさらに始末が悪い。
中国、朝鮮、日本、越南にまたがる東アジアの書の歴史は、書という固有の表現の歴史である。近代、現代という時代に、西欧思想の嵐をくぐり抜ける中で、相当に歪んだ形になってしまったが、それでも書はやはりひとつの表現であって、決して教育に終わるものではない。あるいは表現としてしか書は意味をもたないと言っていいかもしれない。
書の歴史、つまり書の表現史の末席に現在の書の表現がある。小林秀雄の評論が「現代国語」の教科書に引用されていようとも、小林秀雄の評論は受験生のテキストではないように、王羲之や顔真卿の書もまた、書道の手本ではなく、厳然たる歴史的表現である。「上手い」「下手」、習字、書道、書道展という教育、稽古の観点からは、書は決してその真の姿を現わさない。書の表現史の末席に、現在の書の表現がある。その表現を支える底辺に、習字、書道教育、書道展があるという視点を回復しない限り、ほんとうの書の理解、またそのおもしろさには出会えない。
書道は教育であるという論から知識人がどれほど自由でありうるかは措くとしても、知識人の書道や書道界の現状へのいらだちの原因はここにある。
以上、書と書道界の現状を知った人には言わずもがなのことだが、意外に書や書道の現状に不案内の人が多いので、ひととおり書の実情について、前もって問題点を整理しておく。
(まえがき、著者略歴は『書とはどういう芸術か 増補版』初版刊行時のものです)
